
仕事において、満足できるかどうかは「シャローワーク」をいかに減らすかにかかっている!〜DEEP WORK〜
世の中は気が散るものだらけ!というか人間の設計は気が散るようにできてるんだぜ!
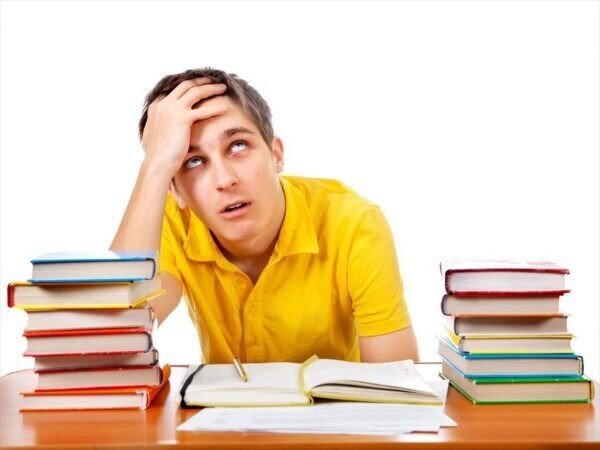
”人間が最高の状態にあるのは、何かやりがいがあるものに深く没頭しているときなのだ”
ーカル・ニューポート
たまには生産性系の本も読んでおこうと思い立ったので、今回は著書『DEEP WORK』のお話をしたいと思います。
本書の著者はコンピュータサイエンスの准教授でありながら、『Study Hacks』という、学業や仕事をうまくこなして、充実した人生を送るためのヒントを書いたブログを運営し、アメリカで人気を博しております。
本書の主張はとてもシンプルで
ディープワークの時間を増やし、シャローワークの時間を減らして生産性を極限まで高めていこう!
というもの。用語説明を簡単にすると
ディープワーク:集中した状態で成される活動。クリエイティブはすべてディープワークから生み出される。
シャローワーク:あまり知的思考を必要としない、補助的な活動。注意散漫でもできるものが多い。
現代において、シャローワークと言われるものは価値がとにかく低くなるんだからディープワークに入る手段を持って、充実して仕事をこなし、自己価値を高めるテクニックを科学的な手法で説いた名著ですね。
ただこれ、一言でいうなら「当たり前じゃん!」となりますけど、
何せ人間はスマホが目の前にあっただけで注意力が削がれてしまうくらい繊細な生き物なものですから、これは意識で少しずつ変えるしかないです。
というのも、遺伝的に人間はとにかく外敵が多かったものですから、
ライオンみたいに食うことに特化した一点集中する目を持つよりも
シマウマみたいに食われる危険性を避ける視野の広い目に近いものを持っております。
だから、人間のデフォルトは注意力が分散しているんですよね(正直肉が食えなくても、物体が動かない木の実や芋類で十分生きていけましたから)。
それ故に、逆にわざわざ時間を割いて集中力をつけることってかなり価値あることだと思うんですよ。
何せ集中が生まれつき得意な人間なんていないですからね。
シャローワークの怖いところ

本書でいうところの「シャローワーク」とは、先ほど申し上げたように
あまり知的思考を必要としない、補助的な活動
例えば事務作業とか、メールチェックや返信がそれに当たります。
それの何が厄介って
なにも意識しないと際限なく時間を浪費しがち
なところにあるんですよね。
仕事においてもそうなのかもしれませんが、わかりやすい例で言ったら日常生活における
YouTubeをダラダラ見る
ネットショッピングをする
SNSを見まくる
と言ったことは気づいたら2時間経ってた!ということはあるあるかなと思います。
日常生活なら、まだ自分の自由時間なのでそれもいいかなと思いつつ仕事でそんなことをしていても自己価値を高めることにはつながらないよなぁと。
なので、少しでもシャローワークを減らし
・新しい企画を考える時間を増やす
・取引先の案件を取ってくるために相手のことを知る
・自分の働く時間を減らして、上司の手伝いをし新しい仕事を教えてもらう
と言った戦略を建てた方がいいかなと。
シャローワークを避けるための3つのアイデア

そこで必要になるアイデアとしては、
・ムダなシャローワークにノーと言う
・シャローワークの時間の固定化
・すべての活動の深度を評価する
と言ったことです。
シャローワークの中でも、「メールの返信」なんかは緊急性が高く、すぐに返さないと後で顰蹙を買うことも・・
ただ、他の事務作業(ファイリングとか)は割と後回しにできるし、なんなら人に任せることができるわけですよ。
それは優先順位の一番後ろに持ってきて、間に合わなければ翌日か、誰かに頼むかして、自分の大事な仕事に集中することです。
また、「午後15~16時のみシャローワークをする!」という風にあらかじめシャローワークをする時間を決めておくというのもアリかと。
その分、他の時間を緊急性の高い仕事を除いて、集中する時間を作ってやることです。
これは定番ですけど意識するとしないで段違いですね。
最後に、「すべての活動の深度を評価する」ということも念頭に入れといた方がいいかと思います。
というのも、シャローワークといえどメールチェックとメールの返信では震度の差が違います。
チェックは一瞬で終わりますけど、返信はお偉いさんほど文章を考えるものです。
というように、シャローワークを評価して、
簡単すぎるものは量が多かったら人任せに、
難しいものは考える余地があるから自分でやってみる
という選択をとると自分の価値が上がる可能性ありです。難しいことができる人は希少ですからね。
もちろん、全部難しくて進まないとノイローゼになるので、簡単な仕事を織り交ぜつつ良いパフォーマンスを保って行いたいところでもあります。
そう言った意味でも、自分の仕事の深度を評価してどう言った優先順位でやっていくかを俯瞰し、分析することは経験上かなり効果ありますね。
以上、3つのアイデアを出しましたが、本書では何物にも邪魔されずに仕事をする戦略が18個ありますので、自分の肌に合ったものを選べる仕様になっております。
生産性についての研究を、ここまで分析してる人っていないんじゃないか?と言わしめるくらい徹底されててビビりますね。
というわけで少しでもヒントになったらなと思います!
