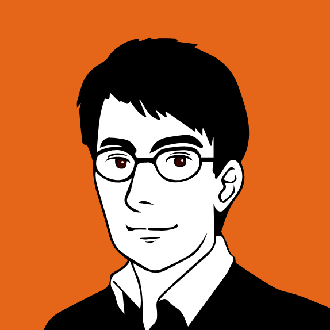「副業人材を受け入れたい部署」が「ドラフトで優秀な社員を2割の時間貸して!」と言った方が健全じゃない?
先週KDDIの「社内副業」の話題をSNSでよく見かけた。
KDDIは国内約1万1千人の正社員を対象に、就業時間中に他の部署でも働ける社内副業ルールを作った。他の部署で働ける時間は就業時間の最大2割とする。
期間は最長6カ月で、他の部署で働いた成果も人事考課に反映する。副業人材を受け入れたい部署を募り、社員が自ら応募できるようにする。副業制度を利用したい社員と直属の上司、受け入れ先の部署の3者が合意したうえで業務内容を調整する。当面は年100人程度の利用を想定する。
「副業?」と呼ぶには違和感を感じてる。特に以下の部分だ。
副業人材を受け入れたい部署を募り、社員が自ら応募できるようにする。副業制度を利用したい社員と直属の上司、受け入れ先の部署の3者が合意したうえで業務内容を調整する。当面は年100人程度の利用を想定する。
「副業」を行いたい社員視点で考えると、「副業」を行う理由は以下の3つの集約されるのではないか?
1. 収入を増やす。
・稼ぐ力を付ける。
・土日、定年後も働く。
2. 人脈を増やす。
・会社の名刺ではない人脈の構築。
3. 挑戦する。
・新しいこと、面白いことに挑戦する
・本業で稼ぎつつ挑戦する。(リスク回避をしての挑戦)
・自分のスキルを外で試す。
KDDIの取り組みの「社内副業」に応募する社員は、おそらく「3. 挑戦する。」だと思う。(今いる部署から逃げたいってのもあるかもしれない)
にしても、
・そこに直属の上司の了解がいるのか?
・「社員が自ら応募」って、上司にとっては「裏切り」ととらえる場合もあると思う。(KDDIにはそんな上司はいない。という文化なら問題なし)
・その「上司」に了解をとる。とか。
制度自体がなんか違う気がする。
これなら、
「副業人材を受け入れたい部署」が「ドラフトで優秀な社員を2割の時間貸して!」と言った方が健全じゃない?
他部署から呼ばれる「優秀な社員」の価値は可視化されるし、呼ばれたら悪い気もしないだろう。あとは社員と直属の上司、受け入れ先の部署の3者が合意したうえで業務内容を調整すればいい。
併せてフリーエージェント宣言の制度もあっても良いかもしれない。
それにしても
事業環境が急速に変化するなか、社内でも技術系や業務系といった専門分野をまたいだ連携が必要とみている。
と日経の記事にあるけど、本気で「必要とみている」なら「社員頼み」ではなく会社で強引にでもやればいいのに。とは考えすぎだろうか。
何れにしても興味ある取り組みではある。
---
Photo by LinkedIn Sales Navigator on Unsplash
いいなと思ったら応援しよう!