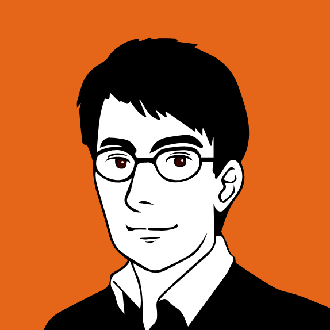個人的発信が組織の対話を活性化する、議論を呼び込むコンテンツ戦略
停滞した組織に、知的好奇心と議論の熱を取り戻すにはどうすればいいのか。
多くの企業が会議やワークショップを繰り返す中で、本質的な課題解決やイノベーションに繋がる深い議論を生み出せずにいる現状を打破するために、本稿では、組織内部の個人による情報発信に着目した新たなアプローチを提案してみたい。
一見遠回りに見える個人の発信が、いかに質の高い議論を「呼び込み」、組織全体の知的好奇心を刺激するのか。
なぜ組織の議論は深まらないのか
多くの企業が、議論の活性化を目的とした取り組みに投資しているという認識がある。特に難しいことではなく、1on1、会議室のデザインや設備(オンライン対応など)、ファシリテーション研修の導入、miroなどコラボレーションツールの導入など、手段は多様化している。
議論が深まらない原因は複合的だが、ある程度しぼられていると思っている。
参加者の準備不足、議題設定の曖昧さ、そして心理的安全性の欠如など。(やる気がないなどは除外)
しかし、本質的な問題は、議論が「必要に迫られて行うもの」つまり仕方なくやること。であり、参加者の内発的な動機や知的好奇心が置き去りにされている点にあるのではないか。
個人的発信が議論を「呼び込む」メカニズム
私は、日々の業務で感じた疑問やアイデアをnoteに投稿する活動を続けています。当初は個人的な備忘録(メモ)でしたが、予想外の効果があることに気が付いています。それは投稿記事が、思わぬ議論を「呼び込む」ようになったのです。
例えば、私が「AI」や「エフェクチュエーション」について考察した記事を公開したところ、「記事の内容を参考に、ワークショップを開催したい」といった反応が寄せられた。実際に開催した例もある。
なぜ個人の発信が議論を活性化するのだろうか。そのメカニズムは以下の4点に集約できるのではないか。
1. 議論の種となる発信
個人の問題意識や興味関心に基づいた発信は、読者の共感や新たな問題意識を喚起し、「議論の種」となる。
2. 議論の参加者の質が向上
事前に発信されたコンテンツに触れた読者は、議論のテーマに対する理解を深めた状態で参加するため、議論の質が向上する。
3. 議論の共通言語として
発信コンテンツは、議論参加者間の共通言語となり、議論の効率と質を高める。
4. 議論の記録と学びの蓄積
発信されたコンテンツは、議論の内容を記録・振り返るための基盤となり、組織全体の学習を促進する。
議論を「呼び込む」コンテンツ戦略の3つのステップ
組織全体で議論を活性化させるためには、個人の発信を戦略的に活用する必要がある。以下に、議論を「呼び込む」コンテンツ戦略の実践方法を3つのステップで考えたので、ここに公開する。
ステップ1:議論したいテーマを特定し、コンテンツとして発信する
まず、議論したいテーマを明確にする。個人の興味関心、日々の業務で感じる問題意識、または組織全体の課題など、出発点は様々で良い。テーマが決まったら、特定の人物や読者層を想定し、彼らに響くテーマ、切り口、表現方法を検討する。発信媒体は、note、ブログ、SNSなど、目的に応じて選択可能だ。コンテンツの種類も、記事、図解、動画など、多様な形式が考えられる。
昨日は「キーボード」についてのnoteを投稿した。ただの趣味であるが、語りたい内容ではある。
ステップ2:発信コンテンツを議論の「呼び水」として活用する
コンテンツを公開したら、積極的に周囲に共有し、フィードバックや意見交換を促す。つまりコンテンツを共通の土台として活用するということだ。
ステップ3:議論の内容を記録し、参加者と共有する
議論の内容は、メモ、議事録、または発信コンテンツへの追記として記録する。記録を参加者と共有することで、議論の振り返りや学びの深化を促す。議論で得られた新たな知見やアイデアは、新たなコンテンツとして発信し、議論のサイクルを継続的に回していくことが理想的だ。(かなり面倒ではある)
効果検証と今後の展望
私自身の経験から言えるのは、個人の発信を起点とした議論は、参加者の主体性、議論の深さ、そして具体的な成果という点で、私個人には確実に質的な変化が見られた点です。
私起点なので、私の興味と参加者の知的好奇心と問題解決への意欲がシナジーを生んだ結果とも言えるだろう。
個人の発信は、単なる情報共有に留まらず、質の高い議論を「呼び込み」、組織の対話と学習を活性化する強力なツールとなり得る。
本稿で紹介した「議論を呼び込むコンテンツ戦略」は、組織の規模や業種を問わず応用可能であり、停滞した組織に新たな活力を与える処方箋となる。
組織は、個人の発信を奨励し、議論を活性化させる文化醸成に積極的に取り組むべきではないだろうか。
いいなと思ったら応援しよう!