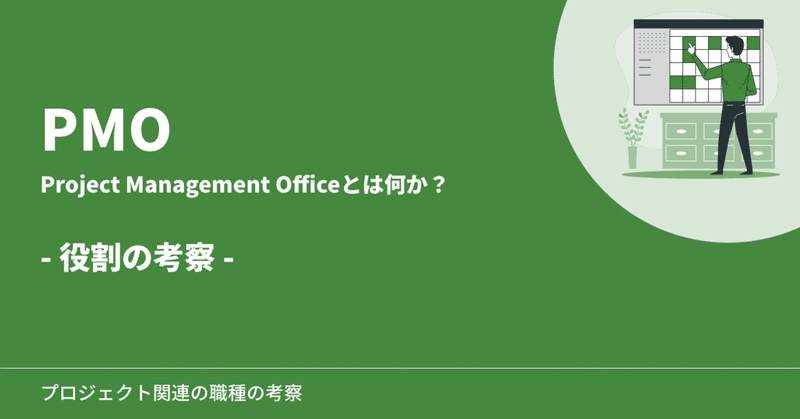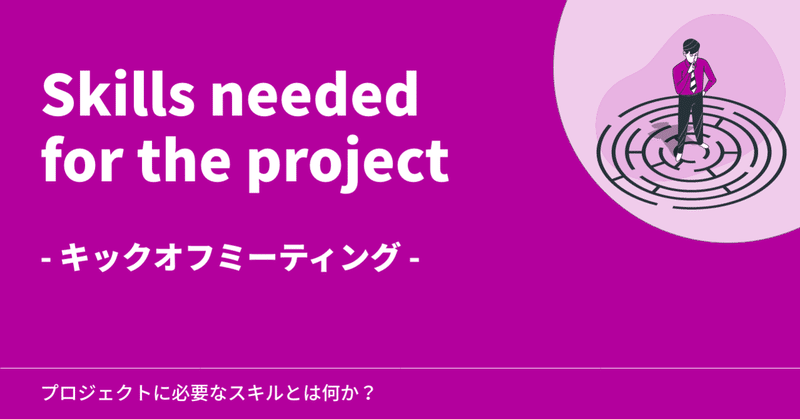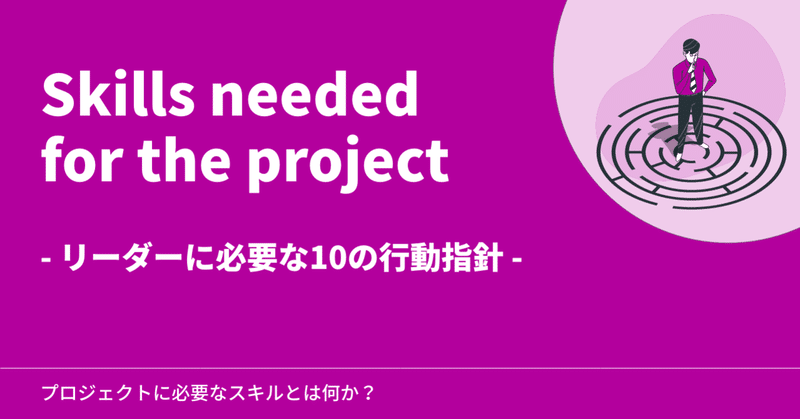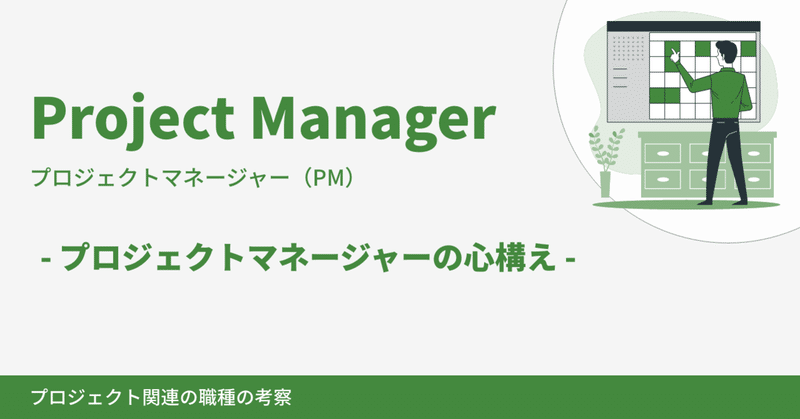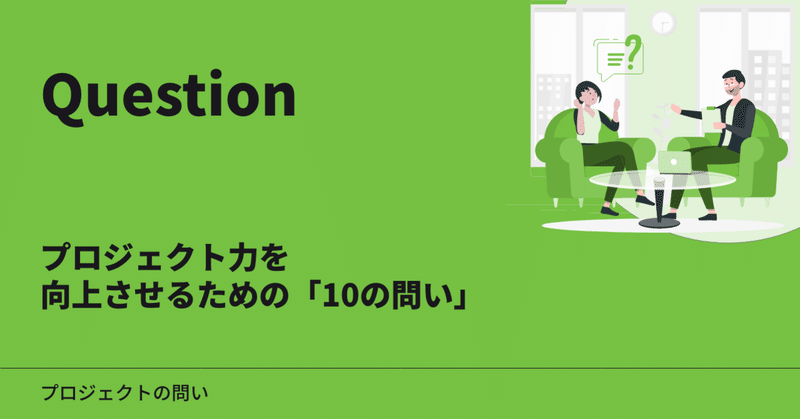- 運営しているクリエイター
記事一覧
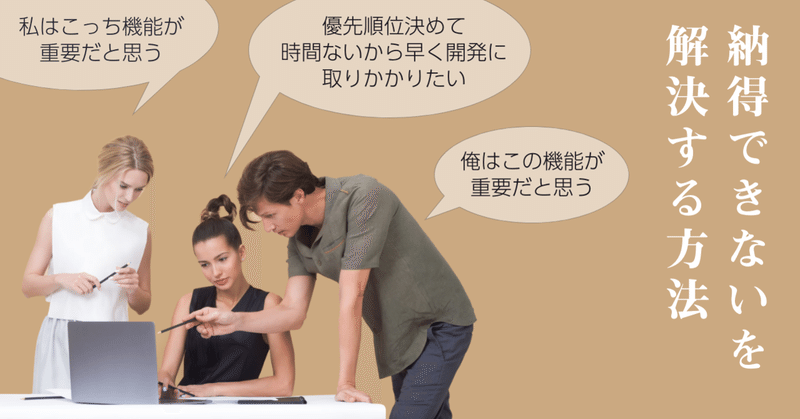
対話とユーザテストからプロジェクトメンバーが納得する課題を抽出する方法と、開発優先度をゲーム的に決めるファンクショナリティ・マトリクスPlus
2年ほど前に書いた2つの記事を再編集して掲載しています。 成功・失敗・頓挫・ペンディングという中途半端な状態問わず、かなりの数のプロジェクトを経験しています。役割はプロジェクトリーダーと言う立場で関わる事が最も多く、その時の最大の悩みは常にプロジェクトの方向性を皆に共感させ、プロジェクトに集中させること。 フェーズ1.対話とユーザテストからプロジェクトメンバーが納得する課題を抽出する方法 まずはプロジェクトメンバーが課題に対して納得感を得るための手法。 ざっくり言うと