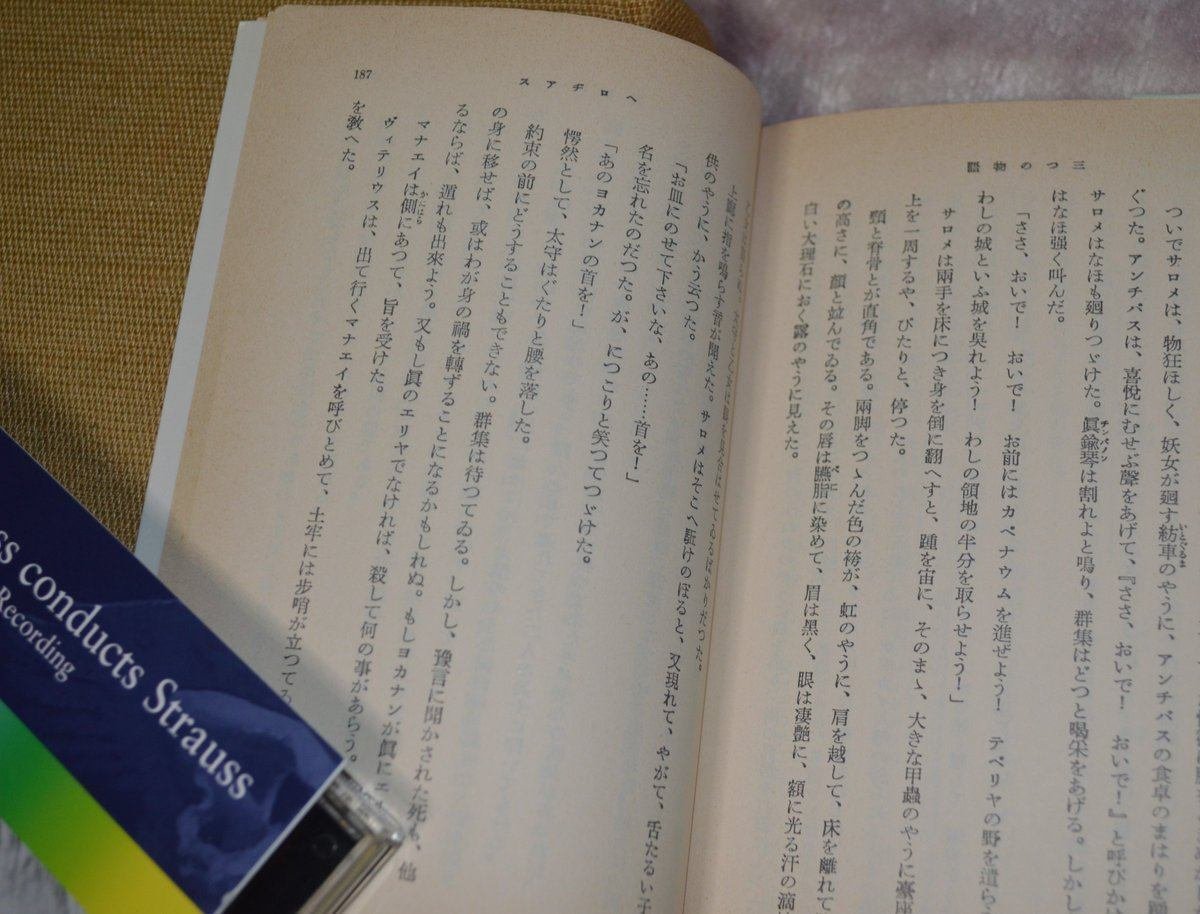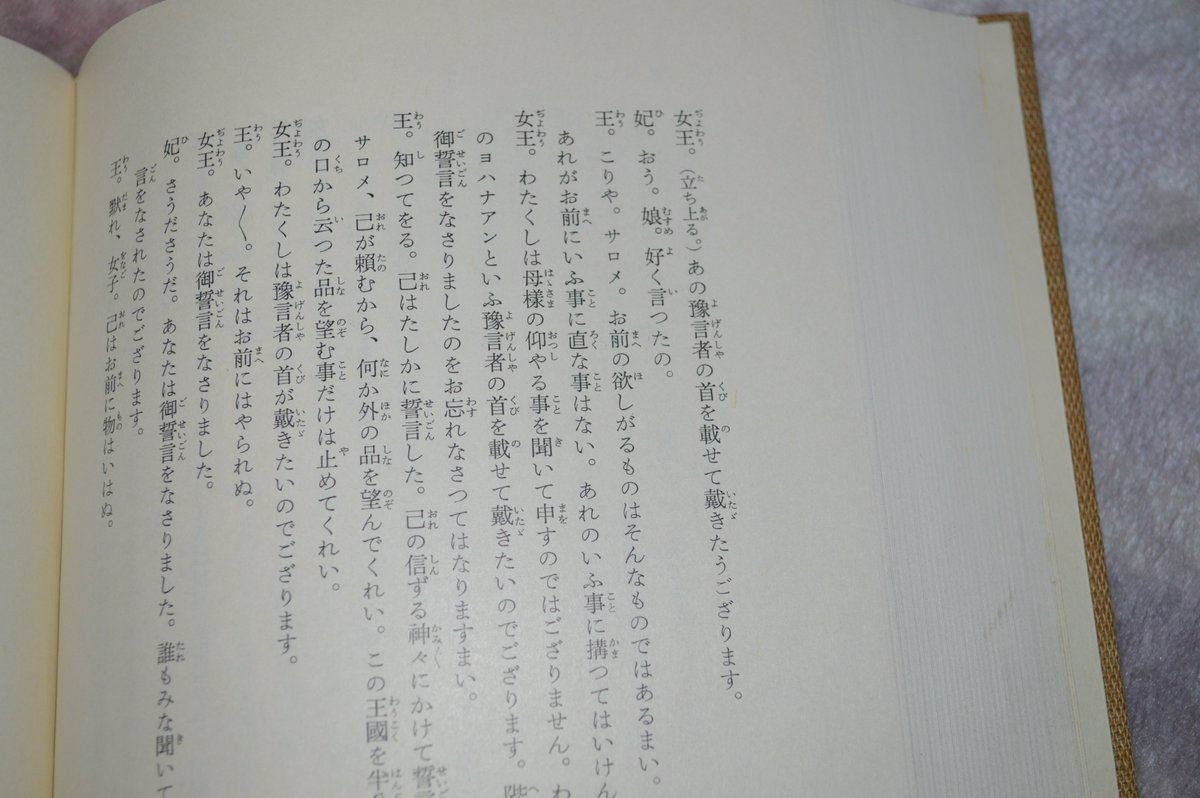『獣サロメ』(獣の仕業 第十五回公演)
河原乞食たちが、奇蹟の到来を待っているとそこにサロメが現れて舞いを舞い、開幕。始まりの印象はそんな風だった。
河原乞食たちは、刑吏であり式部官であったりと役職の肩書をもった公僕たちで、羅馬帝国SPQR : Senātus Populusque Rōmānusの四分封領主ヘロデ・アンティパスを称え、その眼下に真っ青な死海が広がったマカエラスの要塞の食客であり、彼らが散らかした生活のゴミが舞台を埋め尽くす。ゴミはコンビニの、『マカエラス要塞店』の売り物たちの成れの果てだ。コンビニはパンとサーカスを謳う羅馬帝国が支配地域一帯に築いた。
コンビニの屋根には『S P Q R』(ゴミはゴミ箱へ Sono Porci Questi Romani)の標語が掲げられている。ローマ市民とコンビニ文化を憎む国々は Sono Porci Questi Romaniを「これらローマ市民どもは豚」という意味で使って共闘していることを河原乞食たちはよく知っていて、ゴミ溜めの我が身を..…..…河原の水面に、逆さまに映してみせることで、帝国と皇帝の権威を盤石にさせているのだ。
「ローマ皇帝、万歳!」を叫ぶヘロデ宮廷の賛美、ローマROMAの権威の水面に身をひたして前進し、その身を逆さまに映しあげ、ヨカナーンへの愛AMORを謳う。
舞台の原案書は、フラウィウス・ヨセフスの『ユダヤ古代誌』(真偽定かならぬ伝奇的幻惑的著述)、ギュスターヴ・フロオベエルの短篇『ヘロディアス』(『三つの物語』の一篇。訳者は不詳。公演後日に主宰の立夏氏が発言したスペースを拝聴したかぎりでは誰かひとりの訳者の翻訳から特別な感銘を受けたというわけでは無さそうである。わたしは山田九朗による城砦文學調の翻訳で愛読しているので『獣サロメ』から受け取ったフロオベエル的印象は、城砦の石組で受け止めている)そして、森鷗外がドイツ語から重訳したオスカア・ワイルドの戯曲『サロメ』だ。
鷗外の独善に近い美麗な筆で日本語になったワイルドの「偏見の無い意見は常に美点が無い」を地で行く壮麗な台詞まわしが、おやっと息を吞むような事態に。役者ひとりで演じるために書かれた長台詞を分割し、複数の役者にしゃべらせている箇所が数度ある。
シェイクスピアの『マクベス』などの、荘重をきわめる長台詞を力任せに力演すると雄弁になり過ぎてしまいがち。人間の役者でさえそうならば、獣のエネルギーでオスカー・ワイルドを演じるとなったらその熱量は台詞を嚙み殺してしまうことだろう。慟哭を伝言していくような姿の発声がまるで、長い台詞の持っているエネルギー(ローマ帝国の権威)を役者たちが橋渡しする姿に見えた。ちょうど、川に橋をかけるように。
立夏氏のX(旧twitter)で「獣の仕業」のなかで描かれる”穢れ”が説明されていたが、それを押し退けて、私の「印象」がスッと隣に擦り寄る。サロメの時代は性善説しかなく、明確な悪はまだ無い。"穢れ"が、曖昧な悪として存在していたのではないか。
だからこそ、舞台クライマックスを盛り立てるサロメのモノローグはサロメたったひとりで語られるのだ。ここにおいて、ワイルドもフロオベエルも溜めに溜めた情念を限界まで放出する。
サロメの「悪」が成立する過程が、まるでスロー映像で眺めるような大事件として舞台を席捲する。城壁は砕かれる。ローマ旗も半旗をえがいて崩れ落ちる。ヨカナーンが生きている間は「くちつけ」、ヨカナーンが死んだあとは「くちづけ」。 鷗外の文体がうかびあげるおもおもしい裳裾のひきずりの残像を伴って、サロメのセリフの情熱・雄弁・美麗の混然たる溶け合い、表情の変容と幻を読み取る時、水面の中心に、神像をしのぐ魔像の直立を幻視せずにいられない。魔像を引き倒すかのごとく、ヘロデがサロメを「殺せ!」と命じるラスト台詞を、全員が唱えた。あの日(私が観劇した日)、腹のなかで一緒に「殺せ!」と呻いた客が、私の他にも何人もいただろうと信じている。
死海の水流が(水流は事実です。役者たちがみんな頭から水をかぶっていた)星空の高みに築かれたマカエラス要塞まで登ってきて、アウゲイアース王の大牛舎に積り積もった汚わいの塊がアルフィオス川の激流を浴びて一晩で洗い流されるのにも似た、カタストロフの終幕。
「私たちはみんな掃き溜めの底にいる。しかし幾人かは空の星を見上げているのだ(意訳)」オスカー・ワイルドが『ウィンダミア夫人の扇』で書いたセリフ(意訳だが)が炸裂する。星がみんな落ちてくる。
照明が凄かった。まるで、薄物の妖しいヴェールが幾重もの色彩が重ね合いをえがいて、重ね具合が透けて見える輝き。七つ生まれた罪悪が妖しい生き物の呼吸を舞台に轟かせて。
舞を舞うサロメの泣き顔が焼き付いて離れない。獣の涙を見た者は人生観に大きく風穴が開くという言い伝えがこみあげてきて、終演後は言葉も出なかった。会場に、あやうく一眼レフを忘れて帰るところだったw