
合気道の稽古はヤラセである:合気道のキホンの考え方③
合気道の稽古は、稽古する者同士のレベルによってかなり内容が変わる。
まったく同じ型を稽古するにしても、どのような条件設定で行うかによって内容は大きく変わっていく。
つまるところ合気道というのはヤラセなのだけれど、そのヤラセにも色々な種類がある。そこが合気道のいいところでもあり、難しいところなのだ。
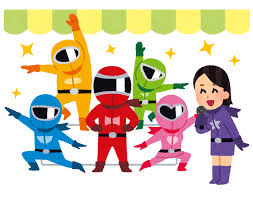
攻撃の対処法
合気道は武器が前提なのだけれど、めちゃくちゃわかりやすくするために銃を例えにしよう。
銃で狙われていたら、絶対にその銃の射線上にいてはならないので、それを避けるように動くのは当然だろう。

では銃が透明になったらどうだろう?銃で狙われているとわからない人は避けようともしない。何も危険がないのに避けるなんてバカじゃん?

しかし、相手の目線や腕の位置などの他の情報から本気で狙われていることがわかる人はその射線を避けるように動く。
ただそれだけのことで、こいうのはカッコつけて「気」というのかも知れない。この稽古はどちらかが「こんなのヤラセじゃん」と真剣に取り合わなければまったく成り立たない。
誤解の原因
こういうのが色んな会派ごとに起こる誤解の原因になってるような気がしてる。
例えばよくあるタイプの話で「〇〇先生はガッチリ握られて動けなかったが、握った相手を怒った」という話があったとしよう。
一方の意見だけ聞くと対抗できずに相手が怒ってしまったという話になりがちだが、反対の意見として腕ばかりに囚われていたら他の攻撃を防げないという意味で怒っている場合もある。

昔の合気道では海外に指導に行く時などに「腕を動かせないくらい握ってくる相手がいたら蹴りを入れろ」などと言われていたらしい。
今ではそんな暴力的な教え方はできないけれど、あらゆる攻撃が飛んでくる可能性をちゃんと考慮しながら稽古することは必要だ。そのためには相手の動きを感じる必要もある。
稽古にはそういう「前提条件」が設定されていることがあるのだ。
ヤラセは難しい
思えばテレビ番組なんかでもヤラセが問題になったりするけれど、ヤラセをしたうえで面白くするには演者にしっかりと前提を共有しておく必要がある。
見えない銃で狙うためには本物の銃を狙っているように動かないといけないし、受ける側はそれを感じて本物の銃と同じように射線を反らそうとしないといけない。

銃がない状態で銃があるかのようなヤラセを成立させるためにはお互いが同じものを見えていないといけない。
合気道開祖は剣がなくても剣の稽古ができるように合気道をつくったと言われていたけれど、それにはこうした意味合いもあると思う。
上手なヤラセの稽古をするためには稽古者の知識や経験が必要になる。

嘘を誠にする
ヤラセがわからない段階では実際に武器で攻撃される経験も必要だし、武器で攻める稽古も必要だろう。
銃を握っていたり、剣を抜こうとしている相手を抑えるために手首を握らないと、そもそも手首を握る意味すら理解できなくなる。

確かに武器を持っていない相手の手首を掴むというのはナンセンスな部分があるけれど、何の稽古をしているかによってその意味合いは変わっていく。
高度なヤラセができるようになるためには、まずは基本的なヤラセができないといけないし、握らせる稽古と握らせない稽古はどちらも同じ理屈に繋げないといけない。
稽古とはフェイク
稽古というのは所詮はフェイクである。偽物だ。どちらかが信じないだけで簡単に崩壊する程度の、本当の争いとは比べ物にならないほど甘ったるいものでしかない。
ただその稽古を実践的にしているのは本物に近づけようという情熱に他ならないと思う。
型というのはとにかく状況を限定的に狭めていったもので、ある特定の条件でしか成り立たない技の稽古を行う。そうした稽古をしながらあらゆる局面に対処できるようになるには共通点を見つけていかなければならない。

そのためにはできるだけ一つ一つの稽古を本物に近づける努力が必要だ。相手が武器を持っていても、素手であっても同じように対処するためには何もなくてもあるように稽古する必要がある。

料理研究家から化学調味料を使ってきた料理であるラーメンを何と定義するか問われての芹沢さんの答え
いいなと思ったら応援しよう!

