「感情」を持ったAIは情報と記憶で作れる 後半 ~「メディア」は感情を必ず刺激する~
本日は、もう一つ皆さんにわたしの専門であるメディアというものについてお話したいと思います。
わたしは、大学を卒業してそのまま、テレビ局というマスコミの世界に飛び込んで、昨年の3月に退職するまでの36年間、番組制作の現場の第一線で仕事をし続けてきました。
テレビの歴史に少しでも足跡を残せていたとしたら、それは新たに開発したニュース系情報番組「とくダネ!」という番組を立ち上げて、それを成功させることによって、当時非常に悪名が高かった「ワイドショー」という分野の番組をほぼ絶滅させたことだと思います。
これが、ワイドショー全盛時代のテレビ欄です。

特殊な日ではなく、なるべくいつものワイドショーが繰り広げられている日のテレビ欄を選んだつもりです。
フジテレビの「おはよう!ナイスデイ」は「美人女子大生メッタ打ち殺人」です。
今ならジェンダーという観点から、当然問題を指摘されるでしょうし、事件の被害者に勝手に「美人」などというレッテルを貼ることは許されません。
しかし当時は、肯定的な「美人」という言葉を使うことは、失礼にはあたらない、問題ないだろうという感覚が蔓延していたのです。
なので、女性が事件に巻き込まれるたびに「美人」という言葉が氾濫することになります。
他を見回すと、堤大二郎、名高達郎、織田裕二、鈴木保奈美&江口洋介といった俳優、タレントの交際といったものを扱っています。
テレビ朝日2時からの、この「夫の痴漢プレー現場直撃!」っていうのは何でしょうね?(笑)
どう考えても自分の夫が痴漢しているところの現場を直撃できるわけがないので、おそらく新しく登場した風俗店を取材したのではないかと想像するのですが…
わたしも20代後半から30代にかけて、このワイドショーという分野の番組制作にどっぷりと浸かっていました。
当時は「主婦向けワイドショー」と呼ばれていました。
午前中やお昼の時間帯は、今ほどお年寄りや退職者が多くありませんでした。
この時間にテレビを見てくれるのは在宅している主婦と決めつけていました。視聴者ターゲットをはっきりさせて番組を制作していたのです。
放送のテーマとして主に選んでいたものは…
芸能ネタ、芸能ゴシップ、芸能スキャンダル、そして愛憎関係、とくに男女関係のもつれに満ちあふれた事件やトラブル、さらに新たに登場した社会現象とその賛否などが取り上げられました。
この頃、テレビ局に寄せられた意見(とくに抗議)としては、
一つ目は、「下らない内容を延々と放送している」
二つ目は、「取材や放送が人権を犯している」
この二つに、集約されると思います。
さきほど紹介した新聞のテレビ欄をもう一度見てみてください。
その雰囲気が、なんとなく伝わると思います。
その渦中に身を置いていたものとしては、ホントにその通りだなと思うことも多くありました。
しかしそういったものを好んで見ているのは、視聴者の方じゃないかと開き直る気持ちもどこかにありました。
皆さんはBPOという名前を聞いたことあると思います。
BPO(放送倫理・番組向上機構)とは、民放とNHKが設立した、放送番組の内容向上や人権侵害について審査し提言を行う組織になります。
その設立の目的の一つ(厳密にはその前身としての「BRC」ですが…)には当時のワイドショーによる取材や放送が社会問題になっていたことも、大きな要素の一つだったと感じていました。
わたしは現場の責任者として、幾度となくこのBPOへの報告書をまとめましたし、委員の方がずらりと揃っているヒアリングの場にに出席して、様々な質問を浴びせかけられもしました。
テレビ局のビジネスモデルが、基本的に視聴率というもので測られることは、皆さんご存じだと思います。
数百から千単位のメーターを、一般視聴者の家庭の置かせてもらい、ある時間にどの局のどの番組を見ているのかという記録が、視聴率のデータとなります。
統計学的な観点からいうと、メーターを置かせてもらったサンプルのデータから母体となる集団(テレビを持っている視聴者全体という母集合)の視聴行動を推測するというものです。
このデータは、いわば番組やテレビ局の「成績表」になります。
一人でも多くの人に見てもらうという競争は、最新のメディアであるネットやSNSでもアクセス数、ページビュー数を競うことを考えると、メディアが利益を上げるための基本的なビジネスモデルは何ら変わっていません。
この視聴率を少しでも多く稼ぐことが、テレビマンとして優秀とされるわけですから、当然のことながら各局、各番組において「視聴率競争」が起きることになります。
その競争の結果として、放送のプロたちは、よってたかって、前述したような同じようなテーマを選び、同じような放送が、テレビ局や午前や午後の番組をまたいで月曜日から金曜日まで毎日、多くの時間放送されました。
さきほどの新聞のテレビ欄を見れば、どれだけ多くの時間が、ワイドショーに占められていたのかということが分かるかと思います。
そしてワイドショーに厳しい声が多く寄せられることになったのです。
それでも、各テレビ局はワイドショーをやめられませんでした。
1980年代から90年代は、ワイドショーの全盛時代と言えます。
実に20年以上にもわたって、熾烈な競争が繰り広げられたのです。
そのワイドショーの制作現場にどっぷり浸かり、テレビというメディアについて向き合った経験から、なぜメディアはこんなにも下らないテーマについて、延々伝え続けるんだろうということを、日夜考え続け、そして分析したことが出発点になっています。
その分析を生かして、どうやったら「社会悪」とまでレッテルを貼られたワイドショーをやめることができるのか?
その結論として「メディアとは感情である」という結論に至ることになります。
これをきょう二つ目の仮説にいたしましょう。
その前提条件としてまず、メディアとは何だろうということからはじめたいと思います。
辞書的な定義としては…
メディア(media)とは、①情報の記録・伝達・保管などに用いられる物や装置のことである。 媒体(ばいたい)などと訳されることもある。記録・保管のための媒体と②コミュニケーションのための媒体とに大別することができる。
これからテーマにするのは、主に後者の②ということになります。
わたしも②を生業とする企業で働いてきた経験を皆さんにお話しすることになります。
しかしメディアの歴史を振り返っていく中で、①も②も区別がつかなくなることが、実はよくあります。
②を保存したものが①ですから、当たり前と言えば当たり前です。
今で言えば、テレビ、そしてラジオ、新聞、雑誌、これらは若者を中心に「マスゴミ」といった悪意のこもった揶揄するような言い方がされています。
またインターネットという新しいメディアに対して「オールド・メディア」という言い方もされます。
皆さんとメディアという言葉について共通認識を持つために、これまでの歴史の中で、これはメディアだなと思えるものを挙げてみてください。
例えば江戸時代の「かわら版」はどうですか?
新聞の原型といわれるのですから、当然メディアといっていいですよね。
そのほか現存する様々な出版物、例えば織田信長の一代記である「信長公記(しんちょうこうき)」は、今の大河ドラマ「どうする家康」にたびたび登場しますし、「平家物語」といった軍記物は、合戦の勝敗とそれに伴う権力の行方という歴史そのものを、文字という情報によって記録したものです。
いわゆる随筆、例えば「方丈記」や「徒然草」は、当時の人の生活様式や考え方などを後世に伝えてくれます。
様々な歴史情報を記録した媒体で、その後の時代もふくめて、多くの人たちに様々な情報をもたらしてくるすことを考えると…
これらはすべてメディアといってよいのではないでしょうか。
もう少し遡ってみましょう。
来年の大河ドラマ「光る君へ」の舞台になるのは…源氏物語の平安絵巻ということで、少々強引ですが「源氏物語」のメディア性を検証してみましょうか。
「源氏物語」の大きな特徴として、
「なぜ54帖にも及ぶ、長編大作になったのか?」
ということが挙げられます。
この謎について、わたしが高校生のときの古典の先生が、ある説を唱えていて、今でも鮮明に記憶しています。
「『源氏物語』はゴシップ満載の週刊誌だった?」
実は、あんなに長い物語になったのは、週刊誌に連載された記事のように、定期的に宮中に出回って、皆で回し読みしながら楽しんでいたのではないかというのです。
例えば源氏物語の始まりである第一帖の桐壺帝(きりつぼてい)のモデルは一条天皇、そして桐壺更衣(きりつぼのこうい)は藤原定子(ふじわらのさだこ)といわれています。
定子は関白である藤原道隆(ふじわらのみちたか)の娘で最高の名家出身でした。
後ろ盾である道隆が亡くなったあとは、宮中では孤立無援になりますが、一条天皇の寵愛を一手に受けることになります。
実は「源氏物語」には、それぞれモデルの人物がいたり、インスパイアを受けるような実際の出来事があったと言われています。
宮中の読者は仮名というオブラートに包まれて面白可笑しく脚色された文章を読みながら、「あぁ、あの人のことだよね」とか「えっ、そんなことがあったの」という風に、回し読みをしながら楽しんでいたのではないかというのです。
わたくしの高校の古典の先生は、「源氏物語」は、宮中を出回る週刊誌だったんじゃないかという大胆な仮説を、授業で披露してくれたのです。
もし週刊誌のような役割を果たしていたとしたら、紛れもなくメディアということになりますが、皆さんどう思われます?
その根拠の一つとして、先生が挙げたのが物語の長さです。
例えば全26巻と長いことで有名な山岡荘八の「徳川家康」は新聞の連載小説でした。
漫画で言えば、「こち亀」にしても「ワンピース」にしても、少年ジャンプという最も人気のある漫画週刊誌で、長年にわたって読者から毎週毎週いつもいつも期待され、その期待に応えようと、毎週毎週力を振り絞って、書き続けてきたら、いつの間にか、100巻を超えるような(こち亀は201巻)長編になっていた。
この「連載」という構造こそが、54帖もの長編大作を生み出した秘訣ではないか。
当時、紙は貴重品だったでしょうから、それなりの理由がないと、写本も含めてこれだけ多くの紙を使うことは許されなかったかもしれません。
今の時代でも「書き下ろし」という形で、とんでもない長さの長編小説が生まれるということは考えにくい、皆さんもそう思いません?
そして、実際に起きた出来事をモデルにしているとしたら…
物語を紡ぐ上で最も才能を要する、その題材やテーマは、周囲に転がっているということです。
メディアの歴史を振り返ることで、皆さんのメディアに対するイメージは、少しは広がりましたかね?
それでは、今のメディアの話に戻しましょう。
では現在社会で繰り広げられている「メディアの競争」、生き残りを賭けて激しく戦う組織の一員になったつもりで、皆さんには少し具体的に想像してもらいます。
当たり前ですが、新製品を紹介してもらう際に、その番組で紹介してもらった方が多く売れるということになれば、その番組の価値そのものは高く評価され、スポンサーから多くのお金を出してもらえることが、容易に想像できます。
その番組で紹介された方が、お店により多くのお客さんが来るということになれば、その番組は高く評価されます。
先ほど触れた「視聴率」とは、その番組を見てくれた視聴者の総数を推測するものですから、より多くの視聴率を取っている番組で発せられた情報は、単純により多くの視聴者に伝わることになります。
メディアとしての価値は、原則として視聴率や部数、ページビュー数に比例することになります。
先ほど例に挙げたワイドショーによる視聴率競争は、当時の雑誌や新聞などで…「ワイドショー戦争」と呼ばれました。
この言葉には、下らない内容で視聴者も作り手も辟易としているという揶揄する意味合いが深く込められていました。
その戦争に主に指揮官として参加していたわたくしが、どのように内容を選び、どんな取材し、どのように構成を立て編集をして放送していたのか。
そのときの感覚をお話しすることが、一番わかりやすいと思います。
その感覚を一言で集約すると、自分たちの放送が、「視聴者の感情」をどれだけ強く刺激できるかということになります。
この感覚について、少し補足してみましょう。
当時の視聴者が、ある番組にチャンネルを合わせる理由はどのようなものが挙げられるでしょうか。
これは今でも変わらないでしょうが、まずどの局の番組が、これまでの経験上、面白かったかということが挙げられます。
これまでの信頼と実績ということになるでしょうか。
しかし、それだけではありません。
当時は、その日の番組内容を知る手段として、新聞のテレビ欄が最もポピュラーな存在でした。
テレビ欄を見て、これは面白そうだなと思った内容の番組にチャンネルを合わせてくれるのです。
だから、なりふり構わず、おどろおどろしいような、扇情的な文言が先ほどのように並んだのです。
「独占」「スクープ」「激白」「発覚」「潜入」「密着」などの形容詞も、頻繁に使われました。
放送が始まってからも、このチャンネル探しは続きます。
視聴者はこの内容少し飽きたなぁと思えば、ザッピングという行為が始まります。
チャンネルを回して、他の番組は何をやっているんだろうと探す行為を指します。
たまたま自分の番組にチャンネル合わせたときに、少しでも興味を持ってもらおうと、画面のかなりの面積を割いて、サイドテロップというキャッチコピーで、今放送されている内容が、いかに刺激的で面白いかと言うことを表現し、視聴者の手を止めさせようとします。
このように視聴者を少しでも振り向かせようとする努力の指針となるのが、「視聴者の感情をどれだけ強く刺激」できるかという一言に集約されるのです。
番組を見た視聴者は、当然のように様々な感情を刺激されます。
「許せない」「酷い」「悲しい」
「そうだよね」という共感
「笑える」「面白い」「楽しい」
「なるほど」という納得
「へぇ~」という驚き
「恐ろしい」「怖い」
これが番組を多くの人に見てもらう最も有効な手段だということは、このワイドショー戦争に身を置いた、その瞬間から感じ取ることができます。
すみません、感覚的な話ばかりで、あまり論理的ではありませんよね。
この感情を刺激するという行為が、何を意味するのか?
その点について、人間の脳の仕組みから考えてみましょう。
皆さん思い出してみてください、これまでの人生で鮮明に記憶していることを…
九死に一生を得た、危うく命を落としかけたという経験は、一生忘れることはないでしょう。
幼い頃、きつく叱られた経験や褒められてうれしかった経験
始めてデートした高揚感
受験や就職に失敗して絶望したあのとき…
喜び、怒り、哀しみ、楽しみといった喜怒哀楽
これまでになかった強い恐怖や、例えようもない至上の快楽
どうです?
皆さんが覚えている様々な事象は、どれも皆さんの様々な感情を揺さぶってきたものばかりではありませんか?
これらはすべて強い感情を伴っていませんか?
当たり前ですが、伝えた情報が視聴者の記憶に残れば、その番組そのもの印象に残ることになります。
人間は記憶の積み重ねによって人格が形成され、次の行動原理が決まります。
「面白いから、次もあの番組を見よう」ということになります。
この視聴率競争に勝ち抜き、多くの視聴者を獲得した番組で、自社の製品を知ってもらうとしたら、それはかなり効率のいい宣伝ということになります。
「あの新製品良さそうだから、今度店頭で手に持ってみよう」
それが購買という消費者の行動につながっていくならば、メディアとしての価値はより高まることになります。
メディアにお金を出すスポンサーは常にそういうことを期待します。
そしてメディアは数多くの視聴者を獲得することによってそれに応えようと、記憶に、印象に残るような伝え方をするのです。
メディアによる競争を単純化するとそういう図式になります。
複数のメディアが存在していて、ビジネスとして社会と関わる限り、メディアはこの根本原理から逃れることはできません。
情報を伝えることを生業とするすべてのメディアは「記憶に残ること」競争を繰り広げることになります。それはメディア側から見ると「感情刺激」競争と言い換えることができるのです。
テレビを例にして言えば、その積み重ねによってしか、視聴率競争を勝ち抜くことができません。
実はメディア側からは、情報の受け手の感情を刺激すること以外、その記憶に働きかける方法がないからです。
これは人間の記憶の仕組み根ざしたことですから、メディアが人間相手に情報を伝えている以上、どうも逃れようがないようです。
伝えた情報が受け手の記憶に残り、そしてその受け手の行動に影響を与える。
その影響の大きさで、そのメディアの価値は決まるということが言えます。
人間の記憶の仕組みとして、この感情が刺激されることと密接な関係があることは、先ほどの例で、なんとなく感じ取っていただけたのではないかとは思います。
感情と記憶の仕組みについて、もう少しだけ見てみましょう。
詳しく触れると、それだけで時間をオーバーしてしまいますので、ごく簡単にご紹介します。
うれしい、たのしい、わくわくする、どきどきするといった前向きの感情や、誇らしいといった他の人に認められたときに、ドーパミンという神経伝達物質が放出されて、記憶を司る「海馬」という脳の部位が活性化して記憶に刻まれると言われています。
一方でこの記憶を司る海馬のそばにある「扁桃体(へんとうたい)」と呼ばれる部位は、心地よい感情や不快な感情の双方と関係していますが、特に「恐怖」や「不安」「緊張」や「怒り」といったネガティブな感情による記憶に深く関係していることが分かっています。
このように記憶という行為は、感情に取り囲まれる形で形成しているようなのです。
なんとなく直感的にご理解いただきたいと思います。
もっと詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら、「人間の記憶に感情が及ぼす影響を教えてください」とチャットGPTに打ち込んでみてください。
わたしの説明よりも格段にわかりやい言葉で教えてくれます。
もちろん、皆さんは科学を志している方ばかりでしょうから、元の論文や文章にあたって、その信憑性についてもよく検証する必要があることは、言うまでもありませんが…。
なぜわたしが、高校生のときに受けた「源氏物語」の授業の内容を、今でも鮮明に覚えているのか?
考えてみれば、いまから半世紀近くも前の話です。
そのときに、わたしの感情、例えば「なるほど」という納得感や新たな発見にワクワクする知的好奇心が湧き上がったことでしょう。
このように「感情」が強く刺激され、わたしは半世紀近く経った今でも鮮明に覚えているのです。
繰り返しになりますが、人間の記憶に感情が大きく作用するとしたら、メディアの影響力の大きさ、すなわちそのメディアの力というものは、その感情を刺激する度合いで測ることができるということが、テレビの世界で40年近く、競争を繰り広げてきたわたしが到達した結論です。
これが、先ほど感情を刺激する競争になるといった事象の本質です。
実は、長年メディアに携ってきた自分の中では「感情」と「記憶」は等価です。
なぜなら、情報の受け手の記憶の残るような伝え方を考えたときに、感情を刺激する以外にその方法が思い浮かばないというのは、先ほど言及した通りです。
もしこの二つの言葉の上位概念として、何か新しい言葉を生み出して名付けたとしたら、それを正面から見たときには感情という言葉で表わされ、後ろから見たときには記憶ということになるのではないかと、思っています。
ここで「メディア」という存在について、わたしなりの定義を申し上げたいと思います。
もうお分かりですよね、すなわち…
「メディアとは感情である」
ということです。
あまりに漠としていて、つかみどころがない、鵺(ぬえ)のような「メディア」という存在を一言で説明するならば、この一言に尽きるのです。
常に競争にさらされているメディアとは、情報の受け手の感情を刺激する競争をしているということです。
メディアというものが情報を伝え、その伝える中で、自分たちの価値を少しでも高める競争を繰り広げるとしたら、情報の受け手の感情を刺激し、記憶に残り、印象づけるということが競争の主眼になります。
これは、人間の記憶の仕組みに根ざした特性ですから、どんなメディアも決して逃れることができません。
メディアの歴史をもう一度振り返ってみましょう。
源氏物語や、そのほか先ほど挙げた古典の本の数々は、すべて、そのときとその後の時代の人たちの感情を常に刺激し続けた結果、人々の記憶に残り、そして今という時代まで生き残ってきたという、逆の言い方もできます。
人々の感情に訴えかける力が弱かったほとんどの情報は淘汰されて消えていく一方で、感情を多く刺激したものだけが、人々の記憶に残り、そして生き残ってきた歴史ではないでしょうか。
もっと古い、原始的なメディアとして、「言い伝え」「伝承」といったものが考えられます。
先ほどの話の続きとしては、このあたりが最も古いメディアということになりますかね。
例えば…
「あの山には首がいくつにも分かれた竜が住んでいる」
近くの山の意外な危険を、麓に住む村人たち皆に伝えるために、こんな伝承が伝わっていたとしましょう。
そこには、聞く物を怖がらせ、印象づけることによって、多くの人々の記憶に残り、社会全体に広まり、そして「教訓」として何世代にもわたって定着していったという構造が見て取れます。
まさしく感情を刺激した結果、教訓として定着するという、メディアの役割を説明する、わかりやすいモデルと言えます。
最新のメディアであるインターネット上のSNSでも、情報の受け手の感情を刺激することが、そのメディアの目的になっているという格好の例があります。
皆さん何か分かりますか?
皆が「いいね」という評価を競い合います。
これこそ、まさに情報の受け手の感情表現である「いいね」という言葉を引き出そうと、感情をどれだけ刺激したか競い合っている証拠ですよね。
テレビの例を取って、感情を刺激するということを、もう少しわかりやすく説明しましょう。
例えば85歳の女性が横断中にクルマにはねられて亡くなったという事実を伝えるとしましょう…
ニュース原稿のように、ただ単に事実を伝えるだけでは、なかなか視聴者の感情に訴えることができません。
しかし、その横断した場所が、横断歩道まで500m以上も遠回りしなければならないといった事情があるかもしれません。
最近はすっかり歩くスピードが遅くなってしまったのかもしれません。
戦後の厳しい時代をたくましく生き抜いて、貧しい中にも子どもを育てていた人なのかもしれません。
その子どもが有名人なのかもしれません。
こういった伝え方の方が、ただ単に事実を伝えるより、視聴者の様々な感情を呼び起こすことができるかもしれません。
テレビをはじめとする大手メディアの世界で感情を刺激するというのは、こういったことを指しています。
そして、その感情刺激合戦が、最も顕著な形で現れたのが、先ほどのワイドショーです。
1980年代90年代は、ワイドショー全盛、「ワイドショー戦争」などと呼ばれたが、決していい意味ではなかったという話は先ほどしましたが、感情を刺激すれば何でもいいじゃないかという競争は、まるで自分のむき出しの欲望を見せられているような、後味の悪いものでした。
しかし、この「感情刺激」競争から簡単に逃れることはできませんでした。
例えば、ワイドショーの中でも「芸能スキャンダル」は、視聴率を稼ぎ出す重要な要素だというのは、先ほどの新聞のテレビ欄を見ていただければ分かるともいます。
ですが、ワイドショー批判の格好のターゲットでもありました。
興味本位の芸能人のスキャンダルは、のぞき見趣味を満たすだけで、国から免許事業として電波、周波数を割り当てられているテレビ局が、長々と時間を使って伝える必要があるのか。
そんな批判を真に受けて…
「わが番組は芸能スキャンダルを扱いません」と宣言したワイドショー番組がありました。
しかし、武器を一つ放棄して戦争に身を置くことは、片手を縛って殴り合うようなものです。
結局視聴率競争で苦戦が続き、3カ月くらい経つと、しれっと芸能スキャンダルを放送して、元の放送内容に戻ったりしていました。
もっと根本的な変革を起こさない限り、この負のスパイラルからは抜け出せないと、幾度となく痛感していました。
扱うことがらの重要性や重大性といった要素を、仮に「ニュース性」という言葉で表現するとしましょう。
例えば政治や経済のニュースには、なかなか視聴者は興味を抱いてくれません。
しかし、多くの人の生活にこれほど大きな影響を与える重要なテーマはありません
税金のありかたやその使われ方、そして今後の経済の行方…。
人々が分かりにくくて興味を持たない、すなわち情報の受け手の感情があまり刺激されないようなテーマについても、実はメディアは伝えなければならないのではないか。
しかし、ワイドショー戦争においては、このニュース性という要素はほとんど重要視されませんでした。
すなわち、どれだけストレートに、即効性がある形で、視聴者の感情を刺激し、働きかけ、行動に影響を与えるかということの方が、メディアとしての力を、わかりやすく表現できるからです。
日々戦争ですから、目の前の結果を求めるのは、当たり前ことです。
芸能人のスキャンダルを見ながら、思っていたよりも酷い男ねとか、なんて身勝手な女なんでしょと、感情をわかりやすく刺激することの方が、近視眼的には、人々の記憶に残り、視聴者の行動に影響を与え、そして何よりも視聴率を取るというビジネスモデルにおける最も大切な要素を満たしていました。
その競争は、激しさを増していくばかりでした。
ワイドショー戦争には、先ほどのような大きなマイナス面がつきまといました。
世の中から大きなバッシングを受けることになりました。
人間の奥底にあるドロドロとした感情を表に出して、これでもかと言うほど見せつける、そんな不快感に、みんな辟易としていました。
今でも最新のインターネットというプラットフォームには、「迷惑系ユーチューバー」と言うものが存在します。
不快な感情を刺激しても、再生数を稼いでしまえば構わないというあり方は、実は当時のワイドショーの悪い面を見せつけられるようで(そこまで酷くはなかったと思いたいのですが)、感情刺激競争のさらされるメディアというものは、いつも同じ轍を踏むものだなと感じます。
そもそも、ワイドショー戦争を言い換えると「ネタ戦争」だったということが言えます。
少しでも刺激的なネタを見つけてきて、少しでも長く放送する。
これこそが、ワイドショーを戦う上で最良の戦略でした。
そして、この戦略こそがワイドショー批判の二大要素、①「下らない内容を延々と放送している」②「取材や放送が人権を犯している」につながりました。
①は少しでも長く放送するから当然そういう批判が生まれます。そして少しでも長く放送するためには、しつこく取材し、ときには対象者のことについてかなり踏み込んで表現されるという構図に陥り②の批判につながりました。
そこには、伝えるメディア側(番組)の人格を考えるなどという余裕はまったくありませんでした。
長期的な展望などまったくないまま、次の日の放送をどれだけ刺激的な内容にするか、その刺激的な内容を少しでも長く放送するか、それしか眼中にありませんでした。
わたしは、先ほど申し上げた通り、そのワイドショー戦争の指揮官の一人として、戦ってきました。
そんな反省点から、「とくダネ!」という番組を立ち上げ、ワイドショーとは違った価値観を持った番組を作り上げたというのが、自分のテレビマン人生において最も大きな足跡といってもいいでしょう。
本当の意味で悪しきワイドショーから決別するきっかけを作ったのは「とくダネ!」だと思っています。
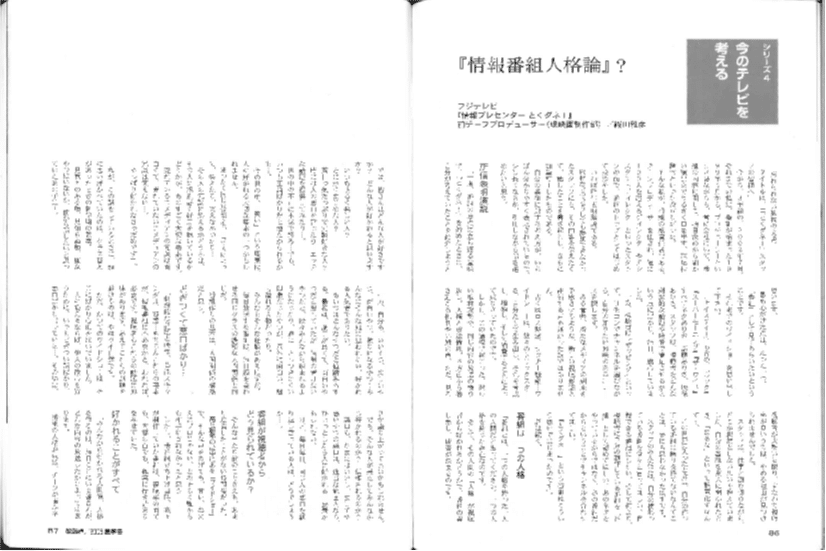
その中核に据えたのが「番組人格論」という考え方です。
すなわち、番組は人格を持った存在であり、その人格を視聴者に好感をもって受けいれてもらおう。
番組に対して好感という前向きの感情を、恒常的に情報の受け手に感じてもらうことによって、伝える情報の印象をより強くして、番組の能力を最大限、発揮しようという戦略です。
例えば、当時のワイドショーは、月から金まで毎日2時間、午後も合わせると4~5時間放送していました。
月~金の平日で、これだけの時間、顔を合わせるといえば、学校における人間関係に例えることができます。
どんな人が、クラスのみんなから好きになってもらえるのか、というテーマを番組の制作スタッフに投げかけました。
みんなに聞くと、だいたい「面白いやつ」という答えが返ってきます。
当然、番組は面白くないと話になりません。
ただ、その面白さということには、様々な意味があります。
表面的に笑いを誘うような面白い冗談を言える、ただ、それだけではありません。
その冗談には、知的なセンスや優しさ、思いやりといった様々な要素があるほうが良いに決まっています。
どうもそれまでのワイドショーは、人を傷つけても構わない、面白ければいいだろう、そんな人格だったと思います。
皆さんもそんなやついたな、とクラスメートを思い浮かべると思います。
その場では表面的に面白がってつい笑ってしまうけど、じゃあ来年のクラス替えのときに、もう一度そいつと同じクラスになりたいかどうか、皆さんどうですか。
信頼できるというのも、重要な要素になります。
先ほど「ニュース性」という言葉を持ち出しました。
大勢の生活に関係していて、表面的には大きく感情を揺さぶられることはないけれども、実はよく考えると、感情を揺さぶられる種は多く含まれているはずです。
そんな情報を、わかりやすく伝えることに、活路を見いだそうとしました。
面白くて、優しくて思いやりがあって、知的で、信頼できる
そんな人格を持った番組で、これまでの面白ければ、目立てばいいやという既存のワイドショーと訣別して戦おうという思いで「とくダネ!」という番組を始めました。
そのきっかけの一つになったのは、番組スタッフが親や友人に自分の担当する番組の名前を聞かれたときに、胸を張って答えられるかということでした。
自分も大学時代の友人と飲みに行ったときに、今どんな番組をやっているのと聞かれたときに、言いよどむことがありました。
それほど、ワイドショーの評判は悪かったのです。
番組の名前を告げた後も、会社員だから、仕事だから、仕方がないんだよと、つい言い訳をしていたような気がします。
このままでは、今の番組を進化させて新しいテレビの歴史を作ってやるというような、気概に満ちたスタッフが集まってくるような気がしませんでした。
さすがにワイドショーというコンテンツそのものが転換点を迎えていることを、理屈だけでなく肌でも感じていました。
番組を「人格」に例えて話しましたが、そういった面では目先の刺激だけを求めて後味の悪さばかりが目立っていたところに、十分つけいる隙があったと言えます。
視聴者から好かれる人格を設定して、その人間が言うことなら聞いてみようという気にさせるというこの戦略は、これもメディアは感情であるという理論の応用になります。
皆さんも好感を抱いている人から言われたことは、大して面白くなくても頬が緩むでしょうし、説教じみていても素直に聞けると思います。
そしてその人の言うことをもっと聞いてみたいと思うものでしょう。
すなわち、人格を伴った存在は、他者の感情を想起しやすいということです。
メディアというものが必ず感情を刺激する競争に巻き込まれるのであるならば、人格を装ったメディアの方が有利に戦えるということが言えるかもしれません。
これが「番組人格論」の本質です。
余談ですが、プロデューサーというのは、何をしているのですかと聞かれることがよくあります。
例えばディレクターという職業は、映像コンテンツを直接作り上げるために撮影したり、撮影を指示したり、編集作業に携わったり…
映像を制作する職人という意味では仕事が具体的でわかりやすく、ある程度想像がつくのではないかと思うのですが、プロデューサーという存在は、何をしている人なのかよく分からないと言う人が多いようです。
皆さんがご存じのプロデューサーといえば、テレビ東京の佐久間宣行(さくまのぶゆき)さんなどが挙げられると思いますが…
彼を見ていると…
ひょっとしてテレビに出演して面白いこと言うのが、プロデューサーなんじゃないかと…。
そのためにはテレビ出演して面白いことを言えるようなタレント性が必要なんじゃないか…。
タレントの知り合いが多いのがプロデューサーなんじゃないか。
よく、タレントを遊びに行くプロデューサーというものが取り上げられたりしますよね。
わたしが考えるプロデューサーとは…
自分がこうしたいと思える番組(コンテンツ)がしっかりあって、それを実現するためにスタッフに方向性をわかりやすい言葉で指し示してまとめあげ、もし新たな人材が必要ならば集めてきて、他にも強化したい必要なところにお金をかける、そのために人事と予算を任されている存在と言えます。
「番組」というミッションを成功させるための総責任者、プロジェクトリーダーと言うことになると思います。
先ほど例として挙げた「番組人格論」によってスタッフの意識をまとめて番組制作にあたるというのは、そういった例の一つになると思います。
担当する番組について、自分が考える理想のイメージを、視聴者が抱くためにはどうしたら良いのかという戦略を、番組スタッフにわかりやすい例を交えながら説明して、それを実践し、実現していく。
そういった仕事が、プロデューサーと呼ばれる職種の一番の仕事であり、これが上手くいったときの快感は、何物にも代えがたいのです。
皆さんも今後の人生で、何か新しいことに取り組むことがあると思います。
そういうときに、この話を思い出していただければ、幸いです
幸いのも、「とくダネ!」という番組は成功して、こういった月曜日から金曜日まで放送される帯番組としては、異例の長寿番組となりました。
2年前の2021年3月までの22年間にわたって、番組が続くなんて、始めたときは思いもよりませんでした。
そして、多くの似たような番組、フォロワーを生み出しました。
ニュース系情報番組というカテゴリーの番組は、今でも「ひるおび」「モーニングショー」「ワイドスクランブル」などには、この「とくダネ!」が始めた改革が色濃く反映されています。
そろそろ結論に参りましょう。
メディアとは感情である
逆に、人間の感情を刺激するものを「メディア」と呼ぶのはどうだろうとすら思っています。
メディアというものの定義は、曖昧でなかなかしっくりくるものがありません。
もちろん「感情」というのも曖昧模糊としてなかなかつかみにくいものであることは、言うまでもありませんが。
メディアから見ると、「感情」と「記憶」が等価と申しましたが、さらに「メディア」もイコール感情ということで等価に見えていることになります。
というか、同じ平面上に乗っているように見えます。
メディアによる情報が入力されて、途中の関数に感情があり、そして出力として記憶という形で定着していく。
そんな図式を、このところよく思い浮かべています。
最初に将棋の世界は、すでにAIが人類のレベルを大きく上回って、2017年を最後に、もう人間とAIが戦うことはショーとして成立しなくなりました。
言ってみれば、シンギュラリティ(特異点)を迎えてしまった状況です。
ちなみにシンギュラリティ=特異点とは、理科系の皆さんに説明するとしたら、微分不可能な点ということですよね。
微分すると無限大に発散したり…滑らかな曲線ではなく、折れ曲がっていることを意味します。
それくらい様々な状況が一度に急激に変化することを指しています。
最近目にしたインタビューで、現代最強の棋士の一人である渡辺明さんは、土日ですら研究に充てなければ、最新の考え方に就いていけず、脱落してしまうと言う趣旨のことを述べていました。
意訳すると、最先端の将棋についていくためには、朝から晩まで休みなく研究に打ち込まなくてならないほど非人間的な生活を強いられるということになるでしょうか。
人間よりも圧倒的に強くなってしまったAIは、その時点ではこれ以上ない「正解」を与えてくれる存在になりました。
(「その時点ではこれ以上ない」と持って回った言いかたをしたのは、将棋AIが毎年のように進化してますます強くなっていく中で、その時点の正解が、翌年には変わっているかもしれないという事情によります)
“シンギュラリティ以前”のことを思い起こすと、棋士たちは皆、正解が与えられていない中で、少しでも正解に近づく考え方を身につけるために、脳を鍛えることを主眼に取り組んできました。
実力をつけるために、古くから様々な方法で訓練を重ねてきました。
藤井さんもそうですが、数多くの棋士は、若い頃から詰め将棋を多く解いて、読みの訓練をしてきました。
深く早く読む訓練こそが、プロ棋士の実力の源泉というのは、決して間違っていません。
また偉大な先人たちの棋譜を実際に将棋盤に並べて、その感覚を身につける「棋譜並べ」というのも、多くの棋士たちが取り入れていた勉強法です。
しかし、これらに必死で取り組んでも、どれだけ効果があるのか、実はよく分かりません。
奨励会という組織に身を置いたプロの卵たちの中で、こういった努力を怠っていたという人はいません。
血の滲むような努力もむなしく、プロ棋士になれないまま、去って行った人たちの方が圧倒的に多いのが、プロの将棋の世界です。
もちろんあるとき突然、努力が報われることもあるでしょう。
何かのきっかけをつかんで飛躍することもあると思います。
しかし必死で取り組んで努力したとしても、報われるとは限りません。
元々能力が高い強い棋士を相手に簡単には勝てない、それも残酷な事実なのです。
学生時代、皆さんは国語の勉強、どうしていましたか?
皆さんは理科系ですけど、「国語」が得意だったという人いませんか?
手が挙がりませんね…。
漢字を覚える? ことわざと覚える?
そうですよね。
でも、試験において得点の比重が最も大きいのは「読解力」を問う問題ではなかったですか。
この「読解力」をどうやって身につけるかという課題に、皆さんは頭を痛めませんでしたか?
よく「本を読みなさい」とか言われました。
でも読解力がついたかどうかなんて、なかなか実感できない。
仕方なく、漢字を書き写したり、ことわざ辞典を眺めたりしていませんでしたか?
将棋が強くなるということも、よく似たところがあります。
どのように考えれば、自分に有利な局面に持って行けるのか。
駒の損得、駒の働き、玉の位置、攻めの急所、守りの強さ…
始めて出会う局面で、様々な要素をどのような捉えるのか。
その考え方を組み合わせたり、優先順位をつけたり、その試行錯誤の中で正解が分からないまま、手を選んでいくのです。
この力は国語における読解力と同じで、様々な局面について常に考え続け、訓練し、感覚を磨くことによってしか身につきません。
読解力と同じで、一朝一夕では将棋の能力は向上しません。
しかしAIの登場によって状況は劇的に変わりました。
必ず試験に出る(国語の)問題の「正解集」が全員に配られました。
脳を鍛え読解力を身につけて試験にのぞむよりも、その問題の答えをできるだけ多く覚えてしまった方がよい成績がとれる、そう考えても不思議ではありません。
“シンギュラリティ”を迎えた将棋の世界は、そういった状況を迎えています。
試験に臨む際に、どれだけ多くの正解を覚えているのかというが成績に直結する。
しかしその問題の数は、基本的に将棋の手の数だけあるので、無限にあると言えます。
それでも、試験に出る可能性が高い問題から順番にその正解を覚えるという作業に、皆忙殺され始めています。
自分が詳しい戦型に誘導するというのも、昔からある作戦でしたが、さらに露骨になり、深いところまで覚えていることが勝敗を分けることも今では当たり前のようになりました。
それが最初に触れた、渡辺さん曰く、土日もパソコンの前から離れられないという状況を生んでいるのです。
その渡辺さんは、130万円もの大枚をはたいて最新型のパソコン購入したのですが、冬の寒い日でも、スイッチを入れるとまったく暖房がいらないそうです(笑)。きっと電気代がすごいことになっているんじゃないかと思います。
それだけでも、どれだけ高いスペックの巨大マシンなのかと想像させられてしまいますが、もしそのマシンが出した答えが、これまでのものよりさらに正解に近いということになると、どれだけ高くても買わざるを得ません。
ちなみに藤井さんは、パソコンを組み立てるのが趣味ということで、一足早く個人で揃えられる中では最高スペックのパソコンを一式、自室に導入しています。
ここで勘違いしてほしくないのですが、藤井さんが強いのは、考える力、思考力の深さや速さが、詰め将棋などの訓練によって研ぎ澄まされ、だれも到達できないようなレベルに、彼一人だけ達したことによります。
それは脳内将棋盤というキーワードで、彼の思考法を検証した結論からも明らかです。
将棋AIが無かったとしても、同様に強いのは間違いないと、他の棋士も口を揃えて言います。
しかし、将棋の世界を広く見回すと、出題されるであろう問題の答えを際限なく覚えて試験に臨むということが、主流になりつつあります。
それも“シンギュラリティ”を迎えた世界の一面だと思わされます。
そもそも「将棋が強い」ってどういうことを意味するんでしょうか?
もちろんシンギュラリティ以前は、人間同士で将棋を指して、勝った方が強いということに疑いを持つ人はいませんでした。
AIと人間の戦いは、人間が白旗を揚げることによって、完全に終止符が打たれましたが、AI同士の戦いは、その後も続いています。
新しいバージョンは、前のバージョンに8割以上の勝率を収める。
そしてその進化は今も止まることを知りません。
最も将棋が強いのは、AI同士の戦いの中で勝利を収めた、そのAIの開発者なのではないか?
そして、そのAI開発を支援したり、そのAIを購入したり、そういう人間のことを「将棋が強い」というのではないか。
そんな風に、どこか価値観が揺らいでくるのです。
今後、様々な分野で“シンギュラリティ”を迎えることでしょう。
その際には、何が変わり、何が失われていくのか…
それを見つめ続けて行く必要ありそうです。
アメリカの未来学者レイ・カーツワイルが、2045年にシンギュラリティが起こるといったのは、ご存じの通りですが。人間と同じような使われ方をする汎用型のAIというものは、今の技術の延長線上にあるのでしょうか?
少なくとも、「感情」という要素を上手く表現出来るAIは、今のところ見当たりません。
人間の顔の表情を読み取って、感情を読み取ろうとする試みがよく取り上げられますが、どうも隔靴掻痒な感じで、わたしには本質に迫っているようには感じられません。
感情は脳の中で起きていることですから、その脳の中での反応を上手く反映させなければ、本質には迫れない気がしています。

メディアから見ると、感情と記憶は等価に見えるといいました。
そこにメディアも含めて、その3つは同じ平面上にあるのではないかとも言いました。
すなわち、入力はメディアが伝える情報、
そして感情という関数を経て、
記憶というかたちで出力があるのではないか。
ならば、メディアの伝えた情報と記憶の関係性を示すビッグデータが得られるならば、学習によって、その中間にある感情を表わすAIが作れるのではないかということです。
メディアで伝えられた情報が、どのように記憶されているのかというビッグデータを集めることは、口で言うほど簡単ではないかもしれません。
記憶と感情の関係について詳しく知りたいと思い、関連する論文に数多く目を通しましたが、何をどのように記憶しているかという検証については、どれもサンプル数が少なく、感情との関連付けの実例も含めて、「なるほど」と納得するものになかなか出会いませんでした。
しかし、メディアと感情、記憶というこの構図はメディアで働いたことのある人なら、意外なほど違和感なく受け入れてくれます。
そういう意味では、試してみる価値はあるのではないかと思っています。
今はスマホでニュースや情報を知る機会が飛躍的に多くなっています。
そのことを考えると、情報へのアクセス履歴とその後の記憶を確かめる調査、その二つが可能ビッグデータとして揃えば、感情を持ったAI(人工知能)の開発が飛躍的に進歩するのではないか?
携帯キャリアのデータに、パソコンの履歴、テレビの視聴データなどそれ以外に接した情報も集め、さらに持ち主の記憶を継続的なアンケートで探る大規模な調査を行うことが出来れば…
少なくとも今まで無かった人格や感情を感じられるような不思議なAI(人工知能)が誕生するのではないか、そんなことを夢想しています。
皆さんの中で「感情」という言葉を上手く説明出来るという人はいますか?
わたしが「感情」とは、「人間の記憶に作用するもの」という説明をしたら、皆さんは驚きますかね。
確かに皆さんがこれまで長年にわたって抱いてきた「感情」という言葉の意味合いを、厳密に表現していないのかもしれません。
一方で、このように定義し直すことによって、始めて定量的に扱うことができるようになるのではないでしょうか。
これによって、感情を持ったAIの実現という意味で、今までのアプローチよりも良い近似値が得られるのであれば、十分取り組む価値があるのではないか、そんな提案になります。
隔靴掻痒な感のあるAIにおける「感情」という要素が、より具体的に、より現実的になるのではないか。
捉えどころ無い「感情」という単語を、人間の記憶に作用するものと定義し直す作業によって、「感情」を実装したAIが実現できるのではないか
この仮説について、皆さんはどう思われますか。
これからの時代、とくにAIが様々な分野で次々とブレイクスルーを起こしていくような時代を迎えて、文化系とか理科系とかという分け方は、あまり意味がないのではないかと思っています。
理科系であっても、今後は間違いなく「感情」というような曖昧で、つかみどころのない実態が見えにくいものを自分なりに理解して、それを表現する方法を探らなければなりません。
文化系であってもAIの仕組み、画像認識やそれに伴う深層学習(ディープラーニング)などの概念を理解することは避けて通れません。
最後に、学生の皆さんに一言だけお伝えして終わりにします。
今後AIが社会においてさらに重要な位置を占めることは間違いありませんが、そんな中で皆さんは人間として、感情というものを(AIより)さらに深く理解する必要があります。
そんな人の感情を上手く読み取る訓練として…
「身近な人に好かれる努力」をしてみてはどうでしょう?
そうすると、思っていたよりも人の感情というものが見えてきます。
ひょっとしたら、就職の面接には役立つかもしれません。
わたしのチームの部下には「身近な人に好かれる努力」をするように求めました。
実は先ほどの「番組人格論」と密接に関係しています。
番組に関わるスタッフ一人一人が身近な人に好かれる方法を実践し、一人でも多くの感情を推し量ることを学んでいくのです。
それを積み重ねていくことで、数百万人から数千万人という大きさになる視聴者というマスの気持ちを、より正確に把握していくことができるようになるのではと考えていました。
スタッフ一人一人の努力は、そういったスタッフが集合体となって作り上げる番組の人格に、必ず影響を及ぼすはずです。
こういった戦略によって、視聴者から好感を持たれる人格を持った番組を作り上げようとしました。
チームの雰囲気は良くなるし、何より仕事の効率が格段にアップしました。
これから様々な分野で、特にAIにおいて「感情」は重要なテーマの一つに間違いなく、なることでしょう。
その感情を感じ取る訓練こそが、新しい発見をするきっかけになり、ブレイクスルーにつながるのではないか。
人から好かれる努力、どうです、絶対に損しない、そして明日からでもできる、実に簡単なことだと思います。
皆さんいかがでしょうか。
すこし大人の説教臭い話で、終わりにしたいと思います。
