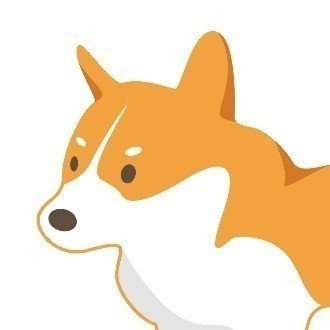GHP2020プログラムの実践研修に参加した
前回の記事
開催概要
実践研修について
昨日と今日は二日間の実践研修だった。
実践研修は下記の内容を行う
次の実践研修はこの内容
- 災害時のシビックテック
- 災害時に活用されるデータ
- プロジェクト運営
この会のコンセプトとしては
技術的に強い人が引っ張るのではなく、チームで課題を解決できるようになる演習をするということだ。
> 「うまくいかないことがあってもそこから学べることは多い」という点にフォーカスした学びに特化したプログラムです
できるだけ実際の災害の場面に近く、初対面同士でどうやって被災者のニーズに沿った活動やサービスができるかが大事になる。
参加者紹介みていると、自分のいる分野と違うから
— まりーな (@marina10172013) February 20, 2021
普段出会えない経験を持っている人多い〜話聞いてみたい#ghp2020
ちょうど先日、東北付近ででかい地震が起きたので、身が引き締まる思いがした。
先日の地震で改めて情報と準備大事だとわかったので、
— まりーな (@marina10172013) February 20, 2021
緊急時にどうすればいいか、何を伝えればいいか、どう伝えたらいいかを考えたい#ghp2020
印象に残った講義
>「なにか困り事無いですか?」→具体的に何ができるかわからないから課題を口に出せないということがわかった
>技術からはいっても、課題を直ぐに解決できないことはある。
>現場に行く、現地の人達と話して、何に困っているのか、一緒に活動して、手を動かしてみる
>得意分野はそれぞれ違う
>だからこそ、全然分野が違う人と組んでみて課題解決をする練習をしたほうがいい
上記はほんとに普段の仕事でも巡り合う話だが、
自分がなにか作るときは、使う人と同じ体験をして、こういうの自動化できますよ、こうすると便利ですよと提案してツールをつくるように意識している。
上から目線で、それこれでできるのになんでしないんですか?ではなく、なにか事情があるのでは?という謙虚な姿勢でまずは自分で取り組んでみる。それから自分が不便に感じたことを技術で解決できないか考えてみる姿勢や行動が間違ってはなかったのではないかと思った。
私は技術に自信が多いになるエンジニアではないが、人に寄り添う姿勢や、何を不便と感じているのだろうと検知して、コミュニケーションをとって教えてもらい、課題を解決できるようになりたいと思っている。そういう強みのあるエンジニアでもいいのではないかと思った。
G空間人材の目標
上げられた目標は下記だ。
1.1人のスーパーマンではなく、コミュニティ・チームの力で役割分担をしながら解決する
2 ステークホルダーの深い課題理解に務める
3. 素早くプロジェクトを立ち上げる。完成形を目座椅子のではなく、ツールやデータをマッシュアップして、出せるものから素早く出していきながら、段階的に改善のサイクルをまわす
4. 素早くデータを収集する。可視化する
防災科研の話
「災害時のシビックテックと扱われるデータ」を聞いている
— まりーな (@marina10172013) February 20, 2021
国立研究開発法人 防災科学研究所の紹介
- 地震計 南海トラフ改定地震津波観測網(N-net)の構築
↑地震速報はこれで検知しているんだって!
- 実験施設
- 災害が起きたときにどうするかを考える#ghp2020
災害が起きたときにこそありがたいと思う組織だ・・
こうやってなにか起きたとき準備してくれている方々がいるから、日々の生活を安心して遅れている
この前の地震が起きたときも検知してくれたのかな?
ありがたい・・・・・
防災科研はブランディングに最近力を入れているとのこと
ロゴの意図やコンセプトが素敵だと思った。
例:茨城県では
— まりーな (@marina10172013) February 20, 2021
浸水面積・浸水建物数の計算
↓
住宅課: 必要仮設住宅数の算出
め・・めちゃくちゃ大事じゃん・・・#ghp2020
N2EMの組織
— まりーな (@marina10172013) February 20, 2021
バラバラに点在する情報
公開場所,フォーマット、公開・更新時期が異なり、
自動収集は困難
↓
人力が必要
解決策
災害対応に必要なデータをみんなで作ろう
ボランティア団体N2EM(ネム)が誕生#ghp2020
課題
— まりーな (@marina10172013) February 20, 2021
1.収集はまとめて行うことができない
電子ファイルや紙媒体 &市町村ごとにすべて内容が違う
2.避難所名称表記ゆれ
3.自治体ごとにデータの個性がある
4.PDFや画像ファイルで渡される
ひ〜〜〜〜〜〜〜厳しい・・・・・・・😱#ghp2020
データをさばくのは、まず整えてからというのがすごい手間だなと思いました・・・・・・・・・
実践研修について
これも詳しいことは権利周りがはっきりしてないので、ぼかして書いておく。
本日は終了〜
— まりーな (@marina10172013) February 20, 2021
知らない分野&緊急時は何が起きるのか、どうしたらユーザーは嬉しいだろうかを議論できて良かった
自分が体験したことがないことは想像で補うしかないから、今から子持ちの場合の被災体験を読んでユーザー調査をしてみる#ghp2020
【Geospatial Hacker's Program 2020 東日本技術者向け実践研修】次はAチームの「おむつバンク-災害時新生児用品支援マッチングサイトー」の発表です。地図上にマップした避難所毎に物資のニーズ・供給の情報をリアルタイムに反映するマッチングサービス。#ghp2020 pic.twitter.com/IXLjx7ooLV
— Geospatial Hackers Program (@GeospatialP) February 21, 2021
コミュニケーションデザインを担当
最初の方のチームビルドや、情報整理、ユーザー調査、ペルソナ設定などをやりました。
最後は10分でロゴをつくり、最終発表をしました。
個人的な反省
プログラムを書いてみたかったが、あまりにも地理情報は分野知らずで可視化にあたって技術的な見通しが自分に立たなかったということだ
とはいえ最終発表をみると
他チームのアイディアは地理情報の可視化というよりは、実際に災害に遭遇したときに何があったらよいかという視点でサービス開発をしており、
普段の開発や個人開発での延長で技術を考えても良かったなと反省した
今回の演習では
初対面で、それぞれ異なるバックグラウンドでチームを組む
↓
実際の災害に近い状況を再現し、
チームビルド、共創や、うまくいかない感、コミュニケーション、開発を実感するを体験できた
これは個人開発では絶対できない体験で、参加できてよかったなと思う
今回自分のチームでは超ベテランがいらっしゃり
こういうデータが無いのかなという話になれば、こういう事例があるという情報を共有してもらえた
専門家の知識を引き出す、共有してもらうように場を作るにはどうしたらいんだろうな〜と思った
チームの反省一部引用
役割分担は適切だったか・他にどんな役割が欲しかったか
- 既存のシステムの開発という観点から、バランスよく役割分担ができていたと思う。
- スピード感のある実装のためには、なるべく早くに役割分担できて、並行で作業が進められるのが理想。そういった意味では今回はディスカッションにかけた時間が長かったかもしれない。
どのような知識・スキル・データがひつようだったか
- 今回、既存のサービスをベースにしたのは有効な方法でしたが、もし新規に作る場合にはどのような技術やプラットホームを使えば素早く実装ができるのか、常日頃から意識していないと難しいと思いました。いつも使っている環境は無料で使えなかったり、以前無料だったものが既に無料ではなくなったりしていたので。
技術・デザインについて
これまで参加したハッカソンにデザイナーはいませんでしたので新鮮でした。
他チームの発表について
詳細は権利関係が絡むので、書いてよいのかどうなのかわからなかった。公式ツイッターで明らかにされている範囲内で掲載する。
【Geospatial Hacker's Program 2020 東日本技術者向け実践研修】Cチーム「聞き取り上手」のデモです。#ghp2020 pic.twitter.com/IBGJQKwwb3
— Geospatial Hackers Program (@GeospatialP) February 21, 2021
【Geospatial Hacker's Program 2020 東日本技術者向け実践研修】次はBチームの「スソワケ 文京区 ー市民の市民による支援物資のおすそ分けサービスー」です。市民発、それぞれの「あまりもの」をうまく「おすそ分け」し再配置することができるサービス。#ghp2020 pic.twitter.com/DZJuwHXUNl
— Geospatial Hackers Program (@GeospatialP) February 21, 2021
【Geospatial Hacker's Program 2020 東日本技術者向け実践研修】次はEチームの「よりそい(YORISOI)」です。被災時に情報難民となる人・家族に対して、アイコンや絵を中心に必要な情報を届けて安心を提供するサービス。#ghp2020 pic.twitter.com/cfJSpE27bs
— Geospatial Hackers Program (@GeospatialP) February 21, 2021
【Geospatial Hacker's Program 2020 東日本技術者向け実践研修】次はAチームの「おむつバンク-災害時新生児用品支援マッチングサイトー」の発表です。地図上にマップした避難所毎に物資のニーズ・供給の情報をリアルタイムに反映するマッチングサービス。#ghp2020 pic.twitter.com/IXLjx7ooLV
— Geospatial Hackers Program (@GeospatialP) February 21, 2021
【Geospatial Hacker's Program 2020 東日本技術者向け実践研修】Dチーム「多言語対応防災マップ」のデモです。#ghp2020 pic.twitter.com/9K0spEz3tN
— Geospatial Hackers Program (@GeospatialP) February 21, 2021
運営に対して抱いた印象
目標設定と確認について
この研修ではちょくちょく目標の確認が挟まっていてよかったと思う。
技術におぼれがち、技術ファーストにしがちな状態から、ユーザーファーストに戻ってこれるからだ。
進め方について
この研修はアクションに対して、何を達成するのか目的を最初に言ってくれるのがいい
> 質問することであるメリット
— まりーな (@marina10172013) February 20, 2021
> 自分が何をしらないかに気づく
> 「正しい質問」は洗練された思考を生む
> 目の前にある課題を質問の形で明確にできる#ghp2020
質問だけ考える
— まりーな (@marina10172013) February 20, 2021
質問を評価しない
回答も考えない
というワークをしている新鮮・・・
心理的安全性たかまる#ghp2020
プログラムからワークショップまで
初顔合わせの人がワークしやすいようにデザインされている気がする
ツールについて
この会はツール一つ一つとっても何故マークダウン記法をつかうのか
何故このツールをえらんだのかという説明やコンセプトがあるのがいいと思った。
ただ使用するツールは多いので、若干混乱した。最終的には慣れたが。
情報の伝達について
伝えるべき情報が多くて、どこをみればよいのかわからなくなってたというのは課題でした。
体験としては、始める前は文章量が多い開催概要とconnpassをみて、ついていけるように昨年の資料を見て、ハンズオンが始まる前に初心者研修の内容をみて予習して
それでようやく技術者研修のハンズオンについていけるという感じでした。
情報量が多いので、確認するのが億劫になっていたところがありました。
いいなと思ったら応援しよう!