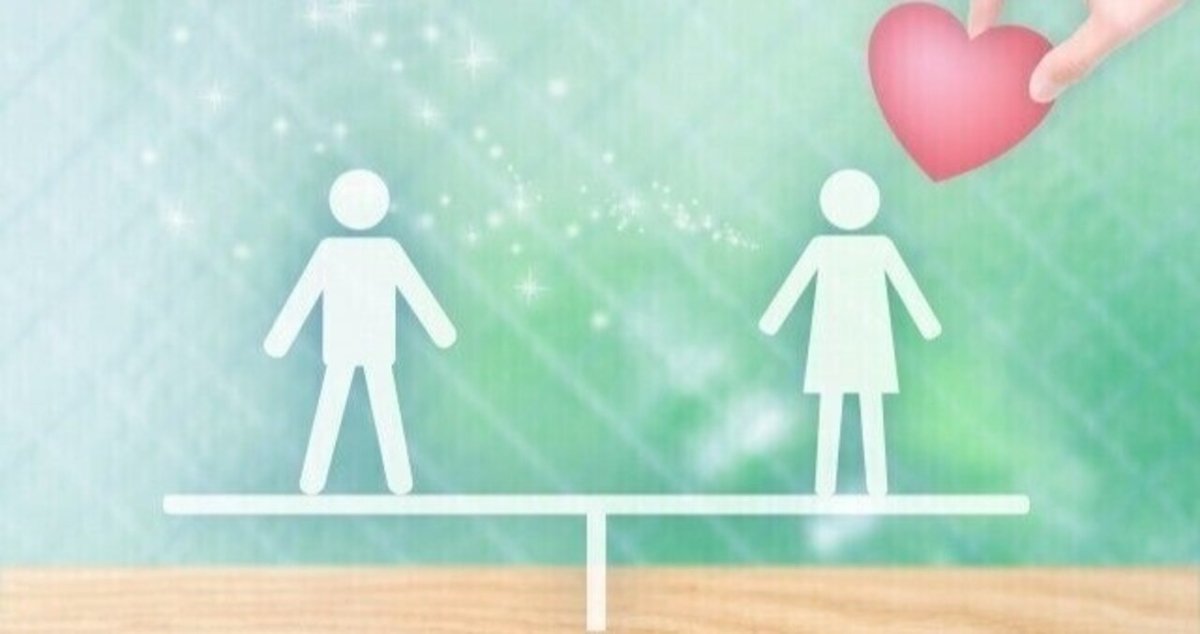
分配の正義
「ふだんづかいの倫理学」という本がある。
平尾昌宏さんが執筆した本だが、すごく読みやすいのだ。文章がやわらかくて、すんなり体や脳に染み込んでくるので、疲れていても読める。
読み進めていくと、「分配の正義と政治」について書かれていた。ちょうど岸田さんが、「分配なくして、成長なし」みたいなことを言っていたので余計に興味が湧いた。
それに、分配にも正義があるんや、と目から鱗だった。なんせ、そんな風に考えたことがなかった。もはや政治の世界には正義はないもん!と思い込んでいた。
嫌みは棚にあげておくとして、分配の正義と呼ばれるものは、何かをみんなで分けるが、ここでは二者関係ではなく、社会全体と個々人の関係になる。
(ここからは、平尾さんの本から引用です)。
そして、二者関係は相互的だが、分配の場合だと、基本的に流れが一方通行になる。
国の予算配分も税金も、イイものも、イヤなものも、すべて社会で分配する。社会全体でみんなの暮らしを支えあう。
その調整の正義を司るのが法であり、交換の正義に関わるのが経済であり、分配の正義を担当するのが政治の役割である、と本の中で平尾さんは述べている。
この3つの正義がうまく働いて、社会を守る正義の味方がたくさんいてくれたら、わたしたちの暮らしも安泰だろう。
・・・・・
ところで、交換の場合には、等価交換で釣り合いをとるし、調整の場合には、罪に応じて罰を与えることで釣り合いをとる。
では、分配はどうやって釣り合いをとる? 分配の正義はいづこ?
ここで、めちゃめちゃ話が逸れるが、どうしても等価交換という言葉で思い浮かぶのは、『鋼の錬金術師』という漫画だ。わたしは、その昔、この漫画にハマった。
舞台となったハガレンの世界では、錬金術が成立するためには、等価交換の原則を満たすことが最低限の必要条件だった。
等価交換とは、交換対象となるAとBの価値が同一であるとする双方の合意によって可能になる。
母を喪って禁忌に手を出した兄弟、兄のエドワード・エルリック、弟のアルフォンスは、人体錬成の代償として大切なものを「持っていかれる」ことを身を持って知った。
「命と等価交換できるものなど存在しない」という真理。
重いテーマだったが、アルフォンスのファンだったわたしは、漫画だけでなく、テレビのアニメもすべて見た。
そして、命について考えた。
つい、じゃあ、新総理の岸田さんは、「命と等価交換できるものなど存在しない」ということをどこまで理解しているのだろうって、考えてしまう。
未だに解決しない、拉致被害者の問題だってそうだ。岸田さんだけでなくて、歴代の総理大臣にも聞いてみたい。
それはさておき、分配の正義だ。
分配の仕方には、「それぞれの人に応じて」というやり方と「全員一律に、同じだけ」というやり方がある。
特別給付金がそうだろう。あれは全員一律の給付だった。「全員が同じ金額だから文句はないよね」という分配の正義だったのかな。
でも、あの分配のやり方に不公平感を抱いた人も多かっただろう。
時短要請に応じた事業者への給付金も、同じような分配の正義だが、やはり、不公平だ。
話は変わるが、わたしは飲み会があっても、飲まない。飲めないのではなく、顔が見事に赤くなるので飲まない選択をする。
しかし、飲み会の参加費は一律だ。どんだけウーロン茶を飲んでも元が取れない。
飲んべえが得する飲み会が嫌いで、個々人の特性に合わせた料金設定をして欲しかった。
それほど、分配、しかも公平な分配は難しい問題だ。
飲み会程度でも、わたしみたいに難しい奴がいるのに、これが日本という国の税金とか、賃金、社会保障なんかの課題になると、国民みんなが自分の正義を振りかざし始める。
「分配なくして、成長なし」 「成長なくして、分配なし」
お手並み拝見!
