
九鬼の記事vol.13(2020.03.09)
0.今週の記事のレビュー
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
「今週の記事のレビュー」では、本記事を簡単にまとめています。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
1️⃣今週の学び:ざっくばらんに書いています。取り止めがありません(笑)。ですが、内容的には、それなりに面白いと思います。ここは無料記事なので、読んでみてください。🙇♂️
2️⃣今週の陸上部・巧のトレーニング:弟のトレーニングを紹介、というか前回の記事の続きになります。トーイング走をやってみたんだけれど。でも、なんかいまいちだって。その理由について考えてみました。
3️⃣今週のオススメ論文:プライオメトリックトレーニング(ここではジャンプトレーニング)が中・長距離選手のランニングパフォーマンスに及ぼす影響について検討した論文を紹介します。パワーが高まったり、全力疾走が速くなって長距離走パフォーマンスも高まったんじゃないかという考察は、僕らの活動にとってポジティブな主張です👏
4️⃣時事ネタ・記事の紹介とコメント:
5️⃣Q&A:
1.今週の学び
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
「今週の学び」では、今週のできごとから九鬼が感じたことについて述べています。主にトレーニング・コーチングの現場での気づきを発信したいと思います。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
今週の学びは、「練習計画の公表」です。すみません、厳密には「学び」ではないですよね(笑)。
コロナウィルスで強制的にシーズンが終了されたランナーも少なくないですよね。。。(泣)。そんなランナーたちに、「高速化してらもおう!」と僕たちで話していました。具体的にはフォームにアプローチするエクササイズとか練習メニューを考えて、noteで発信するのはどうかな、というものです。
そうこう考えていると、ある論文に出会いました。ご縁ですねー。
長距離ランナーのための有酸素性能力トレーニング:伝統からの脱却
Training the Aerobic Capacity of Distance Runners: A Break From Tradition
Anthony Turner氏が執筆されたものを、日本語に訳してくれています。
ざっくりと。本当にざっくりと要約すると(笑)。「筋力トレーニングやパワートレーニングによってランニングエコノミーを改善することができる。さらに、向上した筋力をプライオメトリックのトレーニングによって、ランニングエコノミーに転移させることも重要」と言う内容でした。
Anthony Turner氏は、イギリスの大学で働かれていて、ストレングス&コンディショニングを専門にされている先生です。残念ながら直接お会いしたことはないのですが、彼の論文は多く読んだています。現場の目線を重視された興味深い論文を発表していました。
と言うことで。やはり市民ランナーを高速化するためには、筋力トレーニングやパワートレーニングが重要だと言うことで。でも、実際にジムに行って、、、とするのはハードルが高いので、なるべくその場でできる内容のものを中心に考えています(もちろん、専門のSCコーチについてもらうのがベストですよね)。大まかなイメージはこんな感じ。
(1)エクササイズで必要な部位に刺激を入れる
(2)ジャンプ系(に近いエクササイズ)で爆発的筋力の改善
(3)スプリント系
やっぱり、トレーニングは、「何を目的に・なぜ?」を理解して実施することが重要です。何よりも自分のモチベーションを維持するのに有効です。そこで、その理由づけのところは、フォーム指導のポイントを竹澤さんに説明してもらうことで、より良い練習メニューを提供できると考えています。それは、また後日。そして、今回のオススメ論文もこれと類似した内容になっています。下に書いているので、お楽しみに〜。
そして、今週は4月からゼミ生となる長距離選手の学生たちと簡単な実験(予備実験とも言えません(泣))をしてみました。
購入した1軸フォースプレートを使って
— 九鬼靖太 (@kuki_seita) March 6, 2020
予備実験!というよりは、
機材を使って遊ぼう👏とリバウンドジャンプ測定。
「ざっくり言うと、バネ能力?を評価できるんだよー」と、説明しながら。
試しに、靴を変えながらやってみた。
今話題のヴェイパーで、ジャンプ測定は変わるのか?#大阪経済大学 pic.twitter.com/VUs6geP65G
フォースプレートと呼ばれる実験機材を使って、ジャンプ測定を行いました。このジャンプ測定は、主にヒトのバネ能力?を間接的に評価することができます(大雑把に言うとね。)。で、このジャンプしている学生が履いているのは、ヴェイパーフライ。この前の試技では、ヴェイパープライではない一般的なシューズを履いて同じ連続ジャンプを行いました。つまり、シューズの違い(その他vsヴェイパー)がジャンプ測定に及ぼす影響、を測定しました。
結果は!ヴェイパーフライの方がジャンプの数値が良くて、「仮説通りだー!」と学生は浮かれていました(笑)。そこで、九鬼が「いやいや、これには習熟による影響があるんじゃない?」とツッコミを入れて。じゃあ、もう一度、普通のシューズでジャンプさせてみようとなって再度測定。
そうすると、残念ながら普通のシューズでもほとんど同じ数値が...。そう上手くはいかないよね(笑)って思っていると、ジャンプしていた学生が、「なんかヴェイパーでジャンプしてたら、弾む感覚がわかったような気がする」と言うではないですか!これは僕も考えていなくて、その可能性は面白いね!と。ヴェイパーフライを履くことによって、連続ジャンプに対する即時効果がある、とする可能性はありそうですかね?実際にヴェイパーフライを履いて走っておられる市民ランナーの方々のご意見も聞いてみたいです。
2.今週の陸上部・巧のトレーニング紹介
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
「今週の陸上部・巧のトレーニング紹介」では、九鬼が普段指導しているトレーニングの一コマを紹介します。短距離走のトレーニングを市民ランナーやその他の競技にも応用できるような観点も盛り込んでいきます。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
さて、今日の記事では、前回の記事の続きを書きたいと思います。ちなみに前回の記事はこちら↓↓
前回の記事をざっと要約すると。2月に行われた測定では、ピッチの向上によって疾走速度が高まっていました。さらに、ピッチの向上には接地時間は貢献せず、主に滞空時間の短縮によってピッチの向上が達成されました。つまり、「浮かなくなって速くなった」と言い換えることができます。そして、次のステップとしては、加速区間で努力度を落として加速していくことで、さらに滞空時間を短縮してピッチを高められるのではないか?という仮説を出して。じゃあ、実施にどのようにしてアプローチしていくの?という内容を書いていきたいと思います。
結論から言うと、「トーイングを使った練習」がいいんじゃないか、と思って実施してみましたが。う〜ん、イマイチだな。なんでイマイチと感じたのかを、話していきたいと思います。まずは走った時の動画から。
トーイング走は、なんかイマイチだった。。。
— 九鬼靖太 (@kuki_seita) March 3, 2020
確かにスピードは出るのだけれど、なんか違う🤔
はたしてこれを繰り返して取り入れるべきかどうか?悩みどころです😭 pic.twitter.com/bsWAcYZITz
ここから先は
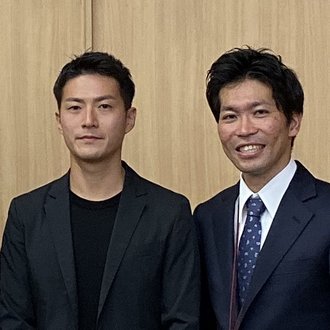
市民ランナー高速化プロジェクト
✅市民ランナー✅指導者・トレーナー✅スポーツ科学を勉強する人、へ役立つ専門情報を届けます👍 知識をアップデートしたい方、僕たちと「オモロイ…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
