
■動画付:課長10100人以上がアクセスした「課長の5役割」です。課長は管理職ではなく『経営職』です。
1.現代では分権型組織が最適
現代の組織で、効果性と効率性を兼ね備えた組織形態は、「分権型組織」です。複数の事業を独立した事業として組織する形態です。適切な規模で編成された分権型組織は、ドラッカーが指摘する、「組織の意思決定は可能な限り意思決定が実行される現場の近いところで実行する」といった組織原則にも沿ったものになります。
そこでは分権型組織の一部を担う課長の役割発揮が重要になります。では、分権型組織における「課長の役割」とは、どのようなものなのでしょうか。それはマネジメント(経営)の機能を最小の単位まで浸透させることです。
2.分権型組織での課長の役割
(1)経営職としての「課長の役割」を考える
♦組織毎にマネジメント(経営)が必要
課長は与えられた目標の達成、言われたことの実行を主要業務とする、主体性に欠けた「管理職」ではありません。これでは組織の機能発揮が不十分になり、課内のモチベーションも高まらず、目標の多くが未達になることは確実です。事実、多くの自治体で未達になっています。
ドラッカーは、「組織全体が事業である。自立した部署のそれぞれもまた事業である。したがって、それらの部署ごとにトップマネジメント(経営)が必要であり、トップマネジメント(経営)としてなすべきことがあり、活動がある」とします(『マネジメント:下』)。
♦課長は経営職
課長とは、所管する分権型の課組織の成果(経営目標の達成)に結果責任のある意思決定者です。よって課長は管理職ではなく現場に近い「経営職」です。
経営職であることから、所管課と共に部全体の成果にも責任があります。各課の成果がなければ部全体の成果もありません。課長とは、所管組織はもちろんのこと、部全体を巻き込んで「住民の幸せ実現」に結びつく成果を出す「部長の協働的経営者」です(下図参照)。

(2)職員の自主性と創造性の発揮から「課長の役割」考える
♦経営職は職員の能力発揮を通じて経営目標を達成する
課長は部長と同じ「経営職」です。両者には「経営職」としての多少の違いはあるものの、経営の仕組みを構築し、職員の主体的な取組からの価値の創造を通じて、1人ではできない組織目標の達成を図るといった、部と課のトップマネジメント(経営)としての基本的な部分は同じです。
例えば、組織の目的である住民を幸せにする組織の価値は、職員の考動から創造され、住民接点で評価されます。部長は経営の仕組みを通じて職員全員に方向を示し、課長は経営の仕組みと、直に個々の職員に接して能力発揮を支援し、組織目標の達成に結びつけます。部課長はこのように所管する組織のトップとしての考動を実践します。
♦職員の能力発揮の方法
その職員は、頭の中にある知識と経験を活用して能力を発揮し仕事を行います。頭の中は外部から見ることはできません。知っているのは職員自身です。職員は自らをマネジメント(セルフマネジメント)し、自らの主体的な考動で自らの能力を活用して成果を産出します。
♦部課長に必要なのは環境の整備と助言
すると、職員の頭の中は見えない外部からの指示や命令は、的外れが多くなり、その過多は本人の主体性を阻害し創造的な能力発揮を妨げます。ここから、部課長ができることは、価値の創造を担う職員のセルフマネジメント(経営)に影響を与えることです。
例えば、課長は、指示・命令は最小にして、主体性の促進と創造力の発揮を可能にする課の経営の仕組みを構築します。内外の変化に対応して組織と経営の基本的な考え方と意義を語り、住民を幸せにするビジョンを明確にし、挑戦的な目標設定を奨励し、心理的安全性を高めて協創を促し、結果の評価基準を明示して、課の経営目標の達成を可能にするマネジメント(経営)の環境整備を行い、必要に応じて助言します。ドラッカーは「リーダー(課長)は言葉と仕組みで人を動かせる人」とします(下図参照)。
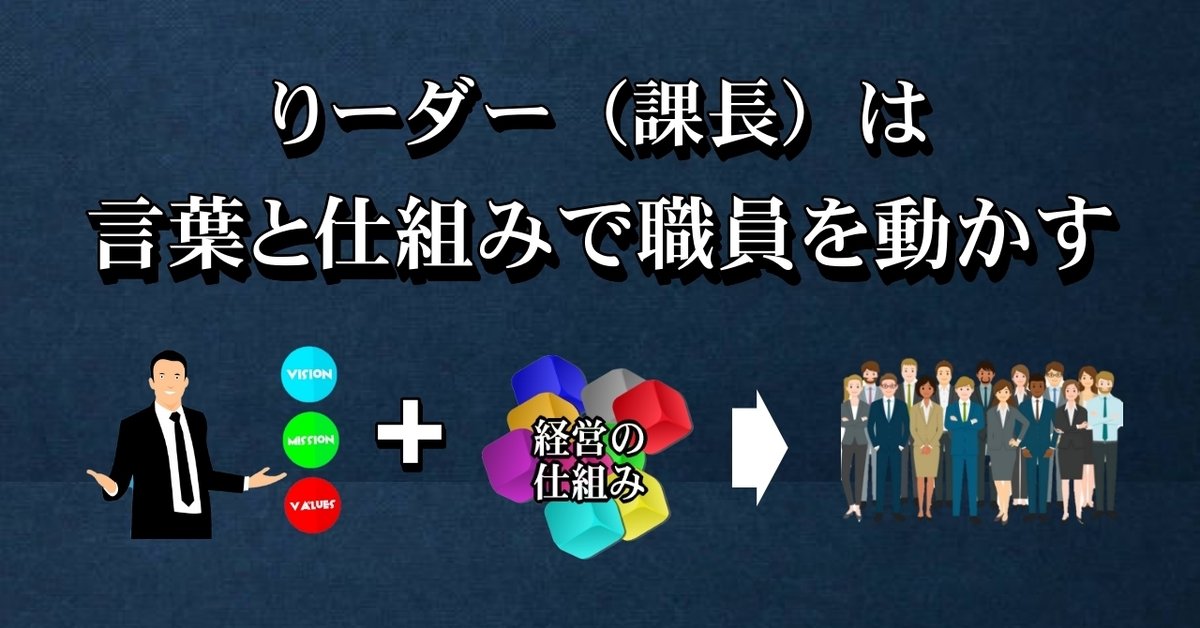
上記の(1)(2)の内容から「課長の5つの役割」を、課長約1万がアクセスした動画(5分43秒)を交えて、以下に掲載しました。ご活用下さい。動画内容とその解説、そして上記内容で課長の中核的な役割が明確になります。課長は管理職ではなく組織の成果に結果責任のある経営の一翼を担う「経営職」です。
3.動画:課長の5つの役割
♦マネジメント(経営)は課長に不可欠な方法論
トップや部長だけでは、組織成果を手にすることはできません。組織の中で一番数が多い、各課の実態をより把握しているリーダーである課長の協働が不可欠です。
よって課長には、経営の基本的な考え方と経営の仕組みを通じて、所管組織に社会の安定と発展に貢献できる成果をもたらす考動が必要です。その方法論として「マネジメント(経営)」があります。
ドラッカーは、マネジメント(経営)は組織に成果をもたらす仕組みとし、そのマネジメント(経営)を活用して成果をあげることが、マネジャー(部課長)の力とします。
♦組織の成果不足は経営職である課長の責任
マネジメントは精神論ではありません。組織をして「住民の幸せ実現」に結びつく成果をあげさせるための経営の基本的な考え方と経営の仕組みです。
具体的には、㋐課の経営者である課長は、自己の役割を理解自覚し、㋑経営の仕組みを構築し、その展開では、㋒経営の基本的な考え方を社会的な観点から語ることで職員のモチベーションを高め、㋓現場での指導・助言を通じて人材育成を図り、㋔職員の能力発揮を通じて最適市民価値の創造を可能にし、「住民の幸せ実現」に結びつく成果の実現を可能にします。
もし現在、成果不足が続いているとしたら「経営職」としての課長の責任です。再度、課長の役割を確認し自身の経営力を高める自己改革が必要です。
―動画:課長の5つの役割―
役割①:課長は、経営の一翼を担う課の経営者です。
役割②:課長は、課経営の仕組み構築の責任者です。
役割③:課長は、モチベーションの経営の仕組み構築者です。
役割④:課長は、市民起点の人材を育成する現場の責任者です。
役割⑤:課長は、市民の声を経営に反映させる市民起点経営の実践者です。
―行政経営総合研究所と関連書籍の紹介―
人口減や成果不足といった「行政経営」に関する課題解決の糸口は必ずあります。お気軽にお問い合わせ下さい。

