
自分の頭で考えないための哲学(前編)
自分の頭で考えるべきなのか
(※この記事は2019/07/17に公開されたものを再編集しています。)

「自分の頭で考えなさい」と、私たちは教えられてきた。学校でも、企業でも、実に色々な場面で。そう教える側にまわった人もいるかもしれない。
「日本社会には自分でイニシアティブをとって動けるだけの自由がないじゃないか」という意見もあるだろう。しかし、“不自由な”場所ですら、「自分の頭で考える」ことが建前としては重視されているはずだ。
自分の頭で考えるというフレーズが、とにもかくにも流通している。そして、誰もそれが何なのかわかっていない。そのこと自体が、自分の頭で考えることの必要性を根拠づけているかのようだ。
私は、いわゆる「哲学者」だ。さりとて、ラーメン屋店主や企業経営者が、「私の哲学は……」と語るそれではなく、私は、専門的な教育を受けた、いわば専門職としての哲学者だ。
繁華街を歩いていて哲学者にぶつかった経験を持つ人は少ないだろうし、哲学者は動物園や博物館で展示されているわけでもない。適当に石を投げて哲学者に当たる確率は、たぶん、宝くじで高額当選するよりも低い。
専門的に哲学を学んだ希少な生物の眼から見ると、「自分の頭で考える」という発想は、あまりにも素朴で、疑わしい。
平凡を生み出すアウトプット
そもそも、「自分の頭で考えた」結果が、創造的だった経験はどれくらいあるだろうか。大抵は、実に平凡で、ありがちな結論に終始しているのではないか。何日も悩んだ成果が、従来言われていることの反復だった経験は一度や二度ではないだろう。自分の経験を思い返してほしい。別に手は挙げなくていいので、心の中でありありと思い出してほしい。
自力思考が平凡なアウトプットに終始するのは、自分が既に持っているものの見方――先入見/偏見(prejudices)――を再提出しているにすぎないからだ。未知の問題に取り組むはずが、実際には、未知を既知へと無遠慮に回収し、自分にとっては当初から明快に感じられていたことを「結論」と考え、飛びついてしまう。
いや、アウトプットが平凡である程度なら害はない。しかし、国内外の事例を見渡すなら、あちこちで景気よく燃えている「炎上」の対象は、当人たちなりに考えた末に出てきた企画であることに疑いはない。実に不用意で問題含みの企画も、正義や道理にもとる方針も、「自分なりに考えた」結果だということを、私たちはシリアスに捉えるべきなのではないか。
どれほど粗雑な意志決定プロセスだとしても、どれほど平凡なアウトプットだとしても、私たちは確かに自分の頭で考えている。どのように、何のために考えるのかということを置き去りにして。
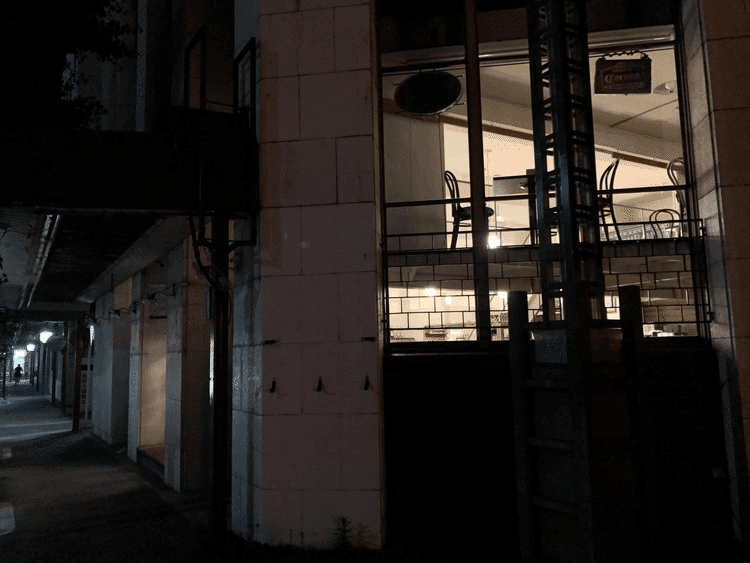
素手で考えるのはいいことか
こういう話をすると、「素手でここまで考えた」と誇ったり、マウンティングしたりする人に出会うこともある。けれど、そうした人の誇る成果の大半は、やはり平凡だ。考え抜いた末に、仮に何か核心的なことがわかった場合ですら、本を読んだり、専門家に聞いたりすれば、数分でわかる程度の情報量だったりすることも多い。
こうした経験そのものは、もちろん貴重なので、ぜひとも積み重ねるべきだ。頭を使う訓練にもなるだろう。しかし、そこでもやはり、自分なりに頭を使うのだということだけが先行して、どのように、なぜ頭を働かせるのかということが置き去りにされている。
私たちは天才ではない
そもそも、私たちの多くは、そして私自身も、天才ではない。善良で平凡な人物か、ちょっと努力のできる秀才程度だろう。そうした人間が手元の知識を転がしても、天才を向こうに張って十分な成果を出せるはずもない。そんな人物が自分で、あるいは、素手で考えても、大抵は予測可能で、ありふれたアウトプットに至るのが関の山だ。
一人ではなく、複数より集まったところで、似た考えと能力の集団なら、やはり同じことだ。あるテーマについて、似たことを考えている人たちが提示できるのは、似た答えでしかない。
だとすれば、私たちに何ができるというのだろうか。
森を歩く技術
最初から答えが見えているわけではない場合、何かを考えることは、未知の場所や未踏の地を前にした開拓者のように、手探りだ。土地を注意深く観察しながら、進むべきところそれ自体を探すことになる。社会人類学者ティム・インゴルドの言葉を借りるなら、考えることは、「歩行(wayfaring)」に似ている(『ラインズ』)。
ジョゼフ・ジャコトという19世紀の教育者は、自分も答えを知らない問題へと生徒たちを案内した。その特異な試みを「森」のメタファーで捉えた哲学者ジャック・ランシエールに倣うことにしよう(『無知な教師』)。私たちが手探りする問題は、その中で歩き回ることのできる森のようなものだ、と。
熟練した森林管理者なら、未知の森からでも、色々な情報を読み取るだろう。大地からは動物の足跡を見つけ、当座の危険や水場の位置を知るかもしれないし、植物の傾きから太陽の位置を読み取り、方位を知るしれない。彼女には、遭難のときの心得もあれば、道具の備えもあるだろう。
しかし、単に森に放り出された普通人が、いきなり手持ちの知識と推論で、同じ情報を得るのは難しい。彼女と同じ道具を与えられていても、使いどころがわからないかもしれない。いずれにせよ、何らかの課題に取り組むときには、鬱蒼とした森を歩くときのように、自分たちの進む先を暗示するような「手がかり」を森から読み取らねばならないのだが、当の手がかりについては、その現場に通じた専門家から“学ぶ”必要がある、ということだ。
迷うことの不安を自分で解消できないのなら、森のどこに注目し、それをどう読み解けば、森を歩く手がかりを見つけられるのか、その手ほどきを受けねばならない。私たちが日々生きる、この現実こそが、人を迷わせる鬱蒼とした森かもしれないのだから。
植物学者や写真家が森から読み取る手がかりは、もちろん森林管理者のそれとは違うだろう。世の中には様々な専門家がいる。そして、専門的な哲学者は、哲学なりの蓄積を利用して、森を歩くための技術を提示することができる。この「学びと哲学」というコラムを通じて、森を読み解き、各人が地図を描くための手がかりの一端を私は提示しようと思う。
後編に続く
2019/07/17
著者紹介

博士(人間・環境学)。1990年生まれ、京都市在住の哲学者。
京都大学大学院人文学連携研究員、京都市立芸術大学特任講師などを経て、現在、京都市立芸術大学デザイン科講師、近畿大学非常勤講師など。 著作に、『スマホ時代の哲学:失われた孤独をめぐる冒険』(Discover 21)、『鶴見俊輔の言葉と倫理:想像力、大衆文化、プラグマティズム』(人文書院)、『信仰と想像力の哲学:ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜』(勁草書房)、『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎)など多数。
