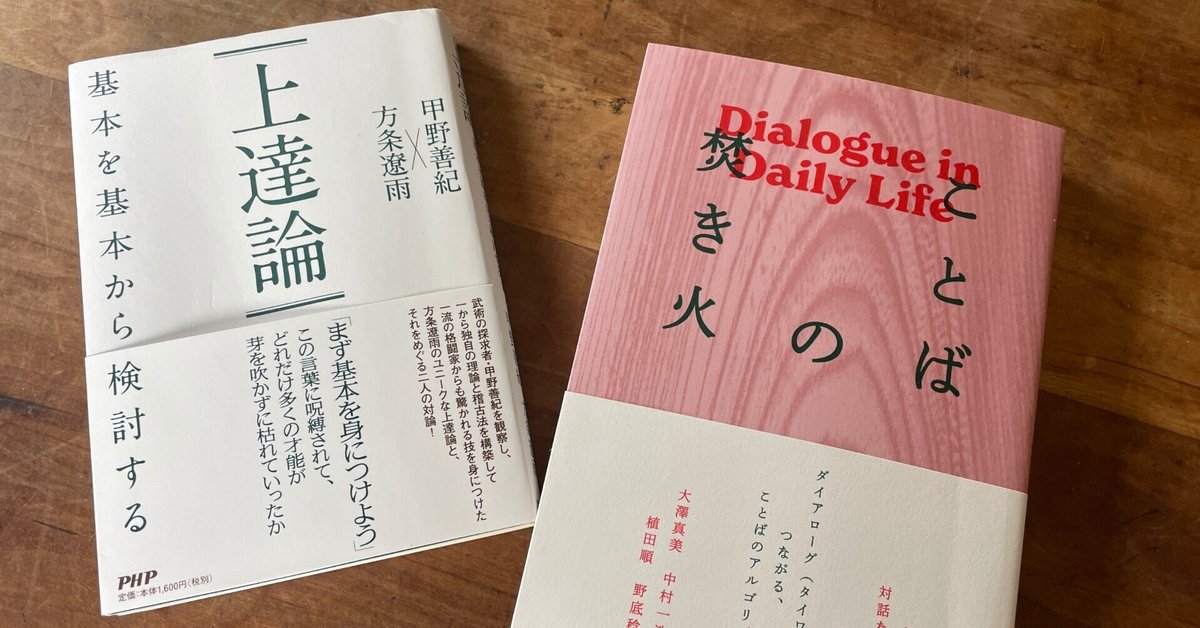
「上達論」と「ことばの焚き火」的対話
「焚き火に薪をくべるように、場に声を出す/置く」という非常にシンプルな対話をしているだけで、人が勝手に変化していく。家族との関係性、仕事への向き合い方、生き方に、手触り感のある違いが生み出されていく。結局これが一番(変化が)早いとすら思う。
一体、これはなんなんだ?その理由の1つを武術研究者 甲野善紀さんを観察して書いた方条遼雨さんの「上達論」に見た気がする。
根本原理組み替えの三原則
自分が依存している癖(パターン)に気づき、それを組み替えて行くために、以下の三原則が挙げられている。
低負荷・・・負荷の少ない環境である事。筋肉が疲労するような重い道具を扱わず、対人の稽古ならば受け手側が全力で阻止するような負荷を掛けない。
低速・・・「ゆっくり」行う事。速度は「ごまかし」となし、自分の動きの「質」を丁寧に観察できない。また、速度を出す事自体も「負荷」なので、「原理組み替え」の支障となります。
単純・・・「単純な道具」「単純な動き」で行う事。道具や動きが複雑になるほどそちらの扱いに意識や神経が偏り、「根本原理」や「癖」にまで思いが届かなくなります。
これを普段対話会でやっている事に置き換えてみると、、、
低負荷・・・言葉を出しても出さなくてもいい。人の言葉は無理に受け取らなくていい。
低速・・・沈黙が続いてもいい。保留しながら、ゆっくり言葉を味わう。自分と対話する。
単純・・・約束事は、普段の役割を脇に置き、「焚き火に薪をくべるように、「焚き火に薪をくべるように、場に声を出す/置く」を意識する事だけ。
この単純な対話の中で、自分のコミュニケーションのパターンに勝手に気づく。「人の顔色を見てしまう」「沈黙が怖い」「バカにされるのではないかと心配になる」「自分に発言なんか取るに足らないような気がする」「人に反応を求めてしまう」「難しいことを話している人がいると、体が硬くなる」「反射的に共感を示すような言葉を出しがち」などなど。
また、自分自身のこと、何が好きで何が嫌いか、何を大切に思っているのかにも気づいて行く。10人で場を囲めば、10通りの世界・10通りの言葉がある。そのそれぞれの発言に共感したり、モヤモヤしたり、ザワザワしたり、イラっとしたり、湧き立ったり。そこで、脊髄反射的に言葉を重ねないで、内にある感情の奥を覗いて行くと、自分の輪郭を手で触れるような感じになる。10人から光が当たって、自分自身がより見えやすくなるかのようだ。
私は、自分が対話の場を持つとき、特にテーマも決めないことが多いし、あまり、説明もしない。それは、やり方を細かく説明したり、言葉を重ねすぎると、頭がそちらに言ってしまい、自分と向き合うという、最も大切な作業がおろそかになってしまうからだ。高負荷・高速・複雑にすると何かすごいことをやった感はするけれど、実がなくなることも多い。
「出来ねば無意味」
「上達論」は、対話とつながることが多くて、首を激しく縦に振りながら、読んだのだけど、「出来ねば無意味」もまさに、自分が大切にしたいと思っている事だ。
「試合が無い事」は「試す事から逃げる口実」に、「平和的思想」が「実戦では通用しない事の言い訳」へと容易に変貌します。
そういった武道界に対し、若き日の甲野先生は苛烈な言葉と共に問題提起し、現在の稽古スタイルを作りあげてゆきました。
その思いを一言でまとめたのが「出来ねば無意味」という言葉です。
どんなに素晴らしい思想を並べていても、本気で抵抗してくる相手に利かない技術は、武術として「無意味」だという事です。
対話会の中で、いかに自他を尊重し、自分の声を場に出すことができても、実生活の中でできなければ、最終的には意味がないと思っている。守られた環境でできているだけでは、仕方がないのだ。
対話会が必要なくなって行く
方条さんは、本の対談パートの中でこのようなことを言っている。
実は、ここ数年「稽古」という言葉にすら、どこか白々しさというか違和感を感じていて、「稽古をしているんだ」と自覚している時間の量がそのまま自分の未熟さであり、武術と一体になっていない部分だなぁという気がしています。そういう意味で、ある種の完成に近づいてゆくほど、道場の上で誰かと組んでやったり、目的を持って何かの動きを磨くような時間は減って行くような気がしています。
対話が日常になると、何をするのも対話の稽古のような状態になって行く。自分、他者、環境は何を言っているのかに耳を澄まし、そこから起こってくる反応を自分の中に見出して、応答するように行動する。まあ、朝から晩まで対話なのだ。
対話を始めると、最初は面白くて、いろんな対話会に行ったり、本を読んだりするかもしれない。でも、それだけでは飽き足らない瞬間が来る。そこから、対話が日常に馴染んでいくのかもしれない。
「楽しい」と感じているうちは、まだまだ武術が「お客さん」なんだなという事です。例えば、「呼吸」とは人間が生きる上で最も重要で、基本的な行為ですけれど、それゆえにもしも一呼吸一呼吸が楽しかったりしたら生活が成り立たない。
この「武術」を「対話」と置き換えても同じなんだろう。
「楽しい」と感じているうちは、まだまだ対話が「お客さん」なんだなという事です。
