
【ヒトコト読書】元サラリーマンの精神科医が教える働く人のためのメンタルヘルス術
【ヒトコト読書】は「ワンフレーズだけでもアウトプット」をテーマに色んな一冊を紹介する記事です。
↓今回はこちらの本
①この本を読んだ理由。
今後のキャリアを考える中で自分の興味を見直し、「働く人の心を支えたいかも…?」という一つの思いが出てきました。
まずは現在、”世の中で人気の心の本”にはどんなことが書いてあるんだろう?と知るために手に取りました。
②本気で支えてくれる先生。

著者は元サラリーマンで精神科医・産業医の尾林誉史さん。
言わずと知れた有名企業、リクルートで働かれていた先生です。
サラリーマン時代、同僚の産業医面談に付き添った際の対応に愕然。
「こんな現状なら、自分がやろう」という思いで医学部に入られます。
日本の医療制度やメンタルヘルスへの誤解から起こる様々な”不合理”に立ち向かい、「患者さんと本気で向き合う」大きな熱意でこれまで多くの方々を支えてこられました。
「しっかりと時間を確保してコミュニケーションをとること」
「身体や心の現状、薬の服用についてもしっかりと説明すること」
これは本書の中からごく一部の紹介に過ぎませんが、一見普通に思えるこのような対応をしっかりと行ってくれる尾林先生。
多くの人を支える根幹には、このような地道なことをしっかりと行ってくれる尾林先生の人間力があるのかもしれません。
③まずはとにかく休むこと。
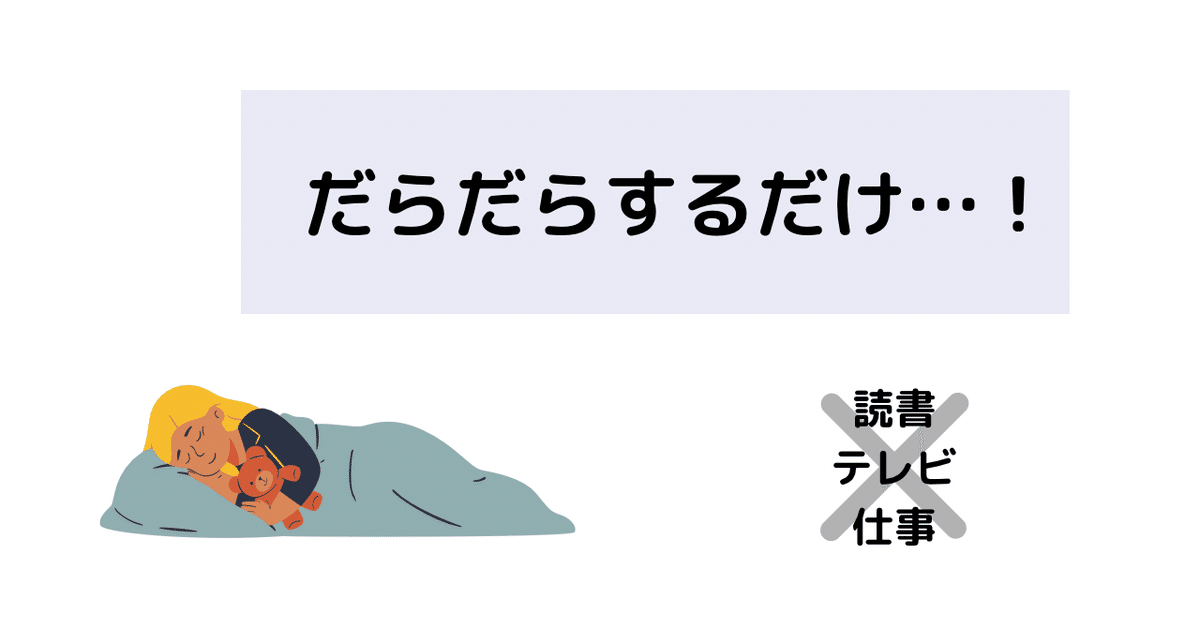
メンタル不調に対する最初の対策は、とにかくダラダラ休むこと。
「ちゃんとダラダラ休む」
ことが第一段階だと尾林先生は書かれています。
簡単なように見えて、実はとても難しいこの「休む」ということ。
メンタル不調に陥る人には周囲に気を遣う人も多く、「こんなに休んでいていいのかな…」と感じてしまうそうです。
まずは1ヶ月〜2ヶ月、読書やテレビも観なくていいので「ダラダラする」ことが、その後の回復にとって重要になります。
④周囲の理解が得られない時には。

「ダラダラ休む」ことから始まり、徐々に段階を踏んで回復していく。
時間をかけて回復へ向かうためには、家族や職場など、関わる人達の理解が必要不可欠です。
しかし、実際に理解してもらうことはとても難しい場合もあります。
周囲の理解が得られない場合は、できるだけその組織からは離れることがベストです。
同居人の理解が得られないならば、一時的な別居も必要。
回復のために周囲の協力は不可欠であり、尾林先生は時に、患者さんの周囲の方々と面談をしてくれるそうです。
患者さんにとっても、この様にお医者さんが周囲に対応してくれるととても心強く、安心できますね。
⑤ボクの個人的な感想。
メンタル不調に対してはまだまだ、世間の理解が追いついていない状態だと思います。
ボク自身、メンタルに不調を感じても「身近な人が本当に自分を受け入れてくれるのか?」と不安を抱いてしまうかもしれません。
尾林先生の様に「ありのままの自分を受け入れ、支えてくれる人」が、現代社会にとってますます必要不可欠な存在となっていく気がしています。
「元には戻らない。前よりもっと、良くなります。」
とても心強い、尾林先生の言葉です。
本書には他にもメンタル不調に関するメカニズムや薬の服用に関してなど、たくさんのためになる知識が書かれています。
ぜひ一度お読み頂き、心のケアに役立ててくださいね。
最後までお読み頂きありがとうございました。次回の記事もぜひご覧ください。
