
【イベントレポ】はじめてのイマーシブシアター③ゲストトーク
長谷川 寧さん
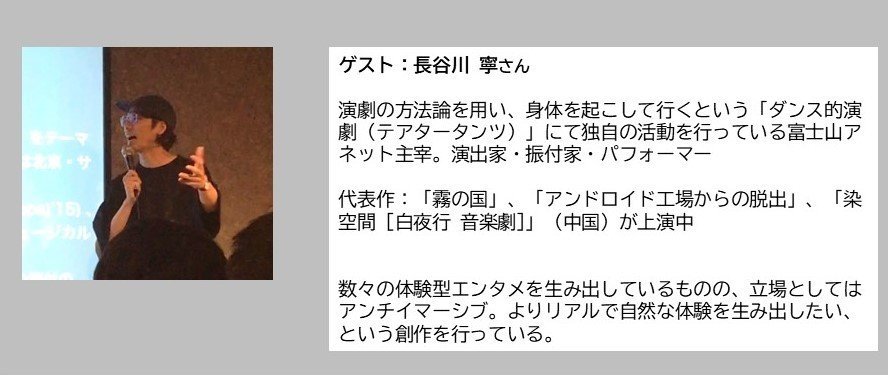
『はじめてのイマーシブシアター』ということでなぜ長谷川さんがイマーシブシアターを作るようになったかということを話してくださいました。
"なぜダンスをやるのか"
長谷川さんが体験型といった形の作品を作られるようになったのは『タプコンダンス』『DANCEHOLE』といった流れからだそう。そもそも『タプコンダンス』を作ったきっかけは東日本大震災でした。
“なぜダンスをやるのか”
そう考えたときに、ダンスで明確な答えを導くのではなく、現実的なリアリティを盛り込むという姿勢で向き合うようになったそうです。その場で質問をされて考える、言葉に反応する、など感覚の延長上にある動きを考えたて『タプコンダンス』『DANCEHOLE』を作り、その流れから脱出ゲームにも関わるようになりました。
脱出ゲームの製作『アンドロイド工場からの脱出』
『アンドロイド工場からの脱出』という今回のイベント参加者の8割以上が体験したほど有名な脱出ゲームは株式会社SCRAPとのコラボ作品で、ペンと紙を使う脱出ゲームが多い中、体だけで体験できるというものを作られました。なぜ今この瞬間にこの行為が必要なのか、という動機性を突き詰めたからです。製作には半年もの時間を費やし、その中で最も大変だったことが
<<長谷川さんは謎に興味がない>>

(余談ですがイベント当日一番写真が撮られたシーンです。笑)
『SLEEP NO MORE』も体験され、目の前でアツイ芝居をされるのが大嫌いだと言う長谷川さんが作品制作上で最も注力しているのはリアリティ、現実感の実現です。
リアリティの追及『霧の国』
『霧の国』という作品は、最初に行われる質問で観客を二つのグループに分け、それぞれのグループごとの体験をさせたうえで、最後に究極の選択を迫るという構成。この選択をするときにはすでに観客はその世界観の中に没入しており、選択をすることによって生じる良心の呵責や嫉妬などリアルな自分の感情と向き合うことになる。
きださんの「長谷川さんの作品は頭脳に直で来るので、じぶんで選ぶ選択肢が生易しいものではないので少しだけ覚悟がいる。」という感想もこのリアリティの追及ならではなのではないでしょうか。
今後のイマーシブ的展望
作る側はやってはいけないこととの闘いとおっしゃる長谷川さん。「触れる系は嫌がるお客さんが多いのですが、僕はどっちかというとやりたいタイプ」とおっしゃるように自由度の高いといいつついまだ長谷川さん的には制約の多いイマーシブシアターにおいてさらに一歩踏み込んだ作品作りを目指されているそう。
*****
村上 大樹さん

“推しに出てほしくない舞台No.1”『私のホストちゃん』
もともとは鈴木おさむさん構成・演出のバラエティ番組をエイベックス株式会社のリクエストにより舞台化。
2013年の初演から毎年公演を重ね、延べ7万人を動員している舞台作品。出演者は一般的にまだ知名度の低い若手俳優たちが主だが、チケットが確実に売れるという作品。ファンの中では”推しに出てほしくない舞台No.1”とも言われている。
『私のホストちゃん』という壮大なシステム
2012年に村上さんのところにエイベックスから舞台化の依頼があった際のリクエストは「ランキングシステムを舞台上で展開すること」というものだったそうです。当時はAKBグループの最盛期でもあり、
・金がモノを言う世界であること
・好きな人にお金を貢ぐ喜びと苦しさ
を体感する作品として構成されたようです。
これらを実現するために、貢ぐシステムとして仮想通貨LOVEを導入し、チケットや物販に付随するLOVEを”推し”に課金するシステムを構築。
作品は前半ではお芝居が繰り広げられ、休憩をはさんで後半は獲得したLOVEの多さで立ち位置が入れ替わるショー形式とする。
ホストちゃんならではのライブ感
・結末がお客様次第
→演技のうまい下手、かっこいい、面白い、に関係なく順位は決まる。
・俳優が本当にホスト
→ホスト=おもてなしの意味でファンサービスがすごい。
・物販の売り上げすらエンターテイメント
→「推しに直接お金を払えるのがよい(きださん談)」ともあって物販には毎回長蛇の列ができる。今までの最高額は〇百万円だとか違うとか。

舞台作品としての成立
応援したいという感情移入をうまく扱った作品であるが、接触イベントではなく、あくまでホスト役のお芝居であることが、役者も観客も世界観に入り込める理由であると村上さん。もしこれが個人としての俳優が出てきたらこの作品の成功はなかったかもしれないと話されます。
村上さんが徹底したのは、必ず芝居を行うこと、アドリブにより過ぎず、きちんと役割を果たすことを役者とともに進めていたということでした。
これらの成功により、『わたしのホストちゃん』は若手俳優の登竜門的作品としても位置付けられるようになりました。
柳田 裕之さん

銀座の街を使った大規模なイマーシブシアタ―
『GINZA THEATRICAL NIGHT TOUR』
銀座に所縁の強い松竹株式会社が、オリンピックなどでインバウンド事業が増えてきていることを受け、海外向けのエンターテイメントを考えた作品。
そもそも諸外国に比べ日本にはナイトライフコンテンツが少なく、夜、銀座、エンタメの3つをコンセプトに構成された。
銀座という街
海外インバウンド向けということで、街を紹介することも重要なイマーシブ作品であり、モダンガール、モダンボーイの闊歩する銀座が最も華やかだった時代の1920~30年代に焦点を当てて製作。
役者は白黒映画から飛び出てきたという設定で、その時代を彷彿とさせるファッション、ストーリーの重要なシーンが行われる場所には1920年代竣工の建物を選らび、実際に飲食まで行われる。
観客は自らの五感で作品を楽しみ街を再発見することができます。
地域との連携
店舗や観光協会との連携には、松竹という企業の力がふんだんに発揮されたと言っていいのではないでしょうか。限られた人した立ち入ることができない和光の時計台がフィナーレの場所だということはその最たるもので、その他にも、作品終了後に再度自分の意志で選んで銀座を楽しめる選択を与えられたり、街と歴史とそして人と、すべてをつないだ見事な作品だったようです。
言葉の壁はあるのか
他の作品との違いは、『GINZA THEATRICAL NIGHT TOUR』は全編が英語だということ。役者は英語日本語どちらも堪能であることが求められたが、観客側は、自由度の高いイマーシブシアターという特性もあり、わからない人に教えたり、話したりということができ、言葉の壁はあまり感じなかったそう。

トークセッション
最後にはトークセッションが行われ、「制作時に気を付けていること」「注目しているエンタメ」「イマーシブのこれからの課題は」など会場の参加者からの質問に答えられていました。
最も印象的だった課題としては、きださんがおっしゃっていた「場所とお金」です。今回のイベントを聞いていても、イマーシブシアターという形式には場所の力がほかの作品よりも強いように感じました。NYの『SLEEP NO MORE』が常設の会場で行われているように、継続して公演し続けられる仕組み(特にお金の仕組み)が、イマーシブシアターの発展にとっては必要不可欠とのことで、その点でも『わたしのホストちゃん』が継続していることは評価されるべきことであるように思います(こちらの作品は場所には縛られませんが)。
*****
私は普段、建築の設計をしています。
自分でもイマーシブシアターの公演に参加したり、このようなイベントを聞いたりして、場所の力の強いイマーシブシアターの会場をぜひ設計してみたいと思うようになっています。普段はなんにでも対応できるようにマルチな四角い箱を作ることが多いので。お仕事お待ちしております~。
いいなと思ったら応援しよう!

