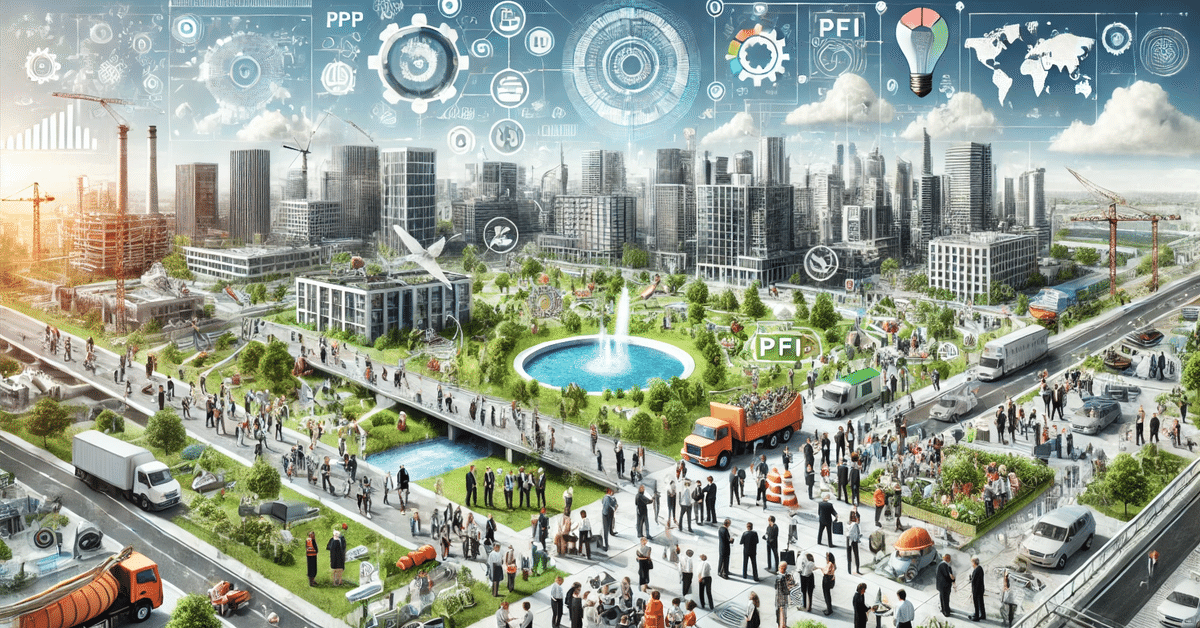
PPP/PFIへの勘違いと「本業での結果」
PPP/PFIの勘違い
なんで行政が金を出すんだ?
業務委託で関わっているある自治体で、当該地に耐震性もなく老朽化した公共施設が存在し、この解体費だけでも数億円を要するなど諸条件が非常に厳しい案件について、首長及び幹部職から「PPP/PFIでやるんだから、行政が財政負担するのはおかしいだろ」と恐ろしく経営感覚のない意見が出された。(色々話を聞いていくと、どうやら議会のドンが頑ならしく、それにビビって自己保身・それらしい?正当化のための「言い訳」としてこう言っているだけらしい)
「PPP/PFIだから行政が金を出してはいけない」論理が破綻していることは、実態としてサービス購入型のPFI事業が結局、サービス購入料としてイニシャル・ランニングコストの(ほぼ)全額を行政が負担する形になっていること一つとってもわかるはずだ。
また、そうした自治体に限って指定管理者制度で天下りの外郭団体を非公募で選定し続け、自主事業を1本もすることなく多額の指定管理料を払いまくっている。
(本来は非常に柔軟でクリエイティブな方法論の一つである)指定管理者制度もPPP/PFI手法の一つなので「PPP/PFIだから行政が金を出さない」に反していないだろうか。
公共資産を活用して民間が儲けるのはおかしい
「公共資産を活用して民間が儲けるのはおかしい」
これも良く聞くフレーズだが、まちとしての総力戦が求められる時代、人の流動性が非常に高く自治体も北海道日本ハムファイターズを巡る北広島市と札幌市に象徴されるように、「選ばれるか捨てられるか」の二択となっている。
行政が成立しているのは、市民・地元プレーヤーがそれぞれのビジネスを展開して利益をあげ、汗と涙と知的財産の結晶である貴重な利益の一部を税金として納税していただいているからである。
公務員時代には議会で「民間と結託しているのでは」といったつまらない声と同時に、なぜか「なぜうちのまちには赤字企業が山ほどあるのか」と同じ議員が口にしていたが、民間が利益を安心してクリエイティブに上げられる環境を作っていくことこそが、シビルミニマムとしての部分だけでなく多様な公共サービスを提供していくためには不可欠である。
そして、公共資産を活用したビジネスを展開していくうえでは、完全な民間ビジネスと比較して非合理的なものも含めて多様な制約条件が課される。そして(Park-PFIでナショナルチェーンのカフェを設置し、周辺の飲食店を駆逐してしまうような民業圧迫型の短絡的なものは別として、)公共資産を活用したビジネスを展開していくためには社会性も求められる。社会性を持ちながら利益を確保していくことは非常に困難なことであるのと同時に、そうしたビジネスモデルで利益を計上できるのは良いサービスをしていることの証左でしかない。
morinekiの大東市ですら・・・
上記のnoteで詳細は記しているが、全国屈指の優れたプロジェクトであるはずのmorinekiの第二期事業が議会で否決されてしまった。
その理由が(正式な議会としての見解は出されていないが、報道・SNS・議会議事録等を総合すると)「第一期の検証がなされていない」ことと「行政が出資しなければいけないプロジェクトは公民連携事業ではない」の2点らしい。
前者はmorinekiのビフォーアフターを考えれば一目瞭然であるが、本当に根が深いのは後者である。
行政が出資する場合には、議会でも決算等でプロジェクトの経営状況が確認できる形になっているし、PPP/PFIでは「最も負担できる人がそのリスクを負担する」ことが原則となっている点も考えると、行政も適切にプロジェクトの結果責任を負う形となっているので、相当な覚悟が必要なものであり、決して悪い方法論ではないはずだ。
(大東市の場合は首長と議会の感情的・政治的な要因が多かったと邪推されるが、)前述のようにPPP/PFIでは行政も民間と同等(以上)のリソースを提供しなけければいけない。
PPP/PFIの根幹
どちらかだけではできない世界を創出すること
PPP/PFIの面白さであり、魅力は「行政または民間のどちらかだけでは成し得なかった世界を創出」することである。現在のまちのなかに存在する多様で複雑な課題は、行政だけではとても対応できるものではないし、縦割り・前例踏襲などをのつまらない文化が残っているようでは全く刃が立たない。
公務員時代には新設の小中併設校を整備する議案を通すためのバーター案件として、既存の23校の小中学校に空調設備を一斉に設置することとなった。実施に際しては「早く・安く・地元事業者の活用」が3つが条件として位置付けられたが、それぞれが相反関係にあるので行政だけでこの条件を整理することを困難であった。
そこで、プロポーザルコンペを実施して「この3条件を満たして空調設備を整備できる方法論を各社3つ以上提案してもらい、実際に施工する事業者の決定まで至ったら委託料を支払う」形で公募した。結果的に「機器の一括購入+地元事業者による設置工事」という方式に落ち着いたが、行政の従来型発注の工事では絶対できなかった方法論・価格・スピードであった。(※当初は一括契約による巨額のコスト削減を志向していたが、最終的な契約方式は執行部と議会の関係が良好でなく、執行部としての覚悟も不足していたため、工区ごとに割り振った地元事業者を契約の相手方として、そこに設備を供給する形となった。)
非合理的な行政の世界では100%の理想的な形になることは少ない・奇跡に近いといっても過言ではないが、実際にプロジェクトを構築していくうえでは様々な与条件が途中で変わっていくことも多い。こうしたことに柔軟に対応していく・できるのもPPP/PFIの良さであり、そうした現実的な「ラインを見据えた変更」もどちらかだけでは創出できない世界である。
お互いがリソースを出し合うこと
PPP/PFIの基本的な方法論は、相互補完とリソースの足し算・掛け算である。
紫波町の庁舎跡地活用事業では、旧庁舎の解体費相当額を負担金として紫波町が負担すること(当該資金・自由度をリソースとして提供)となった。民間事業者は、そのノウハウ・ネットワーク等をフル活用して公共発注より圧倒的に低価格・短期間での解体工事(ノウハウをリソースとして活用)を実施し、解体費相当額の負担金の残額をプロジェクトの原資として利用できるようになったことから、プロジェクト全体の収支構造にも貢献することとなった。
リソースの出し方は単純なサービス料、補助金、SPCへの出向、保険等だけではない。そのプロジェクトを実施するために必要なリソースをそれぞれがどうやって提供していくか、そこをクリエイティブに考えていくこともPPP/PFIでは求められてくる。これをめんどくさいと考えるか、希望を持ってできるかが運命の分かれ目の一つとなってくる。
案件の諸条件を考える
住宅地のなかで1宅地程度(や庭先程度)の土地の単純売却・貸付でキャッシュだけを目指したものであれば、売却等のために最低限必要となる土地の境界確定等の費用以外のコストを行政が資金を負担したり、必要以上のマンパワーを出すのは非合理的である。
一方で、きちんとした管理もしてこなかったために老朽化・陳腐化した公共施設が鎮座して耐震補強・大規模改修・設備更新や解体に何億円ものコストが必要になる場合、市街化調整区域に位置して地区計画等の緩和措置が前提となる場合、補助金の包括承認制(や地域再生計画等)による返還義務をなくす整理が必要となる場合などは、行政が資金・法制度の整理・関係機関との調整などを行うことがプロジェクトの前提となる。
(おそらく公共施設で全国初となる魔改造に手を染めた)津山市のグラスハウス利活用事業では、巨大なガラスドームの改修が前提となったため、要求水準書において最大26,500百万円を津山市が負担(費用は毎年1/10ずつ支出)することを位置付けて民間事業者が手を上げやすい環境を整備している。これまで指定管理委託料として約11,000百万円/年を支出していたのだから、これがゼロになることが確約され(うまくプロジェクトとして進めば)、公共施設等運営権で歳入にも直結することから、キャッシュベースでも企画・財政部門といった執行部だけでなく、議会にも「結果的に」理解を得やすい事業スキーム・ストラクチャーとなっている。
リソース・リスクとリターンの関係
自分たちの想いを叶えたいんだったら
自分たちの想いを叶えたいんだったら、相手と同等以上のリソースを提供すること、その覚悟・決断・行動をしていくことが大前提となる。
よく「うちのまちにはまともな民間がいないし来ない」といった嘆きを聞くが、完全にノーセンス・ノーリアリティでしかない。どんなに小さく厳しい状況にあるまちに行っても必ず、行政には一切頼らず自分たちで資金調達をしてビジネスをしている(、なかにはパブリックマインドを持ってまちともリンクしている)民間事業者の方々が山ほどいる。そうした方々がまちの中で必死になって生きているからこそ、行政に「税収」が発生している。このようなシンプルで基本的な原理原則が理解できていないようでは何もできない。
「民間が来る・来ない」は行政が判断することではなく、民間が自分たちで「行くか・行かないか」を決めるものであり、本当に民間がいない・来ないと思うのだったら行政が自ら営業に出るべきである。
それなりの規模のある企業で営業部門がないのは行政ぐらいである。
そして「PPP/PFIは対等の関係で成立」するので、自分たちの提供するリソースの総和とイコールフッティングする民間事業者がそのまち・事業・プロジェクトのパートナーとなる。
うちのまちには・・・と嘆いてイジけているうちは、その程度の民間事業者としか手を組むことができず、自分たちで負のスパイラルを助長してネガティブに闇堕ちするだけである。
職員もリソース・リスクに見合った対価を

流山市では、(自分も公務員時代にFM推進室として関わり、当時はそれが正義だと思い込んでいたが、)おおたかの森駅北口市有地活用事業において「財政負担ゼロで500人入るホールを整備」することだけを優先し、ビジョン・コンテンツもないままハコモノを整備してしまった。その結果、周辺人口が爆増するなかでも北口周辺のエリア価値の上昇は非常に鈍い状況となってしまった。

そのような状況を憂慮してかどうかはわからないが、2023年2月から流山市職員の有志による任意団体のNまちデザインが地域のプレーヤーを集めながら、税金に一切頼ることなく毎月定期的にNorth Square Marketを開催している。
自分も当時、この重要なプロジェクトを「短絡的なハコモノ整備事業」に堕としてしまった原因者の一人であることから、毎回メインスポンサーとして関わるとともに「金と手は出すが口は一切出さない」ことを約束して、サポートさせていただいている。
自分が見る限り、彼らは自分たちの資金も活用しながら、何より誰に頼まれたわけでもなく、相当のマンパワー・時間等のリソースを駆使してこれだけの活動を継続している。そして、プロジェクトが軌道に乗ってきたら(更なる展開も視野に入れて)営利企業従事に関する手続きを行い、相応の対価をもらうべきだと思う。
持続可能性は経済合理性が大前提であり、全て無償では心が折れた瞬間、自分たちの資金が尽きた瞬間に全てが瓦解してしまう。
そして、得られた利益を再投資していくからこそプロジェクトの魅力は向上し、ビジネスとしても拡大、エリアの価値が向上していく。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000973349.pdf



営利企業への従事については然るべき手続きをすればできることが地方公務員法で明確に位置付けられており、近年はこれを積極的に行なっていくことが結果的にまちにとってもプラスになることから、推進するムーブメントがあることは間違いない。しかし、2024年12月の流山市議会定例会では、ある議員からNorth Square Marketに主体的に関わっている職員を名指しして、次のような一般質問がなされたようである。
市職員の兼業について
公務員の兼業については「特定の利益に偏することなく、常に中立かつ公正であること」また「公務員ではなく、私人として従事し、その従事内容により市民に誤解を与えるといったことを避けること」などが大変重要であると考えるが、当局の見解を問う。
もちろん、市議会ではそれぞれの議員が「自分の立場」をベースに市政に関する一般質問を自由にできることが保障されているが、これはそのまちの意思決定機関を担う議会の議員、つまりプロとしての質問である。当然に背景やその実態等をきちんと調査したうえで確信を持って質問すべきであるが、どうやら「人から聞いた噂レベル」でNまちデザインの主要メンバーを糾弾したようである。
前段で述べたように、まちを支えているのは「それぞれの人たちのクリエイティブな経済活動」であり、その結果の一部が「税金として市民生活を支える原資」となっている。こうした質問をする方は、そのような前提をわかっているのだろうか。
まちの中にはどうしてもサポートが必要な弱者が存在する。そうした方々を支えていくためには優しさだけでなく、相当のリソースが必要となる。まちなかで自らのリソースを出し惜しみなく提供し、リスクを負いながら社会性・公益性のある「何か」をしようとする人たちの揚げ足をとっても誰も得をしないし、それが「あなたが助けたい人を助けられなくなる」ことにつながってしまう。優しさだけでは弱者は絶対に救えない。
同時に、PPP/PFIはオーダーメイド型で「こうすればうまくいく」といった必勝の方程式やマニュアルなど存在しない。刻々と激変する社会経済情勢のなかで試行錯誤していくしかない。試行錯誤なので、うまくいかないことは山ほどあるのが当たり前だが、その試行錯誤のプロセスを指摘して何が得られるのか?
「少なくとも」邪魔しないこと
自分でリソースを提供して「何か」をしようとしない人たちは、「少なくとも」お互いにリスクを負いながら「何か」をしようとしている試行錯誤の渦中にいる人たちの邪魔をしてはいけない。しかも、あなたの限られた世界観・情報でまちのポテンシャルを閉ざしてはいけないし、何のリスクも負わず、1円すら自分のリソースを提供するわけでもない外野にそんなことをする権利はない。
最近、YouTubeで九州のある自治体の市議会と一部の執行部職員を中心とした堕落やプロ意識の欠如・二元代表制への侮辱的な慣習・機能不全等がバズっている。議会の傍聴もメッチャ多くなっているらしい(URL等は敢えて貼らないので、検索してほしい)。
ここで指摘されているドスコイ議員をはじめとする数名の議員、応対する執行部の職員の議会の本会議・各種委員会での発言を聞いていると絶望感すら漂っている。(全てを視聴したわけではないが、)一部の議員・執行部の職員は(勇気を持ってというか当たり前なのだが、)こうした腐った風土・慣習・事実行為に公然と反旗を翻していることだけは希望があるが・・・
いずれにしても、まち全体から見たら「内輪」であり小さな社会でありながら、街へ一定の影響を与えうる行政・議会がこのような調子では、そのまちで一生懸命生きている・可能性を見出そうとしている人・民間事業者の邪魔でしかない。
これからの時代は「そのまちの民間事業者の経済活動をいかにクリエイティブに伸ばしていけるか」が問われるのに、自己の身勝手な汚くセコイ金と名誉のために動く・執行部を牛耳ろうとする議員、そんなアホな連中に迎合・萎縮する行政に未来はない。
職員も本業で結果を出すこと
職務から離れて自分たちで自発的に時間・資金等のリソースを出して、地域に飛び込みながら有機的なネットワークを組成して、リスクも負担しながらマルシェ等を開催したり、リノベーションに取り組むことは非常に尊い活動であることは間違いない。
本来、そうしたことをできない・やらない人、少なくとも資金・マンパワー等で直接的なサポートすらしない人に文句を言われる筋合いは全くないが、非合理的な行政や地域のムラ社会では「あいつら良いカッコしやがって」「公務員の特権使って自分たちが金儲けしている」「職務専念義務違反だ」等のつまらない誹謗・中傷に
晒されることも多い。
上記のように、なかにはレベルの低い上司・執行部や議員・議会もある。行政を取り巻く環境は驚くほど非合理的であるし、(簡単には首にならない・減給すらされないから?)足だけを引っ張る生産性ゼロ・マイナスの人間も混じっている。
もちろん、こうしたつまらない連中の方が悪いのは間違いないが、そんななかでもタフに生きていく・自分たちが本来やるべきこと・やりたいことを実施していくためには、職務を外れた外部の活動だけでなく、「本業で誰にも文句を言わせない・追いつけない」成果を上げていくことが求められる。
大概、つまらない足の引っ張り方をする人たちは大した勉強もしておらず、世の中のことも知らない、確固たるポリシーを持っているわけでもないので、客観的な評価を突きつけることで(一時的に)黙らせられる可能性も高い。
こうしたことから公務員時代には、プロジェクトレベルでは上記ホームページにあるように「今できること」を2つのPPP(Public Private Partnership/Public Public Partnership)により実施してきた。(ホームページの内容・実績がいまだに自分が在籍時のものからほとんど変わっていないのは寂しい限り・・・)
しかし、次第に執行部と議会の関係がギクシャクしてきたことや直系の部長の理解が非常に低く、何をやるにも決裁に想定以上の無駄な時間が生じるようになったことから、客観的な評価を得るためJFMA賞・プラチナ大賞に応募した。結果的にはそれぞれ奨励賞・審査員特別賞で狙っていた大賞には届かなかったが、想定どおりにそこからしばらくはつまらない雑音が小さくなった点では十分な効果があった。
まちの外で頑張ったり、自腹できちんとした実践ベースのスクールに通うなどの自分への投資をしている人たちは本当に尊敬に値するが、そのことは「本業で結果を出せないことのエクスキューズには全くならない」。
自分に対してもいつも思っている・戒めとしているが、「自分はわかっている・勉強している・頑張っているのに周りが足を引っ張るから・アホだからできない」と言い訳している時点で、アホな人をYESと言わせられないので自分自身も同等のレベルでしかないし、何よりまちは何も変わらない。
特に行政の職員は、市民からいただく貴重な税金で公務にあたっている。だからこそ、市民の期待・夢を裏切ってはいけない。
職員が強烈に高い事務処理能力を持っていることはこれまでの経験上、どこの自治体を見ても間違いない。大切なのはそれを実務・プロジェクトに直結させることである。
本業で結果を出す、これがプロとして当たり前のことであり存在意義である。本業で結果を出せる人・出せるようになっていく人は、まちでそれ以上のプロジェクトを実施したときにより大きなムーブメントを起こしていけるはずだ。
お知らせ
2024年度PPP入門講座
来年度に予定する次期入門講座までの間、アーカイブ配信をしています。お申し込みいただいた方にはYouTubeのアドレスをご案内しますので、今からでもお申し込み可能です。
実践!PPP/PFIを成功させる本
2023年11月17日に2冊目の単著「実践!PPP/PFIを成功させる本」が出版されました。「実践に特化した内容・コラム形式・読み切れるボリューム」の書籍となっています。ぜひご購入ください。
PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本
2021年に発売した初の単著。2024年12月現在6刷となっており、多くの方に読んでいただいています。「実践!PPP/PFIを成功させる本」と合わせて読んでいただくとより理解が深まります。
まちみらい案内
まちみらいでは現場重視・実践至上主義を掲げ自治体の公共施設マネジメント、PPP/PFI、自治体経営、まちづくりのサポートや民間事業者のプロジェクト構築支援などを行っています。
現在、2025年度の業務の見積依頼受付中です。
投げ銭募集中
まちみらい公式note、世の中の流れに乗ってサブスク型や単発の有料化も選択肢となりますが、せっかく多くの方にご覧いただき、様々な反応もいただいてますので、無料をできる限り継続していきたいと思います。
https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360009035473-記事をサポートする
そんななかで「投げ銭」については大歓迎ですので、「いいね」と感じていただいたら積極的に「投げ銭」をお願いします。
