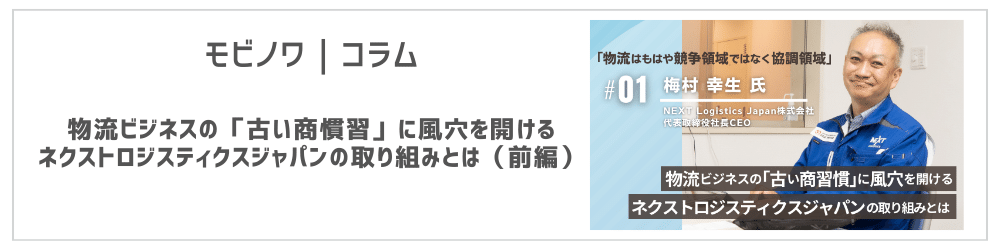「物流は、もはや競争領域ではなく、協調領域です」──物流ビジネスの「古い商慣習」に風穴を開ける、ネクストロジスティクスジャパンの取り組みとは(前編)
こんにちは。
モビノワのnoteに来ていいただいて、ありがとうございます。
今日は、私の大好きなモビノワ記事のご紹介です。
物流ジャーナリストの坂田さんに寄稿いただいたネクストロジスティクスジャパン(NLJ)さんへの取材記事の前編。めちゃめちゃ面白いです。
私自身、自動車整備業界がどのように物流課題解決に貢献できるのか。それを考え続けるきっかけとなった取材記事でした。
ぜひ、お楽しみください!(モビノワ編集長 田中)
物流ビジネスは、人手不足や古い商慣習などに起因する大きな課題を抱えています。
「物流の2024年問題」を筆頭とする物流クライシスが、TVや新聞などの一般メディアでも報道されるようになり、注目を集めています。これは物流クライシスが、私たちの日常生活に大きな影響を与えるにもかかわらず、その解決がとても難しいからです。
ネクストロジスティクスジャパンは、「物流は、もはや競争領域ではなく、協調領域です」と断言します。柔らかく言い直せば、「同じ業界で同じビジネスに取り組む他社は、もはやライバルではなく仲間ですよ」といったところでしょうか。
この言葉は、物流業界が目指すべき課題克服の本質を言い表していますが、これ、あらゆる業界に共通することではないでしょうか。
創業からわずか5年で、着々と成果を上げていく、「物流業界の風雲児」ネクストロジスティクスジャパンの取り組みには、すべての業界に共通する気づきと学びが存在します。
「物流の2024年問題」とは
「物流の2024年問題」とは、トラックドライバーの残業時間が、働き方改革関連法によって制限されることで生じる諸問題を指します。
かいつまんで言えば、これまで事実上好き放題働かされていたトラックドライバーという働き方に、「残業は年間960時間までね!」という枷(かせ)が課されたのが、「物流の2024年問題」です。
「物流の2024年問題」はいろいろな課題を引き起こすのですが、とりわけ厄介なのは、トラックの輸送リソースが減少することです。例えば、これまで一日11時間働いていたトラックドライバーが、9時間しか働けなくなったとします。単純計算すれば、このドライバーが一日に輸送できる貨物の量は、11分の9、すなわち以前の8割ほどになってしまいます。
「物流の2024年問題」を理解するためのポイントを3つ挙げます。
根本的な原因は、就労可能人数が減少する日本社会の構造的課題
少子高齢化が加速し、就労可能人口が恐ろしいほどの勢いで減少していく日本社会においては、当然トラックドライバーも人手不足が進んでいきます。
「トラックドライバーの待遇(収入や労働環境、労働時間など)を改善すれば、『物流の2024年問題』は解消できる」と主張する方もいらっしゃいますが、この考え方では、運送業界だけを救うために、他業界を犠牲にする(他業界から就労者を奪う)ことになってしまいます。
「物流の2024年問題」を根本的に解決するためには、就労者が減少しても、輸送リソースを維持、あるいは向上させるための構造改革が必要となります。
おそまつな政策が、「物流の2024年問題」をややこしくした。
「物流の2024年問題」は、働き方改革関連法によって強制的にトラックドライバーの労働時間が制限されることによって生じる問題です。
本来、労働時間の削減というのは、業務改善やビジネス革新の結果生じる成果のはずなのですが、業務改善・ビジネス変革の具体的な方法を十分に示さず、結果を目的化してしまったところに、政策としての致命的なミスがあります。
古い商慣習が、ビジネス革新の足かせとなっている。
実は、巷で見かけるトラックの半分以上は…
この続きを読みたい方は、ぜひモビノワにてご覧ください。(以下のイラストをクリック!)