
オルタナ・ロックの始祖たちが反響させたラディカルなロックンロール

今回、ご紹介するのは、オルタナティヴ・ロックの系譜に属するバンド群です。
60年代のロック・ミュージックは、サイケデリック/アート・ロック以降、急速な発展を遂げ、同ジャンルは、ジャンルの多様化あるいは細分化の様相を呈し、一つの分岐点を迎えていました。
彼らは、そうした状況下、音楽面においてはコンソールや楽器、スピーカーやエフェクターなどを変則的に使用し、精神面においてはアルコールや新種のドラッグを慢性的に服用し、社会や芸術に対する自身のアティチュードを具現化させていきます。
ロック史における異端者たちによるラディカルなロックンロールは、発表時においてはレセプション面やセールス面で結果を得ることはありませんでした。
しかしながら、90年代以降、ロック・シーンの中心を担っていくオルタナ/インディバンドらの一つのバイブルとなり、そして、彼らのアティチュードは、一つのロールモデルとさえなっていくのです。

『White Light/White Heat』/The Velvet Underground(1968)
作品評価★★★★(4stars)
現代音楽としてのロックを突き詰めるダダイズムの青年二人は、ビートルズやフラワー・ムーヴメントは勿論の事、アンディ・ウォーホルのポップ・アートにさえも拒否を示した。
今作におけるVoxから鳴り響くあまりに振り切られたその実験的なサウンドは、もはや成功か失敗かの判断が付かず、彼らのアヴァンギャルドなアプローチにはプロデューサーのトム・ウィルソンさえ匙を投げ出した。
リードとケイルによるVUは、この問題作を以て、幕を閉じることになったが、その耳を劈く酷いフィードバック・ノイズは、信じ難いことに、約10年後、パンク/ポスト・パンク/ノー・ウェーブにおけるサウンドの核として甦る事となったのである。
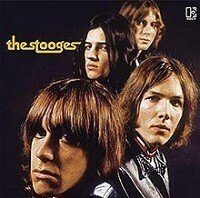
『The Stooges』/The Stooges(1969)
作品評価★★★★(4stars)
ミシガン大学をドロップアウトしたモラトリアムの青年は、MC5やドアーズなどのパフォーマンスに感化されて凶犬と化し、デトロイトから現代のアメリカ社会に蔓延る欺瞞へ中指を突き立てた。
エレクトラからのデビューに漕ぎ着けた彼らは、プロデュースを務めたジョン・ケイルと共に、ケイルが手掛けたミックスをお蔵入りさせつつも、不穏でソリッド且つスリリングなガレージ/サイケデリック・ロックを展開した。
ストゥージズは、今作リリース後、ドラッグ中毒によりイギー・ポップを筆頭に退廃化していく中、サウンド面における強度を上げながらデトロイト産のオルタナティブなハード・ロックを完成させていく。
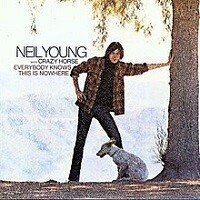
『Everybody Knows This Is Nowhere』/Neil Young With Crazy Horse(1969)
作品評価★★★★(4stars)
トロントからカルフォルニアへと移った渡り鳥の青年は、大学のフォーク・シーンやバッファロー・スプリングフィールドなどを経て、ようやくパーマネントのメンバーとして躍動するバンドの結成へと至った。
盟友であるプロデューサー/デビット・ブリッグスやダニー・ウィッテンらを擁するクレイジー・ホースを従えた彼は、2ndとなる今作で独自の空気感を漂わせる歌声と独特の味があるギター・プレイを高らかに披露した。
ニール・ヤングは、この後に上梓した二枚の名作によってディランやミッチェルらと並び称される偉大な作家へと羽ばたくが、そうした名声をある意味覆していくオルタナ/グランジの開拓者としての偉業は、ここから始まった。

『The Gilded Palace of Sin』/The Flying Burrito Brothers(1969)
作品評価★★★★(4stars)
米国音楽のルーツ/カントリーに蒙を啓かれたハーバード大学出身の青年は、インターナショナル・サブマリン・バンドやバーズを経由した後、派手なヌーディ・スーツを身に纏った新たなバンドに至り、その才能を本格的に開花させた。
ブリトーズは、パーソンズ/ヒルマンによる調和の取れたフォーク/カントリーやゴスペル/ソウルとクレイノウによるファズの効いたサイケデリックなペダル・スティール・ギターを重ね合わせた結果、1stにしてその革新性を決定付けた。
ソロ転身後のパーソンズは、カントリー・ロックが持つ可能性をより求道し、彼のスタイルは、オルタナ・カントリーの先駆をなし、そして、そのフレーバーは、保守的と言われている家元/カントリー・シーンにさえ及んだのである。
それでは、今日ご紹介したアルバムの中から筆者が印象的だった楽曲を♪
