
フロントエンドエンジニア中途採用説明会 フロントエンドQ&A
現在、LINE ヤフーでは多岐にわたるプロダクトの開発に関わるフロントエンドエンジニアを積極採用中です。2024年12月11日に開催されたフロントエンドエンジニア向けのオンライン説明会では、使用技術やサービスごとのチーム体制に加え、フロントエンドエンジニアとしてサービス開発に携わることで得られる経験やスキルについて、「LINE スキマニ」「Yahoo!ズバトク」「LINE Developer Product」を担当するエンジニアが実際の開発事例を通じて詳しく説明しました。
本記事では、イベント当日に参加者からいただいたQ&Aについて、当日回答できなかった質問も含め、掲載します。
LINE ヤフーのフロントエンドエンジニアに興味を持っている方やキャリアを見つめ直している方や、転職を検討中の方はもちろん、情報収集段階で興味を持っている方、迷っている方はぜひご覧ください。
登壇者
花谷 拓磨(はなたに たくま)
toCサービスのWebアプリケーションエンジニア、フリーランスなどを経て2018年にLINEに入社。フロントエンドエンジニアとしてさまざまなサービスの開発や UIT Meetup / UIT INSIDE の運営、2021年3月より「LINEバイト」「LINEスキマニ」の開発リード・エンジニアリングマネージャーを経て、2024年7月からはテクノロジーエンハンスメント部部長として専門技術への探究・プロダクトへの還元を目的とする部署のマネジメントに従事。
泉水勇輝(せんすい ゆうき)
2020 年に LINE(現 LINE ヤフー)のインターンシップに参加し、フロントエンド開発に従事。2022年4月にLINE に新卒入社し、現在にいたるまで「LINE スキマニ」のフロントエンド開発に従事。
渡部 智史(わたなべ さとし)
2016年にヤフー(現LINEヤフー)に新卒入社。現在に至るまで、「Yahoo!ズバトク」を中心とする集客サービスのフロントエンド開発に従事。現在は開発チームのリーダーを務める。
大橋 一真(おおはし かずま)
2020 年に新卒で入社した会社にてバックエンドエンジニアを経験後、2022 年に LINE(現LINEヤフー)へフロントエンドエンジニアとして中途入社。現在は「LINE Developers Product」の LIFF SDKやLINE ログインのフロントエンド開発に従事。
開発経験やスキルに関する質問
Q. Webサイト制作出身のフロントエンドエンジニアは在籍していますか。また、応募するにあたりReactなどのjsライブラリやフレームワークの知識・開発経験は必須でしょうか。
花谷 Webサイト制作系のバックグラウンドを持った方も在籍しています。たとえば、アクセシビリティ領域に詳しい人の場合はWeb制作をバックグラウンドに持って入社されて業務に従事してる方もいます。
Reactなどのjsライブラリやフレームワークの知識、開発経験は基本的に必須となります。ほかの技術領域からフロントエンドエンジニアにキャリアチェンジしている人も多く在籍していますが、基本的にはWebアプリケーションの開発経験、フロントエンドの知識が十分にあることが必須になるかと思います。
Q. 未経験でフロントエンドエンジニアとして入社を希望しています。未経験入社の場合、どの程度の技術スタックが求められますか?(言語、フレームワーク、個人開発経験など)
花谷 担当するプロダクトや組織で実際に利用されている技術の経験を求めています。各ポジションの求人情報を参考にしていただけますと幸いです。
説明会にて紹介したポジション
フロントエンドエンジニアのポジション一覧
Q. コーディング試験に苦手意識があります。普段の業務のなかで実装スピードが早かったら評価されますか?
花谷 プロダクトのフェーズなどにもよって求められることも変化しますが、もちろん実装のスピードが早いことに越したことはありません。
一方で多くのユーザーを抱えるプラットフォームである以上私達がまず目指すべきは品質です。そのため、手の早さは評価の一つの側面であり、今後を考えた設計能力、現時点でのアウトプットのクオリティなどと含めて総合的な能力で評価されます。
Q. バックエンドエンジニアからフロントエンドエンジニアにキャリアチェンジをした方が入社を決めた理由について教えてください。 また、前職のバックエンドエンジニアではどのような言語、フレームワークを使用していたのでしょうか。
大橋 もともとフロントエンドの領域に興味がありました。趣味の範囲でフロントエンドの技術に触れることがあり、その際「LINE Developers Product」の求人がオープンしているのを目にして、応募にいたりました。SDKの開発はバックエンドの開発とも関連性があるように感じ、フロントエンドエンジニアとして入社をしました。
前職のバックエンドエンジニア時代はNode.js、TypeScriptを使って開発をしてました。フレームワークは Expressです。
Q. フロントエンド技術をキャッチアップする際に効果的な学習や役に立ったことなどはありますか。
大橋 チームでフロントエンドの技術について勉強する時間があったため、私自身が学びたい領域をチームのメンバーにリクエストすることもありましたし、経験豊富なメンバーから「こんな技術を学ぶと良いのでは」といった提案をしてくれることもありました。そういった機会を活用し、技術のキャッチアップを続けています。
プロダクトに関する質問
Q. 各プロダクトのフロントエンドエンジニアの方とバックエンドエンジニアは、業務内でどれほど一緒に作業を行なっておりますでしょうか。
泉水 「LINEスキマニ」の場合、毎日行っているバックエンド、フロントエンド、デザイナー、QA、企画の各ロールから数人ずつで編成されたSquadと呼んでいる組織の朝会と開発全体の朝会で、バックエンドとフロントエンドで合わせて話をすることが多いですね。それとは別で、施策で必要になったタイミングで話をするケースがあります。基本的にはフロントエンドとバックエンドは分かれて開発を進めています。
渡部 「Yahoo!ズバトク」の場合、フロントエンドとバックエンドを明確には切り分けていません。メンバーごとにスキルセットも異なるため、フロントエンド中心に担当する方もいれば、フロントエンドとバックエンドを両方担当する方もいます。基本的にはチームの中に両方を担当するケースが多いため、チーム内でコミュニケーションを取りながら開発を進めています。
Q. 定例会議は週にどの程度ありますか?
大橋 私の場合、プロジェクトの定例会議が2つとチームの定例会議が2つで週4回程度です。それに加え、追加でプロジェクトがある場合はその都度会議が入ります。基本的には、Slackなどの非同期でのコミュニケーションが中心です。
渡部 各チームの開発状況や進捗を共有する定例会議を週に1回設けています。スクラムセレモニーが毎週ありますがそれを除けば基本的に会議はそこまで多くなく、作業に集中できるように必要最低限に絞っています。
泉水 「LINEスキマニ」ではSquad制を導入しているため、毎朝Squadごとの朝会を行っています。それとは別に、フロントエンド・バックエンドの開発単位の朝会も行い、各Squadごとの開発進捗を共有する場としています。週次で事業部全体の定例会議も設けられています。それ以外は、定例会議のかたちを取らずに困りごとや相談事項があった際、都度Zoomを繋いで会話し、意思決定を行うケースが多いですね。
Q. 「LINEスキマニ」ではどういった狙いでDenoを採用したのでしょうか。また、移行を決定するまでにどのような意思決定プロセスを踏みましたか?
泉水 これまでは、ES Modulesライクな構文をCommonJSに変換してNode.jsで動かしていました。
しかし、最近はES Modulesネイティブで実行する流れが加速しているため、CommonJSを使い続けることが技術的負債になりそうだと感じていました。
今回、「LINEスキマニ」のCMSをリニューアルすることになり、そこでCMSのSSRサーバーを取り除く判断をしました。このため、Node.js以外のランタイムを採用するハードルが下がりました。
DenoはES Modulesファースト、Web標準ファーストな思想を持っており、我々はそれに共感し、移行を決断しました。
Q. 「LINEスキマニ」ではDenoと同じくWeb標準を推しているBunも最近話題になっているかと思います。Bunは技術選定時に候補にはあがりましたか?また、上がっていた場合Denoを選んだ理由はありますか?
泉水 BunはNode.js compatibleで高速に動作することをメインに打ち出している印象があります。「LINEスキマニ」チームはDenoのES ModulesやWeb標準を優先している思想に将来性を感じており、高速に動作することよりも思想から来る将来性を重要視しました。
Q. 「LINEスキマニ」にてNext.jsを使用していない理由はありますか。
泉水 Next.jsはAll-in-Oneな思想を持ったフレームワークで、特に初期開発をブートストラップできる点において優れていると思いますが、一方でAll-in-Oneであるが故に、例えばビルドツールがwebpackにロックインされるなどのダウンサイドもあります。「LINEスキマニ」チームでは、ミニマムな技術を組み合わせることでトレンドの変化に追従し続けることを優先したかったため、Next.jsなどのフレームワークを採用せずにReact + Viteで開発しています。
Q. 「Yahoo!ズバトク」のフロントエンドエンジニアは、インフラやバックエンド領域に関して、どこまで関わるのでしょうか?
渡部 個人のスキルに応じて柔軟に対応しているため、状況はさまざまですが、インフラやバックエンド領域に関与する場合、基本的には経験者をアサインするケースが多いです。
Q. リファクタリングや技術スタックを見直すようなことは、各プロダクト内で定期的に行なっているのでしょうか?
渡部 「Yahoo!ズバトク」の場合、見直す機会は多く、エンジニアから改善提案を行うケースがあります。プロダクトの歴史が長くなればなるほど、定期的に見直すべきポイントが出てきます。そういった箇所にアプローチし、プロダクトオーナーとも相談しながらスクラムにタスクを載せて開発を進行していくことを日常的に行なっています。
泉水 「LINEスキマニ」も頻繁に行なっています。普段の施策開発の中で、変更する箇所にある既存のコードについても「より良い設計は何か」を常に考え、更新しています。小さなものから、我々がつくっている独自の大きな仕組みまで、常に見直すようにしています。 品質を維持しながら、より良いコードベースに常にリファクタリングしていく動きを意識しています。
大橋 「LINE Developers Product」の場合、素朴なやり方にはなりますが、 リポジトリの中にイシューを立てていって、その中でリポジトリのあるべき姿やペインポイントを洗い出しています。
その内容はプロダクトマネージャーも見られるっていう状況にしていて、優先度が高いものについては、我々開発チームから企画側にも提案し、実施の意思決定を行うケースもあります。
Q. Reactプロダクトの紹介が多いようでしたが、Vue.js, Nuxt.jsの割合はどれくらいありますでしょうか?
花谷 担当プロジェクトベースでの集計となりますが、LINEヤフーでは2023年末時点では7割強の開発者がReactのプロジェクトに携わり、6割強の開発者がVue.jsのプロジェクトに携わっています。
複数のrepository の開発を行うことが多いため高く出ていますが、 React/Vueのシェア率の参考にしていただけますと幸いです。また、近日中に2024年末に実施した最新集計結果についてTechBlog からの公開を予定しております。
働き方に関する質問
Q. 現在自営業で別の事業をしています。入社後今の仕事を副業として継続するのは可能ですか?
花谷 上長や関連部門の事前承認のうえ、副業していただくことも可能です。 社内だけでなく、社外でもさまざまなスキルや経験を積むことができます。 ただし、業務に支障をきたさないこと、会社の名前や財産などを使用しないこと、会社固有の技術やノウハウの漏えいをしないことなどのルールを守っていただくことが大前提です。
Q. 開発拠点とはサテライトオフィスのようなものでしょうか? 地方のオフィスに出社して開発するような働き方はできますか?
花谷 支社のようなところとサテライトオフィスのようなところが両方あり、本日紹介した福岡や京都、大阪のオフィスは、大きな支社のような扱いの開発拠点となっています。その他にも、サテライトオフィスのような小規模オフィスが多数あります。
定常的な所属オフィスは基本的に1つに定める形になりますが、たとえば出張や旅行のついでに有給休暇を取得し、特定の仕事をする場合には、別の拠点に出社して仕事をすることも可能です。
選考や配属に関する質問
Q. 選考でコーディング試験はありますか?
花谷 組織やポジションにより、選考方法は異なります。試験の問題もさまざまで、アルゴリズム系を問うような問題もあれば、ReactやVueを利用したアプリケーションの制作能力を問うような問題を出題している部署も存在します。
Q. 入社後、チーム配置などはどのように行われますか?
花谷 基本的には選考段階で決まったプロダクトの開発にアサインされることとなります。
採用ページにポジションがあるプロダクトから選んでいただき、応募したプロダクトの担当となることが多いですが、カジュアル面談や選考の中で担当が変化するケースもあります。
その他の質問
Q. 社員の平均年齢を教えてください。また、中途採用での年齢制限などはありますか?
花谷 年齢は30代がボリュームゾーンになっているかと思います。選考においての年齢制限はありません。
最後に
LINEヤフーではフロントエンドエンジニアを積極採用中です。記事を読んでLINEヤフーのフロントエンドエンジニアに興味を持っていただいた方は、ぜひ下記より募集職種の詳細をご確認ください。多くの方のご応募、お待ちしております。
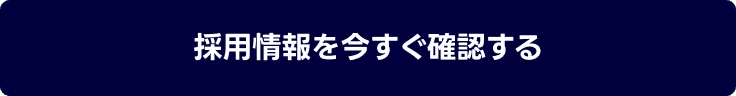
プロダクトごとの開発事例に関するレポートは以下の記事にて詳しく紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
