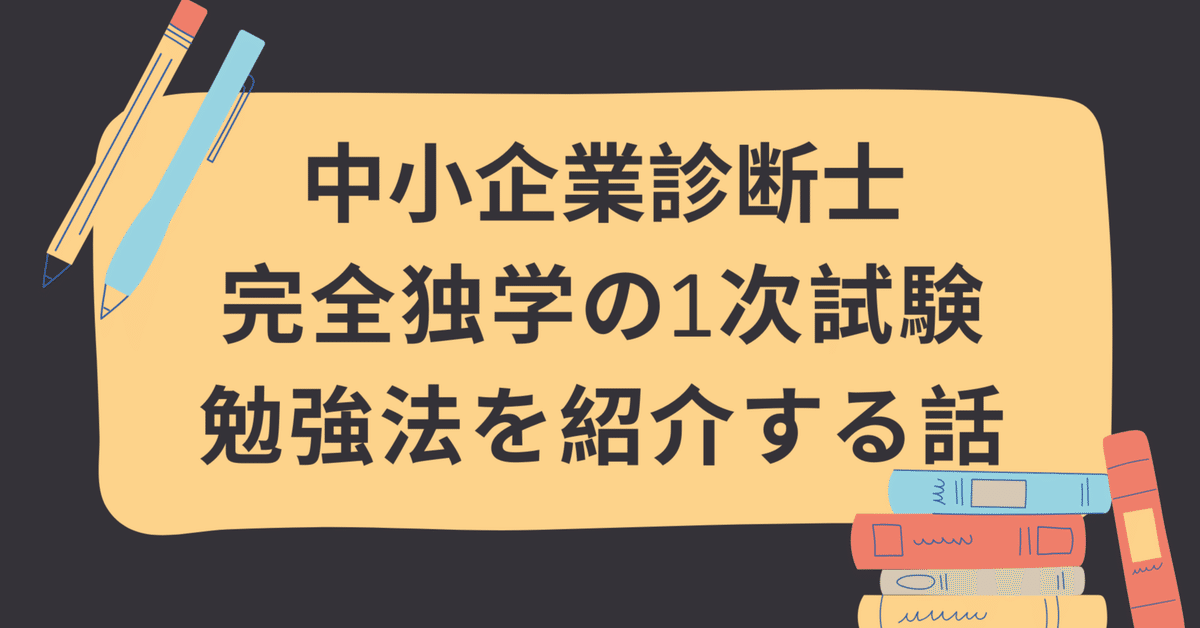
【中小企業診断士】完全独学の1次試験勉強法を紹介する話
〜2月28日 00:00
こんにちは、中小企業診断士のみやけんです!
新年あけましておめでとうございます!!
天気もよくて気持ちのいい正月ですね。
私は毎年恒例の箱根駅伝鑑賞タイムを楽しんでいます。
昔は自分よりもお兄ちゃん達が走っていてカッケェなぁ!!!と思いながら観ていたんですがね。
いつの間にか若い子達の頑張る姿を応援しながら観るような歳になっていました。
今年はなかなか動きがあって実に面白い展開です…みんながんばれ!!!
私の1次試験対策法について書いてみる
さて、今回は少し昔話をしてみようと思います。
以前から書いている通り、私は令和5年度の中小企業診断士試験に合格しました。
最近、診断士はビジネスマンの間で人気度がかなり上がってきています。
🔻診断士について知りたい方はコチラ!
ですので、受験を志してここに辿り着いた方も多いのではないでしょうか??
過激ですが、私はぶっちゃけ診断士の1次試験は正しい勉強法で相応の勉強時間を確保できれば誰でも受かる、と思っています。
しかし、「その勉強法がわからんのじゃ!」という人もいることと思います。
今回はそんな方向けに、私なりの1次試験対策法を紹介してみようと思います!
ただ、最初に断っておきますが、楽して合格!といったマジックな方法ではありません。
しっかりコツコツ堅実に積み上げて確実に受かろうというものですので、ご承知おきください。
🔻2試験版も書いたのでよければどうぞ!!
この記事のターゲット
1.中小企業診断士を受験する人
当たり前ですね。そうでない人は特に読む価値はないです。
2.地頭が良くない人
診断士試験は合格に1000時間の勉強が必要と言われます。
私は昔から勉強が苦手でしたので、ハナから1100時間は勉強しようと計画を立てていました。
実際1170時間(1次のみで言えば900時間強)を費やしています。
反面、200時間程度の勉強時間で超短期合格をする方も少数ですが、います。
今回紹介する方法は、これまでの人生でもそうやって要領良く試験をこなしてきた方には堅実すぎるアプローチだと思います。
我こそは地頭が良くないと思っている方が対象です。
3.完全独学の人
基本的に、色々浮気せず1つのアプローチに集中するのがいいと思います。
予備校に行く方はお金も払っているわけですし、そちらに専念すべきでしょう。
3つともに当てはまった人には参考になると思いますのでぜひ読んでみてください。
私の1次試験結果
さっそくですが、私の実際の点数開示結果はこんな感じでした。
【合計点】513/700点
【経済学・経済政策】84/100点
【財務・会計】76/100点
【企業経営理論】68/100点
【運営管理】76/100点
【経営法務】68/100点
【経営情報システム】64/100点
【中小企業経営・政策】77/100点
結果的に、全科目6割越えでオーバーキルする形になりました。
勉強嫌いな私でもこの点数が取れたので、それなりに参考になる勉強法だと信じています。
勉強する際に意識していたこと
私は理系なので、原理や理論を重視しています。
勉強にも活用できる理論はいっぱいあるので、これは意識するようにしていました。
天才たちがサイエンスとして理論に昇華してくれたものですから、凡人は有難く活用しましょう。笑
1.科目ごとにエビングハウスの忘却曲線を意識する
ご存知の方も多いですよね。

上図の通り、人間は1度勉強したことの大半を時間が経つにつれ忘れてしまいます。
復習をしないと1日後には実に70%の内容を忘れてしまいます。ポンコツすぎる。
それを定期的に復習することで記憶に定着していくというものです。
学校の定期テストなら一夜漬けで乗り越えられますが、診断士試験は範囲が膨大なのでそれは無理なので、必然的に長期戦になります。
長期戦になればなるほど1回のみの勉強では記憶から抜け落ちやすくなるので、この忘却曲線に則ってキチンと定着させることが大事になるというわけです。
2.学習時間と成績は比例関係ではないと肝に銘じること
こちらも有名な図ですが、成績は学習時間に対して指数関数的に伸びていきます。

ですので、勉強開始直後や中弛み期には「勉強しても勉強しても成績が伸びない…やめようかな…」という状態になりやすいです。
このあと爆発的に伸びていくのに、ここでやめてしまうのは非常にもったいないです。
そうならないよう、学習時間と成績の相関関係を頭に入れておくことで心折れないよう留意していました。
私も例に漏れずで、初めて模試で合格点を取ったのが850時間くらい勉強したころで、その時は423/700点とかなりギリギリでした。
そこから100時間弱の勉強時間で本番は513/700点だったので、最後の伸び率がいかに急だったかわかりますね。
「じゃあ具体的にどうするんだい?」という声についてはこれからで答えていき値と思います!
勉強計画と予実管理
1.5か年計画とその勉強実績
さて、いよいよ本題に入っていきます。
私は令和4年5月中旬に受験を決めたのでその年の受験はパスし、令和5年のストレート合格を目指す1.5か年計画を掲げスタートしました。
🔻受験を決めた理由はコチラ!
賛否ありますが、私は勉強時間で計画・予実管理を組んでいました。
合格には1000時間必要と聞いていたので、1次900時間、2次200時間、計1100時間で計画しました。
先程から書いている通り、勉強が苦手な自覚があったので一般的な1000時間よりも長く見繕いました。
私は、コツコツ長距離タイプなので、60時間/月(≒2時間/日)をコンスタントに刻んでいくことを決め、取り組みました。

ここから先は
2月9日 21:30 〜 2月28日 00:00
この記事が参加している募集
よろしければ応援いただけると嬉しいです!、 診断士およびクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
