
書き手が伝えたいことを100%届ける。毎日新聞のベテラン校閲者が語る「読む姿勢」とは
こんにちは、LINE校閲チームの伊藤と申します。
今回は、校閲業界で長く活躍されている、他社のベテラン校閲者にインタビューした内容をお届けします。
弊社の校閲チームは20~30代で構成されていることもあり、「外部の経験豊富な校閲者がどのように校閲と向き合っているのかを知りたい!」と思ったことが企画のはじまりでした。
取材を快諾してくださったのは、毎日新聞・東京本社校閲センターで副部長を務める平山泉さん。辞書のおもしろさを深掘りする人気イベント「国語辞典ナイト」に出演するなど、辞書・校閲の情報発信にも精力的な校閲者として知られています(写真は2018年の「国語辞典ナイト」。右から3番目)。

そもそも校閲という仕事は、原稿内の誤字脱字や言葉の誤用、事実関係の誤りなどを正していくものですが、一文字ずつ注意深く読んでいても指摘すべき点を見逃してしまうことも…。
簡単ではない校閲との向き合い方にヒントを求めたところ、平山さんにも校閲者としてやっていけるか不安な時期があったというのです。
校閲一筋29年の平山さんがどのような仕事の姿勢で周囲の信頼を得てきたのか、校閲者はどうあるべきなのか、貴重なお話を聞くことができました。

平山 泉(ひらやま・いずみ)
毎日新聞東京本社校閲センター副部長(デスク)。1992年入社、2006~08年の大阪時代を含め一貫して校閲記者を務め、「毎日新聞用語集」の改訂に長年携わる。21年7月から用語幹事兼務。18年の「国語辞典ナイト」をはじめ、校閲・辞書に関する講演・講座に登壇。共著に「校閲記者の目」など。
言葉について悩みながら仕事がしたい
「私はほんとダメダメで、それまで新聞を読んでいなかったからニュースに疎くて…。校閲についても不器用で怒られてばかりでした」
入社当時の意外な姿を平山さんが明かす。もともと新聞を読む習慣がなく、毎日新聞の入社試験では当日の朝刊が頭に入っておらず「読めていないのがバレバレで面接官に注意された」ほどだったという。
なぜ平山さんは新聞の校閲を志望したのか。それは新聞が「今の言葉を扱う」と思ったからだ。
「出版の本なら著者の書き方を尊重しなければいけません。もちろんそれは大事なことです。でも新聞だったらこの言葉で良いのだろうかと、言葉について悩みながら仕事ができるかもしれない。きっと主体的に悩むことができるんじゃないかと思ったんです」
たとえば「雨模様」という言葉は「雨が降りそうで降っていない天気」が本来の意味であるものの、「小雨が降っているくらい」や「降ったりやんだり」など受け取り方が人によって異なる。
「本来の意味で使われていても雨が降っていると受け取る人も多い。降っている降っていないという事実関係の伝わり方が異なってしまうので、新聞では『雨模様』という言葉が使いにくくなってしまいました。言葉が使えないなんて悲しい。でも、そうした言葉の変化がおもしろいんです」

時代のなかで変化していく言葉に興味を持ち、大学では国語学を専攻。3年生のときに受けた校正の通信講座で、じっと椅子に座り続け、一文字ずつ入念に目で追っていても飽きないことを実感した。
「校正や校閲は私に向いているかも」
ニュースに疎かったから新聞校閲をやれる自信はなかった。それでも、誰もがわかる言葉で日々の出来事を伝える新聞は、平山さんがぼんやりとイメージした「言葉を扱う仕事」に重なった。
無知であることを思い知らされる
しかし、入社すると厳しい世界が待っていた。当時は記者の直筆の書き原稿も多い時代で、いわゆる「読み合わせ」も行っていた。
ひとりが校正用に刷られたゲラを音読し、もうひとりが書き原稿と合っているかを確認する作業だ。この時間が平山さんには苦痛だった。
「読もうと思っても文字の説明がスラスラと出てこない。知らない地名、たとえば栃木県の『真岡市』が読めなくて、『もおかって読むんだ!』と怒られたり…。ニュース以外でも知らないことが多いと思い知らされました」
勉強になる半面、うまくできないことがつらかった。1年くらい経つと一通り仕事はこなせるようになったものの、ミスが続いてしまう苦しい時期が続いた。
「同期の校閲記者が東京だけでほかに3人いましたが、みんな私より優秀で、自分はどうやって生きていけばいいだろうと思っていました」
信頼されるために必死で取り組んだこと
当時を振り返りながら「めげなかったんだろうなぁ」とつぶやく平山さん。
先輩に怒鳴られ悲しくなっても、自分のために叱ってくれることはわかっていた。
(この人に信頼されたい!)
心のなかに芽生えた強い思いは行動につながっていく。
「でもなにをするって、仕事以外でも新聞を読み込むくらいしかないです。だけど、校閲をするつもりで。必死に読み込みました」

仕事のときのように線を引きながら、気づいたことはどんどんメモに取る。信頼されたいと本気で思うからこそ、細かい違いに気づくようになった。
「昨日とは外国人名の表記が違います」
当時はネット検索も記事データベースもない。記憶に頼るか、ひたすら新聞をめくってなんとか表記の統一を図る時代。些細なことでも報告すると、先輩が話を聞いてくれるようになった。校閲対象である新聞を徹底的に把握する努力を毎日重ねた。
「先輩も言っていたのは、『新聞を読まなくなったら終わりだね』と。校閲は経済、国際、スポーツ…いろんな面をみるので全部読まなきゃだめ。毎日読む必要があります。夏休みで旅行するとたまってしまって大変なので、国内旅行にして旅先でも読めるようにしていました(笑)。校閲時にネット検索も使えますが、出来事や経緯は頭で記憶しておかないと。内容以外にも体裁や知らない言葉も新聞で覚えていく。後輩には『新聞が一番の教材だよ』と言っています」
用語集の改訂チームで見つけた「居場所」
周囲から信頼を得るうえで、社内でのコミュニケーションも意識した。
以前は出稿部から少し離れたところに校閲室があり、記事について指摘や相談をする際にアルバイトを介して問い合わせる人が多かったが、平山さんは根拠となる資料をいっぱい付けて自ら足を運び続けた。
最初はまともに取り合ってくれなかった相手が、次第に顔を覚えてくれるようになり、話を聞いてくれるようになっていく。主体的な行動の積み重ねが少しずつ状況を好転させていった。
「自分の居場所があるかなって考えていたときに、用字用語の仕事があったんです。言葉のことが好きだと常々言っていたら1年目から用字用語にかかわる作業班に入れてもらえて。そこから、4年目には『毎日新聞用語集』の改訂作業のチームに入りました。校閲にとって用語集の改訂作業に携わるのは大切で、中心的な仕事です。大切な仕事を任されているという責任感や自負のような気持ちは生まれました」
校閲時に傍らに置く用語集は、わかりやすい報道のために表記や言葉の使い方などを統一したルールブックのようなもの。用字用語の仕事に携わるうちに同期にも頼りにされる機会が増えていった。
「表記に迷うところでいくつもの辞書を引き比べたり、新しい言葉を加えようとして辞書を読んだりするので勉強になりました。すると『用語集の表記的にはどうだっけ?』と聞かれるわけです。ちゃんと私にも役割があるということがうれしかったです」

一緒に良い紙面を作るため、言うべきことは言う
記事の書き手と校閲者の関係を考えさせられる「事件」も起きた。
朝刊一面コラム「余録」を当時担当していた著名なコラムニスト、故・諏訪正人さんと「ほぼ喧嘩になった」というのだ。
誤解が生まれそうな箇所の修正相談をしたところ「これでいい」と拒否され、平山さんが食い下がったことがきっかけだった。
険悪な雰囲気になるほど粘ったのは「読者が誤解してしまうから」。それでも拒む相手に対して、しかも目上の大ベテランともなれば説明を重ねるのには勇気がいる。引き下がらずに強く言えたのは、平山さんが"ひとり"ではなかったからだ。
「自分だけの思い込みではないことを同僚に確認していたんです。そうすれば『みんなも同じ意見なんだ』と気持ちが強くなる。そして、私個人のためではなく読者のためなので『私の後ろには読者がついている』と思うことが大事です」
喧嘩別れのような形で校閲室に戻った平山さんは悔しさで泣いているように周りから見えたという。ところが再度出てきたゲラでは問題箇所が見事に修正されていた。
「しかも私の考えた文章より良くなっていたんです。当たり前のことですが、書き手と校閲記者は『一緒に良い紙面を作っていくんだ』ということをすごく実感しました。その後は諏訪さんが話を聞いてくれるようになって仕事がしやすくなりました(笑)。どんな仕事でも同じだと思いますが、言うべきことは言うのが大事。もちろん、こちらが折れることもいっぱいある。でも絶対に折れちゃいけないときもあります」
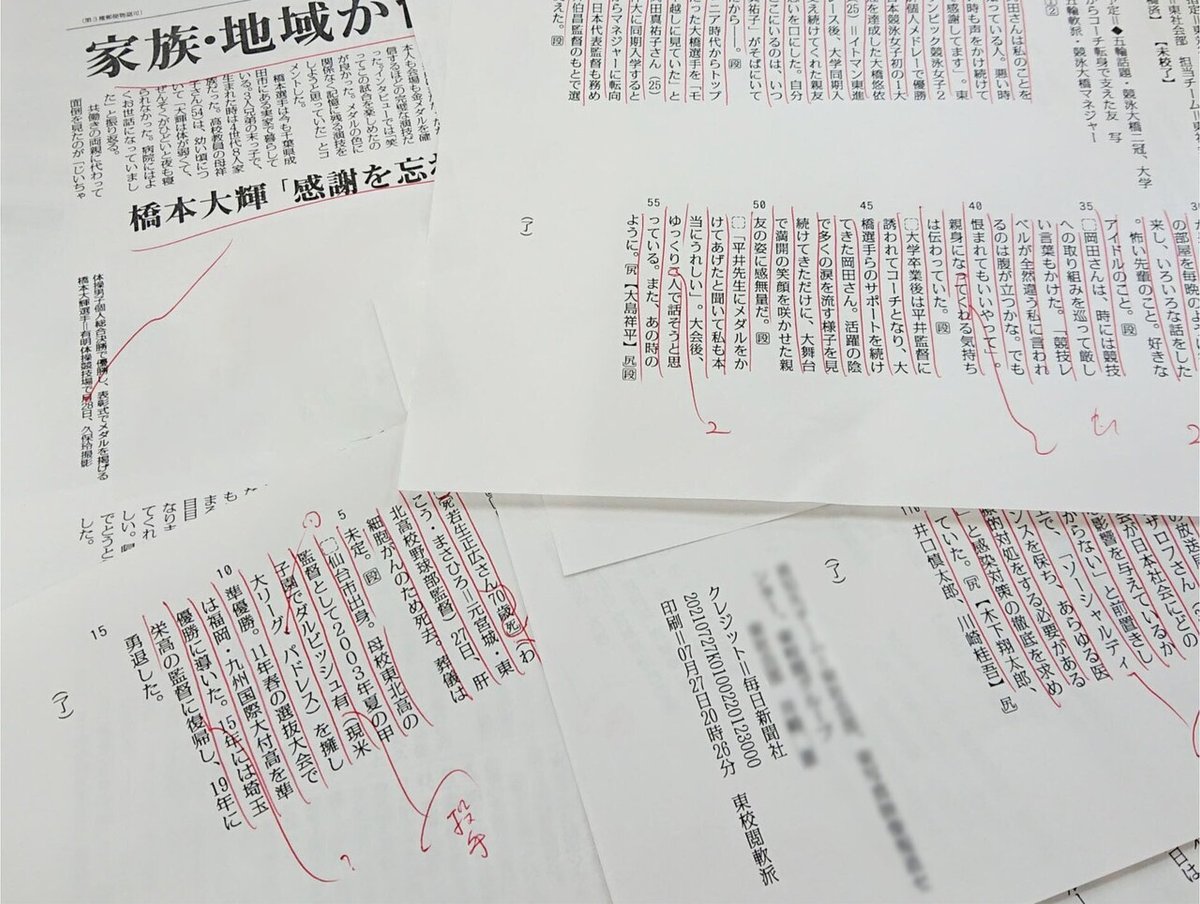
厳しい仕事だからこそ、チームで補い合う
先輩、後輩、記者…それぞれから信頼を得て、認められていく。こうした個人のがんばりは、校閲のチーム全体の評価を高めることにもなる。チームとしての重要性を平山さんはこう話す。
「ひとりがミスをしたからって処分されることはないですが、ミスの積み重ねが校閲の信頼をどんどん落としていくことは間違いない。校閲は信頼されることがなにより大事ですよね。原稿にいくら大きな誤りを見つけて正せたとしても、一つの誤りを見逃したらダメなわけです。記事の誤りをゼロにするのが仕事。でもゼロにするのは大変で、厳しい仕事です。だから必ずニュース面でも最低3人の校閲の目が通るようにしています。みんなで補い合うように仕事をしているので、校閲が信頼されていったんだと思います」
かつては校閲記者が減らされ、人材の採用ゼロの年もあるなど「校閲の地位が低く、校閲が生きていけるか心配な時期」があったそうだ。
厳しい時期でも一人ひとりが信頼される仕事をしたことに加え、先輩や平山さんが毎日新聞労働組合の場で「校閲は大事だ」と訴えたことなども校閲の認知度向上につながったという。
「組合の場は他の職場のこともよく知ることで、『会社のなかでの校閲の存在』を考えることができます。互いの職場を思いやりながら訴えたことで、校閲に一目も二目も置いてもらえるようになったのかもしれません」
現在の毎日新聞の校閲といえば『毎日ことば』やTwitterでもお馴染み。丁寧な言葉の解説が評判で、7月からは紙面の一面・中面に連載を開始した。今や毎日新聞の品質を守るだけでなく、コンテンツ面でも欠かせない存在だ。

校閲として完璧と思えたらつまらない
「29年間ずっとこの仕事をしてこられたのは幸せでした」と語るほど情熱を持って校閲と向き合ってきた平山さんは、校閲者として何を大事にしてきたのだろう。
「校閲は、誰でもできる仕事なんです。誠実に読めば良くて、調べることを怠らなければいい。なにが必要かといえば、原稿の隅から隅までチェックして読者に届けるぞという『読む姿勢』に尽きると思います」
今でも覚えている指摘があるという。入社1年目にみた科学面の記事で「ppb」という単位があった。調べたら「10億分の1」を表す単位なのに、紙面では「1億分の1」になっていた。
調べさえすれば、どんな分野の間違いでも直すことができるかもしれない――。その誤り自体は特別なものではなかったが、科学などの専門的な面でも苦手意識を持たなくていいことを学んだ。
「校閲は『読者』ではありません。読むだけでいいわけではなく、書き手が伝えたいことを100%届ける仕事です。記事に対してすべてチェックしないと気が済まないという『読む姿勢』さえあれば、調べることを怠ろうとは思わないですよね。ここは後でいっか、と手を抜いたところに間違いがあったりしますから」

それでもときには見逃してしまうこともある。失敗してはいけない仕事とはいえ、失敗することも大事な経験ととらえている。
「職場の若手が失敗した姿をみると『よしよし、良い経験したな』って思いますよ。失敗をしないですり抜けてしまうと、あまり成長できない気がします。私も落ち込んだりすることはありますが、寝て起きたら軽くなっていますね」
失敗や反省、さまざまな経験を積み重ねて磨かれていく。校閲29年のベテランとなった今でも校閲者として満足することはない。
「校閲として完璧で、完成する、ということがないからこれまで飽きずに仕事をしてこられたのかもしれません。もし完璧と思えたら安心かもしれないけど、それではつまらないのではないかと思います。先輩から指摘を受けて『やっぱり自分はまだまだ』と思うし、後輩の仕事ぶりに『よく気がついたな』『よく調べたな』と感心もする。残念ながら、いまだに自分自身の失敗もあるということも含めて、こういう刺激を受けられる環境にいることをありがたく思います」
どこまでも謙虚な姿勢も平山さんが信頼を積み重ねていけた理由ではないだろうか。
「校閲として完璧だったらつまらない」
悩みながら仕事がしたいと、校閲の世界に飛び込んだ平山さんらしい言葉だった。
取材を終えて

オンライン取材となりましたが、他社の校閲者の方と交流する機会はほぼないので、平山さんとお話しできて光栄でした。
「実際は事実確認のためにしっかり調べないといけないから、言葉に悩んでいる時間がなかったり…」と平山さんの本音も出たほど、あらためて調べることが校閲の基本だと痛感しました。思い返してみると、社会人になりたてのころ「なんでもかんでも記憶する必要はない。正しい情報をどこで引き出せるか、その場所だけわかっていればいい」と先輩に言われたことを思い出します。平山さんも「そのとおり!」と強くうなずいてくれました。「読む姿勢」を大事にしながら、校閲チームの一員として周りから信頼される仕事を心がけたいと思います。
伊藤 貴彬(いとう・たかあき)
2018年12月入社。LINE株式会社ポータルカンパニー編集局校閲チーム所属。
サッカー雑誌の編集・オートバイ雑誌の編集を経て校閲へ。オートバイ雑誌時代の弾丸日帰り企画(東京~山口往復2000km)など長距離運転の体力には自信あり。
👇「LINE NEWS」LINE公式アカウントを友だちに追加
https://lin.ee/chNt6wW/lnnw
LINEで更新通知を受け取りたい方はこちら。(※スマホ閲覧時のみ有効)
