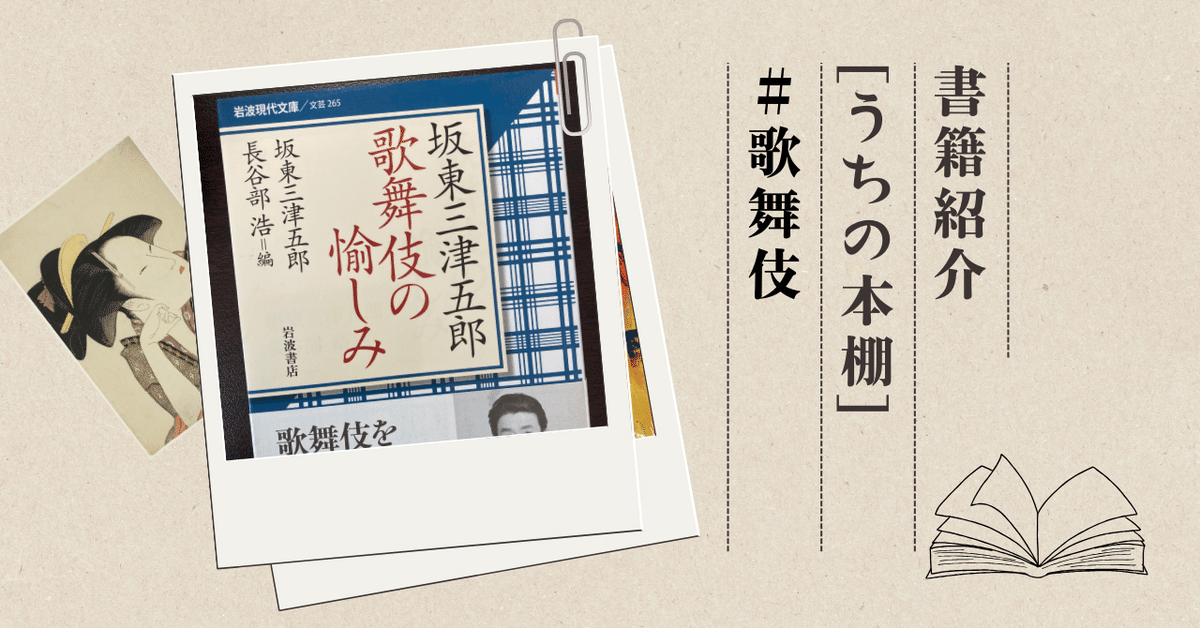
『坂東三津五郎 歌舞伎の愉しみ』 【うちの本棚】#歌舞伎
読書感想でなく、本棚にある歌舞伎関連書籍について、どんな本なのか記録しつつ紹介するものです。
基本情報
タイトル:坂東三津五郎 歌舞伎の愉しみ
発行(奥付の初版の年を記載):2016年 ※2008年に岩波書店から刊行された単行本の文庫化
著者:坂東三津五郎 編:長谷部浩
出版:岩波現代文庫
表紙

歌舞伎を観始めて2年くらい経った人が、歌舞伎をより深く楽しむための本を、という趣旨で作られたもの。十代目坂東三津五郎が、世話物、踊り、時代物、新作歌舞伎などについて具体的な演目を例にして語っている。
おおよそ一年かけて聞き取ったものが文章にされている。ふりがなにそれがよく表れている。
「八代目三津五郎」、「九代目坂東三津五郎」、「二代目尾上松緑」。
目次が8ページにもわたっている。ひとつの話に、演目を2つ3つと例に挙げてある。知識がひとつずつ、結びついてゆくような面白さ。
各章のタイトルもまた、興味をそそる。たとえば第五章の目次だけを挙げてみる。
第五章 鶴屋南北、泥臭い人間の言葉
油絵のような世界 ・・・・・・・・142
『盟三五大切』『鈴ヶ森』
グロテスクなエネルギー ・・・・・153
『東海道四谷怪談』
この章では河竹黙阿弥の作品との違い、南北作品を演じるときに心に留めていることなどが語られている。他の章も、入門書的な「歌舞伎ってどう観るの?」という客席側からの興味に応える内容よりは、役者がどんなふうに役柄や演目を熟成していくのか、何を感じて演じているかを舞台からこちら側へ伝えてくれる内容となっている。
その他
海老蔵(現在の13代目團十郎白猿)の襲名披露公演で、團十郎(12代目)の代役で弁慶をしたときの話に、胸が熱くなる。
代役がどんなふうに進むのか(まずは3日、とか)という話も興味深いが、弁慶を引き受けた三津五郎の、12代目團十郎への思いやり、心意気に涙が堪えきれない。
「本」のありがたみを、あらためて感じる。よくぞ文字にして残してくれたと感謝したい。ふりがなの特徴も含めて、三津五郎の声が聴こえるような文体。長い時間を経て、再び三津五郎に会えた気持ち。
読んでいるうち、いまわたしは、歌舞伎の知識が欲しいのとは違うな、と感じる。
ただただ、見たい、聴きたい。そう思って読んでいる。
三津五郎の芝居を、わたしは再び見たい。言っても詮無いこと。叶わないこと。それでも思わずにいられない。もう一度、十代目三津五郎の芝居が観たい。
三津五郎が踊りについて語った『坂東三津五郎 踊りの愉しみ』という本もある。2冊並べると、三津五郎格子が2色で、しかも色合いがまた、三津五郎らしくて素敵だ。

