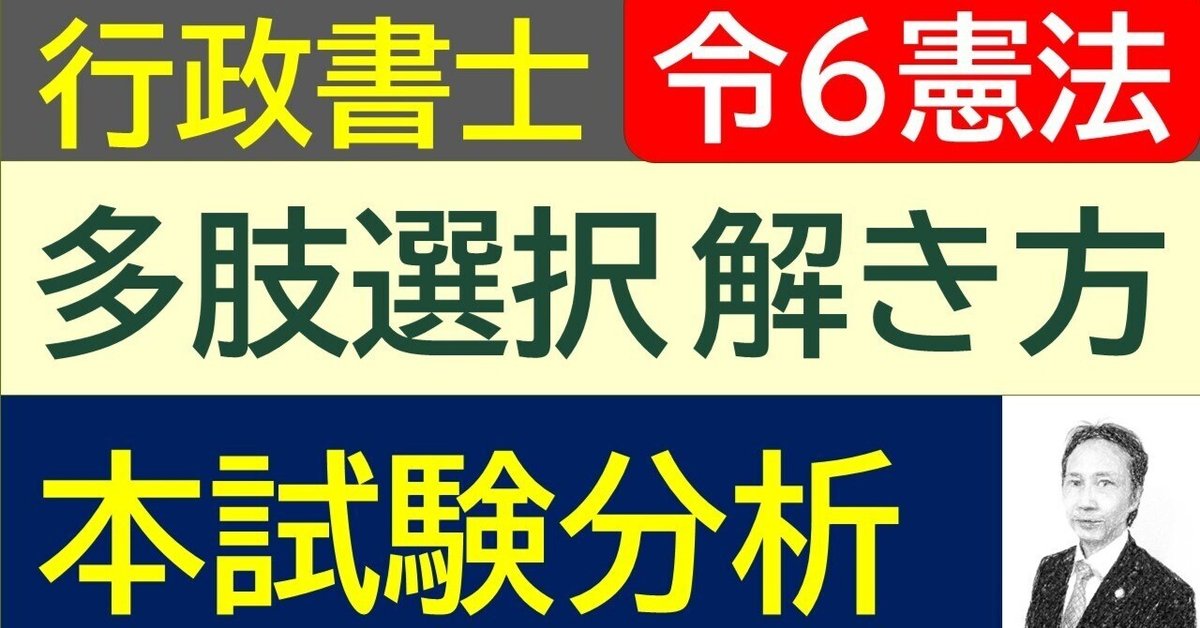
令和6年行政書士多肢選択式の解き方 憲法問41を素材に解説
以下の内容は、YOUTUBE動画と同じ内容です。
令和6年憲法多肢選択 解き方 本試験分析
https://youtu.be/mWmJ5JPSdkM
1 行政書士の多肢選択式問題は解き方がある
行政書士試験の多肢選択式は、選択肢として用意されている多数の用語の中から文章中の空欄を補充するタイプの問題です。素材となっている文章は憲法又は行政法の判例が多いので、判例の単純な知識問題と考えがちですが、実は試験委員側は、多くの受験生が見たことがない文章(例えば、有名な判決の中のあまり書籍で掲載されていない部分の文章等)を素材にして問題を作ることが多いため、事前に覚えてきた判例のキーワードを思い出して解けるような問題ではない場合が多いです。判例の事例や争点が何だったかを知っていることを前提にしつつ、あとは読解力と日本語力で解くことが求められるのが特徴です。つまり、長文読解の法律版であり、日本語を正確に使い分ける力を試す問題だと言えます。
2 令和6年問41を素材に憲法の多肢選択式問題 (空欄補充問題)の解き方を解説
問題文の冒頭に「婚外子の法定相続分を嫡出である子の 2 分の 1 と定めていた民法規定(以下「本件規定」という。)を違憲とした最高裁判所の決定の一部」とあり、非嫡出子相続分差別違憲決定の判例が素材とわかるため、
この判例の「事例」「争点」「結論」を頭の中で思い出します。
事例
嫡出子と非嫡出子の間で、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1という民法の規定に従い、家庭裁判所が遺産分割の審判をした事例。争点
非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1という民法の規定は憲法14条が規定する平等権を不当に侵害して違憲となり無効ではないか。
結論
遅くとも平成13年7月当時(本件相続開始時)において、本件民法の規定は 憲法14条に違反。
有名判例の空欄補充問題については、普段の学習で覚えておいた事例・争点・理由・結論の知識を活用しつつ、読解力と適切な日本語選択をする作業で解くことになりますので、ここまで事前準備ができていないと解けません。
では、ここからは、読解力と日本語選択の緻密に実践して解いてみましょう。
問41で採用された部分の判例の一部を引用しつつ、空欄箇所を示します。
「( ア )としての( イ ) という形で既に行われた遺産の分割等」
もう一度判例の事例を簡潔にまとめると、
「違憲決定が出る前の民法の規定(非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする規定)を参考にする実務の慣例にしばられて家庭裁判所が私人間の遺産分割の審判をした事案」 でした。
空欄のある文章と、事例を比べると、空欄に何が入るか見えてきます。
「( ア )としての( イ ) という形で既に行われた遺産の分割等」
=「民法の規定にしばられて行った遺産分割」と言いたいとわかります。
空欄アと空欄イを分けて、どのようなニュアンスの用語が入るか考えると、
( ア )は民法の規定をあらわすような「ルール」を表現する名詞、
( イ )は「しばられること」を表すような名詞が入るとわかります。
選択肢の中から、空欄アに入りうる「ルール」を表す名詞を探すと、
8の「先例」(前から従ってきたしきたり=ルール)しかありません。
空欄( ア )に入れる用語として、受験生が悩みそうな
12の「家族法秩序」は、「ルール」そのものではなく、「ルールによって調和を保っている状態」をさす言葉なので、「調和を保っている」という意味が入ると、不自然な文章になってしまうので、不適切。
ということで、( ア )には、8の「先例」が入るとわかります。
ここで、( ア )に先例を入れて、( イ )を穴埋めしていきます。
「( 先例 )としての( イ ) という形で既に行われた遺産の分割等」
=「民法の規定にしばられて行った遺産分割」と言いたいのだとわかる。
次に、空欄イに、どのようなニュアンスの用語が入るか考えると、
( イ )は「しばられて行った」を表すような名詞が入るとわかります。
選択肢の中から、空欄イに入りうる「しばられて行った」を表す名詞を探すと、2の「事実上の拘束性」(事実上しばられる)しかありません。
空欄( イ )に入れる用語として、受験生が悩みそうな
20の「裁量統制」は、「行政機関の活動」を制限する方向で使う言葉なので、「私人間」の遺産分割に使うと不自然な文章になり、不適切。
ということで( イ )には2の「事実上の拘束性」が入るとわかります。
次に( ウ )を埋めていきます。
「既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し,いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは,著しく( ウ )を害することになる。( ウ )は法に内在する普遍的な要請であり,」・・・
「( ウ )を害する」のニュアンスは、解決済みの事案として遺産分割の関係者が考えていたのに、「解決済みの状態を害する」と言いたいので、
空欄のある文章と、読み取ったニュアンスを比べると、空欄に何が入るか見えてきます。
「既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し,いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは,著しく( ウ )を害する」
=遺産分割がなされた後の「解決済みの状態を害する」
空欄ウに、どのようなニュアンスの用語が入るか考えると、
( ウ )は「解決済みの状態」を表すような名詞が入るとわかります。
選択肢の中から、空欄ウに入りうる「解決済みの状態」を表す名詞を探すと、4の「法的安定性」(法的に安定した状態)しかありません。
受験生が悩みそうな
12の「家族法秩序」は、2つ目の空欄ウには入りずらい。
「( ウ )は法に内在する普遍的な要請であり」
( ウ )は、法に内在すると言っているので、家族法という特定の法分野だけでなくあらゆる法にあてはまることがらだとわかりますから、
( ウ )には家族法秩序は入りません。
ということで、( ウ )には4の「法的安定性」が入るとわかります。
最後に、( エ )に何が入るか検討します。
「既に関係者間において裁判,合意等により( エ )となったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではない」
裁判により、法律関係が( エ )の状態になったと言っているので、
👇
裁判により法律関係(権利義務の関係)がどうなるのか考えてみると、
紛争が解決し、権利義務の関係が確定しますよね。
よって、
「既に関係者間において裁判,合意等により( エ )となったといえる法律関係」
=裁判等により確定した法律関係
と連想できるので、
( エ )は「確定した状態」を表すような言葉が入るとわかります。
選択肢の中から、空欄エに入りうる「確定した状態」を表す言葉を探すと、10の「確定的」が一番ストレートですし、他に「確定」を表す言葉は見当たりません。
多肢選択式の解き方のまとめ
有名判例が出題された場合は、事前に学習しているはずの事例・争点・結論・理論構成などを思い出してその知識を活用しつつ、初見の文章については、読解力と緻密な日本語選択によって、空欄を丁寧に埋めていきます。
本問は最初の空欄から埋まりますが、最初の空欄が埋まらなければ、埋まりやすい空欄から埋めていき、埋めた用語で違和感が出なければ、空欄に用語をメモして、次の空欄を埋めていきましょう。
行政書士試験の多肢選択式は、判例の事例・争点・結論の知識をベースにはしている場合が少なくないですが、それを前提にしつつ、「読解力と緻密な日本語選択」の問題という意味で、長文読解の問題だと割り切って解きましょう。基礎知識の方で出てくる文章理解3問については、長文読解だと割り切って読解力と緻密な日本語選択をする受験生が多いと思いますが、それと同じやり方になります。
最後に、本問の素材となった判例の文章(空欄なし)を掲載します。
「本決定の違憲判断が,先例としての事実上の拘束性 という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し,いわば解決済みの事案に も効果が及ぶとすることは,著しく法的安定性を害することになる。法的安定性は法に内在する普遍的な要請であり,当裁判所の違憲判断も,その先例としての事実上の拘束性を限定し,法的安定性の確保との調和を図ることが求められているとい わなければならず,このことは,裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる(前記3(3)ク参照)。 以上の観点からすると,既に関係者間において裁判,合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが,関係者間 の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば,本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当で あるといえる。」
いいなと思ったら応援しよう!

