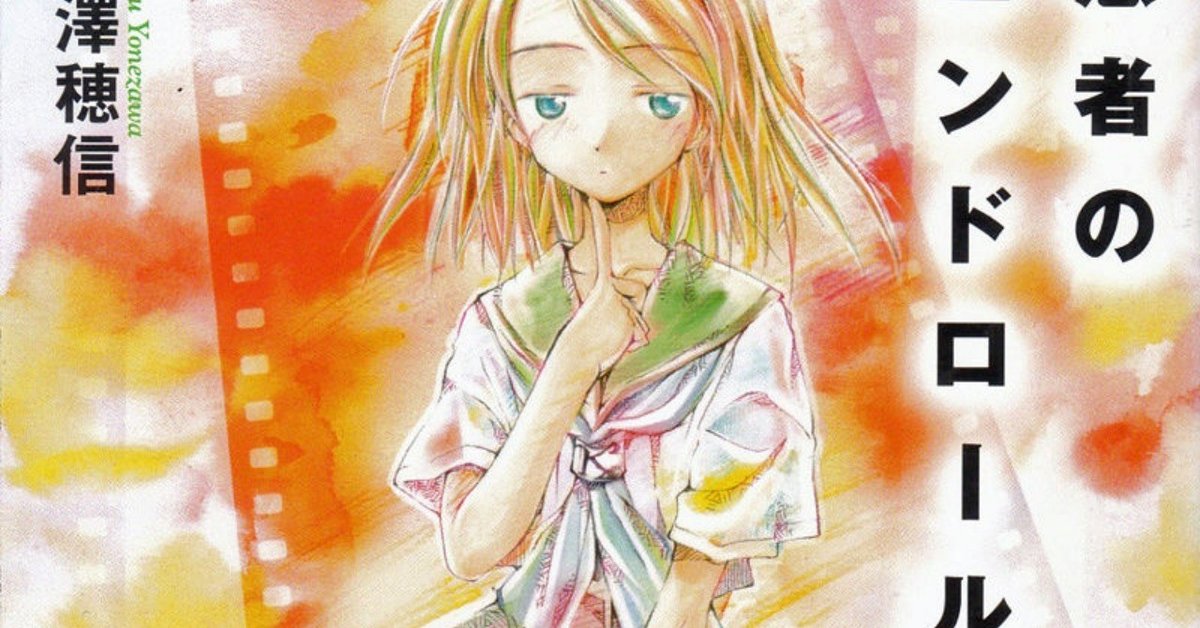
「優しさの理由」
米澤穂信(よねざわ ほのぶ)の小説『〈古典部〉シリーズ』のなかでも、『愚者のエンドロール』が最も気に入っている。このシリーズは、2012年にアニメ化(『氷菓』, 2012.4-9)され、『愚者のエンドロール』は、その8-11話に相当する。このエピソードで、主人公・奉太郎は、未完の自主製作映画の犯人さがしを依頼される。
米澤穂信の作品は、『ドグラマグラ』のように端的にではないが、いわゆるアンチミステリ性を持っている。『〈古典部〉シリーズ』のヒロイン・千反田えるは、主人公で探偵役である奉太郎の推理を常に乗り越えていく。ミステリとしての物語の”解決”は、この物語全体の”解決”でない。千反田えるは、物語のなかに打ち込まれたアンチミステリ的中心点である。そして、これが、省エネをモットーとする奉太郎の唯一の弱点であることも面白い。
さて、(ミステリの)アンチミステリ性とは、ゲーデルの「不完全性定理」や「エピメニデスのパラドックス」として知られる「自己言及」構造に他ならない。自己言及構造は、自我の中心点へまで達する。これは、第一に、己れ以外をすべて否定する否定性であるが、これが自主映画の最後に、その犯人として定立される。これを定立したのは、奉太郎に他ならない。しかし、”える”(エル=天使)によって、否定性としてのこの自我性(即ち省エネとしての奉太郎)がさらに否定され、(エル=天使を「奉」じ一体となることによって)自我の中心点への上昇が下降へと転じ、今度は、この中心点から、すべての創造性が現れ出る。それゆえ、物語のなかで、タロットの「力」に言及されていた点は興味深い。ウェイト版タロットの「力」は、まさにこの創造性を表わしている(s.「Strength,「力」」)。奉太郎は、犯人さがしを依頼した入須=「女帝」への服従では終ることなく、そこへまでたどりつく。
このアンチミステリ性が、まさに、『愚者のエンドロール』という表題に表現されている。「愚者」はタロット(大アルカナの0番)のそれである。実際、作中で古典部員や入須を特徴づけてタロットカードが使われ、「愚者」は、”える”に割り当てられる。そして「エンドロール」とは、物語の”境界”に他ならない。これが、ミステリを越えた、えるの”関心”(「私、気になります」)であり、ハイデガー『存在と時間』における時間性を思わせる。
— しかし、「愚者」=始まりとしての”える”だけではそうなるわけではなく、M,エンデの『はてしない物語』において、幼ごころの君(始まり)と古老(終わり)の出会いが、新たなファンタージエンの創造であるのと同じように、それが”終わり(エンド)”=奉太郎(「力」のライオン〜「太陽」)と共に一つの円環(ロール)をつくるとき、『愚者のエンドロール』は、「力」なのである。
この円環の全体であるときのみ、”える”は、天使であり、アンチミステリー性の中心点である。それは、もしかしたら、絶対的”始まり”であり、大アルカナの最後に置かれるべき「愚者」であるかもしれない。
この作品においては、(2年F組の自主映画の脚本家である)本郷の意図が、えるの関心であった。奉太郎は、えるに導かれて結論へと辿りつく。
えるは、最後、次のように言う。
「クラスメートを刺すわけ、自分を刺したクラスメートを逃がすわけ
それを本郷さんがどう描こうとしたのか、
とても、気になりますが
…
[なぜ本郷の意図を見抜けたかについては]
わたしと本郷さんが、似ていたからだと思います …
実はわたしも
ひとの亡くなるお話は、嫌いなんです」
本郷との共感が、えるの原動力だったのであり、『愚者のエンドロール』が創造したものは、本郷が描こうとしていたもの、「やさしさ」である。
喜びも悲しみもここで
意味が生まれること
ふたり気づきはじめてる
その理由も
『氷菓』OP「優しさの理由」(歌詞 こだまさおり)
