
【Research Conference 2022】miroを使ったオンラインイベントの体験設計
2022年5月28日に開催されたResearch Conference 2022のmiro会場の設計・作成を担当しました。miroには最大同時接続数250名の方にご参加頂けました。ここではmiroを使ったオンラインイベントの設計ポイントについてご紹介します。
Miro会場も大盛況です!#ResearchConf pic.twitter.com/TfIWEHKGRS
— RESEARCH Conference (@researchconfjp) May 28, 2022
miro会場の当日の様子
■フルリモートで参加したオンラインイベント設計
こんにちは、デザインリサーチャーの川勝です🍵 国内初のリサーチのカンファレンスを応援したい、ほかのリサーチャーさんと交流したいという目的で参加しました。地方在住のため準備〜当日までフルリモートで参加しており、共同編集ができるmiroボードの設計を中心に担当しました。
現地スタッフの多大な助力もあり、遠方からでもイベントスタッフとして参加できたことは大変ありがたい経験です🙏 昨今オンラインイベントは増えましたが、リモートでスタッフ参加はハードルを感じる方も多いのではないでしょうか? ご参考の一助になればと思います。
朝の打ち合わせ風景です #Researchconf pic.twitter.com/UqyuAMSsYA
— 木浦 幹雄/ KIURA Mikio @ANKR DESIGN (@kur) May 28, 2022
最終打ち合わせにモニターから参加💻
■オンラインイベントにmiroを使うメリット
今回改めて、オンラインでmiroを活用するメリットを感じた点をご紹介します。
1.会場が盛り上がる🎉
インタラクティブに参加できるmiroを通して「開かれた場だと感じた」「カーソルからほかの参加者の存在を感じた」という反応を頂きました。オフラインイベントと比べると盛り上がりを体感しづらい難点に、miroは寄与できるのではと可能性を感じます!
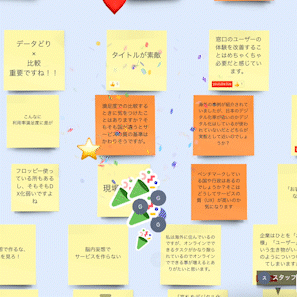
2.学びが深まる✍
Youtube Live・Twitter・miroに散らばった感想や質問を統合し、miroを見たら当日の学びが集約される状態を目指しました。長丁場のイベントでしたので、途中参加の振り返りとしてもご活用頂けたようです。
またリアルタイムでは回答されなかった質問に、登壇後に登壇者が付箋で回答を頂けたのは非同期のmiroだからできたことかと思います!(もちろん登壇者のご厚意があってこそでした🙏)
3.交流を広げる🤝
オンラインイベントでは参加者の様子が見えず交流が生まれづらい状況があります。参加者・登壇者との交流に繋がるよう自己紹介エリアを作成した結果、SNSフォローしあったという声をいただきました。また登壇の合間に自己紹介を記入いただくなど、休憩時の息抜きコンテンツとしての可能性も感じました。

■miroのボード設計のポイント
miro体験設計の裏側はこちらに詳細に記載いただいているので、ここではmiroのボード設計にフォーカスしていきます!
①miroへ至る導線誘導も大事
はじめはmiro会場の設計に注力をしましたが、そもそもmiro会場にたどり着けるか、参加したいと思えるか…と不安がありました。PRチームにtweetいただいたところ「miro会場が楽しみ!」という反応も頂き、告知による期待醸成の重要性を感じました!アクセスしてもらってなんぼですね

②簡単な書き込みから徐々に参加難易度を上げるステップを作る
miro会場は「気づきを共有し、学びを深め合う場所」という位置づけですが、ボードを用意するだけでは誰も書き込まないのでは…とまたまた不安がありました。そこで簡単なワークから徐々に難易度を上げるステップを意識しました(ワークショップ設計と近しいものを感じます)
STEP1導入:まずは読むだけ。会場の全体像や目的が分かる説明文
STEP2アイスブレイク:参加している場所や自己紹介(任意)といった考えずに書き込める
STEP3メインコンテンツ:登壇の感想や質問など、より踏み込んだ内容を書き込む

③miroを過ごしやすくする3つのポイント
miroは参加型イベントには欠かせない存在です。ただ参加人数が多く一人ひとりの参加者をサポートできない場合でも、スムーズに参加ができるポイントを検討しました。
1.miro迷子を防ぐ
参加者が自由に移動ができるmiroは、今どこに注目すると良いか分かりづらい難点もあります。そこで参加者を現在地へ自動移動するボタンを作りました(通称「今ここダッシュボタン」)観光ガイドさんのようにここに着いて行こうとイメージでした💁🚩
ほかには…
・「bring everyone to me」の機能で強制的に全員のカーソルを集める
・会場マップを作り全体像を示す
・ボード同士を繋ぐ大きな矢印を配置する(大げさなくらいでOK)
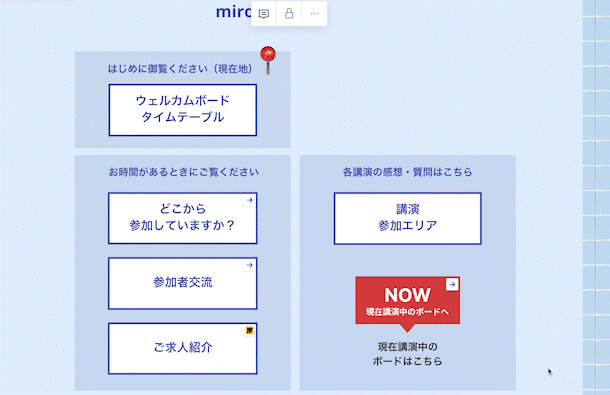
2. 導入説明で安心して参加できる
事前にオンラインイベントのテストを行った時は「どんな目的の場所なのか、どう振る舞ったらよいか分からない…」という声を多く頂きました。そこで具体的な過ごし方をイメージできる説明を載せたウェルカムボードを用意しました!
ほかにも口語体の説明や絵文字で気軽さを演出する、書き込める付箋を二種類に絞って行動をシンプルにするといった改善を行いました。
(余談:参加者が編集できない場所はロックをかけましたが、当日なぜか複製されてる??!!と小さなざわめきが起きました。contrl/cmd + D で複製できるというまだ見ぬmiroの仕様が発見されました)

3.多人数参加を考慮する
参加200名を超えるとmiro一時的にアクセス出来ない状態が続きました.…負荷軽減のためにmiroブラウザ版からアクセス、カーソル非表示などの対策をお願いしました。最終的にはバックアップ会場に付箋等を移動して、ボード上のオブジェクト数を減らすことが効果的だった印象です(アイスブレイクの現在地を示す📍が原因という疑惑)
miro会場に一時的にアクセスできない状況でしたが、現在はアクセスいただけます。
— RESEARCH Conference (@researchconfjp) May 28, 2022
miro会場では、負荷軽減のためブラウザでアクセスいただき、矢印は消して(画像参照)ご参加いただけますようお願いいたします。#ResearchConf pic.twitter.com/MuidGcUq1e
■オンラインイベントを終えて
改めて参加者なしでイベントは成立しないと感じました。イベントを作る一人として皆さまが楽しんでご参加いただいたことで、みんなで作るイベントとして出来上がるのではないかと感じました。
最後にイベントスタッフとしての感想で終えます。ここまで閲覧頂きありがとうございました🙇
参加者の方にmiroを体験してもらい、対面でなくてもオンラインで感想や反応に触れられたことがとてもとても嬉しく励みになりました…😇
やってみないと分からない事が多い初回イベントで、発起人を筆頭に楽しみながら、試しながら作っていくスタッフの姿勢がとても心地よかったです!完璧を目指しすぎず、ベストエフォートを探る
後日、寄せ書きとスタッフグッズが届き感動しました📦😭 やっぱり現地参加すればよかったかな…と寂しさもありましたがとても嬉しかったです。他社のリサーチャーさんと長期に交流できた貴重な機会となりました!
