
『マッキンゼー式 人を動かす話し方』の感想をここに。
『マッキンゼー式 人を動かす話し方』を読んで、”表現してこその人徳だな” と、思った話。

「徳」が大事になった時代
インターネットラジオの番組で、教育の歴史の話を聴いたことがあります。その中で語られていたのが、「徳」についてでした。
農耕が始まり文明が発達するにしたがって、集団が大きくなっていきました。様々な人を統率するようになったときに、その集団の指導者に必要とされたのが、「徳」だったということです。古代のギリシャ、ローマ、中国の為政者は「徳」を学び、それは武士団を率いる日本の武士もまた同様でした。
このことは、武力・兵力だけではなく、人格を磨き教養を身に着けることが指導者の治世に必要なものとなったことを、示しているのだと思います。武力や権威で統率した流れから、「徳」の大切さに気付くというのが、面白いと感じたものでした。
自分の言うことを誰かに聞いてもらうためには、徳を備え、他の人間からの信頼や尊敬を獲得しながら、人間関係の構築や組織の運営を進める必要がありました。そして、それが有益な手段として認知されたわけです。
それは今日でも同じだと思います。
オススメする理由
「徳」は人物の所作の中に現れていきます。そして、それは体系的に学ぶことができるものです。
『マッキンゼー式 人を動かす話し方』では、その具体を体得するための手法が詳細に紹介されているのだと、わたしは解釈しました。
本書では、人や組織を動かすための具体的な手法が、「仕込み」「仕切り」「仕上げ」の3つのセクションに分かれて紹介されています。またそれらの紹介は、利害関係のある他団体・他者との折衝を行うようなビジネスシーンを想定した内容となっています。
わたし個人はそうした業務に就いておらず、(最近は盛夏の中で、もっぱら田んぼの稲と格闘しているわけで) 直接的に役立てることができる場面は少ないようにも思えます。とはいえ、仕事に限らず、私生活の中でも、他者との関りがある限り、本書の内容が活かされる場面はあります。そして、その場面は少なくないと思うわけです。
本書の内容を高いレベルでこなすのは訓練がいるかもしれませんが、知識として知ったうえでそれを活用できれば、現状をかなり改善できるのではないかと感じています。
ビジネスパーソンに限らず、多くの人に薦めたい一冊です。

相手の立場になって、考えていますか?
「本書」を読んで感じたことは、“他者や組織を動かすために、相手の立場に立って物事を理解することがいかに大切であるか” ということでした。また、自分の水準が十分ではなかったことも感じました。
良質な人間関係を作るために必要なことの一つに、「相手の立場になって考える」があります。(自分のことばかりを考えてそれを他者に押し付けたところで、思うような成果にならないばかりか、逆にマイナスに働くこともあります。)
これまでの自分は、それを理解し、相応に必要なことをやってきたつもりではあったのですが…、「本書」を読んで、『ここまでやらなければ、ひとは動かせないのか』と驚くことになりました。(驚く、といいつつ、自分のこれまでの実績を思い返せば、いくらか腑に落ちるところも、あったりはします。)
人を動かすためには、良質な関係を築き、多くの障害を取り除き、背中を押すまでしなければなりません。
自分が頼む側の立場であった場合を考えてみると、なんとも面倒で、そこまで必要かどうかと二の足を踏みそうなところではあります。ただ、ひるがえって自分が頼まれる側の立場であったとしたら、きっとこう思うでしょう。
「そこまでされれば、やるより他はない」
つまり、人を動かすことは、自らの多くのエネルギーを投下することでようやく得られる帰結であった、ということです。それを知り得たことが、本書から学ぶ大きな収穫であったと感じています。
ちょうど同僚に頼んだ仕事の進捗が思わしくないところです。「仕上げ」の精度が悪かったのでしょうか。普段であれば、もうしばらく干渉せずにおくところではあるのですが…。なにか困ったことでもあったのかもしれません。それとなく状況を尋ねてみるところから始めてみたいと思います。

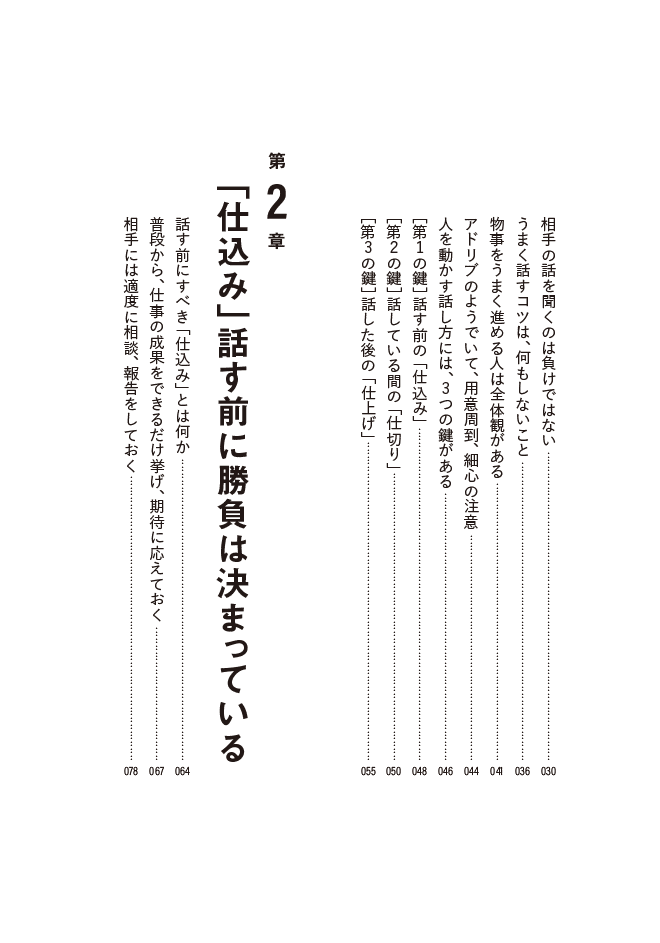

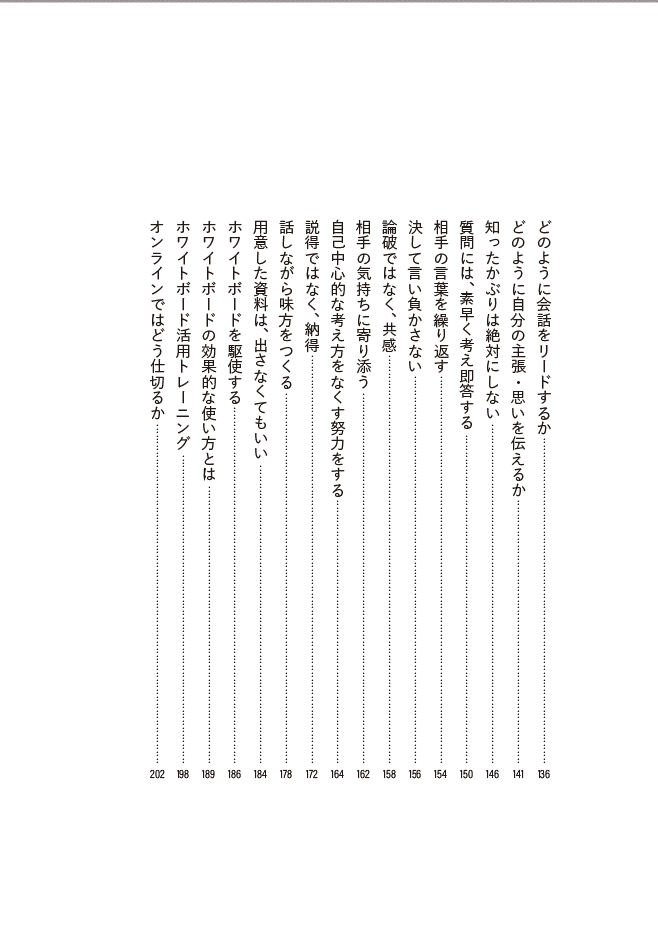

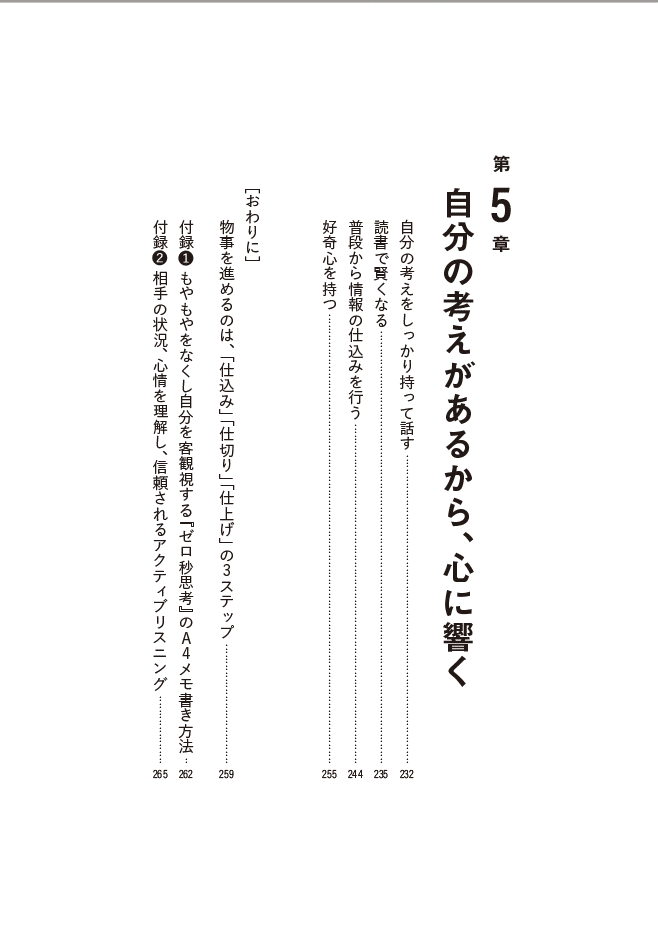
最後に。
本書の5章に述べられた以下の一文が印象に残りました。
「自分の考えをしっかりもつことが、『心に残る話し方』の出発点」
本書の中で紹介されている、相手のことを考えてながらうまく仕事を進めていく方法・技術は間違いなく有用です。それに加えて、自身の研鑽もまた、方法・技術を活かすための土台になりえると、そのことを上の一文から感じました。
“自分はどうしたいのか” が明確であるためには、自身が教養を身に着け内省を重ねることが不可欠だと思います。「徳」を体現するための技術と合わせて、それそのものを磨くことで、循環的にステップアップしていくことができるはずです。
それらの相互を以って自分が動き、人を動かし、仕事や私生活を充実させたい、そして、幸せな人生を歩めたらいい、と思っています。
___
