
第4回 書店人の覚書帳
日経ビジネスの特集「書店再興」というシリーズがあります。
それにしても、【再興】という言葉には、少し違和感があります。
再興とは、衰えていたものがまた興ること。衰え(いったんやめ)ていたものをまた興すこと。
現在、経済産業省ですすめているのは、「書店【振興】プロジェクトです。
振興とは、物事を盛んにすること。物事が盛んになること。
さらに、この記者
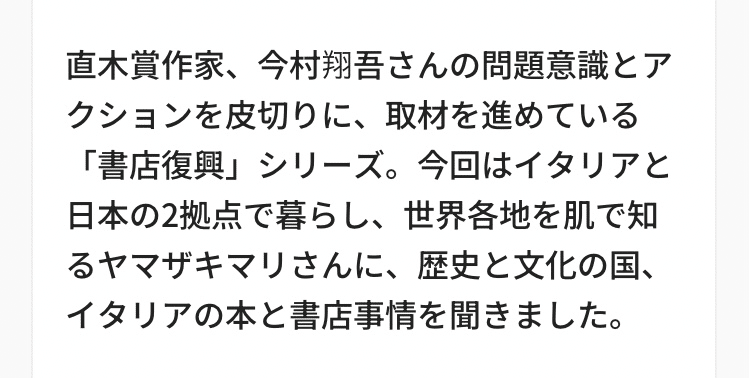
記者が「再興」でなく、「復興」とまで言い始めている。大丈夫なのだろうか?
【復興】とは、一度衰えた(こわれた)ものが、再び盛んに、また整った状態になること。また、そうすること。
そして、この「書店再興」の記事で、漫画家のヤマザキマリさんが取材に応じています。
ヤマザキマリの『テルマエ・ロマエ』は、傑作でしたね。コミックス1巻が発売されたのは、2009年11月ですから、もう15年以上経つのですね。
ヤマザキマリは「本屋でわくわくできなくなってきた」
ヤマザキ:今の世の中では、昔のように本というものが人をわくわくさせなくなってきている印象があります。
ーー漫画、エッセーと次々にヒット書籍を生み出しているヤマザキさんの口から、そういう言葉が出るなんて、本当に危機そのものです。
ヤマザキ:危機的状況だな、と思うことの筆頭に、自分自身が本屋さんに行っても、わくわくできなくなってきていることもありますね。
ーーそれは日本? イタリア? 両方?
ヤマザキ:日本で。
「売れ筋」の圧が本屋への足をすくませる
ヤマザキ:このインタビューの第1回で、私の夫がイタリアの書店へ行くと、金の匂いしかしない本ばかりでうんざりする、と言っていた話をしましたが、私は日本の本屋へ行くと、彼が言っていることと同じような圧力を感じてしまいます。
昔はそんなことはなかったんですけど、自分も本を出す立場になって、そう感じることが多くなりました。ただし、神保町は別です。神保町の古本街は行くとアドレナリンが放出して、8時間ノンストップで本屋巡りをしている、ということはいまだにあります。
ーーそうそう、それは分かります。神保町は特別に楽しいですね。
ヤマザキ:でも、ショッピングセンターの中にあるような書店は、売れ筋の本がズラッとフィーチャーされているじゃないですか。あの光景が私にはとてつもない圧に感じられて「今はこういう作品じゃないとダメなんだよ、お前ももっと頑張れ」みたいに訴えられているような気がして、もうやめよっかな、みたいな気弱な気持ちになる(笑)。根性が足りないんですよ。
渡世は「いわゆる独立系書店」ブーム。店主の目利き、選書に惹かれて足をはこぶ読者も多く、反対に所謂、ローコストオペレーションのチェーンストアの書店のことを、「どこも同じ品揃え」「画一的」などと批判する声もあります。
しかしながら、ヤマザキマリさんの「わくわくできない」「『売れ筋』の圧が」がという言葉に、何故か同調している自分がいます。どうしてなのか?と考えてみました。
「売れる本」と「売らなければならない本」が売場を占めている
「売れる本」とは、ベストセラーのこと。まさに置いておけば、売れる本です。しかし、一頃と違って第一位がミリオンセラーという時代ではなくなってきました。売れる点数も量も減り、売れる期間も短くなっています。
そして、「売らなければならない本」とは、特約店契約を結んでいる出版社の本のことです。売れれば報奨金を受け取れます。書店の営業利益は、売上の1%もなく、出版社から得られる報奨金は、経営にインパクトがある金額です。やめるにやめられないの実態。
特約店制度が書店の売場を「どこも同じ品揃え」にする
この特約店契約、ひと昔前までは機能していました。特約店の書店と特約でない書店が同一立地にある時、特約店には新刊配本が送られてきますが、特約でない書店には、本が配本されず、優遇された書店は、本が売れたのです。
しかし、競合店は閉店し、特約店だけが生き残っても、そもそも特約の出版社からベストセラーが出るとも限らず、やがて、その特約の書店そのものも閉店に追いやられているのが現実なのです。
POPの乱立が「売れない」と泣き叫んでいる
僕は新聞の出版広告を見ても、「?」と思う広告を目にします。今の新聞の読者は、50歳以上ですが、あきらかにティーンや20代、30代の若者向けの本に全5段広告を出しているのを見ると「売れない!売れない!誰でもいいから買ってください!」と泣き叫んでいるように見えてしまいます。
それと同じようにPOPが乱立する書店の売場を見ると、「売れない!売れない!誰でもいいから買ってください!」と泣き叫んでいるように見えてしまうのです。

「画一的な品揃え」からの脱却
ここから脱却するには、特約店制度そのものを見直す必要があります。書店員が自ら選んだ本が店のいいポジションで展開されるようになれば、「画一的な品揃え」と批判されることもなくなるのでは?
ナショナルチェーンをインディ書店の集合体へ
ここに好事例を紹介します。日本ではなく、アメリカ🇺🇸のバーンズ&ノーブルという米国最大の書店チェーンの話です。
書籍チェーンストアの最大手、バーンズ&ノーブルの最高経営責任者(CEO)ジェームス・ドーント氏がメディアの取材に対して、今年は60店舗の新店を予定しているとコメントしていた。昨年は57店舗だったそうだ。
実は同社が再生したという情報は、以前から知っていたのだが、2年続けて大幅に店舗を増やすという計画を目にして、同社の復活は間違いないことだと確信しました。
ー中略ー
「本に情熱をもっている人を雇い、彼らが望むように本を売らせる」
2019年に再建への取り組みをスタートしたときには、「商品の80%は本社が決めて各店舗に供給し、販促は全て本社企画で実施しているので、全店舗がほぼ同じ品揃えになっている。これを変えると言っていた」
業界用語で表現すると、供給主導型のチェーン運営方式だったのを、需要主導型に転換するということを、言っているのである。
『米書店大手B&N、復活のカギ』(鈴木敏仁)

他にもバーンズ&ノーブルに関する記事があります。
いかがでしょうか?!
日本の書店チェーンも、特約制度を見直して、店頭から「売らなければならない本」を減らし、本社で一括して仕入れを決めるのでなく、本に情熱をもった現場のスタッフが選んだ本が売場の前面にでてきたら、日本の書店事情も変わるのではなかろうか!
つづく
