
古書の記憶をたどる
先日、古本屋で一冊の本を書った。講談社学術文庫の『みちの辺の花』だ。
四季折々、散歩中に出会う身近な花にまつわる文章(杉本秀太郎)と淡いタッチの絵(安野光雅)をまとめた画文集。
棚から取り出してパラパラとページをめくると、淡い色で描かれた花々が目に入った。
「美しい本だな」
そう感じて即決で購入した。ポケットにしまい、帰りのバスの中でページをめくった。すると、とびらに赤ペンで書き込みがあった。
「薊」
花の名前? 前の持ち主の名前?

さらに目次を見ると、この本が2年間にわたって春夏秋冬の野辺の花が見出しになっている。しかし、春夏秋冬で章立てはされていない。
そのため、「春」「夏」「秋」「冬」と見出しの上に鉛筆で書き込まれている。

「ああ、前の持ち主が索引しやすくするために書き込んだのだな」と感じた。
そこから書き込みされている箇所に、なにが書かれているか気になって、赤ペンの印を探した。好きな花なのだろうか。
たとえば、「菜の花」を説明する文中の「オランダ芥子」に線と丸印がついている。たとえば、過去の話、戦後すぐの時代の風景描写に線が引いてある。

ほかにも花を使った詩や歌の書名に大きく丸印がついている。読んでみようと思ったのだろうか。
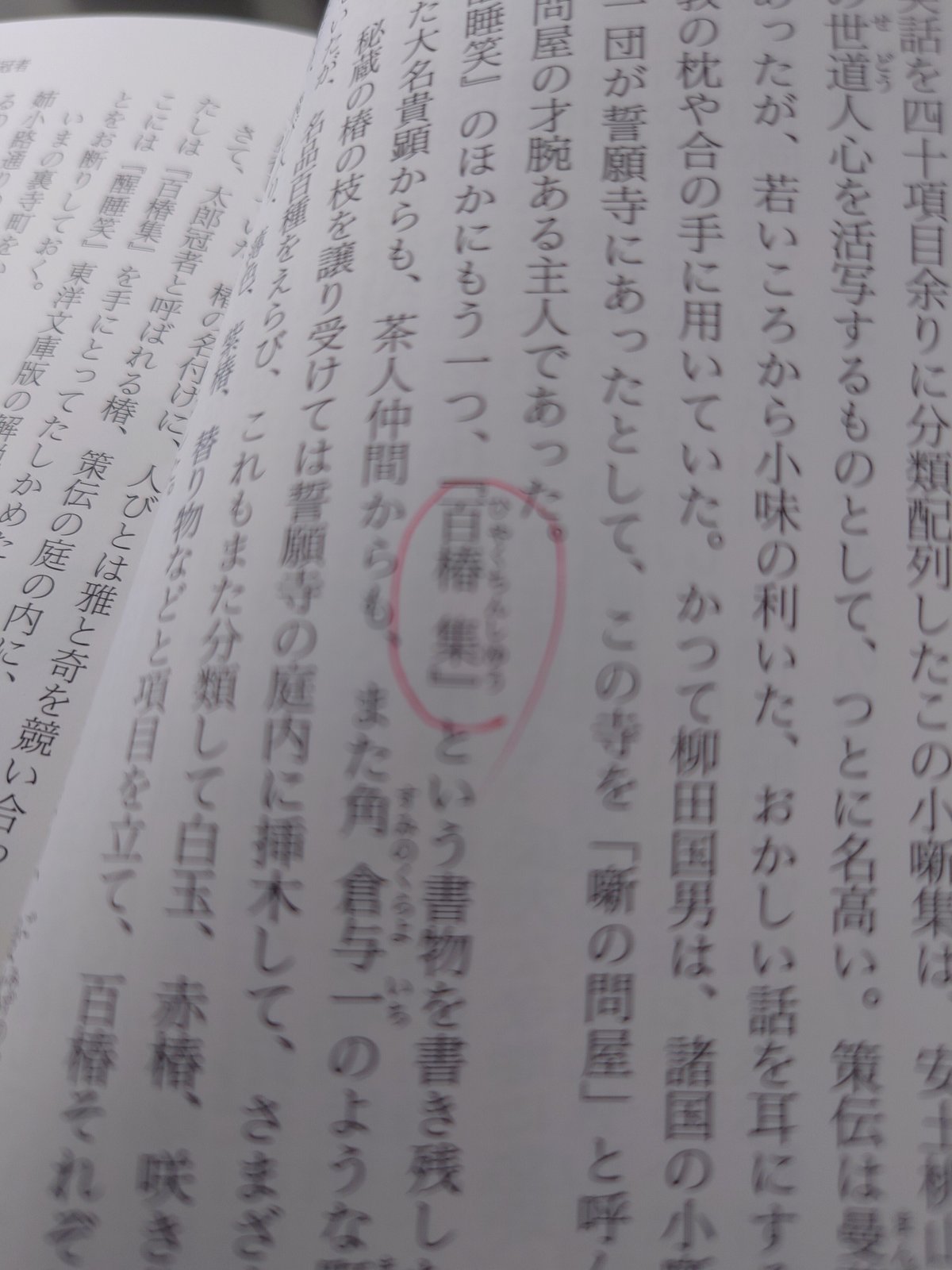
花の別名に関心が強いのか、ときには丸印ふたつを線で結び、余白に「ヤブカンゾウ=ワスレグサ」のような書き込みがある。
ここで、「季のめぐり一 夏」が終わり、以降に書き込みがなくなった。この人は秋と冬の花には興味がないのか。それとも何らかの事情があったのか。
ページをめくり、「花への付け文」と題されたあとがきに、一本の赤線が引かれている。
「道ならぬ恋の淵に沈み、行き暮れていて、ふと」
以前の持ち主は恋に破れたのだろうか。それとも恋が成就して花言葉が不要になったのか。はたまた亡くなってしまったのだろうか。
古書には遍歴がある。絵本の落書きや学術書の片隅のメモ。著名な文人のものであれば博物館に残るであろう痕跡も、市井の民が残した痕跡は、人類が滅びた後の遺跡から発掘でもされない限り価値を持たないかもしれない。
しかし、このように古本は内容を楽しむだけではなく、価値が下がるとされる傷をあえて楽しむことができる。そのような想像力をわたしは持ちたい。
この記事を読んで面白いと感じてくださった方には、原書房から出版された『書籍修繕という仕事』がおすすめ。モノとしての本への偏愛を感じられる1冊です。
