
漆工芸家の三木表悦です。「うるし」を京都で塗ってます。
自然と人と文化が共存できる社会へ


こんにちは。
四代三木表悦と申します。京都で漆工芸をしています。
今回は7月16日に行うイベントの話を少し。
京都は祇園祭の宵山の日。
佐々木酒造さんにて、5人のメンバーが集まって、京都を楽しむイベントを用意しています。そのメインターゲットは子供たち。未来の担い手たちに、日本の伝統文化のエッセンスを体験してもらう予定です。
メンバーはそれぞれのジャンルのプロフェッショナル。それぞれの見つめてきた世界を紹介します。
私はその中で漆工芸でよく使う「押し紅葉」という技法を皆さんに
体験してもらいたい。
文字通り楓(モミジ)の葉っぱに色を付けて押し付けて模様を転写する技法です。技法としてはシンプルな技法なんです。

これは黒の漆の上に黒で押し紅葉

こんな感じとか、、。

こんな感じの作品もあります。
今回は技法の体験なので漆ではなく樹脂で行いますので
かぶれの心配もありません。
ただ大切なことは葉っぱを選ぶこと。
皆さん生い茂る葉を一枚一枚見た事はありますか?

じつは楓は多くの種類があり、その葉っぱの形も様々です。
その中でモミジも一枚ごとに少しづつ特徴が違います。
その木が生えて居る場所や
その年の気候、樹齢などによっても変化があり
一本の枝の中でもよくみると、同じ葉は一枚としてないのです。
人間の指紋のようですね。
今回の体験を通じて、まずは物をよく見る事、
そしてそのものをもっとも印象深い場所に図案として配置するために
どの位置にどちら向きに置けばよいか推敲すること。
この二点を体験してもらえたらと思っています。
葉書に押し紅葉をして世界に一枚だけのカードを作り
大切な人に、今の自分を伝える手紙を書く。
絵を描くのが苦手なら、絵になる「葉っぱ」を一生懸命探す。
その視る力こそが子供たちには大切なのです。
メールが発達し、携帯電話が普及しましたが
やっぱり手紙はいいものです。
未来の担い手たちには、ぜひその経験をしてほしい。
京都、祇園祭、二条城の北、佐々木酒造、
そこで様々な体験をしてそのメッセージを伝えることは
子供たちにとって、エポックポイントになると思います。
そういえば自己紹介

明治24年に初代が12歳の時に
福井県の丸岡から京都に修行に出てきたのが「表悦」の始まりと聞いています。
祖父の本名は「延」で
「表悦」という名は師匠の木村表斎(二代目)から
弟子明けの際に「表」の字をいただき代々その名を継いでおります。
冒頭でもお話しした通り
私自身は四代目の塗師屋の名前を継いでいます。
物心ついたころから家族中が物作りに関わってきました。
そんな家に生まれ育つと初代の事は、否が応でも意識する存在でした。
四代目を継いだ今もその存在の大きさは変わりません。
私自身は初代とは会ったことはありませんが
工房には初代が使った道具や、仕掛品などが少しづつ残されています。
父や祖父から聞く思い出話や
曽祖父の残した作業道具を通じて向き合うことは
名前を継ぐものとして常に意識してきました。

明治大正昭和平成の時代を初代、二代、そして父(三代)と
それぞれが時代と向き合いながら
自分が良いと思うモノづくりを取り組んできました。
代々が商売としては下手だったようですが
作るものは代々の特徴がしっかりとしており
多くの賞もいただいたようです。
漆工芸の作り手としては自由気ままな生き方であったのかもしれませんが
これも京都という町だから受け入れられたのかもしれません。

京生まれ京育ちだけが京都人ではありません
文化の中心地である京都は常に新陳代謝をしながら
多くの若者が全国から京を目指して集まり
京で学んだ技や心を修めて日本中に伝えていくこともおおいようです。
学生の町といわれたことからも、そのことはうかがえます。
また、京都の町衆も全員が代々の京生まれというわけではありません。
京都に思いを持つ人が集まり
京都という生きた街をつくりつづけています。
その中には多くの「職人」たちがいます。
初代も片道切符で京都に修行に来て師匠はじめ
多くの方の縁で京都に根差し、その一生を全うしました。
物づくりにはその人柄が出ます。
特に現在「伝統」と認識される物づくりには
物の一つ一つにドラマが見えます。
作り手と使い手が近い距離にいる京都の町だからこそ
余計にそのドラマは生まれやすいと考えています。

使いたい器と使いやすい器は違います。
使ってみて初めて分かる使いやすさもあります。
頭だけでは理解できない。
知識だけでは気が付かない。
実際に人と人が様々な出会いをして初めての気付きが生まれます。
京都の町はそのコミュニケーションの距離感が適度に近いのです。

永く使い続けると次第に赤が磨き出てきて、唯一無二のお椀になる。
そんな京都の町だから
京都では手仕事で物を作るときには
作り手と使い手がお互いに話をしながら物を作ります。
これは京都以外でも当たり前。
職人が真摯に物を作る必要条件として
顔が見える物づくりであり、顔の見える使い手が望ましいのです。
ただ、こういったスタイルも、時代の変化と共に
どんどん変わっていっています。
残ってほしいと思っても残らないものもあります。
工芸だけでも京都の長い歴史の中で様々な流行やスタイルがありました。
ただし中には変わってないものもあります。
同様に京都の町の気温も、水も、人も景色もどんどん変化していますが
変わってほしくないものもあります。
私は未来の担い手たちに
その変えていきたくないものとして
持続可能な社会を考えるきっかけを私たちなりの目線で
提案したいと思っています。
そのためには様々な経験をする機会を提供したい。
その中で、未来担い手たちに選択してもらえるように
私は私なりの物づくりを貫きたいと考えているのです。

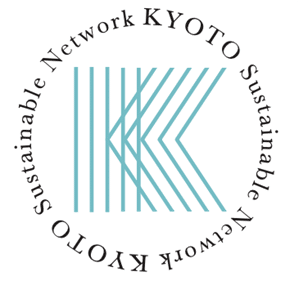
自然と人と文化が共存できる社会へ
KYOTO Sustainable Network
