
おじいちゃんの話
私のおじいちゃんは、大正生まれだ。
もうなくなってしまってずいぶん経つけど、私の子供時代の思い出には必ず登場する重要人物のひとりである。ユーモアがあり、ちょっとわがままで、それから甘えん坊だったのかもしれない。ような気がする。
大人になってから私はおじいちゃんと血液型が同じだったと聞かされた。その血液型は、おじいちゃんからしか遺伝しないことがわかっているので、血を分ける、という言葉は私におじいちゃんを思い出させる。
勝手に、似たところがあるようにも感じている。
おじいちゃんは大正生まれだから、やっぱり、戦争に行った人だった。子供の頃、もちろんそれを知っていたけども、おじいちゃんにあれこれ質問したり、聞いたりした記憶はない。これもあとになって、おじいちゃんはかなり危険で、シビアで、恐ろしい経験をしたことを知るのだけど、実際、おじいちゃんは戦争経験について、孫にはほとんど語ることはなかった。子供に聞かせることのできる話ではなかったのかもしれない。それでも、いくつかその片鱗のようなものを聞いた覚えがある。
よく覚えているのは、暗闇でものを見る方法、である。
おじいちゃんは陸軍にいた。最前線のジャングルに派遣されたと聞いた記憶がある。そんなおじいちゃんが、ある日突然、私にサバイバル術のようなものを教えてくれたのである。
ちょうど私は、祖父母の家の掘りごたつに潜り込んであそんでいるところだった。自宅には掘りごたつがなかったので、それは当然ながら子供の冒険心をくすぐり、私は中に入ってごそごそといつまでも遊んでいた。母もおばあちゃんも、目が悪くなるからやめなさい、だとか、いい加減にしなさい、だとかいって、なんとかして私を外に出そうと苦心していた。おじいちゃんは、出てきなさいとは一度も言わず、そのかわりに足元で熱心に探検する私にこう言った。
赤い光を見てからな、かぁぁっと目ぇ開くとな
暗いところでもよぉ見えるんや
どこまでが実際の話で、どこからが子供向けに噛み砕いてくれた話なのかはわからないけど、暗いところでものを見る前に、赤い光に目を慣らすといいんだ、とおじいちゃんは言った。さらに子供にとって衝撃的だったのはその後だった。なんとおじいちゃんはこう付け加えたのだ。
白目で見るんや
しろめでみる、とは。
直感で言葉を理解する子供だった私はしかし、なんのことだろうとは思わず、なんとなく、わかった、という気がした。「かぁぁっと目ぇ開く」という部分を説明してくれているのだ。なるほど、と私は思い、早速試してみることにした。(良い子は真似をしないことを真にお勧めする)
掘りごたつの中で、赤い光(昔は遠赤外線のランプに赤い色がついていたのだけど、いまのこたつは違うようだね)をじっとにらみつけ、それから目を薄く閉じたままこたつからいそいそと這い出し、締め切った納戸へ向かった。真っ暗な部屋の中で「白目で」見る。
うぅん。なんとなく、見えるような、気がする。
子供の柔軟な目が、あっというまに暗順応しただけのかもしれないし、おじいちゃん直伝のテクニックのおかげなのかもしれない。理由はよくわからない。しかし、たいして待たずとも、暗闇の中にうっすらと、棚や箪笥、おばあちゃんのミシンなどがおぼろげな輪郭と共に浮かび上がる。
ふむふむ。白目で見えるかも。
面白くなった私は、何度もこたつを出たり入ったりし、そのたびにおばあちゃんから、もうやめとき、と声をかけられた。おじいちゃんはにこにこしているだけで、何も言わなかった。
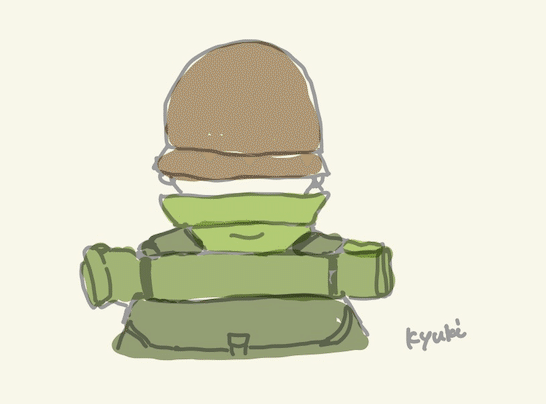
おじいちゃんは、酒の席で、よく踊った。踊って、と言われたら断れないからだ。みんなが笑ってくれるのもうれしかったのだと思う。
そういう人なのだ。
そもそも踊るのが好きだっただけなのかもしれない。あるとき、私がふいにテレビのある部屋に入ったところ、おじいちゃんがひとりで、それはそれは楽しそうに阿波踊りをしているのを見てしまったことがある。テレビで見て一緒に踊りたくなったらしい。狭い部屋の角から角へ。対角線を使って最大限に長い距離をとり、おじいちゃんは実に楽しそうに踊っていた。私と目が合って、あ、という顔をしたけど、いまさらやめるわけにもいかないようで、仕切り直しとばかりに,部屋の角に戻ってまた踊り始めた。実に楽しそうだった。

ひょうきんなだけでなく、ちょっと繊細なところもあった。おじいちゃんは剣道の師範だったし、体つきもいかにも頑丈で、運動して鍛えているのかなと思わせる風情だったけど、見た目とは裏腹に走るのは大の苦手だった。どうやら足が遅いことを気にしていたらしい。子供の頃は学校で走る行事があると、夕方まで掃除道具のはいった小屋に隠れていたと聞いた。
私もうまいへたは別にして、踊るのが実は大好きだし、走るのは大嫌いだ。それにちゃんと足が遅い。
だから、きっとおじいちゃんの血だ。
ちょっと嬉しい。
おじいちゃんは、話のネタになる出来事をたくさん生み出す人だった。おばあちゃんや母の、ほんまにもぉ、という言葉とともに、いつもそれらは語られた。
たとえば、そそっかしいおじいちゃんは、郵便局に郵便を出しに行き、窓口の方とうっかり話し込んで、財布を置き忘れて帰ってきたりした。田舎の郵便局だから名前も電話番号も、どなたか担当の方がよくご存じらしく、おじいちゃんが帰宅するころを見計らって、お忘れですよとわざわざ電話をくださった。すぐに、やぁこれはこれは、といそいそ出かけて行って財布を取り戻し、またうっかり話し込んで、結局郵便は出さなかったりした。
今日一日、なにしとったん、とおばあちゃんは呆れていた。
自由きままなので、やりたいと思ったらすぐやってしまうのも、おじいちゃんらしいところだ。今日は乾燥していて危ないから焚き火はだめですよ、と平和な田舎に有線放送がかかっているそばで、落ち葉をかき集め、庭でもうもうと煙をあげて焚き火をしたりもした。もちろんすぐにおばあちゃんに怒られて火を消されてしまった。
なんでそんなことを、とツッコミたくなるエピソードには事欠かない。

おじいちゃんがなくなってから、田舎の家を整理することになった。その時、大量の土地の権利書が出てきて、母をはじめ家族たちが大騒ぎになった。なぜなら、そこに書かれた土地は他の家族にも心当たりがない、てんでばらばらの場所だったからだ。その上、小さかったりいびつな形だったり、畑もなにもない不思議な場所ばかりだった。いったいなんでこんな土地を、とみんながいぶかった。
やがて情報を整理していくうちに、意外な事実が明らかになった。おじいちゃんは自宅の周囲やいくつかの場所に畑としてまとまった土地を持っていたらしいのだけど、もう歳とって畑はやらんから、と言い、自分のまとまった畑と、若い世代の農家の方が持っていた耕すに耕せないハンパな土地を交換していたらしいのだ。そうやって、もともとバラバラな耕しにくい場所に土地をもっていた農家の方が、まとまった場所で畑をもてるようになったりした、らしい。
いつの間にそんなことをしていたのか、おばあちゃんも知らなかった。きちんと同じくらいの面積を交換したとか、地価を等しくして交換したとか、そんなことはもちろんやっていないようで、いわく、なんや口約束みたいなもん、で交換していたようだ。
あっちゃこっちゃに飛び地みたいなもんこさえて(こさえる=こしらえる、作る)とおばあちゃんは呆れ顔だった。
なくなってからもおじいちゃんは新しいエピソードを提供してくれた。
おばあちゃんと母はまたため息をつき、ほんまにもぉ、と言った。
草葉の陰があるのなら、間違いなくおじいちゃんはそこで笑っているに違いない。いや、踊っているかもしれない。
いずれにしても、私には分けてもらった血が流れているので、おじいちゃんはまだここにいる、ともいえる。これを遺伝的に分ける人はいないけど、おじいちゃんの畑みたいに、知らない誰かに何かを分けることはできる。そうやってこの世界に何かを残しておこうと思う。
ほんまにもぉ、と言われるのは、実は好きだ。
