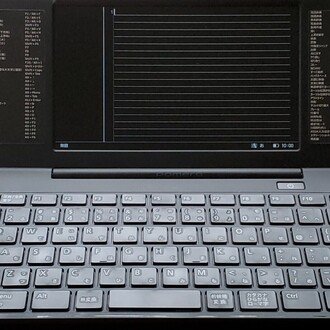これからの教養 激変する世界を生き抜くための知の11講 を読んで 知のフロンティアを垣間見る
今回も続いて書評にしようと思います。
ここのところ、自分のレベルから見ると深い内容の本が多くてあまり進んでいませんが、一冊一冊からは滋味のあふれる知識や考え方に触れることが出来ています。
年明け最初に読了した本ですが、今回の著書も至高の一冊でした。
今回の書評は書評と言うより、講義録のまとめ、みたいな感じになっています。
では、対象著書のメタ情報からです。
今回も読書ノートからの書評ですので、小理屈野郎の読書ノート・ローカルルールの凡例を以下に示しておきます。
・;キーワード
→;全文から導き出されること
※;引用(引用の背景で示されていることもあります)
☆;小理屈野郎自身が考えたこと
書名 これからの教養 激変する世界を生き抜くための知の11講
読書開始日 2022/12/19 18:08
読了日 2023/01/08 17:00
読了後の考察
途中休憩をしながらかなり時間をかけて読了した。
この著書では11人の知のフロンティアが登場する。
これからの教養、というより知のフロンティアの現在 、という感じを個人的には非常に強く受けた。教養という言葉は、マーケティング的には非常に便利な言葉だが実際は上記のようなことではないか。
ここで登場する人たちは、すべて普通にテレビや雑誌などに登場する人たちよりずっと深く、広く考えている 、ということが非常によく分かった。
哲学についても私たち世代とその少し下の世代が思いのほか活躍している こと。
建築系はデザインと結びつき、建築以外のもののデザインを模索している こと。特にデザイン系の人物と建築系の人物の内容はオーバーラップしているところが非常に多かった 。これには驚いた。
デザイン思考、といわれるがそれ以上のことを彼らは普段からやってのけているのだ、と実感した。
文学も独自の進化を遂げるべく、一部の作者たちは非常に研鑽を積んでいること。
理系の人間でも人文系の知識があることでより深く、寄り広く考察ができ新しい結論が出てくる 。
文系の場合は机上の空論と思う人もいるかもしれないが、その机上の空論と思われることでも非常にしっかりと深く、歴史や倫理学などとリンクして考えている場合は、決して机上の空論ではない 、ということがよく分かった。
自分の足下の分野の勉強だけではなくそれ以外の分野の勉強(知識の探求)をしっかりとすることが足下の分野にも大きく影響するのではないかと考えた。
キーワードは?(Permanent notes用)
(なるべく少なく、一般の検索で引っかかりにくい言葉、将来もう一度見つけてみたいと考えられる言葉)
#知のフロンティア
#デザイン
概略・購入の経緯は?
おそらく朝日新聞の書籍広告欄で見たのが契機。平野啓一郎氏、山際寿一氏の講義が載っている ということで購入とした。
どのような講義が展開されているのだろうか?
楽しみである。
本の対象読者は?
知のフロンティアについて知りたい人
各種業界の最先端の思考方法や経路を知りたい人
質問3 著者の考えはどのようなものか?
どんなにたくさんの本を読み、どんなにたくさんの賢い人たちから話を聞いたところで、ひとりの脳の力には悲しいほど限界がある。
有限な人生を生きる、有限な容量の脳を抱えた人間が、それでも少しでも賢くありたいと思う切なさに、知的に生きようとする姿勢の根源がある
→☆これらを実際に経験するために11人の講義録があるのでは、と感じた。
その他(講義のメモ)は書き質問の印象に残ったフレーズやセンテンスは何か?を参照
その考えにどのような印象を持ったか?
上記の質問の考え方には共感を持った。
実際にひとりの能力なんてたいしたことは無いけど、それでも少しでもよくしようと思って読書をしたり思索をしたりする。
その内容は人それぞれなので、それらを前述のようにして知的に鍛えられた「知識人」がフランクに議論することができれば良い社会ができるのではないか 、と思った。
印象に残ったフレーズやセンテンスは何か?
これからの思想(東浩紀)
誰か尊敬する人を見つけて、その人に関連する本だけ読んでいるという状態はダメ(中略)本当は描き手も時代に何かしらの影響を受けているわけで、同時にいろいろな人たちのものを読んでいないといけない
→☆このような言葉が哲学科から出てくるというのもある意味驚きだったが、本当にそうだと考える。
2000年からあとの日本の論壇は政治の話ばかり(中略)今論壇で強いのは内田達樹や佐藤優といった人たち
→☆だから論調が平坦なのかもしれない。このような論争に哲学科、デザイン関連(建築、デザイン)の人が入ってくると非常に面白いものになるのではないかと思う。
中国のような体勢がこれからの社会のモデルになっていくのではないかなと思う。
→☆これは本当に良いことなのかどうだか、ということをしっかりと考える必要あり。個人的にはあのような窮屈な生活はいやだと思っているが、意外とその中に入り込んでしまうとそれほどのことはないのかもしれない、と思うところもある。
インターネットをはじめ資本主義社会は偶然的なつながりをなるべく排除して必然性がある人間関係ばかりをどんどん強化していく装置なんですよね。現代社会では偶然性を導入しなくてはいけない
→☆確かに今の社会は予定調和が多すぎるような気もする。予定調和の中からは予想できる結果しか現れない。これでは人類社会の飛躍はないと考えるべきなのだろう。これでは動物の社会とおなじである。動物の社会は必然性の世界である、ということからこう言えると考える。
僕たちはもう一度偶然性と必然性の関係について考え直さなければいけない。(中略)家族が例になるような「偶然と必然が結びついた」人間関係が大事になる。
シンプルな答えを与えると、それはカルトになってしまいます。(中略)哲学は答えを追い求める日常から少しだけ自由にしてくれる
→☆これは個人的にすごく感じる。哲学する、というか思索することによって、自由な感じを受ける のはこのようなことが原因なのだろう。
哲学を学ぶことに意味なんてあるわけない。
→☆人生の意義について考えることも同様だろう。
これからの生命(池上浩二)
人が生命を作ろうとするとき、通常ものを作るときのような手順で「生きているようなもの」をデザインしようとして「意味ありき」ではじめようとします。だから予測できてしまうものしかできあがらない(中略)予測できないような条件にしておいて、だんだんと意味が見えてくるようになる、といった手順を考えないと、生命を本当にデザインしたとはいえない
→☆これは**「これからの思想」の偶然性にもつながる考え方** だと思う。世の中、偶然、ということが非常に大事なのだ。
遊びは4つに分類できる
1.競争を意味する「アゴン」
2.賭け事のような運の要素を持つ「アレア」
3.まねっこゲームのように模擬を意味する「ミミクリ」
4.ぐるぐる回ると行ったような眩暈を求める「イリンクス」
人類の文明史上、最も複雑なシステムはインターネットなんじゃないか。
自分とは関係の無い世界を持ちながら動いているものを、人は愛する
☆これからの思想ともリンクする内容がたくさんあったと考える。
これからの健康(石川善樹)
予防医学の考え方について非常にわかりやすく書いている。
正義より最善
講演をしている人の考え方の根底に流れるのはこの発想だ。
実際の仕事から得られた結論なので非常に説得力があると感じた。
予防医学とは、病気ではない人たちを対象に、その人たちが元気な状態から転落してしまうのを防ぐことを目的とした学問
そもそも目の前にいるような人が生じてしまった原因に対して怒りの炎を燃やすべき
→☆予防医学の考え方を端的に表現している。
医療制度をどれだけよくしても国民の健康状態は余りよくならない
→☆だからこその予防医学、というところだろう。
意思の力には頼らず、人は弱いという前提で制度設計や環境設計をすべきであるというのが、予防医学で大切にされている考え方
→☆持続可能性のある行動を取るために非常に重要な人間の特性について言及していると考える。
そうすればうまくいきそうに感じる。
「多い数の人たち」に目を向けて対策を立てるようになりました。これを「ポピュレーション戦略」と言います。
→☆この考え方は実際に知らなかった。確かに統計から考えるとこれが妥当と思われる。
医療は病気になった人を対象とする、という考え方を根底から覆し真の意味での社会に属する人たちの健康を創出する、という意味ではこちらの方がより効率的であると考えるに至った。
日本に存在する「社会関係資本」あるいは「ソーシャル・キャピタル」と呼ばれる要素が、長寿と健康に大きく関係している。
→☆おそらく国民皆保険制度についての言及だろう。
WHOでも日本の国民皆保険制度については評価が高いと聞いたことがある。
これからはものを持っていることに価値を置く時代ではなくなっていく
→☆これは世界的な潮流のようだ。確かに必要なときに必要なものを使うだけ、というのが一番良いのかも知れない。
大きな問いを見つけることができれば、その問いは基本的に完全に解けると言うことはないので、楽しい人生になる
→☆常に考え続ける、動き続ける、ということが楽しい人生につながるのではないかと考える。
これからの建築(伊東豊雄)
日本の木造建築には基本的にカベという概念がない(中略)外部環境に応じた様々な場所を用意しておくことが日本の建築の本質
ヨーロッパの建築は、逆に自然からも閉じられている。建築の内部も閉じていて、おまえは一年中ここで寝なさいと言うようなことを機能という概念でもって決める。
→☆日本とヨーロッパの機能についての考え方や、定義などがこれでよく分かると思う。
何か突き抜けていくためには、とんでもないことをやることによって、一気に概念を変えることが必要
→☆継続的な思索ではなく、何かを掛け合わせる必要がある と言うことか。
クライアントが個人として顔を見せない建築は必ず上手くいきません。
建築はずっと遅れていて、遙か以前の思想に基づいて相変わらず作られている
→☆このようなことをしっかりと理解しているからこそよいものが作れるのではないか?
これからの経済(水野和夫)
日本は欧米と比べると比較的格差が小さいと思われていますが、そうではない
→☆企業利益はアップしているのに、個人の収入はダウンしている。おそらく非正規社員が増えたことが原因 だろう(経時的な変化において)
なぜ、富の再分配が上手くいっていないかについて考える必要あり ;原因はおそらく株主への配当性向のアップと企業の内部留保アップではないかと考える。
何のために内部留保をため込んでいるのか、企業は説明しないといけない。
ケインズは「金利がゼロになればこれ以上はもう(内部留保を)増やす必要は無い」と言っている。一方マルクスは「資本は権力の象徴なので無限のプロセスを繰り返すと言っている。
→☆金利ゼロ、ということは内部留保を増やす必要が無い、というのはケインズが昔から言っているのにそれについて言及している記事は見かけたことがない 。どうなっているのか?
その上で
世界の経営者はいわば「マルクス主義経営者」といえる
と喝破している。
本来なら資本主義の主役である株式会社の経営者はケインズの考え方でなければいけない。
ケインズの理論に従ってゼロ金利になれば、「利益はいらないですよ」と言って良いはず。
としている
内部留保があったら、そのうち相当分がキャッシュになっていますから、それを狙った投資家から買収を仕掛けられます。(中略)企業が買収されないように企業自体がM&Aをする
→☆M&Aが盛んになっている理由を理論的に説明すれば、その様になるのだろう。
このあたり、ちゃんと本来ちゃんと記事にすべき日経ビジネスで解説していない。単にトレンドとして捉えている。 このあたりに日経ビジネスの甘さがあるのではないか?
企業の内部留保のうち半分は賃金を減らすことで増やしたもの(中略)これを正当化できる経済理論を作ったら多分ノーベル経済学賞を受賞できる
→☆資本主義社会の株式会社、といってもかなりいびつな形ので運営が現在のトレンドになっているのではないか と考えた。
一番金利が低い国は、一番資本を持っている国であるといえます。低い金利というのは喜ばしいこと(中略)日本の金利が低いのは、コンビニや自動車工場、タワーマンション、空き家、食品など過剰なまでに財・サービスを供給できる資産を有しているから
低金利は新主義先進国の証
→☆このような理論立てた説明を見たことがなかった。非常にクリアカットな説明になっていると考える。
利子率がゼロになるのは望ましいことです。言い換えれば利子率生活者の安楽死がのぞまれると言うこと。
日本はせっかく理想の社会になり始めているにも拘わらずそうなっていなくて、資本を安成長戦略をとっている。日本は資本主義という学校から卒業したくないと引きこもり症候群になっている(中略)問題なのは成長でなんとかなる人は、自分たちが引きこもり症候群だと自覚していないこと
→☆この考え方には目を開かされる。
なるほど、そう考えれば良いのだ。
資本主義をやめたあとにどういう社会にするのかの代替案が全くない
→☆これを個人的に考えようと思ったがなかなか妙案が思いつかない。
経済理論に詳しい人と一度話をしてみたら良いのかもしれない。
資本主義は終わりを決めていないから無限に拡張していく。資本は権力の象徴なので、無限のプロセスになってしまう。(中略)近代の出発の時点からして、資本主義の精神や空間の概念を含めたすべてに終わりがない
→☆ということは資本主義のイグジット政策を考えてもイグジットにはならないと言うことか?どうすれば良いのか?
成長を求めない社会は、基本手kには余り動かない社会
成長を求めなくてよくなれば「よりゆっくり、より近く」な社会になります。
→☆これが要するにスローライフの行き着くところだろう。理論的にも間違っていないようだ。
近代が上手くいかなくなってきたら、一昔前の中世の人たちがやっていたことの仲に良さを見出し、今に適用すれば良い
→☆これが著者のメッセージか。なるほど。
利便性の観点で言えば、現在、日本にはルイ14世ぐらいの生活水準で暮らしている人が200万人いるようなもの
→☆かなり贅沢で浪費をしていると言うことだ。
今の水準が高すぎるのかもしれない。
これからのメディア(佐々木紀彦)
日本ではプリントメディアが今も強いというのが特徴的です。
紙の本については、アメリカではまだのびています。にほんでも、紙の本は残っていくでしょう。
紙媒体として残る可能性が高いのはデザイン誌や、ファッション誌です。それと、200ページ以上あるような単行本や新書などの長い読み物はウェブで読んでいると疲れるので、やはり紙のまま残る。
紙とデジタルを使い分けるという発想自体が古くなっている。
日本は職人文化なので、いろいろなことができるような人はあまり目指されません。
・メディアが稼いでいくためのキーワード8つ
1.広告
2.有料課金
3.イベント
4.ゲーム
5.物販
6.データ販売
7.教育
8.マーケティング支援
・プラティッシャー
→※プラットフォームとパブリッシャーを組み合わせた造語
これが主流になっていくと考えられている。
これからのデザイン(原研哉)
人間は深化したと言うけれども、賢い方向だけに進化したわけではなくて、残虐さやずる賢さなども同時に進化させている。
あるべき環境をどう作っていくかを、道具を通して考えはじめることがデザインのはじまり
すでに身体や感覚が知っていることを、わかり直していく道筋がデザイン
工業化社会のデザイナーの職能とは、工業製品を合理的な形にすることであり、よりよく記憶されるためのブランドアイデンティティを作ったり効果的な広告を考案すること
デザイナーのもう一つの役割は、人の欲望の幾重を示唆すること
デザインとはものの本質を見極めて、潜在するものを目に見える形にしていく
→☆要するに「デザイン哲学」について考えることが重要だ(教育することが重要だ)と言うことだろう。
デザインは蓄積されてきた人間の知恵に気づいていく行為
デザインとは「だったりして」を目に見える形にしていくこと
シンプルについて考える前に、複雑について考えるとわかりやすい
→☆なるほど、4次元的に考えを進めれば良い と言うことだ。
日本に足りないのはバリュー(価値)の想像
クリエイティヴ・クラスが支配する世の中で「3つのT」が重要になってくると言っています。それは「技術(Technology)」「才能(Talent)」「寛容性(Tolerance)」
今の日本はまだ圧倒的に20世紀的な工業社会の幻想に基づいている社会
・残されたフロンティア
1.美意識フロンティア
2.AIフロンティア
→特にこの領域についてもう少しアンテナを張ってみようと思った。
これからのプロダクト(深沢直人)
プロダクトデザインの仕事は、今の生活をよくしていくこと(中略)世の中に対するお医者さんみたいな感じ
デザインをすることよりむしろ、その人の志向になってあげる、志向を貸してあげることの方が重要
→☆これがデザイン経営で美大出身の人が大企業に雇用される理由の一つ になっているのではないか?これを実地にしていると言うことだろう。
「いいデザイン」とは、感覚で受け取ったデザインのこと。
デザイナーは世の中ある方向に行きかけているときに「こっちもあるよ」と、世の中の流れとは別なことをやっていくという役割がある
デザインの定義は元来、装飾をすること
今の若い人たちは、物欲の時代を生きていない
人からデザインを求められることは大きな力になる。
これからの文学(平野啓一郎)
※20世紀には20世紀の小説の書き方があった。
※21世紀にはもはや「小説を読まなければならない」と言った、小説を立派なものと特別視するような考え方が存在しない
「個人」という概念が社会システムを考えていく上で限界に来ている
たった一つの「本当の自分」など存在しない。裏返して言うならば、対人関係毎に魅せる複数の顔が、すべて「本当の自分」であるとして、個人より一回り小さな「分人」という単位で人間を見る
※自分は対人関係毎にいろんな自分を使い分けている
※人は「いろいろな自分」を生きているからこそ精神のバランスを保てているのではないか?
自殺の場合、いくつかの人格を生きている中の「つらい自分の部分」を消したいと言うことと「自分全体の命を絶ちたい」と言うことが混同されてしまっている可能性がある
純文学も社会の中で作用する何かを持っている
→☆だからこそ残っているし、惹かれる人がたくさんいるのだと思う。
これからのアート(松井みどり)
芸術の目的は生を生きるに値するものとして人に気づかせること
ソーシャリー・エンゲージド・アートは、生活芸術のかんっけいを、社会の蹴る開放的なコミュニケーションや共同作業の場の成立や、人間同士の新しく自由な関係性の開発を通して模索する方法
→その定義は
1.反リアリズム
2.参加
3.「現実」の世界に置かれていること
4.政治的領域で行動すること
自分たちの世界は「スペクタクル」に犯されていて、スペクタクルが作り出す偽りの幸福のイメージが「労働者対資本家」のような他律よりもっと複雑に人間の習慣や感情に入り込む故に、より打破しにくいし背景対になっている。
→☆水俣病患者の荻原正人氏とおなじムーブメントと考えることができる 。氏ははSocially-Engaged-Artistsと考えることもできよう。
これは新たな発見だった。
芸術体験は、「自分らしさ」を見いだすための方法ではなく、吉の「自分」領域の外に踏み出して、自分の中の未知の部分にであうきっかけを与えてくれるもの
これからの人類(山際寿一)
(人間は)言葉を生み出したことによって、脳の拡大を停めてしまった生き物
→☆このような切り取り方ができるとはすごいと感じた。
人間における食料革命
1.食物の運搬 ;草原で暮らしているので安全な場所で食べる必要があった。これによって直立二足歩行が起きたのではないかと考えられている。この頃骨髄などが大きな栄養源として扱われていたと考えられる。
2.肉食革命 ;肉食により食べ物の採取・摂取に時間がかからなくなり、余った時間を社会的な行動に当てることができるようになった。
3.調理革命 ;火を使い出した。食材を過酷することで消化率を高くし、なおかつ衛生的になった。
4.農耕・牧畜
実はこれが一番最後の食料革命
特に大きかったのが家畜の力を農業に生かせるようになったこと。
人間の霊視に言語が登場したのは、いくら遡ってもせいぜい7万年前。一方で、脳が大きくなり始めたのは200万年も前
→言葉が脳を大きくした、という理論は間違い。
高次脳機能(大脳新皮質)が脳に占める割合は集団を構成する個体数の平均値が大きくなるほどが高くなると考える。
コミュニケーションのタイプと集団の規模
1.10人前後
スポーツのチーム程度
言葉を交わさなくても、目配せや声や仕草で自分のやりたいことを知らせる、つまりチームワークのとれるせいぜいの数。
2.30~50人
学校の1学級の人数。
先生がコントロールできる人数
3.150人程度
年賀状を書こうと思ったときに顔が思い浮かぶ人数
人間は1500cc止まりの小さな脳容量でもやっていくがために言葉を編み出した
→☆実際に言葉に直すことで一段階、そしてそれを書き留めたり録音したりすることによって二段階目の情報の選別を行っている。
コミュニケーション技術は、情報を外部に預ける方向で進んでいます。
身体でなく脳でつながり合うことをはじめている;インターネットの利用
人間はルールを作り、そのルールに従うことでみんなが安心を得ようとする社会を築きはじめている
→☆人間のサル化
・「サル化」された社会というのはものすごく脆弱な砂上の楼閣
人間に残っているのは考える力、あるいは応用する力(中略)それを発揮させるのが今の人間のすべきこと
人間に残された唯一の能力は、見えないものを見る力(中略)データが無くても行動することができるのが人間(中略)その能力を「直感力」と読んでいる。
類書との違いはどこか
今までに無い人選で知のフロンティアに迫ったところ
関連する情報は何かあるか
デザイン、思想、文学、芸術などに関するとがった考え方
キーワードは?(読書ノート用)
(1~2個と少なめで。もう一度見つけたい、検索して引っかかりにくい言葉を考える)
#芸術
#教養
まとめ
オムニバス形式の対談集だったがそれぞれの人が非常に個性的で非常に興味深かった。
著者の最後の言葉(有限な人生を生きる、有限な容積の脳を抱えた人間が、それでも少しでも賢くありたいと思う切なさに、知的に生きようとする姿勢の根源があるはずだ)は非常に深い言葉で刺さった。
色々な言葉の羅列のようになりましたが、皆さん読んでいただければ自分の刺さる言葉があり、それを書き留めておくことでありありとその感動が分かる本に仕上がっていると思います。
少しでも気になるフレーズがある人は読んでみて下さいね。
いいなと思ったら応援しよう!