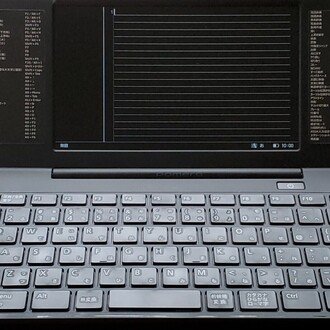漂泊と大地 第一部 狩りと漂泊 を読んで 著者の言う脱システムを更に深く思索する
以前に角幡氏の著作を読んで非常に感銘を受け書評もアップしました。
その続編ともいえる、最新刊を読んでみたので書評として記事をアップしたいと思います。
では、書籍のメタデータを貼っておきますね。
今回も読書ノートからの書評ですので、小理屈野郎の読書ノート・ローカルルールの凡例を以下に示しておきます。
・;キーワード
→;全文から導き出されること
※;引用(引用の背景で示されていることもあります)
☆;小理屈野郎自身が考えたこと
書名 漂泊と大地 第一部 狩りと漂泊
読書開始日 2022/12/01 17:34
読了日 2022/12/05 08:58
読了後の考察
今回はいわゆる探検記、というより自分の内面の体験記 、といった方がふさわしいのかも知れない。
著者はいわゆる到達すべき目標を定めてそこに到達する冒険や探検 、というものをある程度した後、それでは飽き足らず、またその不自由さ というものに気付く。それが今まで著者が言っていた脱システム という思想であり、脱システム、と言う思考に築いた後はいかにそれに近づくか 、と言うことを探検や冒険の主目標にしている。
今回は時間の概念についてかなり突っ込んだ解釈 をしている。この解釈は自分の体を白夜にさらし、さらに食糧が不足するという環境に置いたからこそ到達できる解釈であると感心した。
毎回死にそうになりながら新しい概念をもとめ、それに対して自分なりの答えを見つけたりその過程で新しい概念を発見 している。
狩りをすることによって、予定というものから完全に解放され、それによる(狩りのできる土地で)偶然に任せたままの漂泊をする、というのが著者の主目的になっている 。
狩りについては現在は犬1匹と橇を使ったものだがこれでは機動的な狩りができず自由に動ける範囲が狭くなる 、ということから今度は犬ぞりを使った狩りをしながらの漂泊を目指している とのこと。
これからしばらく先になる可能性があるが、その前に犬ぞりを使った予行演習などで著書が出るのではないか?そのようなことを楽しみに次の著作を待とうと思う。
キーワードは?(Permanent notes用)
(なるべく少なく、一般の検索で引っかかりにくい言葉、将来もう一度見つけてみたいと考えられる言葉)
#時間の概念
#自由とは
概略・購入の経緯は?
角幡唯介氏の著書を一時たくさん読んでいて、その中で積ん読にしていたものがあった。それを掘り出し読んでみることとした。
氏の独特な世界観は引き込まれるし自分も共感するところが多い。
今回はどのようなものであろうか?
本の対象読者は?
角幡唯介氏のファン
哲学に興味のある人
著者の考えはどのようなものか?
探検家は42才で遭難することが多い
探検家としての経験はどんどん積み重なっていく。経験と体力が比例しているのは40才ぐらいまで。40才を超えてくると体力が落ちてくる。それにしばらくは気付かないもしくは目を背けている。そのような状態で探検をするために経験的には予測がつくので上を狙い、体力的には下降する。このギャップが大きくなりそれが一定を超えると遭難して命を落とす ことが多くなる。
その年齢が不思議と41才とか42才である とのこと。
これを意識しているので著者は42才の探検(この著書の内容)では遭難したり死亡したりしなかったのではないかと考えた。
漂泊とは
著者の理想とする山旅のあり方に対しての名前。
近代登山(近代的思考様式)とは矛盾している。
近代登山は頂点を最短時間で目指すことのみが重要視されている 。その過程についてはほぼ考えない。時間を短くするためならGPSを使ったり、デポ(食料や燃料などを前もって置いておく場所)を置いていたり と目標への到達以外のことを度外視することが多い。これにも理由はある。行き当たりばったりに行くと生存の確率が低くなるという側面もある からなのだが、計画通りに行かないという自由を著者はとりたい 、と考えた。
登山とは自力で現場の状況を判断しながら登っていくところに醍醐味がある。そちらを著者は究極まで優先した、ということだろう。
狩りとは
漂泊に必要不可欠な要素。
狩猟に成功する限り、いつまでも、どこまでも旅を続けることができる 。それが永続化すると旅と言うより生活 になる。
ここが著者が狙っていたところ 。
究極的には偶然の産物と考えている。
こちら側の事情となんの関係もなく現れた獲物によって、狩猟者はこの世に存在することが許される。自分の意思や都合によって結果が決まるのではなく、土地や獲物という向こう側の事情によって己の運命が決まる。
狩りをすることで、人はすべての人間が生存している時点で抱える負い目を自覚し、それを引き受けることになる。
→☆この記述は一神教(キリスト教)が発達してきたその過程がなんとなくわかるような記述 だった。
キリスト教では人は原罪を持って生まれてくる、とのことだがその根底には狩猟生活 、というのがあるのかも知れない。
狩りの始原は死肉漁りと考えている。自分も実際にその状況に陥ったことで腹落ちしたのだろうと考える。
著者の探検
探検としての体験はかなり体力的もきついもの。そんな中色々な思索をしている著者の姿勢に脱帽 だ。
時間について
白夜で行動することによって時間とは一体なんなのか という形而上学的な疑問を感じた。
その疑問の答えは1日が24時間というのは時間というものを人間が均質で秩序だったものとして理解するための手引きとなっているだけだ 、と喝破する。
この発想はすごいなと思った。著書を読んでいると自分ならおそらく自分のサーカディアンリズムは22時間、という理解だけで終わってしまう が著者は大きな視点で時間を捉えていることに舌を巻いた。
時刻制度を成立させるのに本当に必要なのは、太陽ではなく夜の闇 ということにも気付く。これも白夜と極夜を経験した著者ならではの結論であろうと考える。
白夜であれ、極夜であれ、1日が24時間である必然性はぜんぜん無くなり、時刻制度は崩壊する と考える。
時刻制度からフリーになって活動をし出すことによって著者は自由を感じるようになった とのこと。
飢餓について
人間性を形作っていた薄っぺらな外殻は無残に剥がれ落ち、はじめて自然と直結することができた(中略)そこに自由を見つけた
→☆究極の体験をしたからこそ出てくる結論ではないか?と感じた。
システムとは
都市がそれに当たる。
都市とは世界というものを均質で固定的に捉えて、それによって確度の高い未来予期を人々に与える巨大システムである と定義。これも刮目ものだ。
今後の著者の探検の方向性
それぞれの土地が語る個別バラバラの物語に組み込まれながら、その物語を拾いつつ、これからもこの地域で旅を続けて行動範囲を広げたい 。
→☆小理屈野郎簿場合は、スキー行で色々なスキー場に行きその周辺のものを食べ、泊まることでその土地を実感し、その土地を自分の庭(守備範囲の場所)、と考えられるようになってきた 。
結局都市というシステムの中で人間は漂泊生活とおなじようなことをしているのではないか と考えた。
そのように考えているから、結局いつでもおなじスキー場に行こうとするのではないか? とも思った。
土地のうごめきに従うほど、土地と私を分断する境目は次第に薄らいでいき、しまいには消失することになるだろう。その時私と土地は存在論的に一致する
→☆小理屈野郎のスキー行に関する思索もこのような状態を思考していると考える。
探検なのか、冒険なのか、言葉の定義はもうどうでもいい。もっと単純に、より上手に土地のうごめきの中に入り込み、昔のエスキモーみたいに北極を旅行できるようになりたい
→☆これが一番わかりやすい強調 でもあると考えた。
その考えにどのような印象を持ったか?
文章も非常に解説的で素晴らしいし、著者の考えも究極の体験をしながら崇高なものだと感激した。
その上で著者の考え方をトレースすることができ非常に得がたい体験ができたと考える。
いざ自分の生活を振り返っても、ここまでは行かないが、おなじようなことを志向している ことにもびっくりした。
人間、やはりどのような環境にいるとしても結局考えたり行動することはそれほど変わらないのではないかな 、とも思われた。
印象に残ったフレーズやセンテンスはなんか?
登頂が絶対的価値を持つため効率優先主義になりがちになる。こうした不自由さ、煩わしさを発生させている頑強こそ、頂を目指す、目標地点に到達するという登山の一方向的、直進的な近代的行動原理である。
事前の計画的管理から解放されて、目の前にある自然環境や現場の状況に没入するのが目的阿野田から、空間的な移動距離よりも、ある意味、時間的な長さの方が重要。
地図が必須なのは、もちろんそれが登頂に必要だからと言うこともあるが、それよりむしろ我々人間が生き物として未来予測を欲しているからであり、現在がカオスとなることを全力を持って阻止し、可能な限り予定調和で登山を終わらせようと無意識に思考する
現代の我々はあまりにこの現在の混沌を封じ込めようとしすぎている。本来、生成的で、刹那刹那で移ろいゆく世界というものを、計量的に認識できるように固定的に作り替えようとしすぎている
→☆偶然性の尊重。これは最近の哲学界でも、東浩紀氏などが提唱している概念だ。偶然の一致とはいえ、少し驚いた。
考えを巡らし、最善の選択を下すよう自分なりに努力した。その判断が好結果を生むかどうかはわからない。でもその不確かな一連の判断の渦中に、私は生きている自分を発見した。
未来により現在が決められるのではなく、その逆に現在によって未来がつくられている
人間はそもそもそのような未来の見えない自由の中で生きていたはずであり、今も本当はそうなのである。
この旅ではGPSや衛星電話に加え、時計も装備リストから外していた。
土地を私が組み込むのではなく、偶然という契機を解することによって土地に私が組み込まれる
私は不確定状況が確定状況に変わるこの瞬間を経験したくて、山や極地に向かうのかも知れない。
登攀という行為は、飢えの不安(不確定状況)→獲物の獲得(確定状況)が続く狩猟民生活における資源的な生の喜びを凝縮して体験できるように、短い時間の中にぎゅっと押し込めた人工的な発明
不確実性を不確実性として受け止め、そこで努力することによってのみ、人はあらかじめ決められた未来ではない、その場でのみ発見され縷々固有の類例なき未来を手に入れることができる
自分という存在がなんなのか、実体はどこにあるのか。実体が欲しい、自分の実体がどこにあるのか知りたい。今までそう思いながら生きてきた。
→☆非常に純粋に人生を歩んできたな、と思う。
類書との違いはどこか
探検記の形をとっているが、探検の形而上学的な思索を行っているところ
関連する情報はなんかあるか
極地に関する情報
キーワードは?(読書ノート用)
(1~2個と少なめで。もう一度見つけたい、検索して引っかかりにくい言葉を考える)
#思索
#脱システム
まとめ
毎回著者の作品には驚かされることが多いが、今回も非常に驚いた。
結論だけ見るとたいしたことはない、と思う人もいるかも知れないが、この結論に至るまでの思考には非常に深いものがあり著者の生きる姿勢に尊敬を覚えた。
丁寧に毎日を生きていくことが大事だと痛感した。
いつも著者の書籍はドキドキハラハラしながらだが、著者と一緒に自分の内面を見直したり、と濃厚な時間を過ごすことができて非常に好きな作家の一人です。
さて、次回の予告ですが次回も書評にします。
今回とは違うつらい思いをした著者が現象は違うけれども大きな目で見ると角幡氏とおなじような発想をしている人の著書です。
この著書とおなじ時期に少しだけ併読したのですが、どちらの著者のワールドにも容易にうつることができて不思議な体験ができました。
次回の書評も乞うご期待。
いいなと思ったら応援しよう!