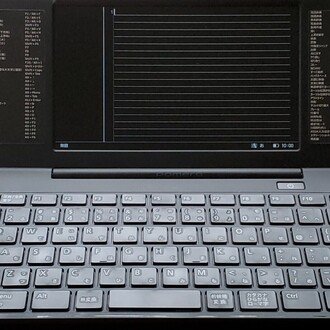歩きながら考える を読んで アフター・ウィズコロナについて思索する
今回はヤマザキマリ氏の最新著作の書評です。
以前に著者は「たちどまって考える」という著書を上梓し、前回のnote記事はこの著作の書評をアップしました。
その後継作、とも言える著作です。
最新著作は、最初は作品名も前作とかなり似ているので、「あれ?」と思っていた のですが、よく調べて、最新作だと言うことが確認できたので購入して読んでみました。
今回も、この時期ならではで、納得することが多かったです。
では、書籍のメタデータを貼っておきますね。
今回も読書ノートからの書評ですので、小理屈野郎の読書ノート・ローカルルールの凡例を以下に示しておきます。
・;キーワード
→;全文から導き出されること
※;引用(引用の背景で示されていることもあります)
☆;小理屈野郎自身が考えたこと
書名 歩きながら考える
読書開始日 2022/09/15 13:05
読了日 2022/09/17 15:52
読了後の考察
氏の以前の著作「たちどまって考える」と対になる書籍だと感じた。
今回は、そろそろためている力を外に出していこう 、という論調の話。
著者はたちどまっている間のことを客観視していたが、これについては個人的に考えていたことと全く一緒。
氏の場合は、居住地を変えることによって物事の多様性を理解していたが、それがかなわないときは、本を読んだり映画を見たりすることによって、それをかなえていた。彼女に言わせると「インナートリップの大事さ」 だ。
個人的にもインナートリップができる状態であれば、ずっとは無理であろうがしばらくの間は少々たちどまっていても問題ない。むしろ走っているときには分からないことがよく分かるのでは 、と思っていた。著者も同じように感じている。ただし著者の方が思索が深いだけに、出てくる結論も深淵 で非常にうなずくところが多かった。
そろそろ、あちこちに行ってみよう。まわりをみてみよう。
そして、希望を持って、希望が叶わない場合のことも淡々と考えつつ、毎日を送っていきたい と感じた。
キーワードは?(Permanent notes用)
(なるべく少なく、一般の検索で引っかかりにくい言葉、将来もう一度見つけてみたいと考えられる言葉)
#インナートリップ
#レジリエンス
概略・購入の経緯は?
以前ヤマザキマリ氏の「たちどまって考える」という著書を読んだ。内容的には非常に納得することの多い著書だったが、今度は「歩きながら考える」
著者の考えがどのように変化しているのか を楽しみに読書してみることとした。
本の対象読者は?
ヤマザキマリ氏のファン
コロナ禍およびアフターコロナの過ごし方について考えたい人
著者の考えはどのようなものか?
・たちどまることによって自分の思い込みを違う角度から見直して、できる範囲で少しずつ行動を始めた。
☆たちどまることによって見えるものが変わる。今回はたちどまることによって自分や日本を見つめ直す機会になったようだ。
・自分の思い通りのことはなかなか起こらない
予測もしなかった変化に、否応なく適応していく。生きるとはそういうもの
☆これはライフネット生命創業者の出口氏もおなじようなことを言っていたと思う。目の前の環境に必死で適応していくだけ だ、というようなことを言っていた。自分で環境なんか整えられない。目の前の環境でしっかりと地に足をつけたことをしていかなければならないと言うこと。
このように考えることで過度のこだわりがなくなり、淡々と目の前の事実を受け入れられるようになるはず。
・自分のメンタリティはそんな簡単に変えられない
☆中高生ぐらいまでの多感な時期を過ごした環境というのが自分のメンタリティを構成していく 。
自分も結局日本的な価値観の中で生きているのではないか?もちろん欧米の価値観、というものもある程度理解はできるが、一般的にはそれが本流にはなっていないと思われる。
・ヨーロッパ人は予定調和にそれほど慣れていない
元々自分の立場すらなかなかはっきりしない(隣国が攻めてくる、など)ため、明日はどうなるか分からない毎日を送っていたヨーロッパ人。だからこそ予定調和外のことが起こる頻度は日本人ほど低くなく、今回のコロナ禍のような先行き不透明な時代にはヨーロッパ人は強い 。
逆に日本人は予定調和に非常に敏感 。だからこそ電車のダイヤの乱れは許されないし、実際に遅れない。そして、予定調和という一種の同調圧力が社会全体を覆っているからそこからはみ出るようなものをバッサリと切り捨てる 風潮が元々日本社会にはある。これは、いじめにつながったり、個人のバッシングにつながったり、自粛警察につながったりするのではないか? また個人のレジリエンスの弱さもここから出てきている と考えられる。
日本人は予定調和という非常に脆弱なものの上にどっかりと居座って社会生活を営んでいる 、ということだろう。これは銘記しておくべきことではないか?
ただし今回のコロナ禍でこれも少し薄まっているように著者は感じている。著者の周りではそうかもしれないが、実際のところはさらに予定調和に対する思い入れがひどくなっている ような気もする。
予定調和と同時にクローズアップされるのが、「○○であるべき」などと言う思い込み思い込むと言うことは予定調和を作り出しているとも考えれないか? 。もちろんそうなってほしいが、そう簡単には世の中は動かない 、ということも知っておくことが大事ではないかと考える。
・信じると言うことは精神的には怠惰なこと
信じることは純粋な感じがして非常に尊い印象があるが、もし信じることがうまくいかなかった場合は、その責任は信じたもの・人に帰依してくる。これは自分で考えることを諦めたと言うことにもならないか 、というのが著者の論点。確かにそれはいえているのではないかと思う。信じるのは良いが、自分を信じるようにしていかなければならないのだろう。
・人間は所詮自然界の一員である
知性がある、という一面だけで、人間は他の生物とは全く違うランクのもの、と考える風潮があるが、所詮人間は自然界の一員で生態系の一部を占めるものである。現在支配的であるのは、エネルギーなどを自分たちで作るだけでなく埋蔵されているものを使えるような状態であるからだ。
現在使っているエネルギーがなくなった場合、人間は滅びるのみ 。そういう目線で物事を見て行きたい。
・仕事と家族、どちらが大事か?
これは比べることができる次元の問題ではない 、ということをしっかりと理解しておきたい。個人的にはそう思っているところがあるのだが社会的にはこれは許さない人が多い。その事実を知っているだけでも気持ちが楽だ。
・欧米人から見る日本人の特性
尋常ではない勤勉性に欧米人は恐れを持っていた 模様。だからこそ日系アメリカ人の差別があった。さらに日本人は修辞性がない(自分のやっていることを説明したり、理解してもらおうという努力をあまりしない。そういうことをするのは美徳ではないと考えられる)が、さらに拍車をかけたのだろう。
八百万の神を信じている日本的なメンタリティが細かいところまで手を抜かずやり抜く、ということにつながっているのではないか?
・世界の男性が結婚に求める女性像
自分のだめなところを認め、どんなときも無条件に寄り添い、慰め、許してくれるかどうか、という母性的なところを男性は求める。これは世界中共通している
とのことだ。
海外の男性は自立している、と思っていたが、イタリア人は基本的にかなりのマザコンである人が多かったりするとのこと。この結論は意外だった。
・戒律について
戒律とは各社会を円滑に回すための集団の理論。だからこそ、イスラム教の一夫多妻制などもあるし、キリスト教的な一夫一婦制の考え方もある。これは善し悪しではなく、その社会の置かれた地理的、気候的、そして社会的な状況によって育まれるもの なので、ある程度リスペクトする必要があるのではないか、という論点。
多様な理論とそれに対する理解がある、というというのがここのところ特に重要になっているのではないか という印象を受けている。決まりを言下に否定するのではなく、その決まりがどのようにできてきたのか、そして現在の社会とどのようにすり合わせていくか、という視点が必要ではないかと考えた。
・オリンピックについて
スポーツはルールのものすべての人間が平等になる、という非常にまれなアクティビティ。言葉もいらない 。だからこそ世界中の人が等しく熱狂するし、それを利用して社会をまとめようとする人も出てくるのだ。みんなで熱狂するから全体意識に気持ちが高揚していく。
これがオリンピックが神聖化される原因の一つ。
実際に東京2020ではそれをうまく使って贈収賄事件が起こったりしている。事件を起こした人々はそこまで考えていないだろうが、前述の基盤の上で、起こるべくして起こった事件とも考えられないか? と感じた。
・哲学とは
日本では、哲学の教科書や歴史から学ぶ、ということについて哲学と捉えているが、著者やヨーロッパ人の多くはもっと広く
ひとりの人間があらゆる経験と思考と試行錯誤を積んだ末に抽出される、その人なりの考え方や思想を指す言葉
と考えても良いのではないか。実際にいろいろなことを思索して自分の方針としている。その思索こそが哲学であり、哲学をしていることになる。そこから出てきた方針などはその人の哲学そのものであると考える。
と捉えている。
自分の哲学に磨きをかける、ということは他の人の哲学に接する(避難しないで包摂する方向で)と言うことであるとも考えられる。
いろいろな事象を余裕を持って、観察し、俯瞰する。その上で自分の今までの経験などから思索をしっかり行う。この行為自体が哲学 なのだ。
そういう意味では、国語(現代文)の読解の問題等を学生時代にしっかりすることは哲学することの練習になっているのではないか とふと思った。国語の読解問題については確かに問題は多いが、これをしっかりすることは最終的には人生において非常に大事な姿勢を学ぶことにもつながるのではないか と考えた。
・良識とは
常識ではない、自分なりの哲学や行動方針のようなもの。
自分なりの審美眼を鍛え、自分の頭で考える実践を積んだ先に獲得できるのが自分にとっての真理、つまり良識。
結局常識も大事だがそれ以上に大事なのは自分で考えた上での良識なのだ。これがあれば、しっかりした行動がとれるし、周りが何を言ってもへこたれないだろう。
常識で判断する人が多いが、良識という判断基準を著者は提示している。良識、と言う言葉を出すと、人によって違うから云々、ということを必ず言う人がいる。確かにそうかも知れないが、各個人による良識の揺らぎも吸収できる社会になっていくことが特にこれからは必要ではないか と思う。それは全体主義を遠ざけ、社会の多様性にもつながるのではないかと考えた。
・人間は怠惰な生き物
文明の発展というのは見方を変えると、人間が物理的に動かなくてよくなるようにしていくムーブメント と捉えることができる。
特に産業革命などはそうだろう。
それ以外にも狩猟生活から農耕生活に変わったこともそうだ。結局怠惰な生き物だから、予定調和を求める方向の生活を送る ようになる。これが問題の根本なのかもしれない。ちょっと不便ぐらいがちょうどよい。
これは個人的には知的生活を送る上でも思うこと。単機能のガジェットを組み合わせていろいろ細かいことをしながら(少し不便ぐらいの感じをトレースしていると考えている)の方が集中できるし実際の成果も出る。
その考えにどのような印象を持ったか?
大体のところは納得いくし、確かに著者の生活パターンを普通に聞いていると奇異に聞こえるところもあるが、彼女が納得してその生活を送っており、その考え方が非常にストレートで納得のいくものだ、と感じることができた。
ぱっと見、自分が納得できないようなことをしている人でもその人なりにかなり思索をしてびっくりするようなことをしている場合もある。そういう人には興味を持って、いろいろと聞いてみると自分も得るものが多いのではないか、そして深く考えさせられるのではないか、と思った。
印象に残ったフレーズやセンテンスは何か?
群衆を壊さないためのガイダンスとしての宗教、そこから生まれる倫理、さらに政府や宗教のリーダーたちが「絶やしてはいけない」ともくろんでいるのは純粋な遺伝子の存続だけではなく、利権と言った経済的な問題、それらが絡んだ国家や組織そのものの維持
→☆上記で言及したオリンピックについてにもつながる論点。
欲の勢いだけではどうにもならないことがこの世にはある、ということを歴史の中で何度もパンデミックを繰り返してきた土地の人間は感じている
→☆ヨーロッパ人の予定調和に対する諦観をしっかりと描いていると思われる。
人間を美化することは、すなわちあらゆる社会の現実から目をそらすこと
→☆日本で今、「日本人はすごい」という論調のドキュメンタリーが結構はやっているし個人的もちょこちょこ見る。これは危険な兆候ではないか?上記の文章の「人間」を「日本人」に変えれば容易に想像がつく。
しっかりと周りも見ていかなければならないと感じる。
バブルは世の中の人たちが皆いわゆる精神的なシークレットブーツを履いていた時代
→※非常に面白い表現だ。もちろん、この時期の日本人もそうだが、明治維新でもおなじではないか?和服から洋服に着替え、髪の毛は散切りになった。しかし精神的には無理なところがあるのでシークレットブーツを履いている、という感じ。
本を読み、音楽を聴き、映画を見る。インナートリップの手段はいくらでもあります
→☆個人的に思っていたことそのままが本に掲載されていた。
人生経験に乏しい人間の表面がつるっとしたものだとすると、あらゆる経験をした人間のそれはざらざらとしていて、その分、外からの情報が引っかかる場所も多くなる。それを内なる思索のたびによって取捨選択し、身のうちに取り込んで自分のものに消化する
→☆これが知的な生活であり、思索ではないかと考える。
keep moving。常に好奇心と感性を動かし続けろという意味。
→☆個人的にはこれが結構かけそうになる。結局自分の「怠惰な面」が出ているのではないか、と反省。
生まれてきてしまったからには、つべこべ言わずに生きるしかありません
→☆この諦観が大事だと思う。生まれてこなかったらよかったとか考えても仕方がない。厳然たる事実として生まれてきてしまってここまで生きている。ここを認めることから始めたい。
類書との違いはどこか
現代の世相に合わせて自分で思索し、「哲学」としているところ。
一個人の思索の過程を、前作と通読するとわかるところ。
関連する情報は何かあるか
イタリアの現在の状況
質問8 キーワードは?(読書ノート用)
(1~2個と少なめで。もう一度見つけたい、検索して引っかかりにくい言葉を考える)
#オリンピック
#諦観
まとめ
少し読み解くのに知的体力が必要だったが非常に面白い論点で納得のいくことが多かった著作であった。
生きていくってことは結構大変ではあるけど、それなりに面白いな、と感じることのできる著作ではなかったかと思います。
そして、著者というひとりの人間が社会の様相の変化に合わせてどのように思索を進めているか、という過程を見ることができ非常に興味深かったです。
仕事の上でもそろそろ出張が再開になったり、リアルな人間の交流が増えてきました。コロナ禍発生から今までそれなりにしっかり考えてきたつもりなので、その成果や果実を享受するためにも少しずつ「歩き出して」行きたいと考えています。
いいなと思ったら応援しよう!