
【運動で伸び悩む人】『truthiness』を外してみよう!
【プロローグ】
僕たちは生まれた時には
文字の読み書きは当然のこと
ろくに言葉も話せません
スタートラインはみんな同じ
そして勉強を始めるタイミングも
義務教育があるのでだいたい同じです
でも高校3年生になって
大学受験をする時
『学力』には結構な差がついています
これはどこのなにでついた差なんでしょうか?
1番つまらない答えが
頭が良い・悪い
天才・凡才
ここで生まれる差です
っていう答えですね

『なんかいい感じ』で
ステップアップできたり・できなかったり
したから差が生まれたのでしょう
そしてそれはカラダの事だって同じです
運動神経の良し悪し
才能のあるなし
これで片付けるとつまらない答え
今回はそんなお話です
✅量と質、ハードとソフト
じゃあ運動能力やスポーツで
考えていきましょう
どういうことをすれば
『なんかいい感じ』に
ステップアップしていけるのか?
あるいは自分がステップアップするためには
今するべきことはどういうことなのか?
ここに繋げていきます
まず、運動の世界では
よく言われる事があります
ただ闇雲にトレーニングしても(量)
効果は出ないよ
目的やフォームなどのテーマを
明確にしてトレーニングしましょう(質)
筋量や筋力を高めても(ハード)
運動能力は高まらないよ
カラダの使い方を考えましょう(ソフト)
もちろん僕も同じようなことを言います
特に『質とソフト』にかなり偏った
情報を発信しているのでより
そういうイメージが強いかと思います
幻滅させたらごめんなさい
はっきり言い切っておきますね
ステップアップの初期に
役立つのは『量とハード』です
✅量とハード
カラダの使い方について伝える時に
よく用いられる例えにこういうのがあります

いくら車の性能(ハード)が良くても
ドライバーの腕(ソフト)がないと
車を速く走らせられません
だからドライビングテクニック
車の操作方法、つまりカラダの使い方を
学びましょう
ってことですね
確かにその通り
でも、プロローグで言いましたよね
スタートラインはみんな同じです
実際にはここからがスタートです
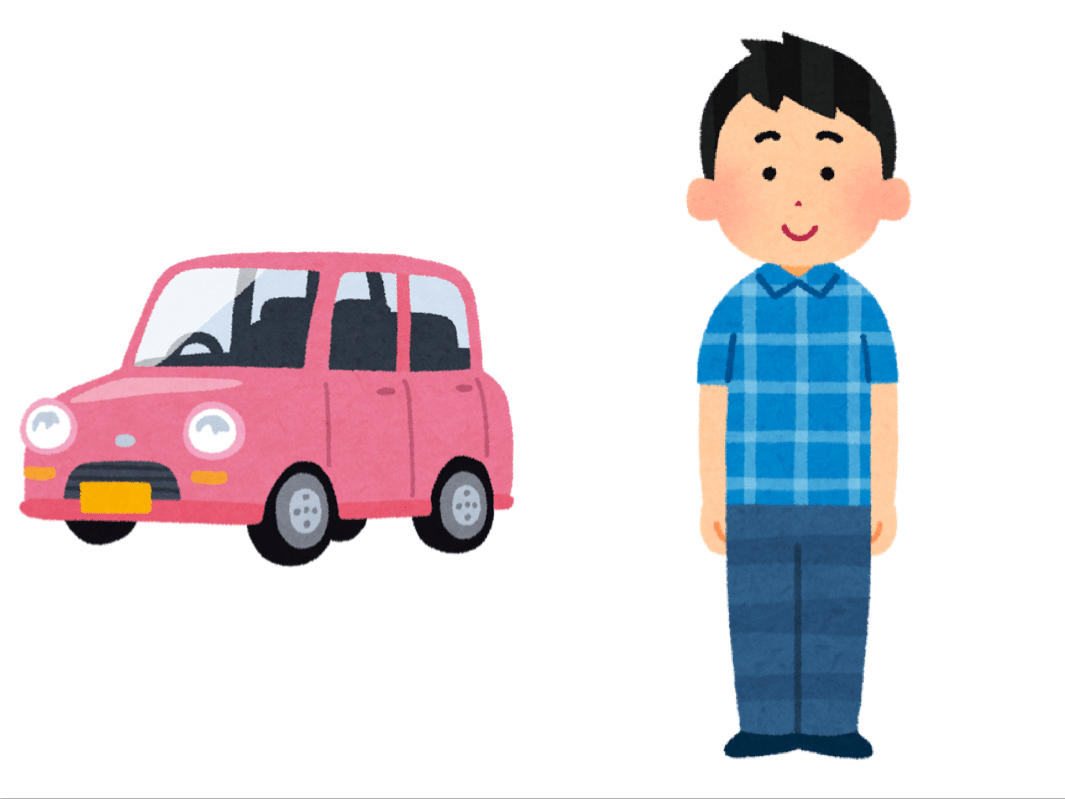
車は軽自動車で
ドライバーは免許取り立て
これでサーキットを走るんです
じゃあどっちをいじったら
とりあえず手っ取り早く
速く走ってタイムを縮められそうですか?
絶対車ですよね
F1にしなくても
セダンタイプのちょっと排気量高い
乗用車にしただけでも
タイム縮まりそうですよね
逆に免許取り立てのこの人に
コーナーでのハンドリングとか
アクセル・ブレーキのペダリング
みたいな運転技術を教えて
理解してくれそうですかね?
ここで実際に僕がお聞きしたことがある
お話をひとつ
韓氏意拳という武術がありまして
『意の拳』というだけあって
とてもイメージや感覚を大切にする
武術っていえばいいですかね
その継承者である韓先生のお話を
聞くことができたんですね
その時に仰られていたことが
『創始者の時代の人たちは
馬に長時間乗って移動したりしていんだ。
蔵みたいなのもない裸の馬に
長時間乗るっていうのは
とても足腰が鍛えられる。
だからトレーニングなんかしなくとも
すぐに武術の練習ができたんだ。
でも現代人はまずそもそもの足腰が弱い。
だからまずは単純に筋力トレーニングを
した方がいいんじゃないかと
最近はすごく思う。』
站樁(タントウ)っていう立ち方というか
鍛錬法があるのですが
ちょっと悪い言い方をすれば
站樁になっていない
站樁をするベースがない
みたいなことが多いらしいです
まぁ、わかりやすく言うと
感覚とかを大切にしている
その道のプロがまずは筋トレせい!
って言ってるようなもんって
思ってもらえればいいですね
逆にトレーナーのフラン・ボッシュさんは
『エリートアスリートは
単純な筋力はもう十分にある。
それ以上筋力を高めても
伸び代はもうあまりない。
だからカラダの使い方を考えなきゃいけない』
まずはスポーツや運動の時間を
できるだけ確保する(量)
基礎的な筋力・筋量あるいは柔軟性
あるいは心肺機能を
高めるために筋トレやストレッチ
または有酸素運動をする(ハード)
これって実はめちゃくちゃ大切なんですね
特に運動初期段階では
いわゆる基礎体力って呼ばれるものが
大きく向上しますし
運動感覚にもちゃんと効果が望めます
だから量とハードでの恩恵を
受けた人ほどそういうトレーニングの
時間を削って代わりに質とソフトの部分を
重視したトレーニングを組み込むことに
抵抗や戸惑い、不安を
感じやすかったりもします
すごく効果があったものを
手放すのは少し怖い、といった感じでしょうか
ただ、ボッシュさんが言っているように
もう十分強い、もう伸び代はあまりない
量とハードにのみアプローチをしても
いずれこうなってしまう事もまた事実です
ここでひとつ大きなキーワードが
出てきています
『伸び代』ですね
✅最も伸び代があることをする
普段あまり中強度以上の
強い負荷がかかるような
トレーニングや運動をしていない人は
そういうトレーニングをすると
主に神経系での反応が顕著に現れてきます
簡単に言うと筋肉の量は変わってないのに
筋力は強くなります
これは神経の発火と言われるところの反応や
全か無の法則と言われる部分と
大きく関係しています
僕たちの筋肉は
例えば100本の筋繊維が
あったとして50%の力を出す時は
100本の筋繊維が50%の力を
出しているのではなくて
50本の筋繊維が働いて
残りの50本は休んでいる
こういう風に出力を調整しています
つまり普段あまり大きな力を
出すことがない人はカラダの中に
ずっと休んで働かずにサボっている
筋繊維があるってことですね
これが全か無の法則です
まずはこいつらが起きてきます
だから筋繊維の数が増えたり
太くなったりする筋量には変化がなくとも
筋力が上がってくるんですね
そして循環器系
こちらも心臓の血液の拍出量や
最大酸素摂取量が増えるのも当然ですが
血液内を見ても
赤血球数の増加、血漿の増加
善玉コレステロールの増加
が起こり
悪玉コレステロールの低下
中性脂肪の低下
これらも起こります
すごく簡単にいうと酸素を多く含んだ
流れやすい血液になるってことですね
だから心臓や血管への負担も減り
安静時の心拍数や血圧も下がる
ということが起きてきます
こういうことが循環器系でも
初期の段階では顕著に現れてきます
この初期段階でのこれらの伸び代(向上率)は
凄まじいものがあります
イメージとしてはもしその伸び代が
変わることなくずっと
そのまま向上していくと
10年あれば(おそらく5年でも十分)
あなたはオリンピックに出場して
なにかしらの世界記録を樹立します
それくらいの伸び代だと思ってください
なのでまずは量で
換算できるトレーニングをする
週に◯回、一回◯◯分、◯kgの負荷
◯回◯セット、◯kmの距離
量のトレーニングというのは
数値化できたり、視覚化できる
トレーニングだと思ってください
なのである意味初心者にも
とてもわかりやすいです
数字を設定をして
それをこなせばいいだけですから
(まぁ、こなすのが大変ではありますが)
そして、それで最も大きな恩恵を
得られるのがカラダ(ハード)です
フィジカルって言ってもいいですね
こちらもまずは数値化・視覚化できる
ところで効果が感じられるのでわかりやすいです
◯kg重いものが挙げられるようになった
タイムが◯分縮まった
血圧が◯mmhg下がった
体脂肪量が◯kg減った
筋肉が◯kg増えた
みたいにね
こんな風にすごく伸び代があって
更に数値化・視覚化もできるから
する事もわかりやすくて
結果も確認しやすいので
誰でも取り組みやすい
だから最初は量とハードですと
言ったわけです
そして
伸び代があるものを選択して
取り入れたからしっかり向上した
伸び代があまりないものを選択して
手を出してしまったからあまり向上しなかった
これも当たり前です
スタートラインは同じでも
ある程度時間が経過した時に
明確に差が出てくるプロローグの話し
原因はこれですよね
じゃあすごく大切なのは
今の自分にとって
1番伸び代があることは何なのか?
これを見極められるようになること
ということになってきます
✅RPDCAサイクル
残念ながら僕は
誰にでもあてはまる現時点での1番の伸び代を
見極められる方法ってのは知りません
パーソナルトレーニングってのは
その名の通り個人を指導しますから
『この人の!』っていうことであれば
直接指導していればある程度わかります
ただ、できれば僕が見極めるんじゃなくて
その人自身が見極めていけるように
なっていけることがベストだとも思っています
かといってこれで話を終わらせるわけにも
いかないので
どこまで役に立つかはわかりませんが
RPDCAっていう言葉を紹介しておきます
これはトレーニングの用語というより
ビジネスのマネージメントで
使われる用語ですね
正確にはPDCAサイクルって言われることが
多いようなので、僕が頭にRをひとつ
足した形になっています
ではサラッと見ていきますと
【R】Research(リサーチ):調査・収集
【P】Plan(プラン):計画・考察・観察
【D】Do(ドゥ):実行・行動
【C】Check(チェック):評価
【A】Action(アクション):改善・対策
どうですかね?
意味はそんなに難しくはないとは思います
カラダやスポーツでいうならば
まずは目的に対して効果がありそうな
情報やデータを集めてみる(R)
それらを自分なりに考察・観察してみて
採用の是非ややり方を計画する(P)
そして実際に実行(トレーニング)してみる(D)
もちろんそれで終わるわけにはいかないので
自分で結果を評価する(C)
良い結果であれ悪い結果であれ
今までのRPDCのどこにその要因が
あったのかをまた考えて改善・対策をする(A)
って感じですかね
まぁ、言葉そのものはそんなに難しくは
ないと思います
最近は進化系?として
OODA(ウーダ)なんてものもある
らしいですが、カラダに当てはまるなら
正直どっちも大差ないです
で、ここからがトレーナーとしての
お話になります
自分の伸び代を見極めるために
RPDCAは役に立つと思っていますが
あくまでも僕が見ていてっていう
個人的な意見ですが
『圧倒的に』ミスが多いな!
って感じるのがこの中に1つあります
【P】Planです
✅truthとtruthiness
RPDCAっていうのは
時系列を表しているものでもあります
上から順番にしていきましょうねって
ことですね
ただ、書いたように【P】planが
ちょっとおかしなことになりやすいです
特にカラダのことで考えた場合には
すごく顕著にそれが出たりもします
そのおかしなことに関わってくるのが
Truth:トゥルース(真実)
と
Truthiness:トゥルーシネス
(真実であって欲しいこと)
です
カラダの使い方さえ上手にすれば
筋力なんていらないよ!
だから筋トレなんてしなくていい!
有酸素運動なんてしても
痩せないよ!
だからランニングなんてしなくていい!
これはtruthですか?
それともtruthinessですか?
筋トレをせずともパワフルに
高い運動能力を発揮する人はいます
有酸素運動を一切せずに
体脂肪量を減らした人もたくさんいます
じゃあこれらはtruthですか?
もう少しわかりやすいのをいきましょうか
全く運動をしなくて
タバコも酒も食事も好き勝手
もちろん見た目も肥満体型
でも平均寿命よりも長生きして
天寿を全うした
こういう人も必ずいます
じゃあ運動もする必要はないし
健康なんて気にせず好き勝手に
飲食もすればいい
これがtruthですか?違いますよね
truthinessです
色んな人間いますからね
真実であって欲しいことを
結果として成立させられた人は
探せば必ず出てきます
ただ、真実は違います
しっかりとトレーニングした人の方が
やっぱり運動能力が高い傾向にあるんです
有酸素運動もしている人の方が
体脂肪量の減少や体組成の維持をしてるんです
健康に気をつかって生活している人の方が
健康寿命も寿命も長いんです
統計をとれば圧倒的に
そっちの結果の方が多いんです
こっちが真実です
✅TruthinessをPlanに組み込まない
truthinessでplanを作る
これは本当にやっちゃうんです
もっと言うなら
まず、真実であって欲しいことが
自分の中にあって
それと整合性がとれる情報を
Researchする
こういう風になってしまっていることが
すごく多いです
僕も思い当たる節がたくさんありました
まずはResearchなんです
そしてその情報をしっかりと
考察・観察するんです
そしてその上で計画を立てる
それが本当のPlan
だから僕はPDCAの頭に
Rを付けて紹介しました
Pをミスるとその後のDCA
行動・評価・改善も
全部おかしくなってきます
これが今回のテーマで言うなら
伸び代がないことをしてしまっている
っていうことですね
より良いPlanを立てるためにも
truthinessを外してResearch
やっぱりこれになります
だからRを頭に付けたいです
プロローグに戻ると
要領よく勉強すればそんなに
必死に勉強しなくていいよ
これはtruthinessです
そうであって欲しいことですよね
勉強あんまりしたくないもん
そして実際のところは
僕はわかりませんが
もしかしたら本当に1日の勉強時間が
1時間未満だったにもかかわらず
東大に合格した人も過去には
探せばいるかもしれません
ただ、それはすごく稀なことであり
例外に近いようなことで
ほとんどの人はもっと勉強時間を
確保してしっかり勉強している人の方が
圧倒的に多いはずです
それがtruth
勉強時間っていう量を
これ以上確保できないから
もう勉強の質、やり方を
いじるしかない
ここで質とソフトが活きてきます
僕の動画や記事を読んでいただいている方は
おそらくほとんどの方が社会人だと思います
仕事もあるでしょう、家族もいるでしょう
プロのアスリートと同じだけの
トレーニング量・練習量なんて
到底確保できないでしょう
じゃあまずはResearchしましょう
自分にとって伸び代があるのは
量とハードなのか
それとも質とソフトなのか
これを見極める、考察するための
調査・収集をしましょう
そこにtruthinessは不必要です
量とハードの方が伸び代があるなら
やればいいんです
というかやるべきです
もちろん質とソフトにより良い伸び代が
あるならそっちをすべきです
じゃあその見極め方は??
truthinessを外しましょう
ちょっと難しくて厳しい注文ですか?
でもtruthinessを外せると
本当に自分がやるべき事も見えてきますし
truthinessありきよりも確実に
ステップアップしていきます
少なくともそれが僕にとってのtruthです
動画の視聴者さんからの質問で
カラダの使い方や感覚的な事を
学んでいくならまずはどんな事から
すればいいのか?
優先的にすることや効率のよい
順番などはあるのか?
っていうご質問を頂いたのですが
本当にちゃんと答えるなら
1番伸び代があるものをすればよくて
それを見極めるためにtruthinessがあるのなら
まずはそれを外す
そしてその上でResearch→Plan→…
としていくのはどうでしょうか?
となります
うーん…やっぱり厳しい注文かなぁ…
でも本当にちゃんと答えると
やっぱりこれです
