
シリア難民の女性に仕事をつくりたい!〜 オリーブの木製食器をヨルダンから世界へ〜大橋希さん
こんにちは!国際協力サロンの渡邉です。今回は、現在ヨルダンにて女性の難民を雇用する事業を起業中の大橋希さんをお招きした、勉強会の様子をお届けします!

大橋 希(おおはし のぞみ)さん
イギリス大学院にて開発学(ガバナンス再建と民主化)を専攻。ソーシャルビジネスの会社、ボーダレス・ジャパンにてグアテマラの女性雇用事業に1年、日本国内の難民を雇用する事業に2年所属。主にセールス・マーケティングを担当。大学4年時にヨルダンに2ヶ月滞在、中東最大の難民キャンプ、ザータリ難民キャンプや首都アンマンの難民宅を訪問。その時に家族を失い、家を爆破さた話を聞き、中東の難民問題に将来取り組むことを決意。現在、ヨルダンにて夫を失った女性の難民を雇用する事業を起業中。
フランス留学と、垣間見えた社会問題
大橋さんが難民問題に関心を抱くようになった最初のきっかけは、交換留学で1年間フランスで生活をした高校2年時まで遡ります。
当時、想像するフランスといえば、先進国であり、ヨーロッパを代表するパリのお洒落な街並み。
しかし、1年間現地校に通い、ホストファミリーのもとで暮らす中で、ホストファザーがアルジェリア系のフランス人でイスラム教徒であったこと、友人の祖父母は北アフリカの国から来ていたことなど、身近なところにたくさんの移民がいることを知りました。
また、街中には移民の方が住む地区があり、そこは窓ガラスが割れていたり壁には大きな落書きがあったりと、他の地域とは全く違う雰囲気が漂う場所も。
「フランスの中にもこんな格差があるんだ」と衝撃を受け、また世界には他にもたくさんの社会問題があるのではないかと考えるようになったと同時に、学校にも通って、当たり前のように3食ご飯も食べられている自分の生きてきた環境は、すごく恵まれたものだったのだと感じるようになりました。
「これから先の人生、自分が経済的な面で豊かになっていくよりは、社会に対して何かできることがあるのではないか」と考え、国際協力・国際開発の分野を目指しはじめました。
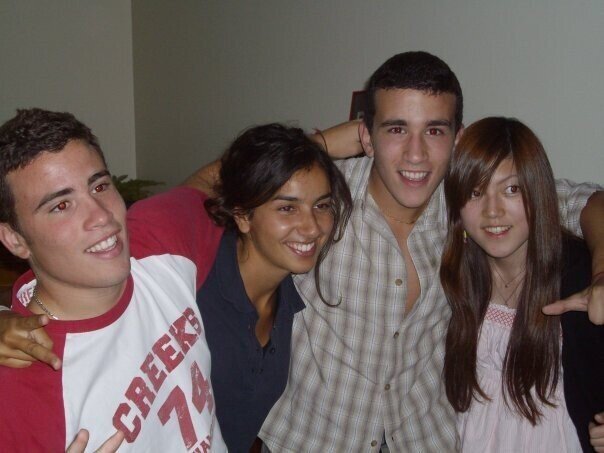
高校時代の留学をきっかけに、イスラム教やアラブ諸国の文化に興味を持ち、大学4年時、初めて中東ヨルダンに渡航。2ヶ月間の滞在中、初めてシリア難民の方とお話しました。
そこで耳にした家族を失くした話、家を爆破され失った話、そして母国から逃げざるを得なかった話。再び、フランス留学で感じた思いが沸々と湧き上がってきました。
「私がこうして旅をしている中で、偶然その土地に生まれた為に、家族や家を失い、母国から出なければいけない人も存在している。」すごくやるせない気持ちになりました。

社会人になってからは難民問題に想いは集中し、ボーダレスジャパンに就職。グアテマラの女性雇用の事業に1年間従事した後、日本国内の難民を雇用する事業に2年間携わりました。
そして、難民の人と一緒に働くことで改めて、私たち(恵まれた人たち)が手を差し伸べていかないと、難民の方たちは世界から放置される存在になると感じ、ヨルダンに戻り彼らをサポートするを立ち上げることにしました。
ヨルダンと難民について
ヨルダンは第一次世界大戦の時にオスマン帝国崩壊に合わせて建国された、建国100周年の新しい国です。4度に渡って勃発した中東戦争を逃れて移住したパレスチナ難民や、その子ども、孫世代がヨルダン国籍を取得し、ヨルダン人として生活を営んでおり、現在パレスチナ系の人々が人口の約70%を占めていると言われています。
また、2011年に勃発したシリア内戦でも多くの難民を受け入れ、現在は約130万人のシリア難民がヨルダン国内に。うち80%が貧困ライン以下の生活を強いられています。
難民全体の20%は難民キャンプで生活しており、ほか80%の人々は街中に住んでいますが、キャンプ内に住む場合は食事の配布等もあり、最低限の生活は見守られている一方、街中に住む難民は所在がどこにあるかもわからず、十分な支援が行き届いていないのが現状です。
ヨルダンにいる難民の3つの問題
このようにヨルダンは多くの難民を受け入れていますが、受け入れにあたる課題も多く存在するのも事実。大きく3つ挙げられます。

①収入
就労許可がないと働くことができませんが、許可は全員におりるわけではありません。就労許可が降りない=働けない=収入ゼロ の悪循環が生じています。
②精神的トラウマ
母国で家族を失ったり、爆破により住む場所をなくしたりした経験を抱えている上に、職がない状況での将来への不安から、精神的に追い込まれていく難民の方も多くいます。
③自由の制限
受け入れ先国のヨルダン人と同じ権利を与えられることはなく、働く業種が限られたり、自身で開業することができたりすることもなく、働き先を自ら生み出すことができない現状もあります。
ヨルダンの難民は多くの問題を抱えていますが、先進国と呼ばれる国々と比べ、決して十分な社会基盤が整っていない環境にありながらも隣国から多くの難民を受け入れており、決して努力を怠っているわけではありません。
わたしたちにできること
収入がないことが問題のひとつであることは前述のとおりであり、現在はヨルダンに住む難民の女性に仕事を提供する、雇用創出事業の拡大に取り組んでいます。

国際機関やNGOが入ってきている中で、雇用創出をサポートする機関はまだまだ少ない印象にあります。縫い物やITのスキルを身につけて、トレーニングを受けることはよくありますが、肝心なその後の仕事がないということも。そのような状況を変えたいと思い、オリーブの木で食器を作る雇用創出の事業を考えています。
たくさんのオリーブの木が生息しているヨルダン。オリーブの木というと、はっきりと木目があらわれて柄が非常にきれいなことに合わせ、耐久性、抗菌作用ともに優れた性能を持っており、子ども用の食器やカフェの食器としての商品化を検討中です。
また、オリーブの木は焼かれることも多いことから資源の再利用に、そしてオリーブは国連旗にもあるように平和の象徴の意味も込められています。
食器の制作、販売によって、難民の人々には普通の生活を送って欲しい。そして、購入者には制作までのストーリーを感じて欲しい。この食器とともに食事を楽しんで、幸せな時間をつくってもらえたらいいなと、思いを込めて事業を進めています。

さいごに
最後に難民認定率が他国と比較し著しく低い日本の難民認定制度についてもわかりやすくお話してくださいました。
はっきりと「難民」について定義されていない中、難民認定の基準がどこにあるのか不明確であり、申請者に対して何の助言もできないのが今の日本の現状です。また、認定の基準やそこに至るプロセスの不明確さといった制度に問題があることに加え、私たち市民側の難民に対する理解不足もこの問題に関係しているのではないでしょうか。
積極的に難民の人々の情報を取りにいき、発信していく事が日本の難民認定制度を変えていく一歩なのかもしれません。
”難民”と聞くとどこか遠い地域の話のように聞こえてしまいそうですが、決してそんなことはない、日本にも存在する身近なものだと教えてくださいました。積極的な情報収集により、まずは難民を知ることから、自分にもできることから取り組んでいきたいと思う筆者でした。
それでは、次回もお楽しみに!
国際協力サロンでは、「まなぶ、つくる、つながる。」を合言葉に国際協力について毎月勉強会を行っています。国際協力サロンで一緒に勉強したいという方のご参加、ぜひお待ちしております!
