
『灰羽連盟』感想:「壁」による呪縛と「鳥」による祝福について
アニメ『灰羽連盟』の感想・考察になります。
また祝福に関連して、以下の作品等にも軽く触れています。
・『響け!ユーフォニアム』2期(アニメ)
・『さなのばくたん。 -ハロー・マイ・バースデイ -』(VTuberイベント)
※引用画像の©は以下になります。
・灰羽連盟 :「©安倍吉俊・光輪密造工房」
・ユーフォニアム:「©武田綾乃・宝島社/『響け!』製作委員会」
牧歌的な暮らしの雰囲気がありつつも、どこか穏やかに終わりに近づいているかのような終末的な雰囲気が漂う世界観。灰羽たちは廃棄された寄宿舎や工場に居を構え、街は「壁」に囲まれている。ヒトも含めてこの「壁」の外に出ることはできない。そんな閉じた世界にラッカは生まれ落ちる。右も左もわからないラッカはとても親切な――だが、煙草は手放せない――レキやオールドホームの面々に迎え入れられる。そして、ラッカはこの世界で「鳥」に教えられ、赦され、また彼女自身が「壁」を超えて行く「鳥」になっていく。
もう20年近く前の作品になるが、印象に残っている作品の1つになる。ある本を読んでいる際に、この作品がふと頭に浮かび、なんとなく今ならば、レキの苦悩や「罪憑き」、またこの作品で示された救い=祝福について、私なりに解釈できるのではないかと思い、再度見直した感想を残そうと思う。
施しとその理由について
こんな小話から始めよう。誰かに施すとき、例えば電車やバスなどで誰かに席を譲ったときについて考えよう。あなたは誰かに席を譲った。このとき、なぜ譲ったかと聞かれたら、(譲った)相手のためと答えるだろう。しかし、その行為の裏に、特定の相手や世間から見て「良い人だな」と思われるため、つまり、社会的に称揚されるため、という算段もなかったかと追及されれば、苦笑いを隠せないのではないだろうか。他者に施すとき、どちらに重きがあるかは個々の状況によるだろうが、この2つの理由――相手のためと自分のため――が不可分に伴う。私が「相手のため」と思っても、傍から「自分のため」ではと邪推されたり、私自身、問われてみると全く「自分のため」ではないとははっきりとは言えない、と感じてしまうこともあるのではないだろうか。
「壁」:良い灰羽と悪い灰羽
この視点をもってレキを見てみよう。レキは話師との会話などで「ラッカは良い灰羽だ」「私は悪い灰羽云々…」などなど、事あるごとに「良い灰羽」「悪い灰羽」について言及をする。ラッカの繭を見つけたときの手記にも【今度こそ……「良い灰羽」になるんだ】と言及されていたのが印象的だった。レキが使う良い/悪いの基準は、何か確固たる基準がレキの中であるわけでなく、「一般的に言って」「常識的な範囲で」良い/悪いのニュアンスで使われている。このような基準を私たち人間は知らぬ間に培っている。世間一般的に言って「これは良いこと」で「これは悪いこと」という価値観をあなたも持っているだろう。これらは世間や神様のような立ち位置の存在から指定されたかのような基準であり、天使のような見た目――羽と光輪――の灰羽たちに対して、まるで天上から私たちを見るようにあるその眼差しを(機能としての)<父>と呼ぼう。
<父>に実体があるわけではない。それぞれ個々の頭の中で、日々他者からの言葉を受け、練られ作られる。そういう意味では<父>は命令、あるいはただの言葉の堆積であるとも言えるだろう。良い/悪いの基準についても、何か具体的なチェックリストがあるわけもなく、人々が口々にする内容から――個々人に境界の幅はあれど――ある一定の良い/悪いの基準が頭の中に自然と浮かんでくるようになる。このようにして、<父>は「お前は〇〇だ」と規定してくるのだ。「良い灰羽だ」「悪い灰羽だ」のように。
街を取り囲むようにある「壁」はこの「<父>の法」の象徴だろう。法はここまでOKだが、ここ以降はNGだとする境界である。私たちは<父>の法を見てみぬふりはできる(人もいる)が、頭の中から存在を消すことはできない。また個人で乗り越えること(<父>の法よりも優先する法を作ること)もできない。私たちは否応なく「壁」に囲まれて暮らさざるを得ない。作中の「壁」はそういう象徴なのだろう。「過ぎ越しの祭り」の後「壁」は”みんな”の思いを受けて光る。終盤、この「壁」を越えれない=『轢』という当てはめを超えないレキは「壁が意味するのは死だ」と豪語する。
『轢』
ラッカがレキに出会ったとき、既にレキは施しの理由のうち【「良い灰羽」であるために】という理由の方に傾倒しており、レキの苦悩がそこに垣間見える。ヒョウコとの関係など、横の関係を作っても相手を不幸にしてしまうというある種のジンクスや「罪憑き」である自身への他者の視線も伴って、横の繋がりを作らない/作れない。レキが主体的に行っているように見える、新人の面倒を見るという役割もクラモリの言葉を受けたから行っているのであって、レキ自身からそれをしたいと思って始めたわけでもない。
基本的にラッカをメインとして進んでいた物語だったが、終盤は、親切心の塊のように見えたレキの苦悩にラッカが気づき、物語が――ラッカの物語であると同時に――レキの物語としてシフトしていく絡み合いが『灰羽連盟』の凄みであるように思う。
空っぽの笑顔を張り付けて、私たちは歩く。
どんなときでもレキは優しい。
誰にも心配かけたくないから、誰にも頼りたくないから、レキは笑う。
どうしてもっと早く気づいてあげられなかったのだろう。
私はずっとレキの一番近くにいたのに。
レキは<父>やクラモリという立ち位置的に上にいるような視線から、認められたい、愛されたいという思いから施しをしている。彼女らからの救済を求めている。実際に施す相手のことを想う気持ちはないことはないだろうが、二の次だという感覚がレキの中では消えない。故に施す相手は特定の誰かである必然はなく「私にとって、ラッカはラッカでなくて良かった」。他者に施しをしているが、それは「良い灰羽」だと言われるためであり、縦からの愛を求め、横のことを想う気持ちを肯定できない、あるいは優先できる気がしない。これが「ひき裂かれる者」である『轢』の状態であった。レキの内面は縦との繋がりを強く求め、横とのつながりからひき裂かれている。他者に施すという行為をしているにもかかわらず……。作中、この言葉は出てこなかったが、レキは「偽善」という言葉を振り切れなかったのではないだろうか。
また個人的に思うのは、レキは(<父>に愛されるために)「良き灰羽」としての振る舞い――作中で「空っぽの笑顔」として言及される――を求められ、ありのままの自分として振る舞うことからも疎外されている。これも「轢かれる」ことの一つではないだろうか。
「罪」:原罪
作中、「罪憑き」や『罪の輪』など「罪」に言及する言葉が頻出する。言及されるこの「罪」とは、一体誰に対しての何の罪なのだろうか。時代や場所が異なれば法は異なる。法が異なれば正しくない行為は異なり、「罪」として言及される行為は異なる。戦時の英雄は平時の殺人鬼と言われるように。普遍的に言及される「罪」などあるのだろうか。
作中で羽の色をもって言及される(普遍的な)「罪」はキリスト教の原罪ではないかと見える。(完全な神様と比べて)不完全な存在である人間は何が悪で何が善かの判断を見誤る。それに気づかず判断を致してしまう、その驕りがヒトの「罪」であると。
この原罪の根底にある理屈は「善は悪の礎となり、悪は善の礎となる」という道理にある。私が良かれと思ってやったことも、悪い結果に結び付くこともあれば、ある悪徳な行為も、ある側面では善に繋がるなど往々にしてあるからだ。悪人はいないのに構造的に悪夢が出来た『ダーヴィンの悪夢』など典型例だろう。人間は全て予測し、ある行為が善か悪かを判断することができない。全能の神様と比べ、人間は最初から劣っている存在なのだから。
罪を知るものに罪はない。では汝に問う。汝は罪人なりや?
話師は「罪憑き」であるレキとラッカにこう問う。そして、答えを出すことができずに、問いの中を彷徨う様を『罪の輪』と呼ぶ。人間の判断能力の無力さを突きつける類の問いだ。この問いは「嘘つきパラドックス」の亜種であり、一般的に「自己言及のパラドックス」と呼ばれる。私は私について述べようとするとき、私は私を見失ってしまう。
「自己言及のパラドックス」自体にはいくつかの理性的な逃げ道が知られている。例えばラッセルは文に次元の区別を作ったり(階型理論)、ラカンは文中の語(シニフィアン)は位置が異なれば、語の同一性を仮定することはできないという立場からパラドックス自体発生してないと見る。が、話師はこんな解答を求めているわけがない。
このパラドックス以前に、私が仮に「私は罪人だ」と思っている場合、私は「私が”正しくない”行為をした」と思っているということであり、また逆に私が「私は罪人でない」と思っている場合、私は「私が”正しくない”行為はしていない(=私は常に”正しい”)」と思っているということだ。このとき、「私が正しいか(善)、正しくないか(悪)」以前に、そもそも正しい、正しくないの判断をヒトである自分が出してしまっている。このことが驕り(原罪)なのだ。
話師が『罪の輪』をラッカやレキにした意図は、私が罪人か罪人ではないかというTrue/Falseの解を理屈をこねてひねり出してもらいたいのではなく、そもそもこの判断自体が自身では答えを出せない類の判断だと気づかせることにある。『罪の輪』はそういう気づきを与えるための禅問答なのだ。この気づきこそが原罪への気づきであり、輪から脱出になる。
判断できないことに対して判断をしてしまうことが「罪」である。では、羽が黒くなることで示された、原罪を犯してしまったラッカやレキは、具体的に何に対して判断をしてしまったとされているのだろうか。
罪憑き
繭から誕生したタイミングから既に「罪憑き」だったレキより、物語の中で羽が黒くなっていったラッカの方が「何の判断をしてしまったか」がわかりやすいだろう。
ラッカはクウが巣立った後、居なくなったクウに対して、少し行き過ぎに感じられるほどの執着(対象喪失)を見せる。フロイトの言うところの「メランコリー」に近いだろう。次の台詞が特徴的だった。
町の人にとってはクウがいなくなったことはたいしたことではないんだ。
きっとクウがいたことなんてすぐに忘れてしまう。
クウ……クウはそれでも平気?
喪われてしまった対象(クウ)の立ち位置に立ち(=同一化)、その立ち位置からの気持ちを想像している。失われている対象に同一化していく私もまた無に向かっていくしかない。ここまでの物語の印象としては、流れとしてラッカがクウにここまで思い入れしていたようには見えなかったため、展開に唐突感があったが、この後に開示されるラッカの「繭の夢」の内容への言及から、おそらくこのメランコリーの起こりやすさは、ラッカに特異的な性質(「私なんていなくなっちゃえばいいんだ」の反復)だったのだろう。
ラッカの羽が黒くなる契機となったのは、クウの部屋でのある行為だった。クウの部屋には、オールドホームの灰羽たちを装った、蛙人形たちの置物があった。ラッカは”ラッカ”と書かれた蛙を指で落とした後、羽が黒くなっている気づく。
私いつも一人ぼっちで、自分がいなくなっても誰も悲しんだりしないって思ってた。だから、消えてしまいたいって思った。

ラッカは自分で自分を落としたのだ。私が私に対して「いなくなればいい」「出来損ない」の存在であると自分一人で自己言及して、自分を堕とした。
「いなくなればいい」私になんでわざわざみんな優しくしてくれるのだろうか。勿体ないじゃないか……。話師はこの状態のラッカを一人「固い殻に籠る」と形容する。
なぜ灰羽は”灰羽”なのか。それは本来白だとも黒だとも判断できない存在だからだ。故に灰色。ただし、判断できないこと(自己言及)に対して、判断してしまった場合だけは明確に過ち(原罪)であるため、黒に染まるのだ。それが「罪憑き」であろう。
ただ『灰羽連盟』においては、自己言及一般というより、自己言及の中でも私は「価値のない」存在であるという類の判断を、特に「罪」と見なしているように見える。
レキについては詳細に語られることはないが、おそらく自ら汽車の前に投身するべき存在と判断して身を投げたのだろう。「私は助けを呼ぶこともできないの?」と悲しげに語る自分自身を置き去りにして。
不完全な存在である人間が本来答えが出せることがない問い――自己言及――に、彼女らは答えを出してしまっている。それは早押しクイズにおいて、最後まで問題を聞くことなく、解答してしまっているようなものだ。最後まで問題を聞かないと早とちりしているかどうかもわからない。問いの途中で答えを出したとしても、正解か不正解かを教えてくれる存在はいない。でも、彼女らはそれが答えだと思い込んでいる。
そして、「鳥」はそこに飛んできて、その答えを変える。
鳥が私に伝えてくれたのは、私が繭の中で見た夢の本当の意味なんです。
井戸の底で夢を見ました。
あの鳥は……私が知っていた誰かなんです。
私のこと心配してくれてた。なのに私、それを分かろうとしないで……
(話師に「思い出せない誰かのことをなぜそれほど悲しむ」と問われて)
わからない。でも、私誰かを傷つけてしまった。
オールドホームの面々や古着屋のおっちゃんだって、ラッカのこと心配していた。その場面を「出来損ないの私になんで……」とラッカが(勝手に)捉えてしまっていたんだ。そして「鳥」はラッカは一人ではないと伝え続けることで、ラッカの自己言及を打ち消した。思い出す場面は同じでも、場面の解釈を変えたのだ。あの場面は――「繭の夢」は――「私が一人ぼっちだと勝手に思い込んでいたこと。そしてそのうえで、そのことで誰かを傷つけてしまっていた」場面だと、ラッカの中で事後的に見方が変わったんだ。
次はレキの話をしよう。レキは「繭の夢」の直後から「罪憑き」の子として生まれ落ちた子だった。
繭の夢
灰羽たちは生まれる前に繭の中で夢を見る。そして、その夢の内容をもって名づけられる。この夢は「繭の夢」と呼ばれるが、精神分析の言うところの「根源的幻想(原光景)」と言っていいだろう。※1
私たち言葉を話す人間は、物理的な身体とは別に、言葉からなる象徴的な身体を持つ。象徴的な身体については、ジョセフ・コスース『1つの、そして3つの椅子』がわかりやすい。
上記の作品で示されるように、椅子について、私たちは実物としての椅子、イメージとしての椅子、そして言葉で表される椅子の3つを保持している。3つ目の椅子が「象徴的な」椅子になる。
椅子だけでなく、私は私自身に対しても、言葉で表される私――象徴的な身体――を持っている。個人的に、私はこの象徴的な身体のことを「虫かご」と呼んでる。それはドーナツがドーナツの穴という存在を捉えるように、空っぽのその虫かごは、無の私を捉える。その虫かごは言葉の織物からできている。
ある研究者について考えてみよう。彼/彼女に「貴方は何者か」と尋ねる。すると彼/彼女は、ある研究分野で研究をしており、いくつかの論文を出していると答えたとしよう。その分野で研究者であることとその論文――もといその論文内の理論など――が彼/彼女にとって、象徴的な身体になっている。彼/彼女にとって、それが「貴方は何者か」への解答であり、言葉の平面上で捉えた”私”である。
では、彼/彼女が研究者になる前――業績がない――は、象徴的な身体をもっていなかったのだろうか。研究者としての”私”以前から、私は”私”を持っていたはずだ。例えば、私はどういう家族の元に生まれたか。家族の中でどういう立ち位置だったか――兄や弟、姉や妹だったか、私は愛されていたか否か。私はどこで生まれ育ってきたか。どういう人たちと一緒に暮らしてきたか。誰に似ていると言われたことがあるか。私は何が好きで、何が嫌いか。エトセトラ……。私は私を”縁取るような何か”を持っている。「貴方は何者か」と尋ねられたときに答えられるような何かを。私の歴史の中で、私は”私”を獲得してきたのだ。
しかし、同じように「それ以前から私は”私”を持っていたか」と辿っていくと、ある原点にぶち当たる。それはブートストラップ問題のように、最初の一回目という問題である。初め、私は何もないところから、私は何者かを把握しなければならない。早押しクイズのようにその答えを出すしかない。このときに、個々人が把握した、最初の”私”の内容が『根源的幻想(原光景)』と呼ばれる。それは”私”にとって最初の風景であり、起源であり、故郷である。
灰羽たちが「繭の夢」をもって、己らを名づけるのは、それは最も根底にある”私”だからだ。
精神分析にはいくつもの派閥があるが、おおよそ「精神分析」の系譜にあたる実践であるならば――治療における原光景の位置づけは異なるかもしれないが――実践の中で「根源的幻想(原光景)」に至るプロセスは必ず含まれるだろう。なぜならこの「根源的幻想(原光景)」が私が”私”を把握するときの最も根底になっているものであり、”私”の建築様式の礎であるから。何らかの生きづらさがこの根にあるならば、ここから”私”を組み立てなおさなければならない。
レキは不幸にも、この根源の地点で【私は『轢』である】という「罪憑き」な早とちりをしてしまっている子、なのだということなのだろう。
私たちはこの「根源的幻想(原光景)」を反復することが知られている。例えばレキの夢解釈をしよう。レキは「繭の夢を思い出せない」。つまり、「繭の夢」とひき裂かれている。思い出せないということ自体が夢の(内容の)反復である(このメタ的な夢解釈はフロイトによって指摘されている。『夢判断』にて、例えば「訳がわからない夢」では「訳がわからないこと自体が解釈のヒント」になる夢解釈が紹介されている。レキは「ひき裂かれた」という夢内容が、覚醒後の「思い出せない=ひき裂かれている」という夢全体に下された判断と一致している。ここにフロイトの例と全く相同な解釈ができる)。そして、レキは他者(横の繋がり)からもひき裂かれ、また自分自身からもひき裂かれているのは見てきたとおりだ。偶然の不幸に見えて、最後はレキ自身の意向(あるいは諦める選択)で、自ら引き裂かれる方向に落ち着く傾向が見られる。
この早とちりから抜け出すための方法として、『灰羽連盟』は真名――”私”を指し示す言葉――を介した意味作用(シニフィカシオン)のずらしをもって「レキ」を組み立てなおそうとする。つまり「レキ」は『轢』ではなく『礫』であるとずらすのだ(ここら辺は(前期)ラカンくささがある)。
「鳥」による祝福
『レキ』
「レキ」という名は、レキにとって自分自身を指し示す音だ。そして「レキ」という音には、様々な当てはめうる言葉がある。歴、暦、礫、轢……。音だけではどの意味を当てはめるべきかは判断できない。どれが当てはまるかという判断には能動的な「聴き・為す」行為が必要となる。意味は全体の中にあって、全体に対しての位置で決まる。そのため、どういう全体の中にあるのかを把握しなければならない。
あまり良い例ではないが、わかりやすい例を紹介しよう。
シャニマス 内容が意外と思想強くてビビるな pic.twitter.com/R0EsDfFINA
— あいう (@ayiuayiu) July 31, 2020
「トランプ」という言葉は、本来何で遊ぶかという文脈で述べられた言葉だが、「思想が強い」というたった一言が加わるだけで、意味が全く異なって捉えられるのがわかるだろう。『灰羽連盟』は「ラッカ」や「レキ」という真名において、この意味作用のずらしを行い、象徴的な身体を組み立て直そうとする。
レキはラッカを介して話師から『轢』という解釈をもらう。話師は灰羽たちの心の根を話すという。故に(この作品においては)解釈というよりも、これは答えそのもの、つまり、彼女自身が抑圧していた、レキ自身の「繭の夢」の解釈そのものと言って良いだろう。
レキという名の少女の物語を語ろう。
その者は悲運に見舞われ、悲しみを分け合うはずの相手すらをも失った。
己の価値を見失い、自らを小石に例えて『礫』と呼んだ。
だが、その名は、轢き裂かれたる者の意を表して『轢』と言う。
ここにラッカという「鳥」が飛んでくる。
ラッカがもし自身の「繭の夢」を思い出すとき、ただ一人落ちる夢だったら、何も変わることができなかっただろう。原光景である夢の中に「鳥」がいて、その「鳥」への解釈が変わり、夢全体の意味合いが変わって、彼女は拾い上げられた。そして、同じようにしてレキを救おうとするならば、ラッカという「鳥」は、レキの「繭の夢」の中にあらねばならない。誰かの心に影響を与えようとするならば、相手の心の中にあらねばらないからだ。ラッカがレキにとってどういう位置づけにあろうとしていたかは、レキの「繭の夢」の中にラッカが入るという演出で示される。
そして、レキが「鳥」を迎え入れた時、レキにとって「レキ」の意味がずれる。
もしも鳥がお前に救いをもたらしたら、『轢』という名は消え、石くれの『礫』が真の名となるであろう。そうなることを信じ、あらかじめ『礫』という名の新たな物語を、ここに記す。
その者は険しき道を選び、弱者を労わることで呪いをすすいだ。その心性は救いを得んがための仮初めであったが、今やその者の本質となった。灰羽が巣立つとき、踏み石となる古い階段がある。『礫』とはその踏み石であり、弱者の導き手になる者である。
違いは、たった1つ、弱者や灰羽として言及される「鳥」が付け加わったこと。レキは自己言及の中で、今までレキ一人だけで(「壁」によって)定義されていたところに他者との交わりが加わり、レキは自身を「灰羽が巣立つときの踏み石」として位置づけれた。<父>とレキの二者関係で閉じた定義から、ラッカとレキという関係が付け加わることで、レキに当てはめる意味が変わったのだ。これが「鳥」による救いであり、祝福である。「鳥」は「壁」を越えるとはこういうことだ。異世界転生しなくても、私は”私”を取り巻く全体に変化があれば、生まれ変われる。
『灰羽連盟』における「鳥」による祝福は、演出的に――ラッカがレキの心の中に入っているという意味合いを込めてだろう――ラッカが急に夢の中に入ったり、汽車(?)が現実に現れたりと、マジックリアリズム的な表現がなされている。副作用的にどうしてもどこかファンタジー感が抜けないため、他の作品で「鳥」による祝福だなと思えたものを紹介しよう。
『響け!ユーフォニアム』:久美子と麻美子
1つ目はアニメ『響け!ユーフォニアム』の2期。主人公である久美子と姉・麻美子の話。

幼少の久美子は姉・麻美子の吹奏楽の演奏を見て、吹奏楽に入りたい、姉と一緒に演奏したいと思うようになる。また楽器なしで音を出す練習を姉に教えてもらうなどして、姉や吹奏楽により惹かれていく。

お姉ちゃん、かっこいいんだ!
しかし、久美子が吹奏楽に入れる年齢になる前に、麻美子は吹奏楽を辞めてしまう。その理由を麻美子は久美子にはっきりと伝えることはなかった。そして、久美子が高校生、麻美子が大学生のときに、急に麻美子が大学を辞めると言い出し、親と喧嘩をして、その口論から久美子が真意を知ることになる。
(親との口論で)
麻美子「今まで私はお母さんの言う通りにしてきた。
全部我慢して、お姉ちゃんだからってずっと!
転校だって、受験だって、本当は全部嫌だった。
私だって久美子みたいに部活を続けたかった。
トロンボーンだってやめたくなかった。」
(CDを流すのを止められて)
久美子「だったら……。だったら、続けたかったなんて言わないでよ!
吹奏楽嫌いなんでしょ!?
今になって続けたかったなんて言うのずるいよ」
麻美子「うるさい!!
あんたに…私の気持ちなんて分かるわけない」
麻美子にとって、吹奏楽とは「続けたかったのに辞めさせられた」ものだった。そして、麻美子は自分の気持ちを抑圧し、久美子に吹奏楽が嫌いだ、と当たるようになっていたのだった。
麻美子は今度からは自分のやりたいことを抑圧せずにやっていくために、親元を離れていく。
私ね、ずっと自分で決めることを避けてきたの
文句言いながら、ずっとお母さんたちの言う通りにしてきた
それが頑張ることだって勘違いしてた。
我慢して、親の言うこと聞いて堪える…それが大人だって
……
高校生なのに大人のふりして、世の中なんてこんなもんだって全部飲み込んで、我慢して…
でも…そんなの何の意味もない
自分の道を行きたい…そう素直に言えばよかった
だから今度は間違えない
ここで第三者が麻美子に「久美子が麻美子に憧れて吹奏楽始めたこと」「演奏を聞きに来てほしい」と伝え、全国大会という舞台での妹の演奏を、姉が聞きに来ることになる。
久美子は大会が終わったあと麻美子を見つけ、部活のことも置き去りにして飛び出し、そして、伝える。

久美子「お姉ちゃん!私、ユーフォ好きだよ!
お姉ちゃんがいたから私、ユーフォ好きになれたよ
お姉ちゃんがいたから、吹奏楽好きになれたよ
お姉ちゃん!大好き!」
この場面、久美子はラッカだった。「鳥」だった。麻美子にとって、吹奏楽をしていたことは、自身にとってはもう何の意味のないことだった。無駄なことだった。辞めてしまったことは苦悩でもあった。そこに麻美子が吹奏楽をしていたから、今・ここの全国大会まで来た私(久美子)はあると強く伝え、麻美子に書き込んだんだ。「今度は」以前も全てが間違いというわけではなかった、と。
麻美子「…私も!大好きだよ!」

『さなのばくたん。 -ハロー・マイ・バースデイ -』名取さなと、せんせえたち(リスナー)
もう1つは個人的な話でもあるが、VTuber「名取さな」さんの誕生日イベント『さなのばくたん。 -ハロー・マイ・バースデイ -』について。
名取さんがVTuber『名取さな』となるにあたって、せんせえたち(リスナー)がいなければ『名取さな』になれることはなかった。自身の内面をメタ的に仄めかし語ることで、そのことを強く伝えてくれるイベントであった。
名取さんにとって、まずせんせえたちは「鳥」だったのだろう。彼女の活動に対しての感想だけでなく、イベントで手紙を送るせんせえたちもいた。その中には、分厚く、名取さんと絡んだ、せんせえ自身の人生について綴られていた手紙もあったという。「先生になりました」という手紙も多かったらしい。
そして、このイベントでは名取さんがせんせえたちにとって「鳥」だった。せんせえたちとの関係の中で『名取さな』を位置づけ、それを強く伝えてきてくれた。
だからもっとなりたかった私になれるよう、名取は頑張りたい。
だから今日ここで、せんせえたちの前で、私の悩みと向き合う新しい約束をさせてください。
今思うと、私も彼女から祝福を受けたのだろう。少し大げさかもしれないが、このイベントに――もはや儀式と言ってもよいだろう――せんせえとして立ち会えたことを光栄に思う。
巣立ち
灰羽たちの旅立ちは「巣立ち」と形容される。つまり、「鳥」となる準備を果たせたことが「巣立ち」の条件なのだろう。ここで言う準備とは【私が私自身を「他者の〇〇」と思えること】であるように見える。このとき、もはや己の生は自分のためだけにあるわけではない。だからこそ己の「壁」も越えられる。
クウは「他者の手本」であること、レキは「他者の踏み石」であることと自らを位置づけたとき「巣立った」。誰かの人生に祝福を与えれるように飛んでいけること。私自身が誰かにとっての「鳥」であること。それが「巣立ち」なのだろう。
レキを救い上げたのはラッカだった。レキはラッカがいなければ、灰羽の踏み石として『礫』であると思えることはなかった。一方で、ラッカもレキがいなければ『絡果』として「鳥」を成し得なかったとも言えるだろう。このような相互的な関係は「托鉢の鉢とお布施の関係」と呼ばれる。布施という「与える行為」をするためには、相手が必要不可欠となる。きっとクラモリもレキがいたから、レキに施せたから「巣立て」たのではないだろうか。
レキはやはり――早押しクイズで――間違った自己言及を成してしまっていた。自分はただ厄介者で、クラモリにもラッカにも皆にも迷惑かけてばかりだと。クラモリの「踏み石」だったかもしれないとも露とも思わずに。原罪とは、見えない将来や知らぬに与えていた過去のことを考慮せず、今・ここ――現在――の己の視点だけで判断してしまうからこそ、過ちを犯す、ということなのかもしれない。
私たち不完全たる人間は判断を誤る。この理屈は、どうせ間違えるというニヒリズムや考えても無駄だから考えることを放棄するという判断にも繋がってしまうこともあるが、こと自己言及に関しては、原罪意識は、私が「私には価値がない」という、本来は断定ができないはずの断定をしてしまった道から救い上げるための、道しるべなのだろう。
もちろん「私には価値がある」という誇大的な判断も同様に早計なのだが。そちらは『灰羽連盟』では出てこないので、ドフトエフスキー『罪と罰』を参照すると良いだろう。「壁」を超えることはできるが、「壁」の上に立つことはできない。
最後に『灰羽連盟』で見てきたことをまとめよう。
<父>はあなたを直接祝福しない。あくまで経路を、方向性を説くだけのようだ。ときに自分のことを「価値がない」と自己言及してしまう原罪に陥ってしまう私を救い上げ、祝福できるのは横の繋がりである「鳥」だけだ。
私は、自分一人では「壁」に規定される私以外の何物にもなれないが、誰かにとっての「鳥」にはなれる。それが腑に落ちた時、私は「鳥」としても祝福されよう。それが「巣立ち」の時なのだろう。そのとき私は<父>に「あなたの言うことなんて関係ない!」と言いながら、<父>から離れられるのだ。席を譲ったのは”私”が譲りたかったから譲ったのだと。
愛されることには失敗したけど、愛することなら、うまくゆくかも知れない。そう、きっと素晴らしい泡になれるでしょう
話師 「鳥の骸を見た時、お前は恐れを感じたか?」
ラッカ「いいえ」
話師 「ならばその骸はお前が知るべきことを知った証。
使命を果たしたことを誇りに思って、お前に骸を見せたのだ。
悲しむことはない」
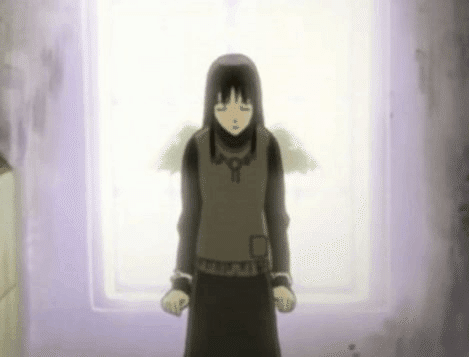
・蛇足1
題名について。原作は『オールドホームの灰羽達』であったが、アニメでは『灰羽連盟』に変わっている。印象の残りやすさというビジネス的な視点もあるだろうが、『灰羽連盟』という言葉が印象的に使われた場面があり、そのあたりが意図ではないかと思えた。
その場面とは、レキが「巣立て」ないかもしれないという話をしている際、話師が「私が……いや『灰羽連盟』は灰羽たちが無事に「巣立つ」ことを願う」と言い直した場面だ。この台詞の際、描写・演出からも話師が「巣立て」なかった=「壁」を越えられなかった灰羽だということが仄めかされていた。
『灰羽連盟』という題名の選択は、この『灰羽連盟』という作品自体が、あなたに直接寄り添ってあげる「鳥」にはなれず、言葉を通じて物語として語りかけるしかない憐れな話師=ワシ(=私)の願いであるということ、なのかもしれない。
・蛇足2
別の作品であるが、レキとは対照的に、最後まで自分を変えれなかった人物として『刀語』のとがめを思い出す。
咎め……なんと因果な名なのだろうか。
※1
『灰羽連盟』の設定としては、灰羽たちには前世があるのだろう。が、メタ的には灰羽とは実質的に人に言及した存在だろう。私たち人間は前世を持たないが原光景は持つ。『灰羽連盟』は原光景を一種の前世として捉えて表現したのだろう。それを持った瞬間、私は言葉の上で、それ以前の私を想像/創造できるようになるのだから(象徴界への参入)。例えば、仮にレキの「繭の夢」が前世ではなく、本当に頭の中で組み立てただけの原光景だったとしても、投身に至る以前のレキはどうだったかと想像ができるようになるように。

