
【U149 第2話】感想:個性の称揚の前に
アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』第二話の感想です。
またアニメ『THE IDOLM@STER』第二話にも言及しています。
画像は同アニメの画像になり、それぞれ下記になります。
・『U149』:「©Bandai Namco Entertainment Inc. / PROJECT U149」
・『THE IDOLM@STER』:「©BNEI/PROJECT iM@S」
アイドルマスターは本数はそこまで多くはないが、シリーズとして長年アニメ化され続けてきた。基本的に作品ごとに描かれるアイドルたちが異なっているが、作品ごとにテーマも異なっている。
『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』(以下『U149』)でも、ただ地続きにアイドルを紹介していくのではなく、作品単位で以前のアニメと差別化している。内容自体は過去のアニメを視聴していなくとも、『U149』単品で見れる話の作りになっているが、過去の作品を知っていた方がより深みが感じられる作りになっているように思う。個人的に、第三話まで見た時点で唸ってしまった。
ここでは『U149』第二話について、初代のアニメ『THE IDOLM@STER』(以下『795AS』)の第二話と比較する。この2つを比較するのは、第二話は「宣材写真」が題材になるという、ある種のお決まりがあって、その同じ題材の上で、『U149』では『795AS』の結論が拒絶されているように見えるところから話が始まるからだ。この差異が発生するのは、一般的な結論ありきの話にせず、『795AS』では水瀬伊織、『U149』では市原仁奈という、それぞれの個の状態に向き合っているからこそであり、同じ題材なのに結論が変わるという面白さがある。
『U149』
まず『U149』の特色の話から。
『U149』はシンデレラガールズのうち身長149cm以下の小学生アイドルを主役とした作品となる。今までの作品との差別化としては、身長や年齢の違いというよりも、ある心理的な差異を主題にしているように見える。その差異とは、彼女たちはまだ親との心理的な結びつきがとても強いということであり、『U149』ではその微妙な機微が扱われている。

「前にも言ったけど、勉強の邪魔にならない程度ならありすの好きにしていいからね」
1話での、特徴的なすれ違いの場面
アリスは親からアイドル活動は趣味程度だと見られてしまっている
自身の気持ちと親の受け止め方の乖離に対して、しかし、何も言い出せない
1話は親ではなく(大人になり切れない)Pがアリスの背中を代わりに押す話だった
『U149』は「子ども」を扱った作品であると言えるだろう。それは「大人=分別のある存在」との対比としての「子ども」であり、また「親」の下(もと)にいる「子ども」である。この「子ども」がどういう立ち位置なのか、またどのように「子ども」から変わっていくのか。そして最終的には「大人」と「子ども」が溶け合うように垣根が消えていく様を『U149』は作品全体を介して丁寧に描いている。
第二話は仁奈の回であるが、上述したように同時にアイマスシリーズのお約束で宣材写真撮影の話になっている。宣材写真撮影という同一の主題を扱うことで、この「子ども」を対象にしたときの、微妙な差異を鋭く捉えることに成功している。
『THE IDOLM@STER』第二話
まず『765PRO ALLSTARS』の宣材写真回で、伊織の話。
宣材写真を撮るにあたって、あずさの、グラマーな体形や上品で落ち着いた女性の雰囲気が感じられる装いに対して、伊織は自身の貧相なスタイルや幼さが垣間見えてしまう――「シャルル」というぬいぐるみを抱えている――自身の装いにコンプレックスを感じてしまう。そこで、没個性にならず、目立つことも踏まえて、伊織たちは(世間から評価されるであろう)グラマーな、大人の女性のように着飾ろうとしてしまう。

この話を覚えていたのは”これ”が印象に残っていたからでもある
しかし、他のメンバーの撮影を観察することを通じて、それぞれのメンバーが持つ素のままの美しさを感じ、伊織自身もまた(仲間内から見て)伊織らしい、飾らない姿で撮影に挑むことにする。

「シャルル」とともに
伊織が持つぬいぐるみ「シャルル」は、当初彼女が見せようとした大人らしさとは正反対の幼い印象を与えるものだ。だが、とても伊織らしい、伊織の人となりが垣間見える装いなんだ(この”らしさ”は後で詳細に述べる)。
世間から見られる私を意識したとき、私は着飾ってしまう。でも、一番美しいのは、実は、私らしく、一番似合っている装いである。『795AS』の第二話は、そう述べているような話だった。
『U149』第二話

着ぐるみはPへ
一方で『U149』。仁奈ちゃんと言えば――視聴者から見れば――着ぐるみを被っている姿が可愛らしく、また仁奈ちゃんらしくて、ある意味彼女のトレードマークと言って差し支えないと思えるだろう。しかし、着ぐるみを着て宣材写真を撮るということを『U149』ではしない。話の途中だけという話でもなく、結論としても着ぐるみなしに宣材写真を撮る形で話を終える。
この違いは、監督の主義主張の違い……というわけではなく、伊織と「シャルル」の関係と、仁奈と着ぐるみの関係の違いを的確に捉えた上での結論だろう。
水瀬伊織と「シャルル」
まず伊織と「シャルル」の関係から見て行こう。この関係は本編で直接語られることはないが、EDのイラストや伊織のアイドル志望動機(「お父様を見返してやる」)や彼女の性格から示唆されている。
まず伊織と仁奈の共通点として挙げられるのは、幼いころ、あまり親の愛情を授かることができなかったであろう家庭環境である。(また仁奈の回で重要な役割を果たす志希も「父親が海外にいる」という点で似通っている)

挿絵から、この年齢の時期から伊織は「シャルル」の手を引いていたことが示されている。このように幼子が特別な愛情を寄せる、毛布やタイル、ぬいぐるみなどは「移行対象」と呼ばれ、「シャルル」は親から引き離されている状態に耐えるための、母親の象徴的な代理であると言われている。
またもう1つ特徴的なイラストがある。「ままごと」遊びである。

ままごと
伊織は母役=面倒を見る側をしている
この遊びの中で「シャルル」は面倒を見られる側=本来あるべき、愛されるべき伊織の位置にある
子どもの遊びについて、有名な報告としてフロイトが報告した『フォルト・ダー(fort da)』と呼ばれる遊びがある。それは、子どもが糸巻きをベットの下に放り投げて見えないようにし、また糸を手繰り寄せて見えるようにして喜ぶという遊びであった。この遊びは(解釈として)母親との別離と再開を再現していると言われている。つまり、子どもが親の位置に立ち、糸巻きを子ども自身に見立て、消しては現わせ、喜ぶ。あたかも母が私を求める空想という遊びの中で「母は私を見つけて喜ぶ」というもう一つの現実(Reality)を――私が愛されていない現実(Reality)の上に――作り出し、覆い隠す。
伊織の「ままごと」も同じ構図だろう。伊織が「シャルル」の面倒を見る。つまり、愛されなかった私が、私の代わりの私と見立てた「シャルル」を愛するのだ。そうすることで(遊びの中で)、私が愛されているという、もう1つの現実(Reality)を作り出す。「私が愛されたい」という思いが「母親は私を愛する(べきだ)」というもう1つの現実(Reality)を遊びの中で作り上げる。そうやって愛されていない現実(Reality)から耐えるのだ。

伊織にとって「シャルル」は他者の代わりであり、また同時に本来あるべき、愛される私という鏡像でもある。宣材写真の溌溂とした笑顔の横に「シャルル」は添えられる。「シャルル」は伊織にとって、とても大事な鏡像であるが、同時に彼女の悲しみも映し出している。なぜなら本当に私が愛されいれば、その鏡像は必要なかったのだろうから。
この宣材写真が伊織らしくて良いのは「シャルル」と共にあることによって――EDのイラストさえ見ていれば、になるが――伊織の心の根にある悲しみとそれに耐えている強さも垣間見れる写真だから。悲しみを抱えながらも、それを前面に出さず――被害者面しすぎて周りを辟易させることなく――自分の内側で耐える強さには、独特の魅力的な香りがするものだ。このみさん(ミリオン)然り、チョコ先輩(シャニマス)然り、みりあちゃん然り……。
伊織はもはや他者(世界)は私を愛していないんだ、という確信を半ば得てしまった状態で、そして、その現実(Reality)を覆い隠す鏡像を作り上げ、「シャルル」はもう伊織にとって交換不可能な鏡像になっている。「シャルル」は伊織にとっては紛れもなく”私”の一部だろう。
一方で、仁奈の、伊織との違いは、仁奈はまだ「他者(世界)は私を愛していない」という確信の一線は越えていない、という点にあるように見える。
市原仁奈と着ぐるみ
『U149』では、仁奈にとって着ぐるみが、伊織にとっての「シャルル」と同じような物ではないかと思っていると、違和感がある台詞が飛んでくる。

(宣材写真撮影で)
着ぐるみ脱いだら、プロデューサー、一緒に写真写ってくれるですか?
伊織にとっては「シャルル」はもはや交換不可能な対象であり、Pが「シャルル」の代わりに撮影に入ればOKとはならないだろう。だから、この提案はあり得ない。この違和感を見逃してはいけない。
仁奈にとって着ぐるみとはどういうものなのだろうか。物語は仁奈から着ぐるみを奪い取り、その答えに迫る。また同時に着ぐるみを介さない世界と仁奈の関係に気づいてもらうために、着ぐるみを着ずに仁奈に世界を歩かせる。終盤、志希が「着ぐるみはなくしたのではなく、明確に奪われた」という状況を作り出すことで、仁奈の、返してほしいという気持ちに沿った激情を引き出す。

仁奈の着ぐるみはすげぇんです! 魔法ですげぇ着ぐるみなんです!
仁奈のパパ、海外にいるですよ。ママもお仕事忙しくて…
だけど、着ぐるみ着てたら、いろんな人が仁奈と遊んでくれるです
ありすちゃんたちもプロデューサーもみんな! 仁奈のこと見てくれるです
着ぐるみがあれば仁奈、一人じゃないから
着ぐるみなしの仁奈なんておもしろくねえですよ
つまり、仁奈にとって着ぐるみとは、他者を惹きつけるための手段であり、「世界の関心を惹きつけ、引き留める力」が宿った魔法の道具なのだ。仁奈の目から見て、着ぐるみには他者から愛されるための力が宿っており、着ていれば他者が私の前に来てくれる。と同時に、仁奈自身には――着ぐるみを着てない仁奈――には何もそのような力はないと感じている。
似たような状態として挙げられるのは、例えば、勉強や楽器が上手い子の話で、彼/彼女を勉強や楽器ができることだけを褒めてしまっていれば、聡い子ならば「勉強や楽器が出来れば私じゃなくてもいいんじゃないか」と感づいてしまう。そう感じた時、そこに残るのは勉強や楽器ができなれば何も価値がない”私”である。仁奈に対して、着ぐるみを彼女らしいと誉めたてる行為は――仁奈の方ではなく着ぐるみの方に着目するような行為は――同じような自己疎外を引き起こしてしまうのが目に見える。それは避けなければいけない。”私らしさ”というどこか相対的な評価の前に、”私”で良いんだと。
半ば志希に誘導された形になるが、上の仁奈の台詞に対してPは被せる。

「そんなことない!」
「今日…今日だってどこに行ってもみんな笑顔だっただろ?」
「市原さん。着ぐるみがすごいんじゃない。市原さんがすごいんだよ」
「市原さんが元気だからみんなも元気になれるんじゃないか。市原さんは市原さんのままで魅力的なんだよ」
仁奈「仁奈が?」
ありす「今日事務所を出てからずっと着ぐるみ着ていませんでしたよ」
仁奈「あっ…。そっか。仁奈がもっともっと元気だったらパパも喜んでくれるかな?」
P「もちろん!お父さんが世界のどこにいたって市原さんの元気が伝わるようなすっごいアイドルになろう。俺が全力でサポートするからさ!」
仁奈「すげぇアイドル…」
仁奈「あっアイドルになったら、着ぐるみなくてもパパもみんな仁奈のことを見てくれるですか?」
P「ああ!」

私は世界に愛されているか、いないか。その判定は他者(世界)の視線という回答がなくては出せない。またその答えを与えられるのは彼/彼女の周りの人々である。自尊心――世界から私は愛されているんだという感覚――は一人の心の中だけで生まれるのではなく、周りに与えられて育まれるものだ。
Pや第三芸能課のメンバー、仁奈と交流した外の人たち。彼らを介して、仁奈の心の中に一つの動きがあった。それは着ぐるみの内にあると思っていた「世界の関心を惹きつけ、引き留める力」が、着ぐるみから仁奈自身と「アイドル」という言葉の上へ移ったことだ。他の人に声をかけられ体験して、それは私の中に宿る。私自身にその力があると確信できる。それは伊織(やいくつかの他のアイマスのアイドル達)が獲得できなかったことが示される、この世界と私の関係においての、ベースとしての自尊心の感覚。彼女らに与えようにも「今更」になりがちなもの。
おでかけなのにただいまをするもの、なに?
第二話題名のなぞなぞの答えは「里帰り」だろう。私たちは生まれた頃、ただ泣きわめくだけで母を惹きつける力を持っていた。この話において、帰ってきたのは「世界の関心を惹きつけ、引き留める力」であり、それが(仁奈の心の中で)着ぐるみから仁奈自身へと帰った、ということだろう。

へちまの花

誰とも分け隔てなく明るく接する仁奈。仁奈が外の人たちと交流を深めるとき、黄色いへちまの花が咲く描写が挟まれる。フレデリカは「この黄金の花はまさしくはるか彼方に忘れ去られた人類の宝!」と(裏で)叫ぶ。それは仁奈が貰ったものなのか、それとも与えたものなのだろうか。きっと仁奈が貰ったものであると同時に与えたものでもあるように思う。仁奈と他者との関わり合いについて、愛されているという感覚はきっとお互いに感じるものだろうから。
うちの死んだばあちゃんが言ってた「無償の愛を与えてるのは子供の方」っていう言葉がずっと好き。深い。
— トリッキー母ちゃんレ (@ganbaruman6180) July 28, 2023
最後に。にしても志希が鋭すぎる。彼女自身が父親が海外にいるという経験を経てきた存在であることと、仁奈の心の根はトレーナーに事情を聞いて把握したのだろうけど、比較的損な役を買って出てまでして、ちゃんと答えまで導いている。その上、自分で答えを言ってしまうのではなく、今後の仁奈とPの関係構築をも加味してPに花を持たせているのは出来すぎに思えるほど。他の回でも登場したけど、志希はほぼ唯一の、『U149』で言及される「大人」らしくない大人なんですよね。
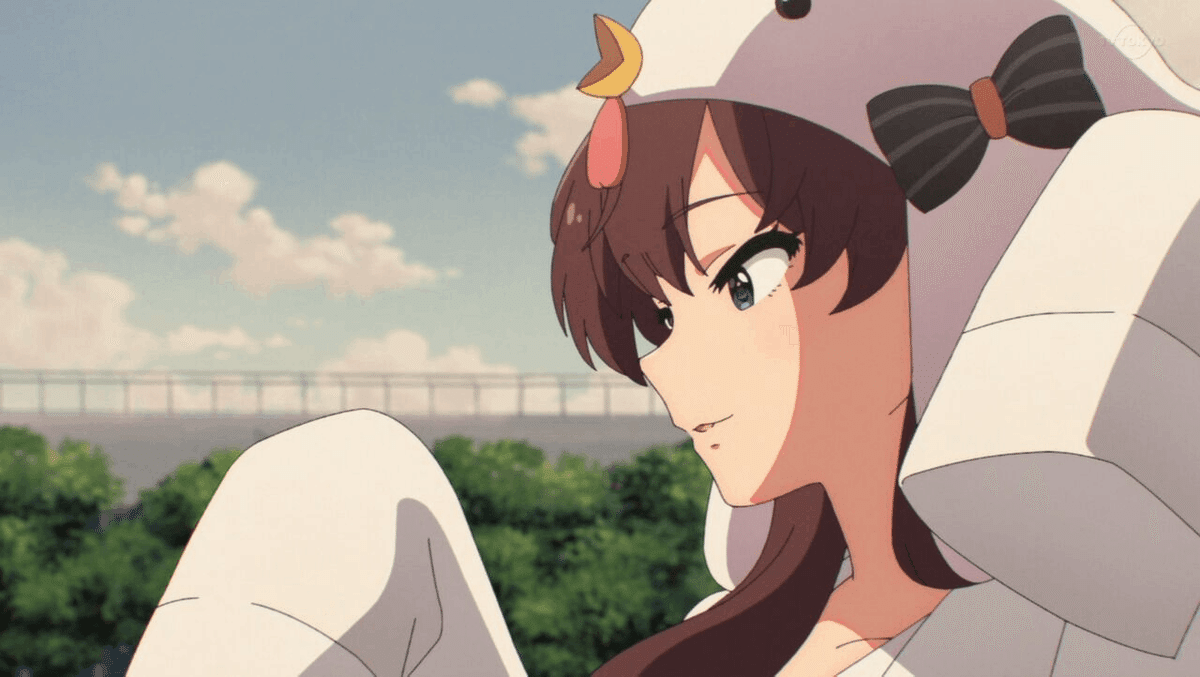
こういう答えを与えられるのは周りなのだけど、日本は諸外国と比べると明らかにかなり低い。ここは周りの責任で、志希のようにならないといけませんね。


