
私が学び続ける意味とは!
1. はじめに🤓
私が勉強をするのが好きな理由。
それは、常に新しい自分を更新してくれるから。新しい視点や事実を知るたびに、それを身につける前の自分とは違う、一歩成長した新たな自分が生まれると感じる。このように感じるようになったきっかけには、高校生の頃に受けた世界史の授業が深く影響をしている。その授業は、私にただ知識を与えるだけでなく、物事のつながりや背景を深く知ることの面白さを教えてくれた。さらに、世界史を学ぶことに使命感さえ覚えたのを今でもはっきりと覚えている。
2. 世界史との出会い
高校生の時に、世界史選択をした時から私の人生観は大きく、広く変わった。
その時はまだコロナ真っ只中で、生徒は原則マスク着用、先生は透明のフェイスシールド、もしくはアクリル板を利用しながら授業を進行させなければならなかった。熱心さ、ひたむきさが誰よりも印象の強かった丸眼鏡をかけたT先生。元考古学専攻で少しマニアックな知識をもっていたからか、彼の教え方には、ミステリアスな謎解きをしていくかのような楽しさと、ワクワクさが秘められていた。一方で、中年くらいのお年頃ということもあってか、彼の話すトーンはいつも眠たくなるのが特徴的だったので、クラスを見渡せば、いつのまにか “机”との距離間がだんだん近くなっていく生徒でいっぱいだった。わたしも時にはその1人であったが、そういった場合にはとてもひどく後悔をしたのを覚えている。
3. 世界史を通じて気づいたこと
さては本題に戻って、彼の授業が私にもたらしたもの、それはなにか。
それは一言では言い表せない。
言い切れないほどの無数で多様な “情報”と “事実とされてる出来事の繋がり” を教えてくれた。何千世紀も前である “古代”から遡って世界のいろんな国々の起源や、中世から現代へと至るまでの物事の変化の仕様を、段階ごとに、実際に起きた年月と人物の功績を辿りながら世界史を学んだ。人類によるこれまでの文明発展が時代区分で分けられ、世界各地で起こった交わりと合体が様々な “章”で分別されたノンフィクションストーリー。

T先生は、立てかけられたアクリル板が熱気で曇るほどに、熱心にそれらのストーリーを語った。どんな時も真剣な眼差しと穏やかな表情を変えずに。
けれども私の頭のどこかでは、常に疑問の声が上がっていた。歴史が全て事実かなんてわからない。何世紀も前の出来事なんて本当にあったかどうかなんて知るはずがない。その証拠として、大切に政府や学校機関によって保管された一次資料が頼るべくデータとして残っているかも知れないが、それは一方で宇宙人を信じるか否かと同レベルだと言ってもといいほどの、私にとっては信憑性に欠けたものであった。

しかし大事なのは、最終的にそれらが事実かどうかではなかった。そのストーリーたちがどう、今を生きる私たちの生活、いま常識とされているものごとを反映しているのか、反映しつづけてきたのか、あるいは反映し続けるのか、ということであった。その線のつながりを理解し、そのコネクトを世界史は説明してくれているということ。
4. 現代社会との関連
度々目にする、セレブたちのゴシップ以外の報道は、 “政治・宗教・国籍・人種・性別” などの要素が原因となり社会問題が起こっている実態を映し出している。国レベルのものもあれば、世界レベルのものもあり、グルーバル化が進む今では、海外の商品はもちろん、 “情報”が簡単に入手しやすい世の中となってしまった分、後者の報道は増えていくばかりである。
そんな世の中に身を置く私たち。特に、この変動が大きく起こっている時代を代表するのが21世紀。テクノロジーによる発展がベースに敷かれ、グローバル化の進んだ多様性の中でどう多様な物事に対応していくかが問われる時代である。この先の日本も、教室には半分の生徒は多国籍ルーツを持つ子供たちで埋まり、エコと技術発展に優先を置いた政策で、紙とペン、教科書すらない教室やオフィスが “普通” になるまでの過程を歩み始めていくであろう。

その過程で発生する課題、人と人の間で起こる価値観の違いから生まれる対立、国と国の間で起こる利益紛争、世界が直面していくであろうサステイナビリティへの共通課題。私たちがその壁に突入する前に、認識しておかなければならない現実が “Social Issues”として可視化されてきている。

そのSolutionsともなるべくカギが世界史にはある。私たちが生きている世界線のバックグラウンドを知らずして、この世の中で生き抜いていくことはできない。
5. 学びの意義
世界史は人と人のつながりを勉強しているかのようだと思ったこともある。家族ごとのコミュニティがあり、その中で人類が発展をし、成長を遂げていく。しかし時には、考えの違いのズレで衝突してしまったり、最悪な場合、極論的に正反対の考えを持つ相互理解不能な人たち同士の間でぶつかることもあるだろう。或いは時に、個人の利益を追求したいがために、相手を騙すことも手段としてあるだろう。そういった場合に喧嘩が勃発し、親交の深さが決まり、関係性が築き上げられていく。

国家レベルの外交でも同じことが言えよう。
戦争や紛争が起きてしまうのは、利益追求の先でどちらかが相手国を裏切ったり、もしくは宗教的概念の違いや文化的価値観の違いによって対立構造が出来上がってしまうからだ。相手のことを知れば知るほど、共感部分が増したり、考えに納得する要素が増す場合もあれば、根本的に意見が合わず相互理解にすら及ばず対立してしまう場合もある。人レベルで考えるのと同様、世界史で目にする国家間の対立の多くは、この上文で描写されているような、外交の結果や国家のとった行動が語り継がれてきているのだ。
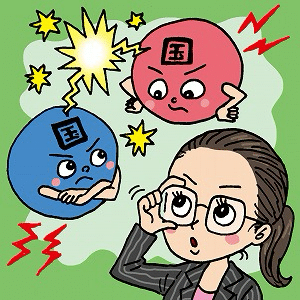
”政治・宗教・国籍・人種・性別”というこれらの要素は、私たち人間自身、個人個人の特異性を特徴づけるものであり、 “個性” につながる重要なマテリアルである。そのマテリアルが背景となって、それぞれ個々が異なる視点と言語や、人生の価値観を形成していく。それが最終的に、ユニークな個性となって、その人ならではのアイデンティティとして輝くのだ。

しかし、悲しいことに、その多様なる価値観はみんながみんな容易に理解のし合える、素敵〜とされるものではないのだ。人、世の中はそんなに甘い社会で出来上がってはいない。 “平和的ではない” のが事実である。しかし平和にすることは可能であると信じたい。

ホッブズが提唱したリヴァイアサンがあるのよね🤔
戦争や貧困が解決の難しいテーマであっても、解決できる道探しは無駄なことではないはず。
世界史がそう私に教えてくれた。諦めないで国のために、コミュニティのために、そして自分のために、世界平和・愛を願って行動を起こして、狭き固定概念と常識を変えようと改革を起こした人たちのおかげで、今の私たちが生きる世の中がある。あるいは、まだ変化途中であるプロセスの中に私たちは存在している。
それを忘れてはならない。

そう、私が学び続けたい理由は、まだ知らない世界線が過去にも未来にも無数に広がっており、そこには今を生きるための “ゴール”と “意義”を探し続ける希望が満ち溢れていると感じる原動力があるから。過去からは、出来事の “良し悪し”の両側面を結果から学ぶことができる。それは無限に広がる世界線から、多数に広がる国と長い年月と時代の中で生きた人類史から学びとれることを世界史は示してくれたのだ。そして未来は、私たちが理想とする平和な世の中のために構築すべく、 “努力” が私たちには委ねられている。
どう努力をしていくのか。
そこが私たちの課題である。
少なくとも私はこれまで大学に通うまでに培った知識と見解、学んだことのアウトプットをこのBlogではしていきたい。考えたプロセスと、それに至るまでの私なりの解釈がどう最終的な考えへと形成されたのか。文章という形に残して可視化させる、それを共有し広めることで、他人と一緒に将来への平和構築を目指していきたい。たとえそれが同じ視点からでなくても。

私は世界史で気づくことのできた、現在に至るまでに成されてきた、“人々”や ”国々”の努力を学び取って、現在の課題解決が求められる問題へのアプローチを、未来の平和構築のために探究し続けていきたい。それが、私の学ぶ意義であり、このBlogを活用させていく意味である。
明日からはもっと詳しい、私の “この頃の学び”、 “現在の留学生活”にフォーカスした実情なり!を届けていこうかな〜!!!
私一個人のあつ〜い思いでしたっ以上!読んでくれてありがとうございました🤍🫷🏻bye:)
