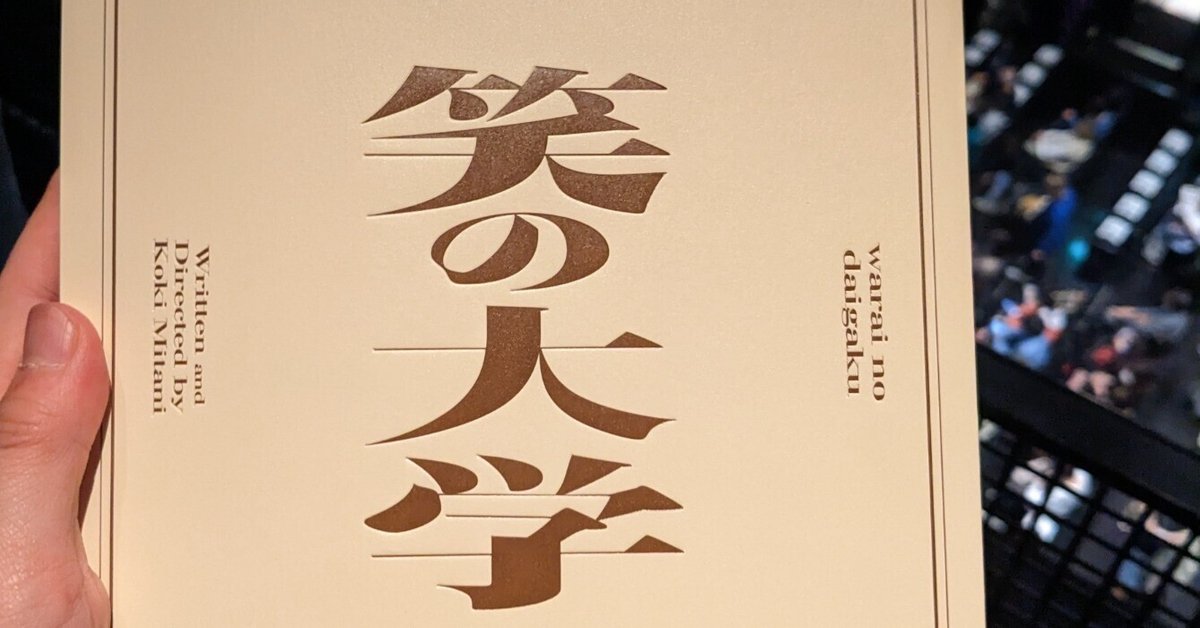
『笑の大学』感想など
核心に触れるようなネタバレにはなるたけ配慮したのですが、割としっかり話の内容について語ってますのでその辺りはご容赦ください。多分また加筆修正誤字訂正等行います。
『笑の大学』大阪公演を観に行った。元々三谷幸喜脚本のドラマや映画は好きだったし、2007年に上演された本作の英語版『The Last Laugh』に推し俳優マーティン・フリーマンが出演していたと聞いていたから、今回の再上演は興味があった。とはいえ突発的に思い立ってチケットを取ったので二階バルコニー席というものすごく遠い位置からの観劇。手摺から半ば乗り出すようにして観ていた。
舞台は取調室で向かい合う作家と検閲官から始まる。腹の探り合いのようなふたりの会話は次第にテンポを上げていき、かなり早い段階からささやかな笑いを誘う。この作家が気難しい検閲官をどうやって『その気』にさせていくのだろうか。そう思った瞬間、検閲官が真面目くさった表情で飼い始めたカラスについて話し出した。カラス? なんでまた。ささやかだった笑いは一瞬で大爆笑に変わった。思いがけず最初から全力で笑ってしまった。同時に駄目だ、と悟った。
駄目だ。笑うことから逃れられない。
Story
時は戦時色濃厚な昭和15年。
登場人物は、警視庁検閲係・向坂睦男と
劇団「笑の大学」座付作家・椿一。
非常時に喜劇など断じて許さないとする向坂は、
上演中止に追い込もうと執拗なまでの注文を繰り返す。
しかしなんとか上演許可をもらいたい椿は、
向坂が要求する無理難題を逆手に取りながら、
あくまで真正面からの書き直しに挑戦する。
警視庁の取調室を舞台に、
相対する男二人のドラマが始まる。
不謹慎だ、削除しろ、ここは書き直せ、ああでもこういう台詞は入れてくれ。劇作家、椿一(演・瀬戸康史)は検閲官の理不尽な注文に真っ向から向き合い、何度も何度も喜劇の脚本を書き直す。いつも最敬礼の角度で頭を下げ、感情が昂ると声がひっくり返る、やることなすこと少々オーバーな椿だが、自分の作品を諦めない姿はつい応援したくなる。と思っていたのだが、かなり早い段階で、「あ、こいつ何と言われようと絶対にこの脚本で行く気だな」と安心したので応援するのは止めた。要するにものすごく打たれ強い。面白いネタを思いついたのに、それのどういう点が面白いのか説明を求められた時の恥ずかしがりようが良かった。自分のネタの解説はさすがにきつい。
一方で笑ったことも笑わせたこともなく、笑いというものがわからない検閲官、向坂睦男(演・内野聖陽)だが、話が進むにつれ、椿の笑わせずにはいられない性分に次第に影響されていく。表面上は高圧的に接しているつもりでも、やはりどこか椿のことを気にかけずにいられないから、回りくどいやり方で思いやったり、一人になったところで却下したはずの脚本を読んだりするのだ。しかも椿の察しが良すぎてそれがすべて裏目に出てしまう。この属性の名前を私は知っている。と思っていたら、パンフレットに載っているインタビューで内野がまったく同じことを言っていた。「向坂はいわばツンデレの極致のような男」。笑いから遠い場所で生きてきたつもりなのに、とにかく面白い人間だ。冒頭のカラスを飼う話もそう。彼はつまりそれ、真面目に言ってるんだよな? だとしたらものすごくポテンシャルが高いぞ。
あらすじの通り、劇作家とその脚本が登場するというある意味入れ子構造の話なので、観ていると観客としての自分はどの次元にいるんだ……?と不思議な気分になった。『椿の書いた脚本』という『劇中劇』の中に、さらに『劇中劇』が入っていたり、椿が向坂に解説した笑いの取り方を向坂が体現していたり。この設定、このストーリー展開を生身の人間の演技によって表現するからこそ成しえるメタな笑いがクセになる。
何だか真面目に考察している風に書いてみたが、実際はそこまで深く考えることなく、純粋に笑って楽しめる作品だったと思う。喜劇について真剣に考える男たちの喜劇。真剣だからこそにじみ出るおかしさが笑いを誘い、苦悩する姿が共感を呼び、怒りあるいは悲しみから来る叫びに空気が引き締まる。何より台詞ひとつ取っても、小道具や衣装、光の使い方を見ても、とにかくセンス抜群だから、椿と向坂、そして瀬戸と内野のもつかっこよさが存分に引き出されるようになっている。椅子に座り足を組んだ時、茶や煙草を口にする時など『様になっている』瞬間が何度もあり、笑いながらも度々はっとさせられた。
それでもラストは一気に現実に引き戻されたような気分になった。ふたりが次第に互いを理解していき、戦友にも似た関係を作っていく取調室の外でも当然時間は動き、人々は生きている。ゆえに本当の「理解者」「戦友」にはなれないやるせなさ、寂しさ、切なさが皺寄せとなったような、そんな終わり方だと感じた。それでもきっとあれはやるせないだけではないのだろう――これが見たかった、この瞬間のために今までの流れがあったのだと思わずにはいられないほどに完璧なシーンを以ってこの喜劇は幕を閉じる。
作業BGM
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

