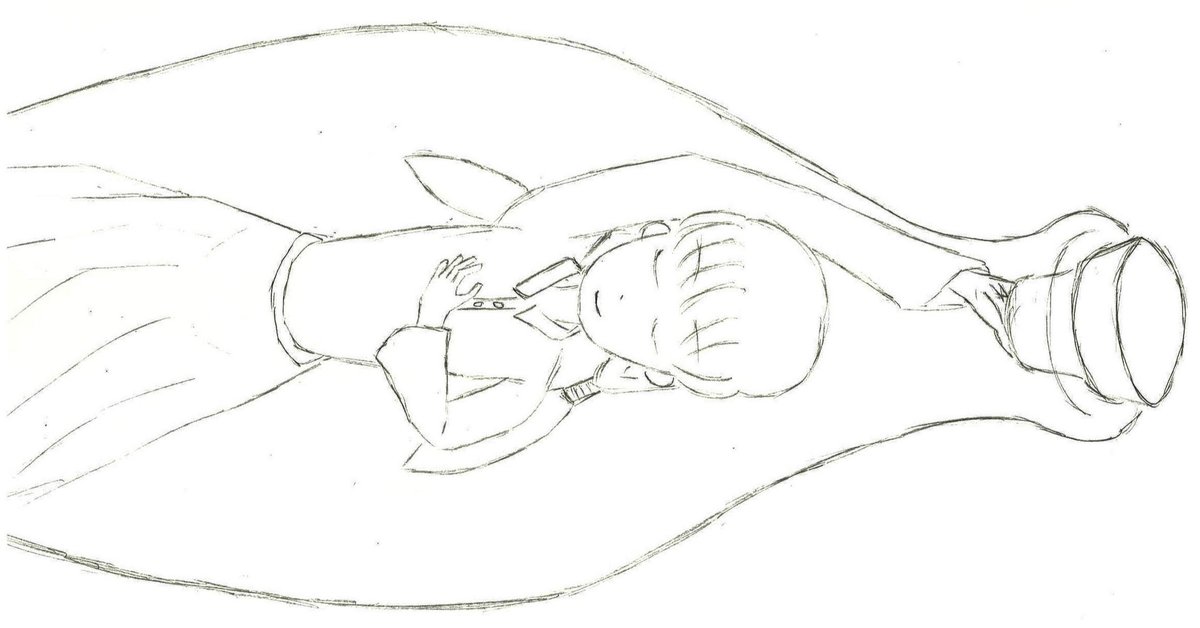
ボクと魔王とボトルメール
部屋に入り、戸を閉め切ると、部屋に普段とは違った香りがする。独特な匂い、私の知らない匂い。お母様の介助を断って一人で階段を上がり、そのせいで切れた息を整えるべく深呼吸をする。鼻腔に、肺に、青が満ちていくような気がする。本の中でしか見たことのない美しい湖上の村、リシェロが瞼の裏に浮かぶ気がした。
点滴でいくらか和らいだものの、身体はまだ思うように動かない。それでもベッドに戻る前に、机の上の瓶を手に取った。私が閉めた時よりも強く閉められた蓋、それに少し苦戦しながらやっとの思いで開くと、その時の反動で中の水がちゃぷんと音をたてた。
透き通った水が、窓から射す光できらきらと輝く。水面の揺れに合わせてふわりと舞う白い砂は宝石のようだ。それが見渡す限りに広がっているだなんて、本やおじい様の話で聞く以上に素晴らしい景色なんだろうな。
それにしても、と瓶を抱きしめる。ここに詰まっている湖は、私が世界と繋がった証拠だ。いつもこの小さな部屋に一人だった。窓一枚隔てた向こうから聞こえる村の子供たちの楽しそうな声、そこへ行くことさえ、この病のせいでままならない。
そんな私を気遣って、おじい様は色々なお話しを聞かせてくださった。お母様は年甲斐もないなんて言うけれど、経験豊富と自称するだけあって、そのお話はとても面白かった。白砂の湖、そこに浮かぶ村、渦巻きのような岬、機械仕掛けの町、トンネルの先の雪原。私が本の中でしか繋がれないような広い世界に、おじい様は繋がっていたんだ。
ある日、家族がみんな留守にしていた時のこと。その日は私の調子が比較的良い日で、リビングに水を飲みに降りていた。ちょうど最後の段を降りたところで、誰かが玄関の戸を叩いた。普段は寝室で寝ているので、来客の応対なんてほとんどしたことがなかった。俄かに波立つ胸を押さえながら玄関に向かう。
「おや、あなたがお噂のお孫さんかな。こんにちは。長老はご在宅かな?」
「いいえ、祖父は外出しております」
「それは残念だ。では、この手紙をお渡し願えるかな。それでは」
「お待ちください。どちら様からとお伝えすれば?」
足早に去ろうとしていたタキシードに蝶ネクタイの男に呼び留めると、彼は振り返って手紙の裏を指してニヒルな表情を浮かべる。
「手紙の裏に書いてあるよ。しっかり伝えてくれたまえ」
そう言ってさっさと立ち去ってしまった。戸惑いながら手紙を裏返すと奇妙な文章が二列、不自然な空間を挟んで並んでいる。
すおあんをげいかゃいおあ
そきういあざえくらえきう
意味不明な文字列に困惑していたが、しっかり伝えてくれと頼まれてしまったので、ちゃんと考えなくてはいけない。そう思ってリビングに戻ってにらめっこしていると、ある法則が見えてきた。上の列と下の列の間の空白が五十音順になっているんだ。
「ただいま、どうしたんじゃ。寝てなくて大丈夫かの」
「おじい様、世界暗号協会からお手紙を預かりました」
「な、なんじゃと」
世界暗号協会、その言葉を聞いた途端におじい様は酷く狼狽した。私にはその理由がわからなかった。お母様がいつも愚痴を言っているのを聞いていたけれど、秘密のつもりだったのだろうか。
「しかし、おまえそれが読めたのかい。大したものだ」
「ええ、謎解きみたいで楽しかったわ」
そうか、ちょっと待っていなさい。そう言うとおじい様は自室からまた、違う手紙を持ってきた。
「これはな、暗号と言ってな。この世界暗号協会というものが作っておるのじゃ。ただこれはヒミツ結社じゃ。誰にも言うてはならんぞ」
そう言って神妙な顔を作って見せ、その暗号をこちらへ渡した。
「わしはな、この協会に、その、友人がおっての。おまえが楽しいと言うのなら、また時々持ってきてやろう」
続きは部屋で読みなさい、お母さんに見つかるといけないから。それからというもの、私はおじい様の持ってくる暗号を時々解くようになった。
暗号を解くのは面白かった。病と二人ぼっちの起伏のない寝室での毎日に楽しみが出来たのだ。私は渡される暗号を夢中で解いては、おじい様に次の暗号をせがんだ。夜、苦しくて眠れないとき、紛らすように解いた暗号を置き放していると、次の朝に別の暗号が置かれていることもあった。それを見つけたお母様がおじい様に小言を言って、おじい様はおどけたように肩をすくませながらこちらに目配せをしたりした。
けれど、私は段々ある考えに支配されはじめた。世界暗号協会、おじい様は暗号を通じて世界と繋がっているんだ。よく聞かせてくれる豊富な昔話も暗号を通じて得たものだったのかもしれない。同じように暗号を解いていても、私はどうしてこの部屋から出られないんだろう。そう思ったとき、前のように暗号を楽しめなくなってしまった。
それからの私の体調は思わしくなかった。前よりもずっと、身体は思うように動かなくなくなり、私の気分はどんどん沈んでいった。深夜に目を覚ますと、心配そうなお母様やおじい様がこちらを覗いていることがあった。私は無性に申し訳なくなって、布団を頭までかぶって泣いた。
朝、目が覚めて布団から顔を出す。すると光の射し方がいつもと違う。そちらを見ると、お母様がいつも水を入れて枕元に置いてくれるガラス瓶が窓際にあり、光を反射していた。眩しさに目を細めながらよく見ると、底に小さな物体がある。入っていたのは暗号の書かれたメモだった。まだ少し水が残っているのに気がつかなかったのだろうか。そのせいでメモは滲んで読むことはできなかった。
おじい様ったら、瓶に入れたりして。そう笑った時にふと思い出した。そういえば、ずっと昔におじい様が言っていた。ガラスの瓶に手紙を詰めて、それを川に流す。そうして見知らぬ誰かが拾い、また手紙を流す。そんな迂遠なやり取り、けれども美しい繋がり。
思わず筆をとっていた。私もみんなのように、外の世界と繋がりたい。おじい様のように世界と繋がりたい。私の身体がここから出られなくても、せめて想いだけでも世界と繋がれたら。そうしてお母様に頼み込み、ボトルメールに願いを込めて川へ流した。
おじい様の知り合いがリシェロの側に住んでいて、波打ち際がよく見えるところからボトルメールを見つけては持ってきてくれていたが、帰ってくるのはいつも私が送ったものだった。そんな都合のいい話はない。そうだとしても、私にはこれしかない。戻ってきた瓶から手紙を取り出し、書き直してはまた流すことを繰り返した。
それからしばらくのことだ。目が覚めた私が窓を見ると、二つの瓶が並んでいた。思わず声をあげると、部屋の隅に置いた椅子でうたた寝をしていたお母様が目を覚ました。
「これ、どうしたの?」
「おはよう。具合はどう?」
「大丈夫。それよりこれは?」
「今日は二本あったみたいよ」
食事の準備をすると言ってお母様は降りていく。一つ目の瓶を開ける。そこにあるのは私の字だった。すぐに次の手紙を取り出す。そこにはこう書かれていた。
"あなたにいつも良い風が吹きますように。"
食事を持って戻ってきたお母様に、すぐに返事の手紙を持って行ってもらうようにお願いした。興奮する私をなだめながら食事をするように言い残して、お母様はすぐに川へ行ってくれた。今なら、繋がれるかもしれない。そう思うと嬉しくてたまらなかった。
それから数日後、ボトルメールはまた帰ってきた。私と同じ文章で、けれど違う筆跡で。とうとう、繋がったんだ。どこにも行けないと諦めていた私が、今確かに繋がっているんだ。
私はどうしてもその人に会いたくなった。私が病気なこと、テネルにいること、会いにきてくれたら嬉しいということ。それを書いたものをまた流した。見ず知らずの、こんな私に本当に会いに来てくれるのか。自信はなかったが、期待せずにはいられなかった。ボトルメールなんて回りくどい方法でわざわざ返事をくれた、そんな優しい人に会えたら。その時にはお礼をしなければいけない。体調のいい日を見つけては、来るかもわからないその時を思って帽子を編み続けた。湖の風が、冷たいといけないから。
思い出に耽っていると、戸の向こうからおじい様が現れた。
「最近は、だいぶ元気になってきたの」
「ええ、もう家の中を歩くのには困らないわ」
「その調子なら、そのうち村へも出られるじゃろう」
頷きながら、おじい様は私にメモ用紙を手渡した。おじい様がこうして暗号を渡してくるのも随分久しぶりだ。
うこゆへばろひたきがすかーさ
「おまえがもう少し元気になったら、そこへ行ってみなさい」
おじい様は微笑みながら言った。私にはもう答えが分かってしまった。
「これはおまえのために作った暗号じゃったが、あの少年も、これと同じ暗号を解いておるところじゃ。あの子と同じように、広い世界をたくさん見てきなさい」
私はおじい様をじっと見た。昔からずっと思っていたことがある。それを確かめてみたい気になった。
「ねえ、おじい様。もしかして、昔話も、暗号も、私のためにしてくれてたの?」
「さて、それは、ヒミツ、じゃの」
おじい様は愉快そうに笑いながら部屋を出ていった。
それにしても、あの人が来てくれた時に思わず神様に感謝してしまったけれど、神様ってどんな人なんだろう。ボトルメールが届くなんて滅多にありえないことが、続けざまに起こったのだ。それを叶えてくれた神様は、きっと優しい人に違いない。
窓から差し込む日に向かって静かに指を組む。神様、ありがとう。これからは私の足で、世界と繋がっていきます。どうか、あなたにも良い風が吹きますように。
