寄生生物から脳腸相関を考える
自由意志というものはあるのか。無意識のついて以前書いたところでもご紹介したのが『心を操る寄生生物』です。文字通り、われわれの心を操り、さも自分で決断したかのように思わせているといった、よく考えると非常にショッキングな内容の本です。
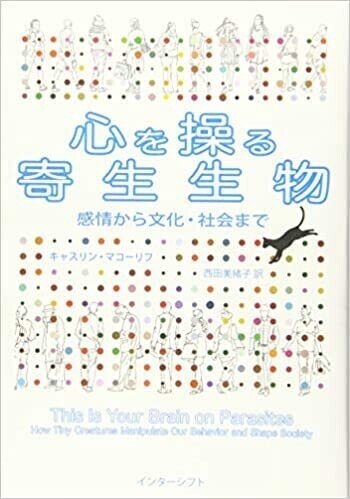
心を操る寄生生物 : 感情から文化・社会まで [単行本]
キャスリン・マコーリフ インターシフト 2017-04-15
コオロギを内部から操り、プールへと飛び込ませる「ハリガネムシ」、感染した人を交通事故に合わせる確率を2.7倍に押し上げる「トキソプラズマ」、人を社交的にさせ感染の機会を増やす「インフルエンザウイルス」、認知症のリスクを増加させる「トキソカラ」・・・いくつもの衝撃的な寄生生物の実態が紹介されています。
そうした内容の一環として、プロバイオティクスについても言及があり、腸内細菌が、腸内環境の変化を通じて、自律神経としての「迷走神経」を介して(求心性に)脳に影響を及ぼすということも詳述されています。プロバイオティクスがアレルギー疾患などさまざまな疾患の治療に有効なことは、目新しいことではないのですが、寄生生物による介入という視点でとらえると何とも不気味にも感じます。また、脳は腸の出先機関として進化した可能性がある、という記載も常識と逆転した視点で、考えさせられます。
とりわけ、ピロリ菌については、胃潰瘍から悪性腫瘍までの予防的な効果を述べつつも、グレリンの調整を介して肥満をも調整しているというのです。つまりピロリ除菌により食べ過ぎにつながるというわけです。逆流性食道炎の増加など、負の側面も伝えられてはいますが、体重増加への関連はかなりショッキングなものなのではないでしょうか。
これらの例を見ても明らかなように、これまでの中枢から末梢という片道的な考えだけではなく、あきらかに末梢から中枢というルートの重要性が示唆されているわけです。
こうした「脳腸相関」の関連から、腹部の打鍼など腹部への治療的介入が、全身に影響することの理論的な基盤とも考えることが出来そうです。
横隔膜や上腹部への徒手的な圧迫などの理論的基盤だけでなく、アルベックスやいくつかのプロバイオティクスの内臓的のみならず精神的作用機序を説明するのに、寄生生物は重要な視点を提供しているように感じました。
