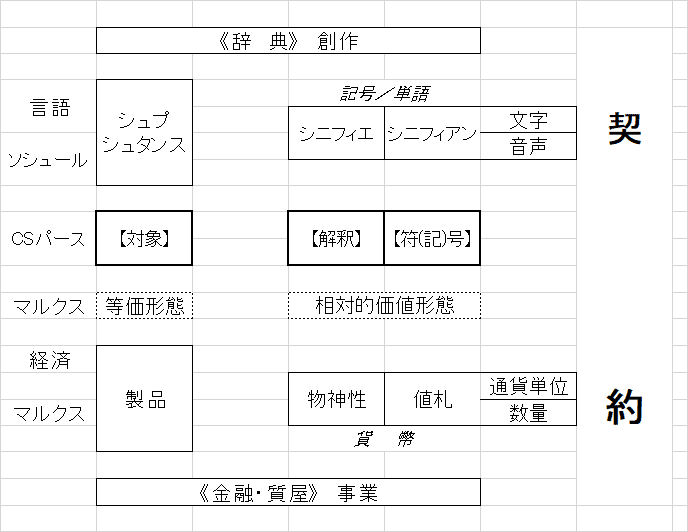前編・「記号/単語と貨幣」の 基礎形態・CS.パース座標
*この論究の全ての根拠はf'ree理い」論から導く。但しここでは、f'ree理論に深くは立ち入る時間はない。詳しくは、その内出されるかもしれないそれについての著作か、youtubeの講義を見て頂きたい。
単語(記号)をそれだけ取り出して、単語(記号)のみで、同様に、貨幣をそれだけ取り出して、貨幣のみで、理解しようとするのは間違っている。だが、事はそう容易くない。人は「図」だけ見て、「地」を見ない。否、あまりにも「図」が眩しくて、「地」が見えないのだ。人は真実が、自然に隠蔽されてしまう生き物なんだ。
経済と言語、貨幣と記号(単語)、事業と創作、この対比関係は、共鳴し、互いが互いの理解を促進させる。
この2つは結び付けて、同じ地平線で理解してもいいと思う。
もちろん、言語領域における、符号・品詞や記号(単語)・語彙らのポジションは理解しにくいが。それはここでは省く。
ところで、貨幣と記号(単語)の類似は、ずっと言及されてきた。
丸山圭三郎
テルケル派
j.j・グー
柄谷行人等、
そこに3つのスケールを入れる・CS.パース座標・ラカン座標・ボードリヤール座標だ。それらに、配置し、鎮め、できうるなら彼らの、一旦の姿だけでも暴こうとする試考である。というところまでは、緒論を通して、暗示してきた。
さて、基礎編、貨幣と単語の基礎形態についてだ。
「マクロ的な手続き」と「マイクロ的な手続き」、この2つで彼らの正座を仕留める。もしくは、蠢いて、手からするりと抜ける、貨幣と単語を、鎮座させる。
第一に、マクロで網を放つなら、貨幣も単語も、
経済学的事業の一形態である「●金融業(契約業)」と、言語学的創作活動の一形態である「●辞書」の一部である。つまり、双方の契約、これから、【A】は【1】にします、みんな同意してね、ということで、同意という行為を担保として、すなわちそういう契約という大きな公的な約束のもと、設計されたものの世界の一部。
具体的に説き起こせば、
【A】は、事物であり、シュプスタンスであり、
【1】は、言語論的にはシーニュ/記号であり、
辞書の一部として言うなら、
記号というより、単語が精確な云いである。
そして、経済学的には、貨幣である。
こういえば、イメージできるだろうか。
契約というマクロ界における、左にたいする右である。
現実には、貨幣しか、単語しか見えないが、一セットの対偶としての左辺もしくは右辺であることを、忘れてはいけない。
更にここで、その事物と単語(記号)・貨幣の関係をマルクス解釈に従えば、
事物 ⇒ 等価形態
貨幣やら単語/記号 ⇒ 相対的価値形態
である。柄谷行人は、隠喩としての建築・「形式化の諸問題」で
シニフィエ ⇒ 相対的価値形態
シニフィアン ⇒ 等価形態
と言っているが、その双つを貼り付けたシーニュ・記号、単語が、
相対的価値形態である。
第二に、マイクロで銛を打つなら、
実物と対置される一方である、単語(記号)、貨幣は2つに分割される。
有名な二分法である、ソシュール的分割。
つまり、「意味されるもの」と「意味するもの」。でもここでも僕は一言、口を挟みたい。
「意味するもの」は、記号・単語が相応しく、
「意味させるもの」が、シニフィアン、
「意味されるもの」が、シニフィエ。
一方、貨幣はどうか? マルクスはどうか?
マルクスはそこまでは、輪郭を描いていない。否言及はしているが、それぞれが離れ離れである。なので、僕がそれを強引に結びつける。
「値札」と「物神性」に。
ただ、ここでも値札と言わず、価値と言ってるが、価値では不純物が入りすぎている。やはり、不純物を除いた、それ自体である値札がいい。
「価値を示させるもの」が、値札、
「価値を示されるもの」が、物神性、
「価値を示すもの」が、貨幣という記号。
そう、
ここで単語(記号)と貨幣を同値・同置させられた。
【言語学・単語(記号)】
シニフィアン シニフィエ
↕ ↕
値札 物神性
【経済学・貨幣】
これでいいだろう。これで、終止符を打てた筈だ。
意味的に言っても、シニフィエに値するのは
グー的な、「使用価値」でもないし、
柄谷行人的な、「相対的価値形態」でも、正確ではない。
シニフィエの物語喚起能力に匹敵する呪力を持つ、
マルクス的言辞は、「物神性」しかない。
マイクロ的解釈に、もう一つだけ加えて終えたい。
シニフィアンと値札の構成要素の問題だ。
この2つも、また2つに分割できるし、分割する。
・シニフィアンは、音声と文字
・値札は、 数量と貨幣単位
前者は、自然物理的なもの、後者は、人造物理的なもの、である。
それだけ、ここでは言っておく。
マクロ・マイクロ的解釈後、CS.パース座標で、測定して、
彼らの基礎形態の論究を終わりにする。
パースは、記号関係で3つの軸を入れてきた。
X軸、対象
Y軸、解釈
Z軸、記号*正確には、「符号」と言った方が良い。
ここまで来たら、もう良いだろう。対応表は以下だ。
パース・対象 ⇒ シュプスタンス・事物
パース・解釈 ⇒ シニフィエ・物神性
パース・符号(パース的記号) ⇒ シニフィアン・値札
これで、単語(記号)と貨幣を、パース座標に配列させることができた。
これが、対応だ。そして、この間に挟まった、解釈・シニフィエ・物神性が
この両極の、パラレル異物同士を結合させる。
この媒体がなければ、この2つの人生は、平行線を辿り、決して交差することはなかった。
その離別されている差異を、出会わせたのは、
「解釈・シニフィエ・物神性」である。
多分であるが、基礎形態から基本形態に進む中で、
その原動力は、この媒体だり、メディアである。
人間は、意味に溢れている。いや、憑りつかれている存在。
それが、喜劇なのか、悲劇に終わるのか、
誰も知らない。
人間は、ただ、その中を、生きるだけだ。