
姿勢が悪いのは、1000年以上受け継いできた日本の歴史にあるのかも。
こばです。
今回はちょっとマニアック回です
スーパーのレジや駅で待っている時、職業柄つい足元を見てしまいます。
最近、よく思うのが
前重心で立っている人めちゃめちゃ多い!
です。立っている時にカカトがちょっと浮いている人があまりにも多いのです。これは特に女性に多く、その中でも中高年以降の方はだいたい前に重心をかけているなぁ。という印象を受けます。
前重心ってなにか悪いの?
と思われるかもしれませんが、実はカラダのバランスがやや崩れるのです。そもそも、解剖学的に見ると人の足にかかる荷重バランスは
おおよそ3:7と言われています。
前足部 3 後足部 7 の割合です。

カカト側にかかる力の割合が大きいのです。
立っている時にカカトがやや浮いて見えるという事はつまり、
この荷重バランスが崩れている。という事になります。
※ここで話を広げると終わらなくなります。
前重心による弊害はgoogle先生にお任せします!
検索してください。
これも踏まえて、なぜこうなるのだろう?
という疑問を抱いて生活をしていたらある文献と出会いました。
それが、小泉八雲の「神々の国の首都」という本です。
これは文献というよりも見聞録で、その中にある面白い一文がありました。
「人々は皆が爪先で歩いている。 (中略)歩くときにはいつもまず第 一に足指に重心が乗る。実際、下駄を用いる場合にはそれより他に方法がない。 なぜなら、踵(かかと)は下駄にも地面にもつかないから。」
これは小泉八雲さん(ギリシャ人)がまだ小泉八雲と名乗る前の時代。
ラフガディオ=ハーンとして明治20年代に日本に降り立った時
「日本人の歩き方を見て驚いた」という一文に添えられていた文章です。
今では洋風の靴を履くことが当たり前ですが、それ以前は
下駄、草履、草鞋、藁沓、和沓、足袋、足桶など
足の指で挟んで履くという形態が日本では当たり前でした。
下駄や草履を履いた事がない人は多いと思うのですが
似たものでビーチサンダルは履いた経験があると思います
わたしも海や川でよく履きましたし
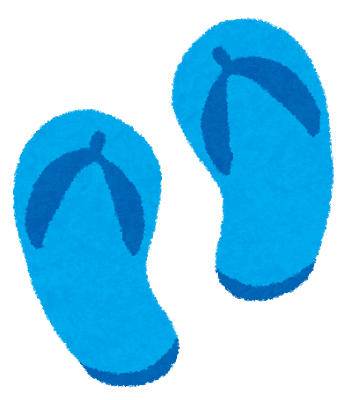
ただ、あれって物凄く歩きにくいですよね。そして歩くときはカカトから着地するのではなく、「足の指の付け根から着地をする」ように歩いていたと思います。カカトからつこうものなら脱げやすいので。
こういうところが当時の小泉八雲さんの目に写った
「人々は皆が爪先で歩いている」という所に繋がるのだと思います
※ 明治10年まで生きられた「西郷隆盛さん」も足半草履(あしなかぞうり)という前半分しかない草履(鎌倉時代から使用されている草履)を履かれていましたし、本当に当たり前の履きものでした。※
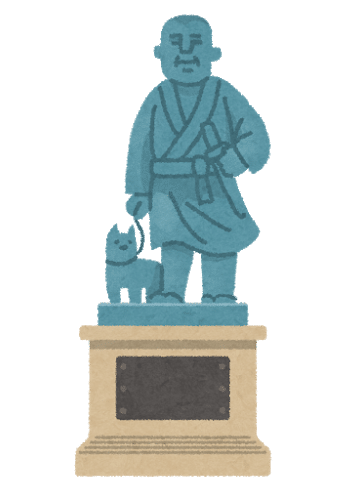
昔の日本の履物(草履や下駄、ワラジ)だとつま先で歩く傾向が強いのですが、今の流行りの欧米式の靴を履くと後ろ体重傾向になります。
では、日本において履物が今のような洋風の靴に変わったのはいつ頃
だと思いますか?
実は、一般的に欧米式の靴をみんなが履くようになってから
まだ、たったの70年ぐらいしか経っていないのです。
履物の歴史
— コバ靴店@ 足トラブルのかけこみ寺 (@kobakutsu) October 24, 2020
日本人が日常的に欧米式の靴を履くようになって、まだ70年ほどの歴史しかありません。それまでも、履物はあったのですがカカトのある履物は少なかったようです。
日本人が自分にあった靴を選ぶことができない理由として、靴文化の歴史の浅さが影響していると言われています🤔 pic.twitter.com/hXDEIqZzJ4
これって面白いですよね!
ここで話が戻るのですが
ざっくりとググった程度ですが、
日本において記録されている履物は奈良時代からです。
※もっと昔からありそうだとは思います※
およそ700年代の奈良時代。
約1300年前から70年前まで履物使用時
わたし達の子孫はずっと「前重心」でした

だからといって日常生活全てが前重心という訳でもないと思います。
しかし、生物には遺伝と進化があります。
脈々と1000年以上受け継いできた「前重心」という
日常生活動作がたったの70年で簡単に変わってしまうのでしょうか?
中高年の女性に多い前重心
わたしが感じた事ですが
【中高年に多い】というのは何となく想像できます。
世代交代の数が少ないのです。
0~1回でしょうか。
御年70歳以上というのは高齢化社会の日本において、そんなに少なくないと思います。働き盛りの人にとっては自分の両親がその世代であっても決しておかしな事ではありません。
前重心の原生遺伝子とでも呼べましょうか。
古来より受け継いできた履物様式を直接継承している人だから
前重心傾向が強いのかなぁという印象です。
また、たったの70年前なので今生まれたばかりの子でも
靴環境になっておそらく3回前後の世代交代を経ている程度です。
まだまだ新参者ですね!
あと、女性に多いのは基本的に【女性らしい靴】という
ヒールが高いものが多い靴環境も関係しているのかと思います。
これはハイヒールだけではありません。
スニーカーであろうがサンダルであろうが
ほとんどの女性用の靴は、ヒールがやや高い傾向にあるのです。
これに関しては以前、下のnoteにまとめました
あとは、スリッポンタイプの靴の影響も大きいように思います。
これまた中高年に好まれるいわゆる【脱ぎ履きのしやすい靴】です。

スリッポンタイプを履くことによる弊害はいくつもあります。
代表的なものは浮き指とも言われます。
すぐに履ける靴はすぐに脱げる靴です。
靴が脱げやすい時にどうするか、というと足の指を上に反らせて
靴の天井に足の指を引っ掛ける形で脱げにくくするのです。

ブリオン様より引用
足の指を使って靴を脱げにくくする・・・・・
どこかで聞きませんでしたか?
そう、ビーチサンダルです。
ビーチサンダルは脱げやすいので下駄や草履を履くように
足の指を使って履物を固定させます。しかし、それ故に着地をカカトから行うことが困難になります。靴が脱げるからです。
足指の方向は違っても、同じような意図で
足の指を使ってスリッポンタイプで歩いた時、
足のどこから着地するでしょうか?
足に合ったものならカカトから着けるでしょうが
きっと足の指の付け根から付きやすい傾向にあると思います
そう、先祖代々脈々と履いてきた下駄や草履のように

前重心の系譜となる【足の指の使用に比重をおいた履物】はこんな形で
中高年に好まれているのです。
潜在意識というか本能的に
このような履き方をするから好まれている。
という可能性すらありますね。
前重心の輪廻から解き放たれるのはまだまだ先の話かもしれません
とは言っても、簡単な解決方法はいくつかございます。
しかし、疲れてきたのでそれはまた次回
追記
もっと詳しくまとめてある本が出版されていました。
いいなと思ったら応援しよう!

