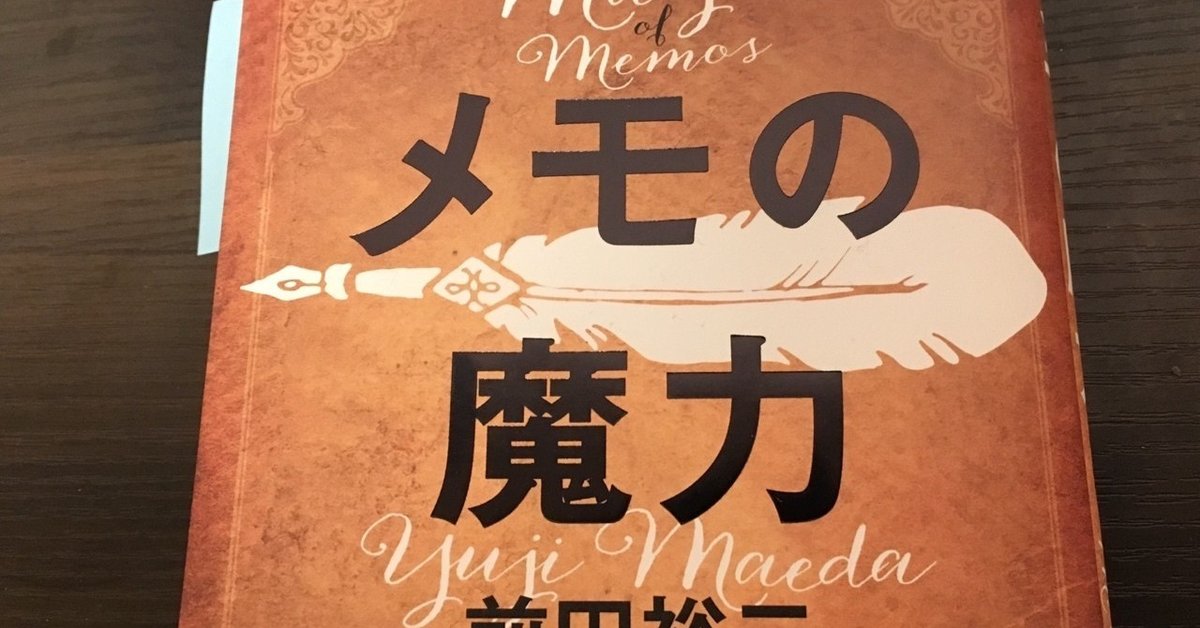
読書記録(2019年1月)「メモの魔力」
前回読んだアウトプット大全でノートを取ろう!と思い、その流れでこのタイトルに惹かれました。しかも著者の前田裕二さんの前著の人生の勝算も読んでいて良かったので、本屋で出会って結構すぐ買っちゃいました。
今回も気づきや印象に残ったところを3つ書きます。
「ファクト」→「抽象化」→「転用」のフレームワーク
この本で一番大事なところはこのフレームワークです。
①インプットした「ファクト」をもとに
②気づきを応用可能な粒度に「抽象化」し
③自らのアクションに「転用」する
これをノートの見開きでメモしていくのが基本のパターンで
①を左のページ、②と③を右のページに書いていく。
抽象化→転用と考えることで、これってあれと同じだよね。
この構造って他にも応用出来ると考えることが出来る。
(たまにそうやって考えることが多いので抽象化は得意なのかも)
この抽象化のところはKA法の価値抽出に似ていると読みながら思いました。抽象化はWhat型、How型、Why型の3つのパターンに分類しているが、
特にWhy型がKA法の価値抽出に似ていると感じました。
頭のいい人はこの抽象化したものを抽象化したまま扱えるって井登さんが言っていました。自分たちみたいな凡人は抽象化して転用して具体化して他に応用していくことにしよう。
解くべき課題の明確化
どこでも言われる言葉だが、やっぱり「目的が大事」。
やはりここでも出てくるのか。解くべき問題を明確にしないといけない。
転用のアクションをどこに向けて何に活かすのか?
活かす先がないとダメ。
「倒したい敵は何なのか?」
セミナーをよりよいものにするには?
仕事で上手く行くには?
目標を達成するには?
(もっと詳細にした方が答えが見つかるだろうな)
それを明確にした上で3つのフレームでメモしていこう。
自分を知る、人生の軸
メモで言語化するによって自分を知ることができる。
これは本を読み始める前は期待していなかった予想外の発見で、
就活のときはろくに自己分析をしていなかったので、付録にある自己分析1000問(まずは100問だな)を答えよう。
しかもこの自己分析も「ファクト」「抽象化」「転用」のフレームワークで
見開き2ページで書いていくので結構時間かかりそう。
そんな中でも
なぜUXデザインを学んでいるのか?
なぜHCD-Net活動をやり続けているのか?
自分は何をしたいのか
を明確にしていきたい。
少しずつ見えてきてはいるのだが、まだ分からないところもある
何かか自分を突き動かしてる。それを見つけていきたい。
最後に
ちなみにこの本を読み始めているときから既に4色ボールペンを買って
ノートも無印のノートを買いました。無印のボールペンも4色買ったのでもしかしたらそっちがメインになるかもしれない。

そのノートとペンを使ってどんどんメモしていきたいと思います。
いいなと思ったら応援しよう!

