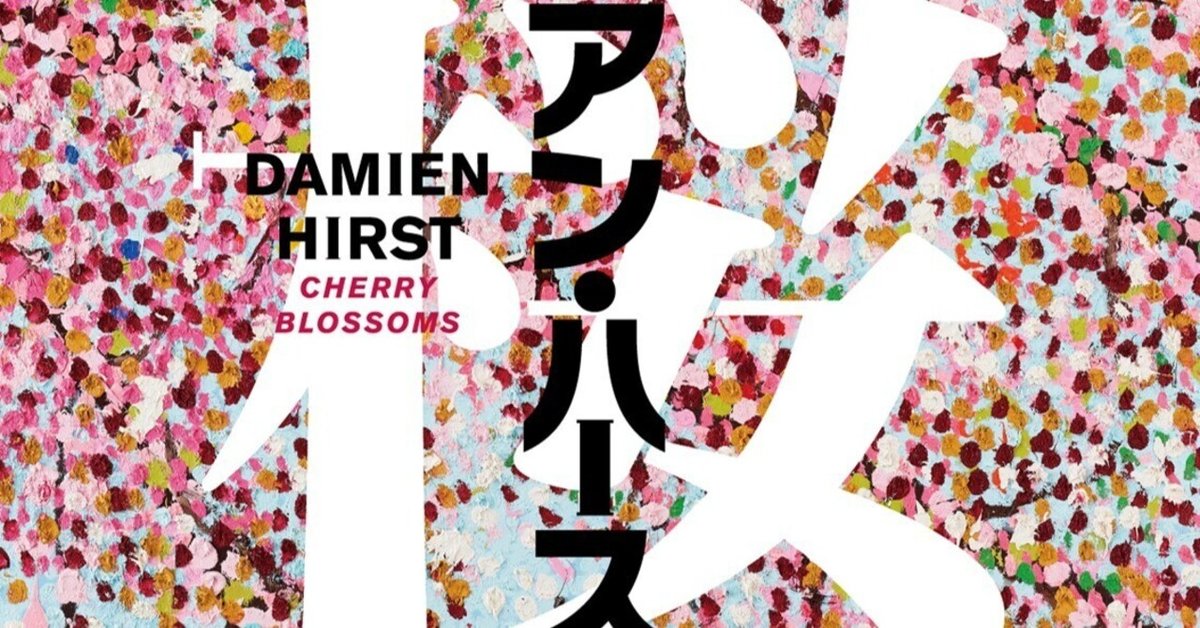
ダミアン・ハースト「桜」
《Day Critique》103
ダミアン・ハースト
「桜」
@国立新美術館
ダミアン・ハーストの最新の絵画シリーズ<桜>を展示する大型展覧会。主催はカルティエ財団。そういえばミシェル・ウエルベックの小説『地図と領土』では、ハーストとジェフ・クーンズが現代アート市場をわけあう二大巨頭として戯画的に描かれていたが、コロナ禍を経た今はどうだろうか。ハーストがこの全107点からなる<桜>のシリーズを描いている途中、ロンドンはロックダウンされ、以降彼は助手もつけずにひとりでキャンバスに向かっていたという。
今回出品されている24点は、どれも桜を主題とした大型の絵画という点で一致している。枝と葉の間に見られる微妙な奥行きのイリュージョンや、おそらくは溶液の配分によるマチエールの違い、二連画や三連画といった形式の差はあれど、基本的にはすべてが同じ絵のよく似たヴァリエーションである。それらを一見して気づくのは、近・現代美術からの引用だ。桜の花や葉を示す鮮やかなドットは、印象派の筆触分割やスーラの点描を思わせる。抽象化された枝はモンドリアンのようだし、絵具を叩きつけた跡はアクションペインティングを、観客を没入させるために選んだという大画面はカラーフィールドを想起させる。そしてそこに接ぎ木されるように、スポットペインティングやヴェールペインティングといった自身の過去の表現手法がリサイクルされている。
作家は、本作に関するインタビューの中で「こんな多面的な世界で誰もオリジナルにはなれない。組み合わせるしかない」と述べている(カルティエ現代美術財団によるドキュメンタリー・フィルム「ダミアン・ハースト 桜」)。このコメントの通り、多元的に複数の要素がパッチワークされた<桜>は、まるで近・現代美術のキメラだ。しかしもっとも重要なことは、それらの諸要素がすべて表現の核を奪われ、脱臼されているということである。
たとえば筆触ひとつとっても、ハーストの筆によるドットは大きすぎ、印象派の画面を見るときのように視覚の中で色彩が混ざり合う効果はない。また、寝かせたキャンバスに絵具を注いだポロックのオールオーバーな画面とは異なり、キャンバスを立てて描いたハーストの画面には垂直方向に力がかかり、かつ画面を横切る枝の形象から左右の区別も生まれている。機械が描いたように見えることを目指したスポットペインティングと違ってその画面は雑然としているし、ヴェールペインティングのようにドットは画面を覆い尽くしていない。この美術のキメラは、あらゆるものに似ていながら、あらゆるものの本質からは遠ざけられた想像上の怪物なのである。
インタビューで、ハーストは素朴な絵画への回帰や、絵を描く喜びを語っている。しかし、できあがった作品はあらゆる絵画表現を脱臼させるという意味で破壊的であり、誰もが知る有名な美術のパッチワークという意味でマーケット的である。これがハーストにとって初の日本での大規模個展であり、その個展会場は若者のフォトスポットと化していたことは、作家の思惑どおりなのだろうか。絵が下手だと評されるハーストが、それを自覚するゆえに自身の戦略性から逃れられないのだとしたら、それは不幸なことではないか。
ハーストは、英国政府からコロナ対策の支援金131万ポンド(約2億円)を受け取りながら、数十人の従業員を解雇していたという(ARTnewsJAPAN「ダミアン・ハーストの会社、コロナ支援金を受給しながらも従業員を大量解雇」)。いくら金があっても、いや、金があるゆえにさらなる利潤を求めてこのような作品を作り続けなければならないのだとしたら、ダミアン・ハーストという作家は、世間からそう思われているような資本主義の勝者ではなく、資本の運動の悲しい奴隷なのかもしれない。
(2022年5月20日記)
※トップ画像は公式ニュースより転載




