
JR新宿駅東口改札徒歩15秒で会えるジョンとヨーコ
「連れ合いだから迫川をお店のパートナーに選んだのではなく、迫川尚子という一人の人間を見込んで新しい店を作るメンバーになってもらうよう頼んだつもりでした。でしたが、承諾してもらうまでにまさか一年もかかるとは思いませんでした」(『新宿最後の小さなお店ベルク』より)
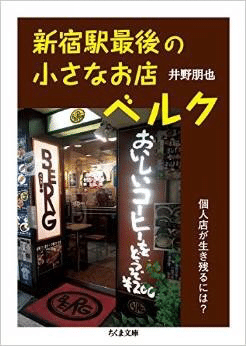
ジョン・レノンにとってオノ・ヨーコが欠かせないなパートナーであったように、ベルクの店長、井野朋也さんにとって副店長の迫川尚子さんは、ベルクを経営していく上で欠かせない“同志”なのです。
以前インタビューさせていただいたときのやりとりを、ぜひお読みください。そこに個人店が生き残っていくための真実があります。
“美味しい”を早く安く提供するには?
――ベルクはコーヒー一杯210円の低価格高回転のファストフード業態ですが、コーヒーもフードもいい意味で価格に見合わない味ですね。
迫川 どうせやるなら中途半端なこと、自分たちにとって価値がないことをしたくなかったんです。私たちは素人だったから、大手のチェーンのように売価から逆算して原価に見合った食材を探し、利益を得ていくということをあえて考えませんでした。コーヒーも、パンもソーセージやハムも、本物の味を出していれば、お客さまにはわかってもらえるはずだから、と。
井野 迫川は、児童書の編集者として仕事が面白くなっていた時期だったのに、僕が1年かけて口説いて、ベルクで働くことを決意してくれているから、中途半端なことはしたくないという気持ちが強いよね。
迫川 そう、「仕事を辞めて取り組むんだから!」というのは案外今でも呪縛になっているかも(笑)。
井野 実際、ベルクの材料コスト率は42・5%ととても高いんです。でも、一日1500人が来店し、日販は60万円。しかも、おかげさまで増え続けています。新宿駅東口改札から15秒という人通りが絶えない立地だからこそ、味がよければまた立ち寄ってもらえる。多くのお客さまにご来店いただければ売上げがつくれ、利益も得られると考えました。
迫川 そのために厨房内はすごく効率化しています。無駄な動きがないように、トースターの置く位置から、冷蔵庫の中の食材の配置も決まっていて、目を閉じていても手に取れるくらい。
――効率化を求められる業態にも関わらず、ビールやワイン、日本酒、つまみ系のフードなど、メニュー数がとても多いですね。

井野 仕込みが増えるし、メニューを増やすときはスタッフからはブーイングが起きますが、メニュー開発はスタッフも関わっているので、みんなそれぞれのメニューに思い入れもあるんです。お客さまもメニューに愛着があって。通常なら新商品を出すとどれかを削るものですが、そういうわけでどんどん増えてしまった。ただ、それに伴って客数が増えてきたことも事実です。
迫川 ビールの種類を拡充したときも、生ビールの注文が減るかと思ったら、定番プラス新しい味を頼むお客さまが増えて、結果的に客単価がアップしました。
井野 ロスがないのもメニューを削らない要因の一つだよね。
迫川 ええ、仕込みを最小限にとどめているんです。例えばソーセージを20~30本、まとめてボイルしておけば効率的ですが、味が落ちるでしょう? だから、2本ずつ茹でる。レタスも1個ずつしか洗わない。それでロスがないんです。
守りと攻めのバランスと役割
――効率化は自分たちの仕事を楽にするためではなく、お気に入りのメニューがいつもあるという顧客の安心感を損なわないための影の努力でもあるわけですね。では、商品開発で心がけていることは?

井野 「自分たちが毎日食べられるもの」で、「100人ではなく1000人を対象に」です。他では出していないようなマニアックな方向を目指しつつも、ベルクにはさまざまなお客さまが毎日1500人も来てくれますから、多くの人においしい、また飲みたい、食べたいと受け入れてもらえるものでなくてはいけません。
以前、ドッグパンをつくるときに、パン職人の高橋康弘さんにいろいろと試作品をつくってもらい、僕らとしてはライ麦の強い固めのパンにしたかったのですが、コンサルタントの押野見喜八郎先生に、柔らかいパンのほうがいいと言われた。「100人のお店ならいけるけど、ベルクは1000人の店だから」と指摘されて、とてもわかりやすかった。以後、頭の片隅にはそれを置いています。
だからといって、万人受けするものばかりでもつまらない。大衆と趣味の葛藤の中でベルクの味があるといえるでしょうね。
迫川 食材探しや、商品開発はもちろん、サービス、店づくりにおいて、「ベルクらしさ」も常に考えます。飲食店では無難さが求められる音楽や壁を使ったギャラリーなんかは、ベルクらしく趣味に走っています。
――前年同月比を上回って成長し続けていますが、その秘訣とは?

井野 変えちゃいけないことは守りつつ、変化してきたことです。ベルクは「日用品+娯楽」だと思っています。つまり、毎日朝7時には開いていて、フードは1分以内、ドリンクは20秒以内に出てくる、基本の約束が守られているから日用品のように使ってもらえます。さらに、いろいろな味が用意されているから、今日はちょっと違うものを頼んでみようという楽しみがあります。
迫川 店長は「続ける」役目で、私は「変化をさせる」ことが役割なんですけど、そこで店長から教えられたのは、「続ける」人にとって、ちょっとした変化も恐怖だし、これまでのことを否定されたようで傷つくことだと。
だから、「今まではこれでよかったんだけど、こうしてみたらどうだろう?」と話を持っていくようにしています。それから、「いまこんな改革をやっています」って冷蔵庫に張ったりノートに書いたりして覚悟を迫るように(笑)。
井野 だから迫川には程よく現場から離れてもらっています。現場感覚が強くなると、すべき変化が見つけられなくなりますから。個人経営の場合、客観的な判断を下す本部機能がないのが弱味かもしれないですね。
家族以上、親子以上の同志という存在
――では、個人店が生き続けていくために大事なものとは何だと思われますか?

井野 著書『新宿最後の小さなお店ベルク』では、①未経験であること、②同士の存在、③助言者、④多額の借金というふうに書きましたが、あえて一番大事なものというと、同士の存在ですね。人を雇うというのはとても大変だし一人のほうが気楽です。でも、現場を守ってくれる人、商品開発が得意な人などトータルで考えると、自分だけの感覚では壁にぶつかった時に限界がある。
迫川 社員、アルバイトスタッフはもちろん、私たちはベルクそのものも同志だと思っています。変に聞こえるかもしれませんが、私たちはベルクには人格があるように感じていて……。
井野 そうだね、明らかに、怒ったり喜んだりしている。
迫川 だから、仕事で悩んでいるスタッフに助言する時も、ポイントは「ベルクにとってどうしたらいいか」ということを考えるように話します。それがお客さまのためでもあり、結果的にベルクで働く自分たちのためにもなるから。
――社員8人、アルバイトスタッフ約30人が、志を同じくして働くべく、店をまとめるのも大変ですね。

井野 僕らも含めて、社会生活が上手じゃない不器用なタイプが多いんです。あいさつから始まって、食材の扱い方、効率的に作業をする方法なども、厳しく教えなくてはいけないことも。
でも一つ一つ仕事を覚えて、クリアできると喜びを感じる。最初から器用にこなせる人は、動けない人がどうして動けないのか理解できず、イライラしてぴりぴりとした雰囲気になってしまうものですが、ベルクでは「他の人を気に掛ける」ことを常に言っています。
迫川 たとえば新人スタッフが何をどうすればいいのか迷っていたら、サポートするとか。一日1500人のお客さまを相手にしていると、とにかく助け合わないとやっていけない。連絡ノートを通して、こまごまと“お小言”は書きますが、いざとなれば本人に直接話します。
――井野さんも、迫川さんに怒られたり?
井野 僕はあまり……。でも、怖いですね(笑)
迫川 ふふふふ。仕事において何か問題行動をしたら、ただ厳しく叱るのではないんです。行動の根底には、その人の考え方や生き方が出てくるので、そこをきちんと話し合わないと仕事に生きないと思っています。
仕事の話だけど、すごく突き詰めて話すこともありますね。何度も崖から落としても、指一本くらい崖に引っ掛けて這い上がってきてくれるスタッフは、その指を引っ張り上げる感じで……。家族以上、親子以上のこともしゃべってきた気がします。
井野 学校だと思っています。
迫川 子供が30人くらいいる感じです(笑)。
井野 人材も、メニューもお客さまとの関係も、ベルクそのものも、時間をかけてお互いに育ってきた。意識してきませんでしたけど、それは個人店だからできたことなんでしょうね。
――貴重なお話をありがとうございました。店とは、まさに学校ですね。
⌘井野朋也さん
1960年、東京・新宿生まれ、新宿育ち。音楽や漫画などで表現者を目指していたが、20代後半でライフワークを見つけようと両親が経営していた純喫茶を改装。1990年より、新宿駅ビル地下のビア&カフェ「ベルク」の経営に携わる。ベルクの商いについてまとめた『新宿駅最後の小さなお店 ベルク』はロングセラー。
⌘迫川尚子さん
ベルク副店長。唎酒師。調理師。種子島生まれ。女子美術短期大学服飾デザイン科卒業。現代写真研究所卒業。テキスタイルデザイン、絵本美術系出版社の編集を経て、1990年、新宿駅ビル地下 「BEER&CAFE BERG」 の共同経営に参加。仕事の合間に日々、新宿を撮り続けている。写真集に「日計り」。著書に『食の職 小さなお店ベルクの発想』など。
