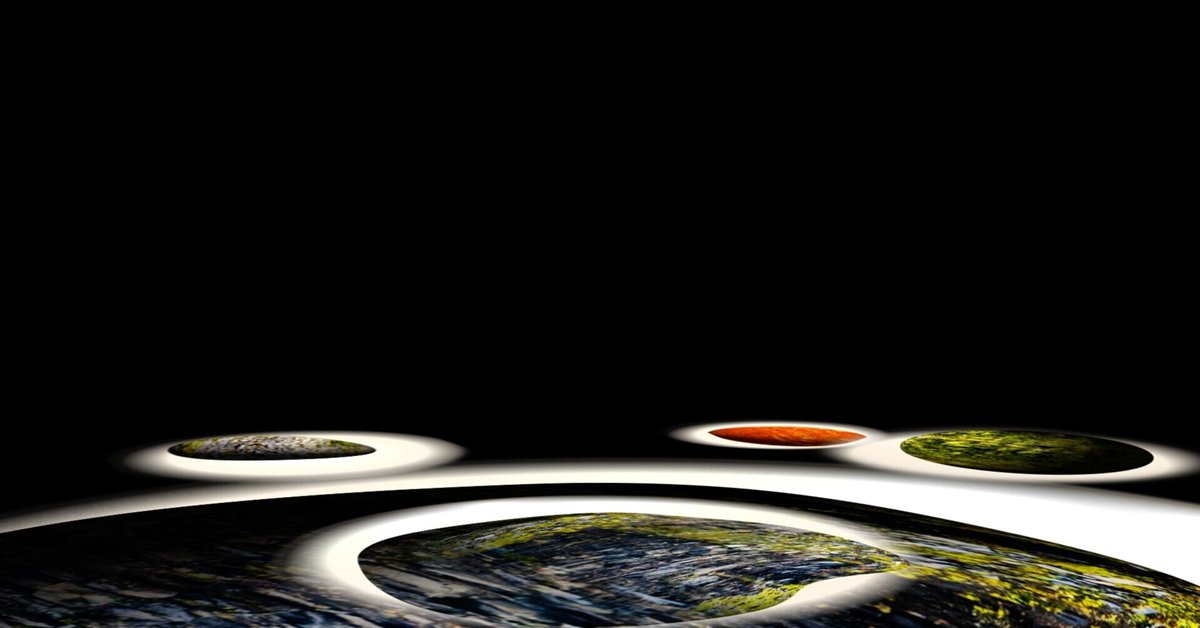
きわダイアローグ09 渡邊淳司×向井知子 1/4
1. 言語的な「分かる」ではない感覚を重ねていく
///
向井:ご著書『表現する認知科学』の中で、社会に実装化していくために必要な、伝えやすさ、わかりやすさがある一方、それではこぼれてしまうことの難しさや危うさについて、非常に言葉を選ばれて書いていらっしゃいましたね。

2020年、新曜社
渡邊:この間の心臓ピクニックの話とも関連するのですが、周りの人と一緒に何かをするとき、周囲との関係性に注意を向けるのではなく自分の身体がしっくりくるところを探ることで、最終的には周りとの調和がうまく取れることがあると思うんです。外部の規範に自分を合わせようとするより、自分の中にある身体という規範に対する差異を感じていくやり方がうまくいくこともあるのではないでしょうか。常に「わたし」という自己を、最も身近にあるわからないもの、つまり身体というものとの共同行為としてつくっていく。自分の気持ちいいことを探ることと、人と調和することは実は同じベクトル上にあり、外部の規範からではないテクノロジーの在り方もあると思っています。
僕は、触覚について、情報を伝える感覚というより、社会的な関わりをつくったり、関わり方を変えるためのスイッチなのではないかと考えています。そういう意味ですごいと思う触覚装置があって、実はそれは足湯です。まず、機能として、たくさんの人に同時に温度感覚を提示し、「同じ身体感覚を体験する」ことを実現しています。加えて、身体感覚を共有していることを前提に、ある程度のコミュニケーションの儀式が決まっている。隣の人に「いいお湯ですね」なんて話しかけてもいいし、それぞれが一人でお湯に浸かっていても構わない。そういう触覚の共同体験の場をつくる装置として、足湯はすごく面白いと思うんです。
それから、タバコを吸う方にとっては、喫煙所がコミュニケーションの場になっていますよね。そこでは、煙を吐くことによって「呼吸」が、手に持つタバコの長さによって「時間」が、可視化されています。個々のペースでそれぞれが過ごしているなかで、息遣いのような身体的な同期や、「火を貸してください」と言われた人が火を貸すような儀式的なやり取りといった、コミュニケーションのきっかけがちりばめられている。別の目的がありつつ、何かを合わせていくことは、コロナ禍の今だからこそすごく重要な感じがします。
向井:一つのルールのある場を共有することで、それぞれの感覚は違っても言葉や掛け合いがとても大切になるということを、このコロナ禍で考えるようになりました。わたしは両親が近くに住んでいて、コロナが流行り始めてから、彼らの食事も毎日つくるようになったんですね。感染予防のために、実家に行っても玄関に食事を置いて、ものの1、2分のやりとりをして帰るだけ。でも、その他愛もないいくつかの言葉でのやりとりのほうが、普段のコミュニケーションよりうまくできているなという気がしています。同じ食卓上ではなくとも同じものを食べて、「味付けがどうだった」とか「あれは美味しいわね」と話すことが、意外といいものだと思っているんです。とても主観的だけれど、よくわからない「味覚」を共有することによって、人間ってかなり安心するんだなということに気づきました。見えないものの感覚って重要なんですね。
渡邊:なるほど。確かに「同じものを食べている」という感覚があるとないとでは全然違いますね。同じ「食」を経験していると、無条件で相手を信頼する部分がだいぶ大きくなる気がします。
向井:だから「同じの釜の飯を食う」という言葉があるのかもしれませんね。比喩的にでも「同じ釜の飯」という言葉があるのは、人間のコミュニケーションの中に味覚や嗅覚、息遣いといった主観的感受性に関わる部分が、ものすごく重要な意味を持っているからなのかもしれないなと思いました。
渡邊:コミュニケーションは相手の反応を予測しながら行いますが、予測とは対象を時間的な存在として捉えることです。相手の動きや気持ちを予測して、期待通りになったら嬉しいですし、裏切られたら悲しくなる。自分自身に対しても、未来を想像して、希望を感じることもあれば、不安になることもある。そういう時間的な行為や考え方のモデルみたいなものができてくると、対象を受け入れられるのかもしれません。共在という言葉がありますが、まさに「共に」「在る」ことができるわけです。
触覚の話をすると、どうしても「共感」という言葉にいきがちです。「相手の感情を自分も感じることができる」ことを前提に話されることが多いですが、本来、わからないもの同士では、同じことを感じられるかどうかへのためらいが常にあります。でも、そういうときにでも、「受け入れる」ことや「祝福する」ことはできると思っています。
向井:「祝福できる」ってとてもいい言葉ですね。「共在」と言われて思い出したのですが、ドイツ人は友だちに会うと‟Das ist sehr schön dass Du da bist. (あなたがここにいてよかった)‟と言うんです。会った時に「あなたが来てくれて嬉しいわ」という意味に近いのですが、「あなたの存在がここにあることが嬉しい、素晴らしい」と伝えている。西洋社会では、個人主義であるがゆえに「相手がわからない」ことが前提となっています。だからこそ、共感を求めるのではなく「あなたがいることが素晴らしい」と言えるのでしょうね。
渡邊:「祝う」ってすごく重要なことだと思っています。話の本筋からそれるかもしれないですが、僕は昔、毎月誕生日会をやっていたんです。会の目的はいろいろな国の料理を食べることなのですが、主要メンバーの友だちで、その月が誕生日の人を必ず何人か呼んできてもらうんです。僕は、会ったことも、見たこともない、友人の友人という「2.5人称くらいの人」のためにプレゼントを買うのですが、どんな人かを想像しながら贈りものを選ぶというのは、今までにないポジティブな感覚でした。「祝う」ということについて考えはじめた個人的なきっかけですね。
向井:これはニュースで見た話なのですが、触手話をされる盲ろうの高齢の方が、コロナによって、話す機会を失った結果、すごく衰弱してしまったそうなんです。その方にとっては、生活が送れる云々以上に、それまで行っていた触手話の会に行けなくなってしまったことが大きかったんですね。人に触れてもらうことが生命線で、単なるコミュニケーション、言語以上に必然的な何かだったのでしょう。そのニュースを見て、たとえ一回性の触れ合いであっても、それを習慣の中に組み込むことで、人間は無意識下で安心するのかもしれないなとは思いました。
渡邊:さっきの食の話もそうですね。毎食、もしくは一日に1回でも、食べたり、触ったりすることで、言語的な「分かる」ではない感覚を重ねていく。それがその人にとってはエネルギーとなり、相手がいるのであれば、共在の信頼みたいなものになっていく。食べものから「おいしさ」や「栄養」を得ることはもちろん大事ですが、それとともに、つくってくれた相手との関わりといった、もう少し広い意味でのエネルギーももらっているんですね。習慣、時間もそうです。それらとどう関わっていくかが、コミュニケーションでも、すごく重要な気がします。
向井:おっしゃるとおりですね。栄養素みたいな話で言うと、「おいしかった」という気持ちは毎回の問題かもしれないですが、栄養素だと1日、1週間、1か月といったいろんなフェーズの時間軸が関わっていますよね。実際細胞が入れ替わるのに3か月かかりますから。渡邊:おそらく、身体化されているものほど長いんですよね。
「わかった」「おいしい」といった感覚は瞬間のものですけれど、同時に、ある時間をかけてダイナミックに変わっていくものがある。その時間軸の違いを分けながら、人は人に何かを伝えたり、アウトプットしたりするのかもしれないですね。
///
渡邊淳司(わたなべじゅんじ)
NTTコミュニケーション科学基礎研究所人間情報研究部上席特別研究員
専門は触覚情報学。主著に『情報を生み出す触覚の知性』(毎日出版文化賞(自然科学部門)受賞)、『表現する認知科学』、『情報環世界』(共著)。触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌「ふるえ」編集長。近年の活動に、スポーツの非言語的翻訳やウェルビーイングに関する研究がある。
向井知子(むかいともこ)
きわプロジェクト・クリエイティブディレクター、映像空間演出
日々の暮らしの延長上に、思索の空間づくりを展開。国内外の歴史文化的拠点での映像空間演出、美術館等の映像展示デザイン、舞台の映像制作等に従事。公共空間の演出に、東京国立博物館、谷中「柏湯通り」、防府天満宮、一の坂川(山口)、聖ゲルトゥルトゥ教会(ドイツ)他。
///
