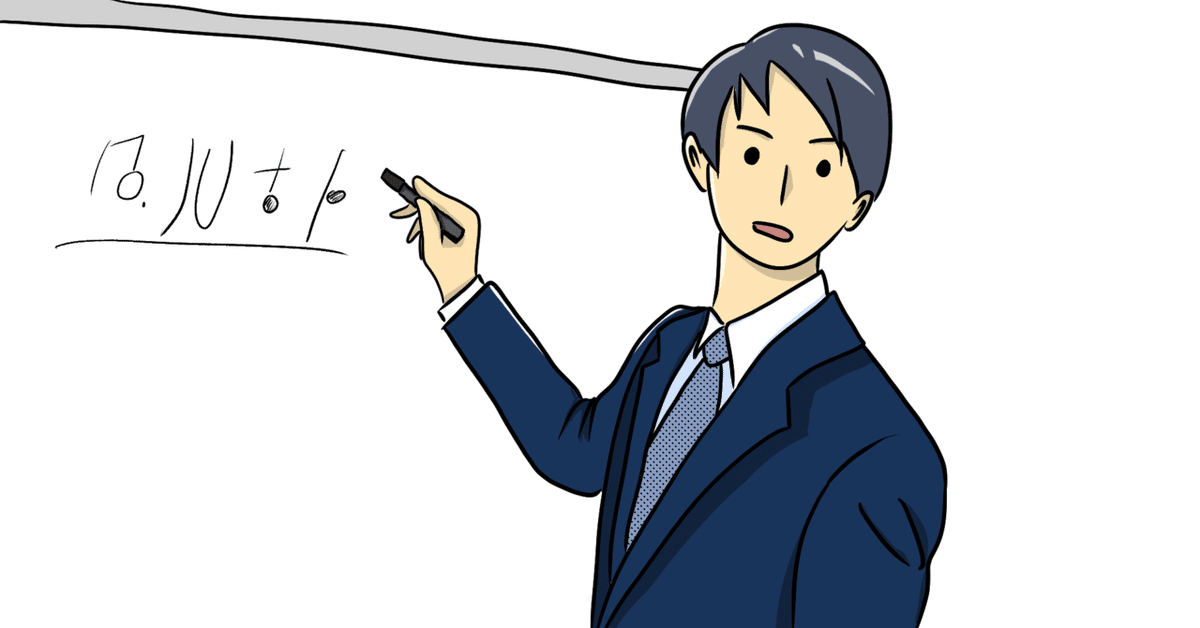
話題ごとに友達を作った方が良いのかもという話
休みの日こそ頑張ろうと思うけど、仕事の日ほど頑張れる以下同文です。
昨日投稿した記事の中で人って結局はコミュニケーションの為の話題を探してるよねみたいなことを書きました。(そんなこと書いたっけ?)
そこで自分が持っている話題をジャンル分けしてみたのですがその結果が下です。
「映画」
「テクノロジー」
「生物学、進化学」
「メカニズム」
「健康」
「経済学」
このうち「映画」については大学のコミュニティや仕事の都合上話せる人が多いのですが、他のジャンルに関しては話せる人が殆どいないことに気がつきました。
なのでnoteやメモに書いて話せない鬱憤みたいなものを少しずつ晴らしているのですが、それだけだとやっぱり足りないみたいで本来映画の話をするべき友達に何故か健康の話題を振って「?」みたいな顔をされながら話をして心の中で「なんで分からないんだ!」というお互いにとって一番悪い状況を生み出してしまっています。
友達もジャンル分けで作った方が良いかも
古今東西「なんでも話せる友達」を作っておくべきだという話は聞きますが、ここでいうところの「なんでも」は自分の悩みだったり相談したいことだったりを指すはずで「どんなジャンルでも」ということではなさそうです。
確かにどんなジャンルでも話せる友達がいれば最高なのでしょうが、どんなジャンルでも話せる友達なんてなかなか見つかりそうにありません。
そこでジャンルごとに友達を作る方がいいんじゃないかと思うわけです。
例えば「生物学に詳しい友達」を作っておけば生物学に関する新しい知識を知ったらその話をその友達にすると単純に楽しいですし、反対に自分の知らない面白い生物学の知識を教えてくれるかもしれません。
「話したいという欲」も発散できるし情報源としても一つ増えるし、もし違う意見があれば話し合いもできるし「同じジャンルの話をできる友達」というのはめちゃくちゃ重宝しそうです。
どうやって友達を作るか?
大人になると友達を作るのは難しいみたいな話を聞きますが確かにその事に関しては実感しています。
さらにジャンル別の友達となるともっと難しい様に思います。たまたま同じ職場の人がたまたま同じジャンルに興味を持っていてしかもウマが合うなんて確率的に考えてみても結構低そうじゃないですか?
もはやそうなってくるとそういったジャンルが好きな人が集まるところに自ら訪れるしかなさそうですね。
果たしてそんなところがあるのかと考えてみましたが、結論としては「ジャンルによってかなり違う」といったところだとおもいます。
比較対象として「音楽」と「生物学」の2つを比べてみましょう。
「音楽」だとライブハウスやフェスみたいなところが友達を作るきっかけになったりする気がしますが「生物学」というジャンルだとパッと思いつくのが大学とかになりそうです。
(「カブトムシ愛好会」みたいなのはあるみたいですが、「生物学」となると研究や協会の様に少し敷居の高いものが目立ちます。)
正直コミュニケーションをとるためだけに大学に入学するのは流石にコスパが悪すぎるのでもっとカジュアルなコミュニティって作れないのかな?と思って良い案を思いついたのでちょっと提案してみようかと思います。
大学の仕組みを考えてみる
突然ですが大学って結構いいコミュニティが作れる機関じゃないかと思っています。
ただコミュニティを得るための他に+αの要素が強すぎてお金や時間がかかりすぎたり、敷居が高くなってる気がするのでまずは大学を分解して必要な要素だけ残せばいいコミュニティが作れそうじゃないですか?
突然ですが大学って「何か」を学ぶための場所ですよね。
それを仮に映画だとしましょう。
じゃあ映画の大学には映画を学ぶ人たちが来るので映画好きのコミュニティが出来上がるわけです。
そしてその中から気の合う人同士で更に繋がりが強くなって友達になるわけですが、この仕組みをインターネットに置き換えてみたいと思います。
インターネットコミュニティを作る
オリエンタルラジオの中田敦彦さんがYouTube大学を始めてからというもの、YouTubeには色んなジャンルの「大学」が増えた様に思います。
よく耳にするのが「ゆっくり解説」です。
ゆっくりボイスというソフトを使ってキャラクターがなんらかのテーマについて解説するというものです。
僕がよくみるジャンルは生物学のゆっくり解説なんですが、これがかなり面白いんです。
本や論文を読むほど敷居は高くないし、モノによっては耳で聞くだけで楽しめるので何かしらの作業をしながらでも楽しめます。
さらにゆっくり解説は1人が話すひともう1人が聞く人みたいに役割分担がされていることが多く、聞き役の人が初心者やあまりそのジャンルに知識のない人たちの疑問をぶつけてくれるので入門としても面白いです。
ここで結構勿体無いと思うのが、知識を得た視聴者の知識を吐き出す場所がないということです。
「話題」を仕入れたけど話す友達がいない!
みたいな状況ですね。
これが結構もどかしくてうちの父親もYouTubeで車の情報をバンバン仕入れてるのに話す人がいないもんでモヤモヤしてるんです。
なので車の話を振るとめちゃくちゃマニアックな知識とかをウッキウキで話してくれるんですね。
「話題」が溢れてるのに「友達」が不足してるんです。
で「話題」を仕入れる場所が友達作りの場と同じであればめっちゃいいと思います。
要はLINEでもFacebookでもいいんでコミュニティを作ってゆっくり解説の後にその宣伝を入れてください!
というお話です。
そうすれば僕が生物学の話をする場所もできるしゆっくり解説が常に「話題」を提供してくれるので、今日のゆっくり解説みた?
みたいな話も出来るのでなんだか楽しそうだなぁと思います。
今はTwitterとかInstagramで面白いと思ったものを雑多に共有しているだけですが、それを興味のある人たちだけに向けて発信すればより楽しくなりそうだなぁというお話です。
最後に
なんだかめちゃくちゃ長くなりそうだったので強引に結論に持っていきましたが、ゆっくり解説とかnoteの記事といった「コンテンツ」はもう溢れていて「話題」を吸収しまくっているけど吐き出すところがないので誰かそれを作ってよってことなんです。
それがコンテンツ制作者なら手っ取り早いよねというお話でした。
なんだかな友達が出来ないので友達を作る場を誰か作ってという心の叫びをダラダラと書く回になりましたが許して下さい!
ということで以上以下同文でした。
