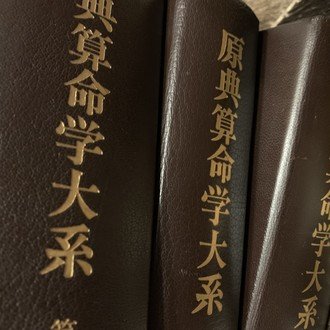3/7 守護神を捉えるときの「命式の6文字」と「命式全体(蔵干含む)の使い分け、「忌神が土性」の意味
守護神の説明をするときに「命式の6文字」をもってバランスを捉える、
…という書き方をすることについて、
誤解を招いている可能性があることに気づいたので、
本日はそれについて書きます。
例えば、「守護神が土性」とか「忌神が土性」とかいう場合について、
地支がすべて土性の十二支であった場合、
それが「守護神多過」とか「忌神多過」ということになるのではないか?
…という印象を持っている方がときどきおられるようなので、
必ずしもそうではないですよ、ということの説明と、
それと併せて月干支の重要性についてここで説明しておこうと思います。
さて、一般的に、命式全体のバランスを捉え、
どの十干をもって守護神とするか?…を考えるときには、
「命式の6文字」をもって判断します。
例えば、昨日は、樹木希林さんの命式を挙げましたが、
その守護神は何か?
…を判断するときには、
日干と月支で全体の枠組みをとらえ、
それ以外の要素(年干・年支・月干・日支)の五行が、
その枠組み(日干と月支の組み合わせ)にどのような影響を与えるか?
月支という舞台(季節)に、「それ以外の要素」があることは、
日干癸水が流動性を維持しながら存在し続けることに貢献するかどうか?
…という観点でもって守護神は何かを判断しました。
但し、この「命式の6文字」でバランスを見るというのは、
あくまで「命式のバランス」を客観的に捉えるための作業であり、
この6文字でもって守護神・忌神を判断できるものでも、
この6文字の中にしか守護神・忌神がないわけでもありません。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?