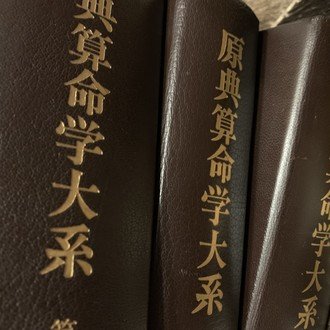8/30 十干・十二支をもって人物を捉える⑩ 十二大従星のカタチ(5)天胡星・天極星
昨日の続きです。
十二大従星についてカタチで捉える続きです。
十二大従星を「カタチ」で捉える、などというと、
奇想天外で亜流の考え方、取るに足らない戯言であるように思う方もおられるかもしれませんが、
算命学の要素というのは、
すべて構造で捉えることができるのと同様に「カタチ」をもって捉えることが可能で、
むしろ、構造やカタチをもって捉えるほうが、実は正しい理解を得やすいことも多くあります。
というのも、
古代の人たちの使っていた言葉と現代の言葉、現代日本の言葉というのはまるで異なるため、言葉・文章での説明というのは、字面だけを切り取った、誤解を招きがちな説明となりやすいからです。
外国語を翻訳する際に、単語の意味ばかりを追うと、本来の内容を損なうことになりがちなものですが、
それと同じように、古代の概念についての説明を、言葉や文章だけで説明しようとすると、それは多分に誤解を招きやすいものとなってしまいます。
例えば、車騎星というのは「攻撃的な星である」という文章で説明されることがありますが、
その字面だけを捉えれば、車騎星は乱暴で危険な星であるかに思うのですけれど、
車騎星の構造が「日干が剋される」という構造であることが分かれば、
その攻撃性は、何かに駆り立てられて発揮されるものであることが分かる、
何かに突き動かされることの先に発揮される攻撃性であることが分かるので、
決して単に乱暴で危険なわけではなく、その攻撃性に対応するには、その攻撃性の裏側に何があるかを知ることが大事であることが分かります。
このように、文字の文章による説明というのは、表面的な理解に留まる一方で、
「構造やカタチによる理解」
…というのは、多義的にして奥行き深い理解を実現するとともに、その対処や活用についての示唆をももたらす、という点でたいへんに有効なのだということです。
さて、前置きが長くなりましたが、その前提で、本日は天胡星のカタチから説明いたします。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?